
第53回 多賀麻希(17) 彼を試す自己開示ギャンブル
「マキマキさんって貯金ないっすよね」
モリゾウの言葉に、麻希は針を動かしていた手を止めた。

緑の糸の刺繍で描く四つ葉のクローバーがいびつに見える。初めてショップを訪れた人が手を出しやすい価格のがま口ポーチに刺繍を入れている。気持ちが波立っていても針は揺らがない。それくらいにはプロだと自負している。クローバーの見え方が変わったのは、受け止め方の問題だ。
以前なら、「そうなの。ほんと、貯金ないの」と屈託なく応じられた。
以前なら。
モリゾウが麻希よりも蓄えがないと思えていた頃なら。
けれど、知ってしまった。モリゾウが動画配信の学習講座で英語講師をしていることを。
アルバイト講師なのか、正社員なのか、野球選手みたいに年契約なのかはわからないが、麻希がバイトしている新宿三丁目のカフェの時給の何倍も稼いでいることは想像できる。元々そのカフェでモリゾウがバイトしていて、モリゾウと入れ替わる形で麻希が入った。モリゾウは舞台で忙しくなったとマスターからは聞いていたが、もっと稼ぎのいい仕事を見つけて、そちらへ乗り換えたのだ。
モリゾウに仕事のことを尋ねたことはなかったが、働いている様子はなかった。定職につくと、稽古や公演の時間を作れないから、バイトでやりくりする。映画製作会社で働いていた頃、そういう演劇人を何人も見てきた。無職で無給なのだと決めつけ、家賃も光熱費も食費も受け取ろうとしなかったのは麻希だ。嘘をつかれていたわけではない。けれど、真実を隠されていたという意味では、騙されていたといえる。
恋愛ドラマの相手役のつもりでいたら、詐欺ドラマの被害者だった。
布雑貨のオンラインショップを開こうと言ってくれたのは、モリゾウなりの埋め合わせなのだろうか。こんなものでお茶を濁すつもりなのかと思ったら白ける。作家として扱ってくれたことを喜んだのも、軽率だった……。
バイトに向かう電車の中で隣に立つ人が見ているスマホ画面にモリゾウを見つけたあの日、どんな顔をして会えばいいのかと思いあぐねながら帰宅すると、麻希の屈託を知らないモリゾウは、いつもと変わらなかった。

「マキマキさん、売れたっすよ」
よりによってその日、大物の18651円のチューリップバッグが売れたのだった。モリゾウがその値段をつけてくれたとき、うれしかった。作家として大切にされているのを感じた。18651円。麻希にとってはカフェのバイト3日分だが、モリゾウは数時間カメラの前でしゃべったら稼いでしまうのだろう。以前は存在しなかった換算レートが恨めしい。
「近場の温泉ぐらいなら行けちゃいますよ」
喜びたいのに、顔が引きつる。何か言おうとしても、言葉が出ない。唇が渇いている。喉が渇いている。何もかも渇いている。
モリゾウは麻希が呆気に取られていると思ったのか、「マキマキさん、まだまだ行けるっす!」と声を弾ませたが、「まだまだ俺のために稼げ」とせっつかれているように聞こえてしまうのが苦しかった。
モリゾウの秘密を知る前の青春みたいに思えた日々が傷だらけのフィルムで脳内再生される。
ふたりともお金がないと思っていたから、同じ地平に立って、同じ方向を向いて、夢を追いかけられていた。でも、それは麻希のおめでたい思い込みだった。モリゾウにいいように使われていただけだった。
国語の教科書で習った宮沢賢治の「オツベルと象」を唐突に思い出した。オツベルの期待に懸命に応えようと働き、すり減っていく象と自分が重なった。
あの日から、モリゾウを見る目が変わってしまった。モリゾウの声も、モリゾウが放つ言葉も、モリゾウの姿も。モリゾウの存在すべてが曇り、濁り、くぐもっている。
今までが晴れ渡り過ぎていたのだろう。年下で魅力的なルックスで声が抜群に良く、東大に入れる頭を持ち、電気がついていれば幸せだと言い、寝床と温かい食事に感謝し、それ以上を求めない。これでワケもウラもないなんて、おとぎ話だ。
半年あまりの間、モリゾウが麻希から離れなかったのは、居心地が良かったからではなく、都合が良かったからなのだ。恋愛に持ち込ませず、結婚を口にしない、30代最後の女。
「マキマキさんって貯金ないっすよね」の後の短い沈黙の間に、この数週間考え続けていることが渦を巻くように頭を巡った。麻希が黙り込んだので、モリゾウは「あ、いや、金借りたいってことじゃなくて、素朴な疑問っす」と取り繕った。
「マキマキさん、全然高い買い物してないし、家賃もそんな高くないよね。金入れてない俺が言うのもなんだけど、何に使ったのかなと思って」
モリゾウはどういうつもりでこの話をしているのだろう。何が目的なのだろう。勘繰らずにはいられないのがしんどい。
「……わたしが使ったってわけじゃないんだけど」
「あ……なるほど」
モリゾウは察したようだ。麻希の貯めた金が消えた事情を。
麻希の貯金箱は底が抜けていた。というより蛇口がついていた。都合よく緩む蛇口で、男の人に頼まれると、お金を吐き出すのだ。そのお金は返ってこなかった。返してと言えば、返してもらえたのかもしれないが、麻希は言わなかった。言うと壊れてしまうもの、失ってしまうものに比べれば、諦めがつく金額だった。
必要とされるのがうれしくて、がっかりされるのが怖くて、拒むことより差し出すことを選んでしまっていた。
お金も、からだも、こころも。
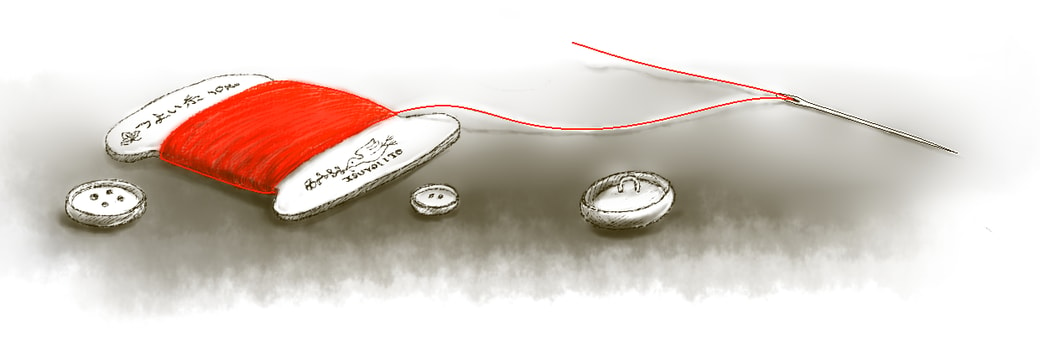
20年近く働いてきて、車やマンションを買ったわけでもなく、壁の薄い安アパートに住んでいるのに、貯金残高が数十万円しかない。その何十倍もが蛇口から流れ出たということだ。
麻希に近づいてきた男たちは、麻希にからだを開かせ、蛇口を緩めさせ、麻希が持っているものを吸い上げていった。モリゾウは、そんな男たちとは違うと思っていた。だけど、アプローチが違うだけだったのだ。からだを求めてこないが、麻希をいい気にさせ、気持ち良く蛇口を緩めさせている。
そのことに後ろめたさも申し訳なさも感じていないとしたら、モリゾウにとって麻希はそのように扱って良い対象ということなのだろう。
「昔からそうなんだよね。専門学校の頃から。吸い上げられて、何も残らない」
派遣社員だった10年の間に派遣先の歳上男性4人と不倫した。全員、妻が妊娠中だったり、子どもが産まれたばかりだったりした。最初につき合った人は30代半ばだった。おじさんだと思っていたが、今の麻希より若い。
どこまでが心の声で、どこからモリゾウに聞かせたのか、境界線が曖昧になっている。モリゾウには知られたくなかったことを、あえて口にして、彼を試している。嫌われてもいい、いっそ嫌われたほうがいい。そしたら、わたしもモリゾウを嫌いになれる。
モリゾウもあの人たちと同じなの?
違うなら、違うと言って。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第54回 多賀麻希(18)「回りくどい女が欲しかった一言」へ。
イラスト:ジョンジー敦子
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!






















































































































































































































































































































































































































































