
第181回 佐藤千佳子(61)シュークリーム即興劇
ドアを押し開けると、香ばしいにおいが立ち込めていた。「やってますか?」と声をかけると、カウンター席の先客ふたりが振り返り、千佳子も相手も「あっ」となった。
マキマキさんとパセリ先生、じゃなくてモリゾウさんだ。
「あ、マキマキらの家を世話してくれた人?」
カウンターの中に立つマスターが千佳子の顔を見て言った。存在感の薄さには自信がある千佳子だが、ちゃんと覚えられていたらしい。
「お世話してはないですけど、あのとき、いました」
アムステルダムから一時帰国中の野間さんに連れられて初めてこの店に来たとき、バイトで入っていたマキマキさんが引っ越し先を探していると聞き、「うちに住まない?」と野間さんが飛びついた。留守宅の管理を息子さんたちに託していたのだが、貴重な週末に横浜まで通うのが重荷だと訴えられ、代わりに家を見てくれる人を探していたのだった。
「今日は、たまたま?」とマスターが聞いた。
「たまたまです」と千佳子が言うと、マキマキさんとモリゾウさんの声も重なった。
ここに来ることになったのは、kirikabuに振られたからだった。店の前にのびる長い列を見て、「やめときます?」とサツキさんと顔を見合わせた。絵映えのするパンケーキがインスタで話題になるたび、行列がのびるのだが、しばらくすると落ち着く。モテ期みたいなもので、周期がある。
「こうなったら、遠出しちゃいます?」
サツキさんが言った。千佳子も近場のチェーン店で妥協したくない気持ちはあった。こっちにして正解だったと思える代案が欲しい。
「新宿御苑とか」
サツキさんの提案に「新宿御苑?」と思わず聞き返すと、「あ、遠い?」と言われた。
「いえ、ちょっとびっくりして。さっき話した人と去年、桜を見に行ったんです」と続けた。
さっき話した人というのは、野間さんのことだった。千佳子のチューリップバッグを見たサツキさんに「それ、どこの?」と聞かれ、パートの同僚だった人に贈られたオーダーメイド品だと話したのだった。

「新宿御苑の帰りに寄ったカフェで、バッグの作者さんがバイトしてて」
「じゃあ、そのお店に行ったら、作者さんに会えるの?」
「でも、今もバイトしているかどうか。あ、引っ越して、地元にいるので、良かったらつなぎます」
「じゃあ、そのカフェで何か食べてから新宿御苑に行きます?」
千佳子が「でも」と言っても、サツキさんは「じゃあ」とつなげる。
「でも、メニューがたしか気まぐれで。お店の場所もうろ覚えなんですけど」
「大丈夫。行ける気がします」
サツキさんは駅へ続く坂道をすたすたと歩き出した。サツキさんは、いつだって迷わない。自分は運がいいと信じられる人には幸運が寄ってくるというけれど、そういう人は運に見放されて痛い目に遭ったことがないのだと千佳子は思う。
新宿三丁目駅から新宿御苑のほうへ向かうと、見覚えのある「焙煎珈琲 然」の木の看板が目に留まった。やっているのかなとドアを開けてみたところ、いいにおいに迎えられ、地元ではなかなか会えないマキマキさんとモリゾウさんにまで会えた。
チューリップバッグに導かれたのか、サツキさんに導かれたのか。
隣にいるサツキさんを紹介すべきだろうか。でも、わたしだってここに来るのは2度目だし、と頭の中で足踏みをしていると、
「このにおい、シュークリームですね!」
答えを見つけたようにサツキさんが弾む声でマスターに話しかけた。体の前で控え目に指差した先、厨房の奥にシュー皮が並んでいる。
千佳子も見て、シュー皮を焼くにおいだったのかと答え合わせをする。メニューはなく、マスターの気まぐれなのだが、野間さんと来たとき、シュークリームはなかったはずだ。あのとき食べた台湾式サンドイッチを時々思い出す。ピーナツバターの甘さとベーコンのしょっぱさが絶妙だった。
「クリーム待ちのシューです」
マスターがとぼけた口調で言った。皮だけということだろうか。
「クリーム待ちのシュー」
サツキさんが復唱してから、「ふふっ」といたずらっぽく笑った。マスターの言葉を引き取って繰り返しただけで、企みを分かち合っているような親しみが生まれる。
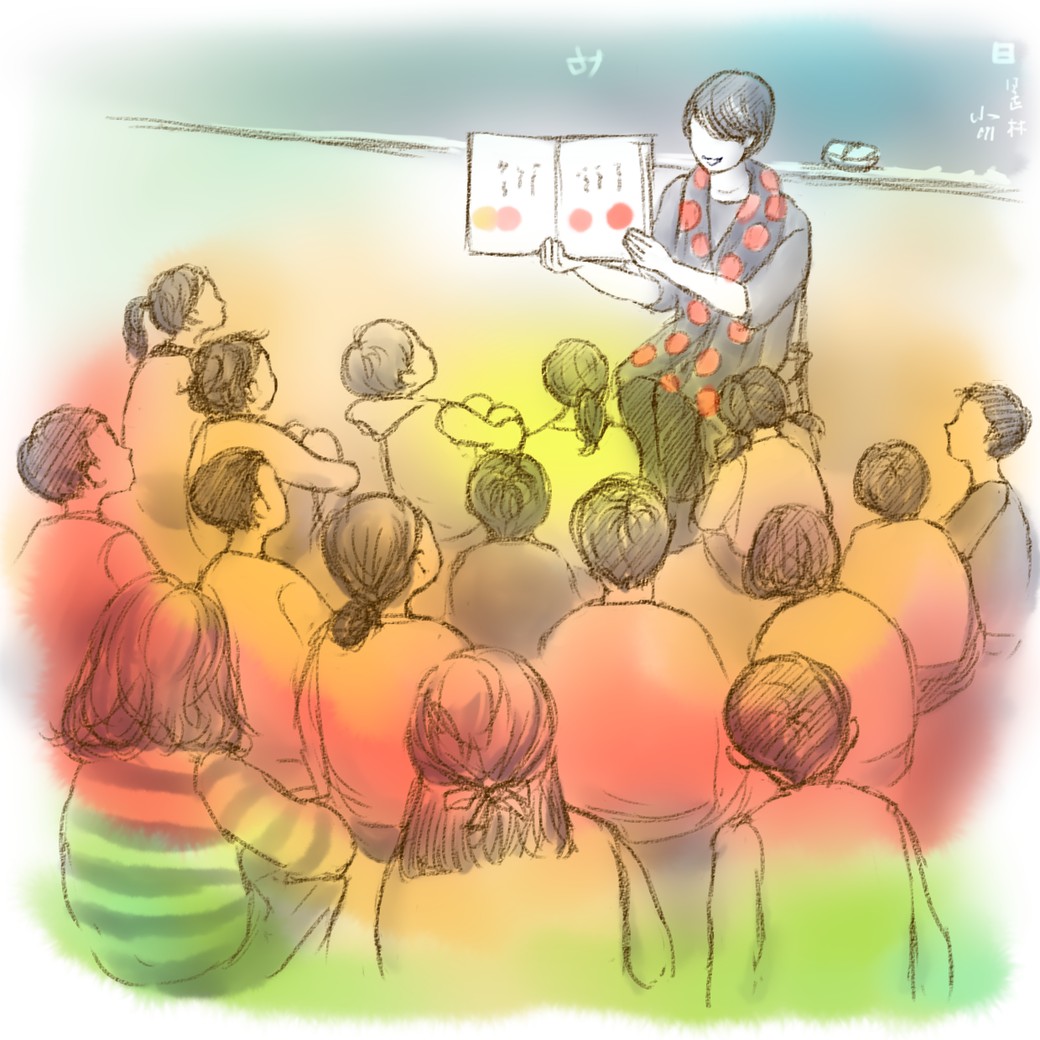
サツキさんのコートの襟元から、いつものスカーフの水玉模様がのぞいている。初めてのお店にも、スカーフみたいにふわりとなじんでしまう。千佳子より前からこの店に通って、ふふっと笑っている人みたいだ。
スカーフとストールの違いって何だったっけ。サツキさんが愛用しているのは、どっちなのだろう。日によってスカーフと思ったりストールと思ったりする。
「クリーム待ちのシュー」
モリゾウさんも重低音で繰り返す。声に出して言いたくなる言葉らしい。
千佳子は声に出さず、心の中でつぶやいてみる。マキマキさんもそんな顔をしている。今日を含めて顔を合わせたのは数えるほどしかないが、言葉を押し出すよりも飲み込むことのほうが多い人という印象がある。そこに勝手に親しみを感じている。
「私のシューは、たっぷりの生クリームとフルーツを待ってます。フルーツは、いちごとキウイがいいかな」
サツキさんが言った。kirikabuで食べたいと言っていたパンケーキのトッピングだと千佳子は気づく。
希望を伝えたら作ってくれるオーダーメイド・シューなのだろうか。そんなことはどこにも書いていないけど。
「佐藤さんは?」とサツキさんが千佳子を見た。
「わたしも生クリームとフルーツ、かな。フルーツは柑橘系」
「そっか。カスタードじゃなくてもありなんだ?」とマキマキさんが言った。
モリゾウさんなら、どんなクリームを詰めるだろう。パセリ先生のイメージでグリーンのクリームを想像する。ミント、ピスタチオ、メロン。アクセントにパセリを突き刺してみる。マスターはコーヒーのクリームだろうか。

「待ってるのはクリームとは限らんで。サラダ詰めてもええし」
マスターが言った。
「こう見えて、シューの皮じゃないかもしれない」
モリゾウさんが言った。
「実は貝殻だったりして」
サツキさんが言った。
「こういう貝、確かにあるな」
マスターが引き取った。
「カスタネットだったりして」
何を言っても受け入れられる空気が心地良くて千佳子が言うと、モリゾウさんが言った。
「それで言うと、エクレアって棺桶に似てますよね?」
「なんでカスタネットから棺桶? 木魚やったらわかるけど」
マスターに突っ込まれて、「上と下の色が違うから?」とマキマキさんが代わりに答えた。
自分の言葉が拾われて、思いがけない言葉につながるのが面白い。さいころの出た目で進んだり引き返したりが決まるすごろくに似た楽しさがある。
「なんか、演劇みたいですね」
「エチュードっぽいっすか?」
モリゾウさんが聞き返す。
「エチュード?」
今度は千佳子が聞き返す。さっきまでの弾むような会話にブレーキをかけてしまった気がして申し訳なくなる。
「与えられた設定で芝居をするんです。今の場合、何かを待っているシュー皮っていうのが設定で、そこに何を込めるかっていうセリフが引き出されているというわけです」
噛んで含めるようなモリゾウさんの口調に千佳子はなじみがある。オンライン学習講座で英語の構文を説明するときの口調だ。自分はよく知っていることを知らない人に理解してもらうために言葉を選び、ゆっくり話す。

「本の表紙にも似てますね」とサツキさんが言い、
「本やったら、何でも入るな」とマスターが言った。
そうだったと千佳子は思い出す。kirikabuのパンケーキにサツキさんを誘ったのは、お疲れさま会のつもりだった。
本読み隊再開は、サツキさんが思うようには進まなかった。いろいろ、あった。ゴタゴタも、あった。千佳子の前ではふわりふわりと受け流していたサツキさんだが、実は大変な思いをしていたのではないか、関わりたくないと思っているのではないかと心配だった。
でも、良かった。今でもうれしそうに本の話をするサツキさんのままだ。

次回3月1日に佐藤千佳子(62)を公開予定です。
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!




















































































































































































































































































































































































































































