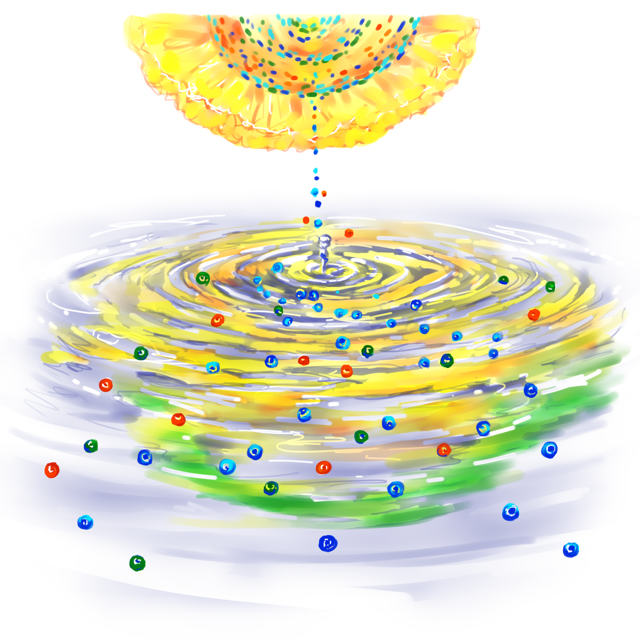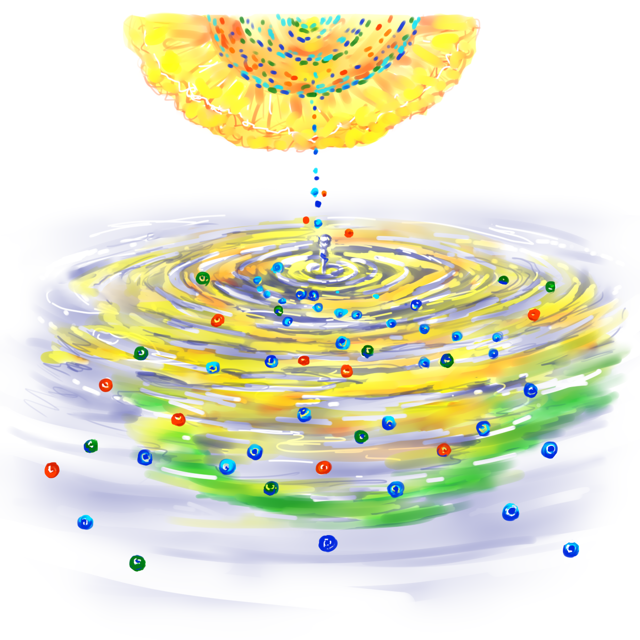第184回 伊澤直美(62)波風立ててどうする気?
ミラノ風カツレツがテーブルに運ばれ、「ごめんね」「タヌキは悪くないよ」を繰り返していたタヌキと直美の口はチーズのしたたるカツレツにしばし塞がれることになった。
「こうなるって、わかってたよね」
カツレツのふた切れ目を食べ終えて、タヌキが口を開いた。
「黙ってたら好き勝手言われて悪者にされてしまうけど、言い返したら長引くし、その分、傷つくし」
直美に向けて言っているのだろうか。アイラインを引いていないのにくっきりした切れ長の目は、カツレツに向けられている。
「うん」と直美は曖昧にうなずく。間延びして語尾が消え入りそうな、自信のない、肯定と否定と疑問が混ざったような「うん」。それから努めて明るく、冗談めかして言う。
「ケイティの信者って、今もいるんだね」
タヌキが披露宴に持って行ったひまわりバッグへの反応は、今もケイティを崇めている取り巻きたちの存在とその熱量をあぶり出しみたいに浮かび上がらせた。一日のうちに数百件のコメントがついたかつての勢いはない。
決まった数人が何度も書き込みに来ている。数が少なくなった分、一人一人が今まで以上に声を出していかなくてはという使命感に駆り立てられたかのように、コメントの一つ一つが長く熱い。ひまわりバッグを持ったタヌキとの写真をアップした新婦のインスタでケイティの擁護に躍起になっているのは、その数人だ。同じ顔ぶれのアイコンが並んでいる。
「なんか、もう必死だよね」
直美がそう言うと、タヌキが顔を上げた。
「どっちが?」
その言葉と今の状況に直美はデジャヴを覚える。
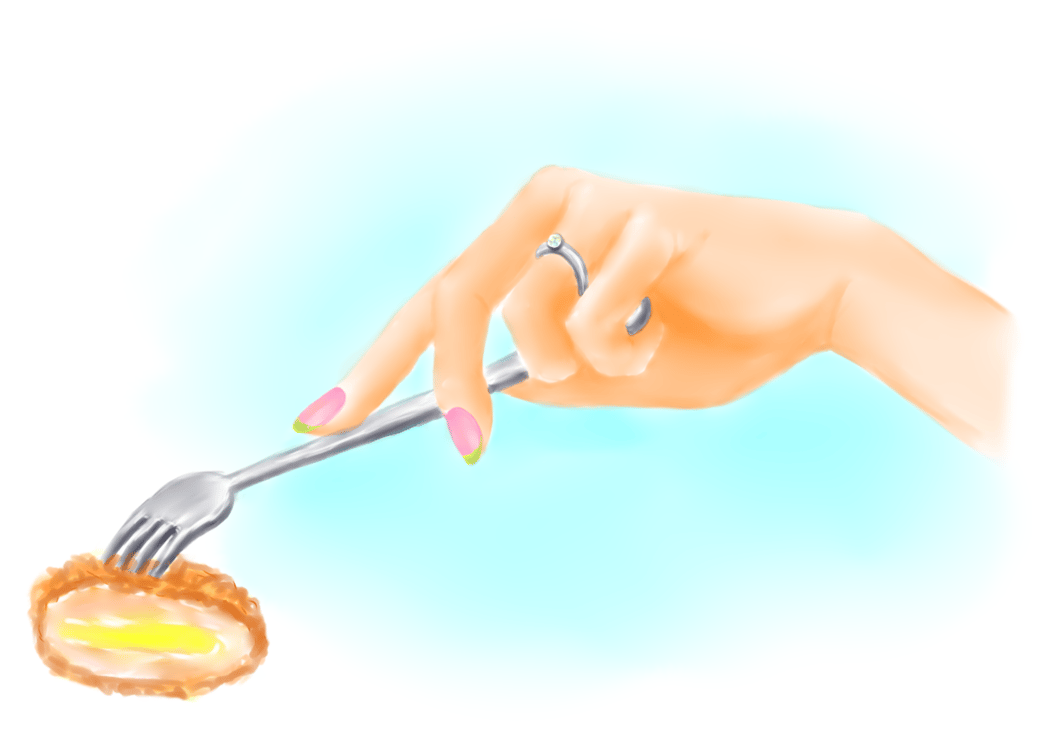
2年前の春、このテーブルでミラノ風カツレツを食べていたとき、タヌキに告げられた。
「ひまわりバッグの人に会ったよ」
6月に挙式を控えていたタヌキの指先は桜色のネイルに彩られていた。
「どっちの?」
あの日の直美は咄嗟に聞いた。
あの頃、ケイティのインスタを見た後にmakimakimorizoのサイトが更新されていないかを見に行くのが直美の日課になっていた。タヌキがどちらかの「ひまわりバッグの人」に会うとしたら、ケイティのほうだと思ったのだ。直美とケイティは住む世界が違うが、有名私大のミスキャンパスだったタヌキとなら接点はありそうだった。
だが、タヌキが会ったのは、亜子姉さんのひまわりバッグのほうの人だった。
「これが6万円ってどう思う?」と直美にひまわりバッグの写真を見せられたタヌキは、この作者にウェディングドレスのリフォームをお願いしたいと思ったという。
ひまわりバッグによく似たバッグをケイティが販売していることは知っているのかと、あのとき直美はタヌキに聞いた。
親切心で教えたのではなく、嫉妬心からだった。
あの頃の直美は、ひまわりバッグのことを追いかけることで満たされない何かを満たそうとしていた。初めての子育て。母乳を、睡眠を、本を読む時間を、観たかった映画を、捧げたすべてを成長に変えてくれる存在に報われていると思っていた。けれど、夫が何気なく言った「腹を貸したね」を思い出すたび、抉られた。積み上げてきたものが蝕まれ、崩れていくようだった。母親って吸い取られるだけの存在なんじゃないかと空しくなった。気を紛らわせたくて、ひまわりバッグのことを追いかけていた。
タヌキにひまわりバッグを教えたのは、わたしなのに、こんなにひまわりバッグのことばかり考えているのに。ネットをぐるぐる巡回しているだけで何もできないわたしを差し置いて、会いに行ってしまうなんて。ウェディングドレスなんて切り札、わたしには使えないのに。
面白くない。だから、ひまわりバッグにケチをつけた。ケイティのひまわりバッグのことは知らなかったとタヌキは言ったが、動じなかった。

「ケイティのひまわりバッグのこと、ほんとは知ってた」
直美の頭の中を見透かしたかのようにタヌキが言い、「だから会いに行ったの」と続けた。
「どういうこと?」
直美の質問に答える代わりに、「幸せのしっぽ、どう思った?」とタヌキは聞いた。
「可愛い映画だと思った」
当たり障りのない感想を伝えたが、内容をほとんど覚えていない。
タヌキに借りたままだったDVDをようやく観たのは、タヌキの結婚式の前の晩だった。イザオとギクシャクしていて、一人で観るつもりだったが、「何観てるの?」とイザオに聞かれ、タヌキが高校生の頃に何度も観た映画だと話した。
DVDのパッケージ写真、しっぽの生えたヒロインが着ている衣装は、スカートから飛び出したしっぽのまわりに大きな花があしらわれている。ひまわりではないが、花びらの色と質感がひまわりバッグを思わせる。同じ人がデザインを手がけたのではないかと直感したタヌキは、この人にウェディングドレスのリフォームをお願いしたいと思ったのだが、後日、ケイティがこの映画の衣装デザインに関わっていることをインスタで匂わせていたということも話した。
「ケイティって人が映画に関わっていると、なんか問題なわけ?」
イザオの反応は薄かった。
「亜子姉さんのバッグをデザインしたのもケイティの可能性が出てきちゃうじゃない?」
「ハラミは関係なくない?」
そう言いつつ、イザオは直美の隣に腰を下ろし、ソファが軽く沈んだ。一人になりたいと思いながら無言で画面を見つめ続けた。ウェディングドレスの依頼につながるほどタヌキには刺さった作品だが、直美の記憶に残っているのは、なんとも言えない気まずさとエンドロールの「衣装デザイン協力 ケイティ」だった。
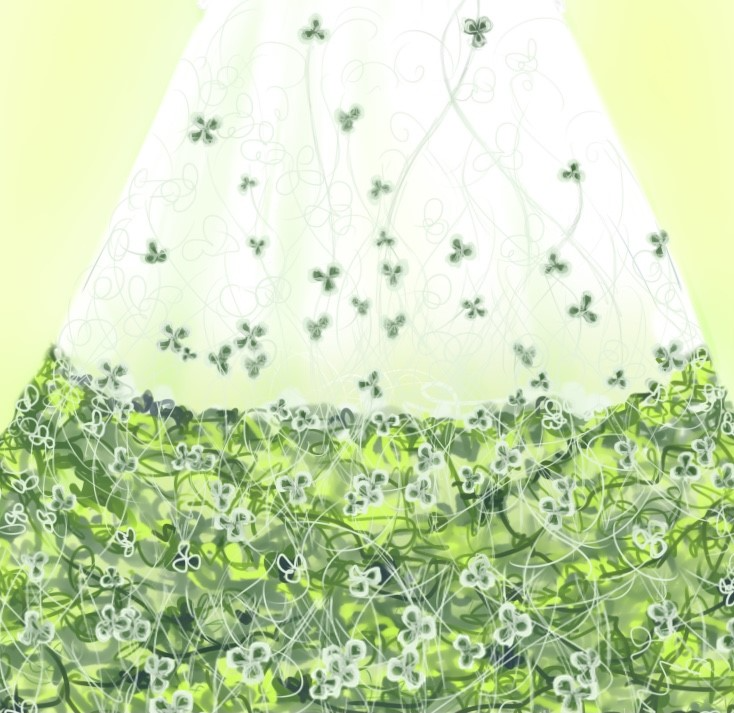
「究極のファンタジーだよね。しっぽなんて邪魔なだけなのに。目立つし、かさばるし、いらないことに巻き込まれるし」
まるで自分にしっぽがあって迷惑しているみたいにタヌキが言う。タヌキにしっぽはないけれど、余計な注目と興味を集める煩わしさを知っている。
『幸せのしっぽ』を繰り返し観ていた高校時代のタヌキの体重が80キロを超えていたことを直美は思い出す。目立って、かさばって、いらないことに巻き込まれていたのは、その頃のことを指しているのかもしれない。
直美は中学受験の結果が母を裏切る形となり、「お母さんの人生返して」と言われてからしばらく、母の出す料理を口に入れては吐き出していた。溜め込むか吐き出すかの違いはあるが、体を痛めつけるほど追い詰められた記憶を直美も体に刻んでいる。
「結婚式、自分たちのときぶりだったの。それでmakimakiさんに会いに行ったときのこと思い出してて。太陽の色のものを着けて欲しいって言われて、もしかしたらケイティのひまわりバッグを持って来る人がいるかもって思って。私がオリジナルを持って行ったらどうなるだろうって」
そこまで考えた上で、バッグを貸して欲しいと言ってきたのか。
「実はわたしも、タヌキに相談されたとき、似たようなこと思った」
「そうなんだ?」
「披露宴でひまわりバッグが鉢合わせするかもとは思わなかったけど、ケイティに伝わるかなって思った。ケイティはmakimakimorizoのバッグの持ち主が誰か、知らないから。タヌキみたいな人が持ってて話題になったら……」
直美がそこで言葉を区切ると、「なったら?」とタヌキが続きを促した。
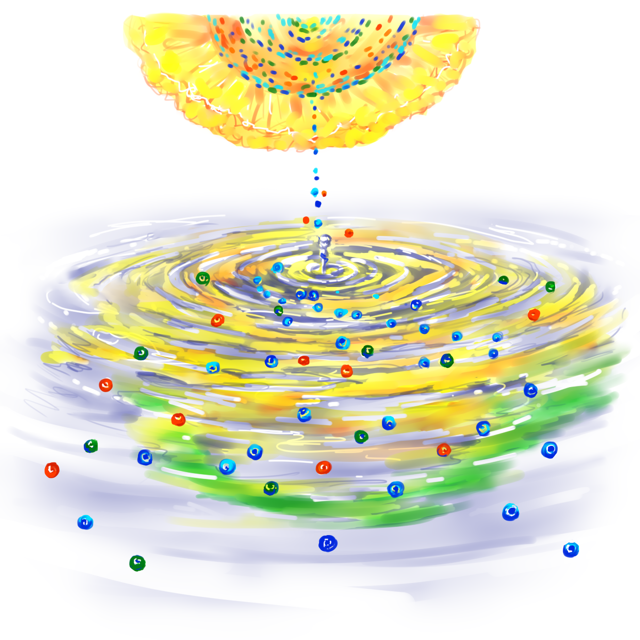
「困るっていうか、焦るっていうか、ザワザワするかなって」
実際、すでにケイティは新婦のインスタのことを聞きつけているだろうし、見ているだろう。こういう書き込みをしてねと頼んだり仕向けてたりしているかもしれない。別アカウントを作って、自ら書き込んでいる可能性もある。
その先に、何があるのだろう。波風を立てて、どうしたかったのだろう。わたしも、タヌキも。
「これ、どうやって収拾つけたらいいのかな」
「ごめんね」
「だから、タヌキは悪くないってば」
タヌキが謝り、直美が打ち消す。会話が振り出しに戻る。
「《こちらケイティがプロデュースしたバッグです》って書き込んだの、私だから」
驚いた直美の視線を打ち返すように、タヌキの切れ長の目がまっすぐ直美を見ていた。

次回4月5日に多賀麻希(61)を公開予定です。
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!