
第110回 佐藤千佳子(38)埋蔵主婦の値段
「卒業って!? 野間さん、マルフルやめちゃうんですか?」
「あー、やっぱり佐藤さん、そういう顔しちゃうよね」
そういう顔がどういう顔なのか、手元に鏡がないので見られないが、千佳子は今、野間さんが予想した顔をしているらしい。野間さんを困らせる、困った顔だ。
「マルフルやめて、どうするんですか? 転職、とか?」
野間さんは元々、外資系広告代理店で働いていた。結婚してからも仕事を続けていたが、ダンナさんの海外転勤について行くことになり、会社を離れた。野間さんは中断のつもりだったけれど、再開はなかった。2児の母になって帰国した野間さんの復職をダンナさんが渋ったからだ。下の子が小学校に上がったときには、元の会社に野間さんの戻る場所はなかった。一旦降りたキャリアのレールに戻りそびれた野間さんは専業主婦を続けることになった。
再び働くようになったのは、息子さん2人が独り立ちした後だ。定年退職後の再雇用の任期も終えたダンナさんが突然亡くなり、野間さんはマルフルで働き始めた。キャリアを活かすためではなく、持て余した時間とやりきれなさを埋めるために。
腰かけのつもりだったのが、思いのほか長く続いているともいえる。それは、時間をお金に替える以上のやり甲斐や張り合いを野間さんが作り出してきたからだ。自分で自分の仕事を面白くしてきたのだ。
「実はね、社外取締役にならないかって本部から声がかかったの」
「パートから取締役って、すごいじゃないですか。なーんだ、マルフルを卒業するって、パートをやめるってことだったんですね」
千佳子はほっとして、言葉があふれる。
「野間さん、広告のことわかってるし、英語もできるし、現場もわかってるし、最強ですよね。野間さんと一緒に仕事できなくなるのは淋しいけど、大出世、おめでとうございます」
乾杯をしようと千佳子がグラスを持ち上げると、
「違うの。それでやめる踏ん切りがついたの」
持ち上げたグラスとお祝いの言葉が宙に浮いた。
野間さんは「もう一本開けよっか」と冷蔵庫へワインを取りに行った。席を外す理由を作ったのかもしれない。
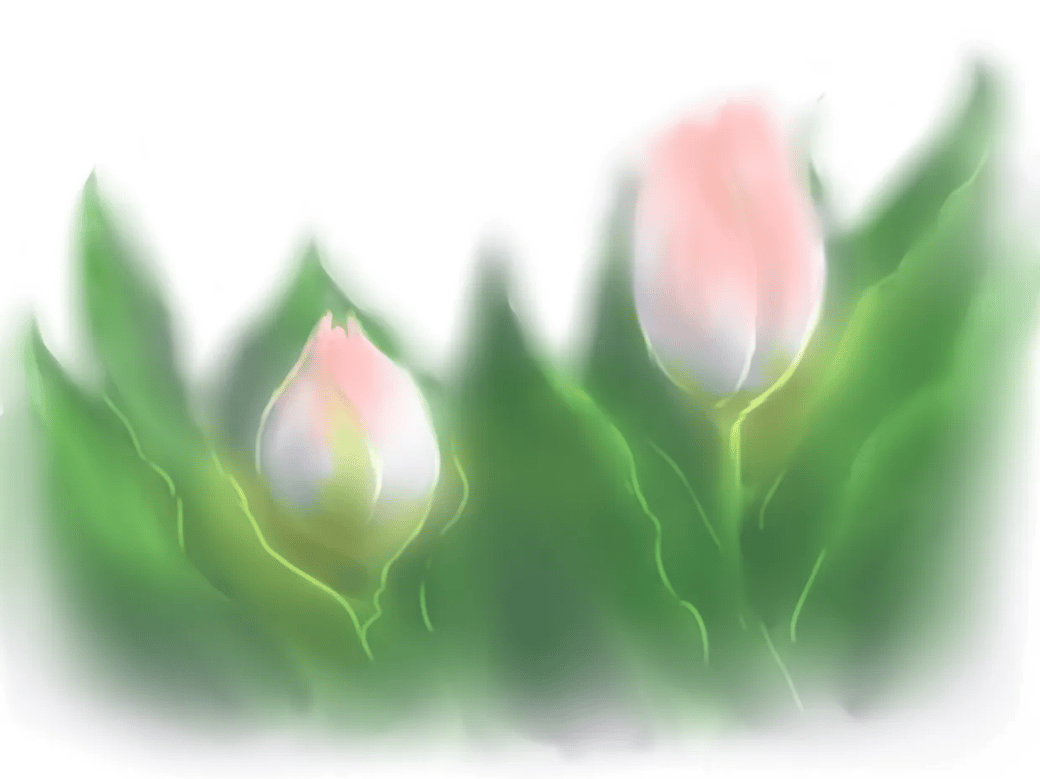
2本目のスパークリングワインのコルクを抜くと、1本目ほど威勢のいい音はしなかった。
「あれ? 気が抜けちゃってる?」
野間さんは、空いている自分のグラスに少しだけ注いで、味を見る。
「微発泡になっちゃってるけど、これはこれでありかな。佐藤さん、注いじゃうから飲んで」
ボトルを傾け、千佳子が飲み干したグラスと自分のグラスにワインを注ぎ終えると、野間さんはもう一度グラスに口をつけて、「やっぱり気が抜けてる」と言った。
千佳子は「そんなことないです。おいしいです」と言いつつ、確かに気が抜けているなと思う。野間さんがマルフルからいなくなる淋しさで、千佳子の気も抜けてしまっている。
「わたし、文香が高校に上がったら、シフトふやそうと思ってたんです」
「そっか。私は逆。これからは間引いていこうって。ハーブも、ぎゅうぎゅう詰めだと、よく育たないからね」
野間さんがノマリー・アントワネットの庭に目をやる。あの辺りがハーブガーデンなんだなと千佳子も目で追う。
「私さ、ずっとがんばってたじゃない?」
「がんばってましたね」
分厚いプレゼン資料を抱えて本部に乗り込んだ野間さんを千佳子は思い出す。パセリのクリスマスツリーの手柄を店長に横取りされたと思い込んだ野間さんは、あれは自分たちがやったことだとアピールすることに躍起になっていた。たかがパセリにリボンを巻いただけなのにと野間さんの必死さに千佳子の気持ちは冷め、一時期は野間さんと距離を置いた。
認められることへの情熱が人一倍低く、人より抜きん出ようとすることに罪悪感すら覚えてしまう千佳子にとって、認められるためにそこまでがんばる野間さんは、同じ言葉を話すけれど違う文化圏に生きている人のようだった。

「びっくりするような年俸を提示されて、その数字見たら、気が済んじゃった」
気の抜けたスパークリングワインをジュースみたいに飲みながら野間さんが言う。びっくりするような年俸っていくらぐらいなんだろう。うちの夫より当然多いんだろうなと千佳子は想像する。
「やっぱり、どこかで意地があったんだよね。あんたがいなくたって私は元気だし、あんたが埋もれさせた私は、こんなに仕事ができるんだぞって」
あれっと千佳子は思う。野間さんをがんばらせていたのは、ダンナさんへの意地だったのか。
「良かったです。野間さんのがんばりが認められて」
「まぁ、私に値段がついたわけじゃないけどね。私の利用価値に値段がついただけだから」
「どういうことですか?」
「『パートから社外取締役に』っていうタイトルで取材受けてる自分が想像できちゃったの。マルフルが変わりますって広告打つより、記事で取り上げてもらうほうが安上がりじゃない? びっくりするような年俸の何倍もの宣伝効果を見込めるならお釣りが来る。それが透けて見えちゃった。そうなると、私が元々外資系広告代理店で働いていたとか、英語ができるとか、そういうスペックは邪魔になっちゃうかもしれない。パートのおばちゃんを抜擢したっていうストーリーが欲しいだけ」
頭の回転にお酒の勢いが加わって、野間さんの言葉は演説みたいに力強い。
「そんな都合のいいことって、あるんですか」
「あるよ。私、そういうストーリーを提案してきた側だから」
野間さんはあちら側の人なのだと千佳子はあらためて思う。本当だったら同じ職場で働ける人じゃないのだ。同じテーブルで、お揃いのグラスでワイン飲んだりできる人じゃないのだ。
ハーブガーデンの手前でゴールドクレストが新緑の葉を茂らせている。ダンナさんが亡くなったお悔やみに贈られた木だ。
「私、もうすぐダンナが亡くなった歳に追いつくの。だから、これからの時間、好きなことだけに使わせてもらう」
「例えば?」
「旅行かな」
野間さんがダンナさんの木から視線を移した先、リビングの棚の上に置かれた地球儀があった。インテリアになじむレトロ調の色合い。アンティークだろうか。30年間の結婚生活を労ってもらう約束だったと野間さんが話していたのを千佳子は思い出す。あの地球儀を回しながら、旅の計画を温めていたのかもしれない。そのアテが外れてしまった。
「行きたい場所、あるんですか」
「そりゃあマリー・アントワネットの庭でしょう」
野間さんの長い寄り道は役目を終えた。ダンナさんが突然いなくなって持て余した時間を、もう埋めなくていい。ぶつける相手のいなくなった鬱屈を、もう仕事にぶつけなくていい。気が抜けて、力が抜けたら、縮こまっていた羽を伸ばす余白ができた。
卒業おめでとう、野間さん。
千佳子はグラスを持ち上げ、心の中で小さく乾杯し、祝福を贈る。
野間さんに。庭のゴールドクレストの木に。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第111回 伊澤直美(37)「四つ葉のクローバーに胸がざわつく」へ。
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!
























































































































































































































































































































































































































































