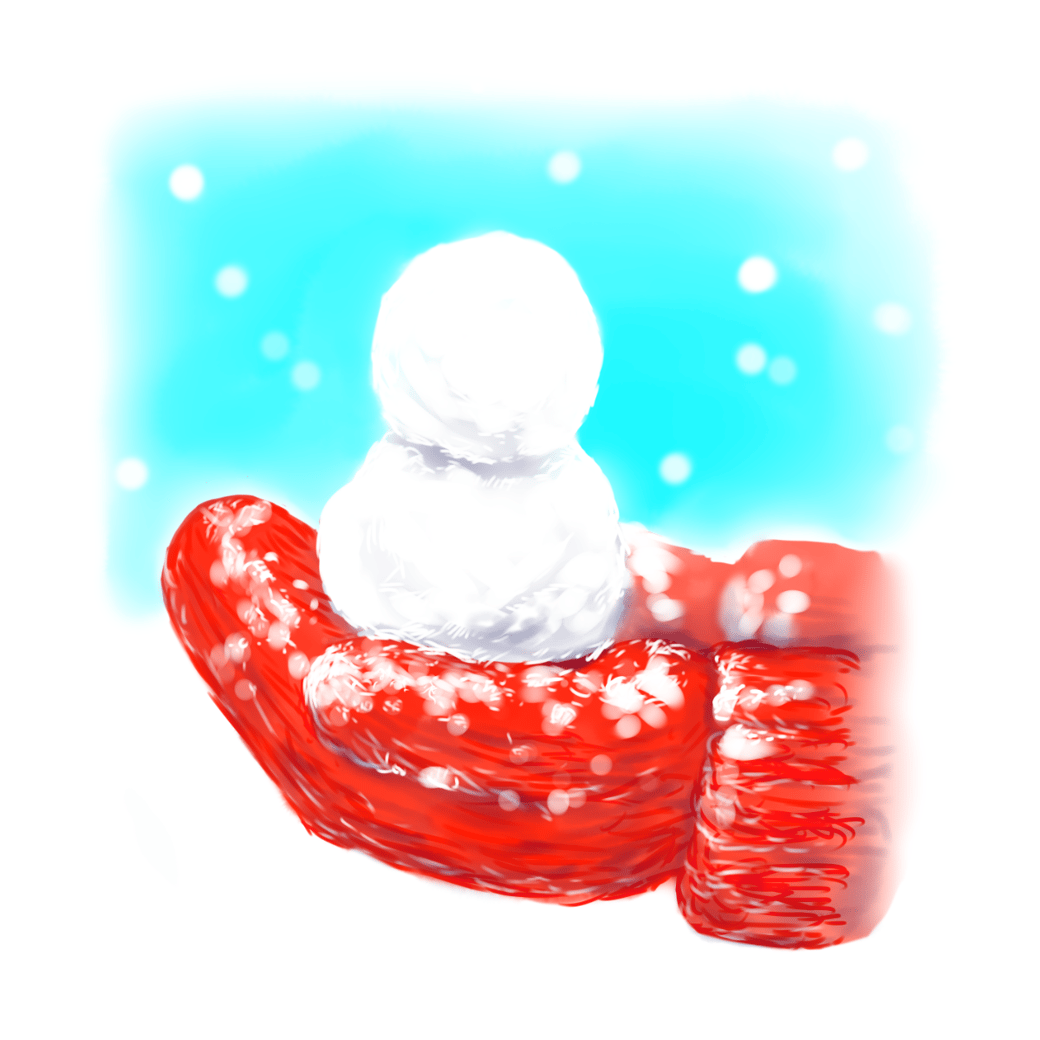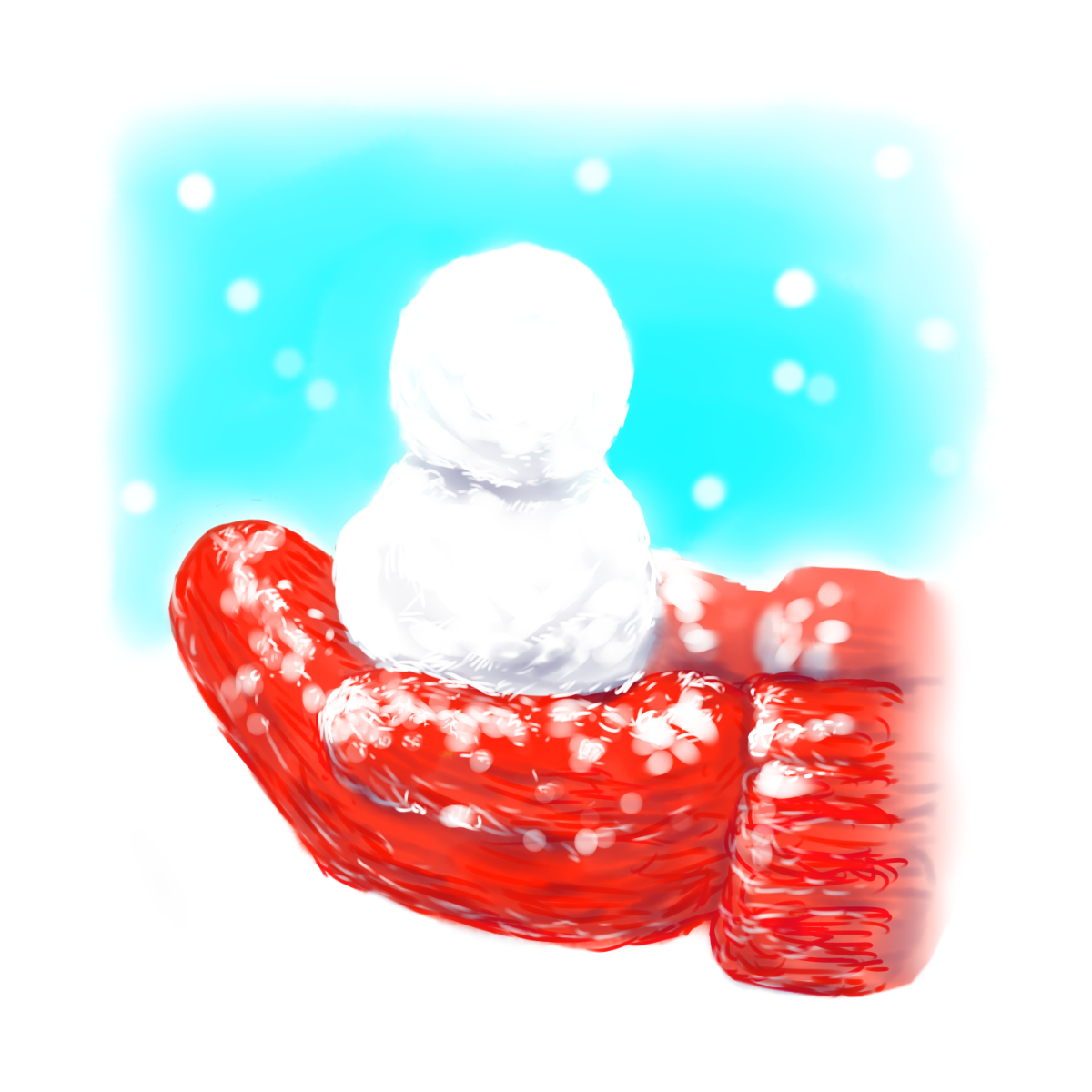第102回 多賀麻希(34)呪うより祝うほうがめでたいから
駅でモリゾウと落ち合い、歩き出す。麻希がモリゾウのコートのポケットに手を突っ込むと、「あったかいの?」とモリゾウが聞いた。「あったかいよ」と答えると、モリゾウも手を突っ込んで、ポケットの中で重なり合ったお互いの手に「冷たい」と声を上げて笑い合った。
何気ないやりとりが、あたたかい。朝、モリゾウが出かけてから誰とも口をきいていなかった。
「耳鼻咽喉科」の看板が貼りついた電柱を通り過ぎ、酒屋の前に差しかかる。「じびいんこうか」の漢字を読めず、「じーびーか」と読んでいた子ども時代の思い出話からの連想で地ビールを買い求め、麻希の部屋で飲み、そのままモリゾウが部屋に居着いたあの日、人ひとり分の距離を空けて並んで歩いた道を、今は体を寄せ合って歩いている。
「真っ直ぐ、うち帰る?」と麻希が聞くと、
「歩こっか」とモリゾウが言った。
もう少し外の空気を吸おっかと言われた気がする。
「どっか行く?」
歩くのが目的だとわかっているのに、聞いてみる。
「シュークリーム買いに行く?」とモリゾウが言った。
「なんもお祝いすることないのに?」
シュークリームは、麻希にとって、ごほうびに食べるものだった。シュークリームで幸せを数えながら大きくなった。モリゾウにその話をしてからは、ふたりにとって、シュークリームがごほうびの単位になった。ひまわりバッグが6万円で売れたときは、パティスリーのシュークリームを奮発した。
子どもの頃は、たくさん食べることで満たされた。今は、シュークリームを食べながら、この後、口に残ったクリームをモリゾウと分け合うのだろうかと考える。シュークリームを食べると、キスをして、その先にもつれ込む確率が高い。モリゾウとはしばらく、そういうことになっていない。最後がいつだったか思い出せない。ケイティのせいですべてに無気力になって、日付の感覚もおかしくなっているし、シュークリームを食べるようなめでたい出来事もないから、キスもその続きもない。だから、モリゾウの「シュークリームを買いに行く?」が麻希の中で「今日、する?」に変換される。モリゾウは全然そんなつもりじゃないかもしれないのに。
なんだろ。埋め合わせを求めているのかな、わたし。

シュークリームがきっかけで久しぶりに唇を重ねて、体を重ねたら、その再開はお祝いすべきかもしれない。事が起こるのはシュークリームを食べた後だけど。
「祝うこと、あるよ。フォロワー100万人のインフルエンサーがデザインを盗みたくなるバッグを作った」
「それ全然めでたい話じゃないし。フォロワー100万人ったって、YouTubeとかインスタとかフォローできるもの手当たり次第足し上げて100万人だからね。ケイティって、自己プロデュースの天才だから」
「その100万人に向けて、マキマキから盗んだデザインを売り込んでる」
「本人は盗んだ自覚ないんじゃない? わたしのデザインは著作権フリーだって思ってる」
言葉が尖っているのを麻希は自覚する。エゴサしすぎたせいかもしれない。
「お金の話をしたら、自分のデザインじゃないって認めてしまうことになるから」
「どうかなー」
「ほんとなら、盗みたくないんだよ。自分で生み出せるなら、マキマキのデザインを使う必要はないんだから」
だからシュークリームで祝う価値があるのだとモリゾウは言った。
「なんでモリゾウはいちいちおめでたい方向に持っていくわけ?」
「呪うより祝うほうがめでたいから」
「へ?」と間抜けな声が出た。「呪う」という言葉が唐突で、「呪う」「祝う」「めでたい」のつながりも芝居がかっている。
「それ、なんかのセリフ?」と聞くと、
「俺もマキマキと似たようなことあって」と答えになっていない返事があった。
「似たようなことって?」
「シモキタで昼夜2日だけやった舞台があって。そっから半年ぐらいして始まった連ドラが、そっくりで。医療ミスで記憶の蓄積ができなくなった夫とその妻の話だったんだけど、結婚前のヒロインとその婚約者に置き換えられてた」
「最近?」
「ううん。マキマキに会う前。5年、もうちょい前かな。
『雪だるまの涙』というドラマのタイトルを、口にするのも辛そうにモリゾウは告げた。それから、『たとえこの雪が溶けてしまうとしても』という元のタイトルを告げた。
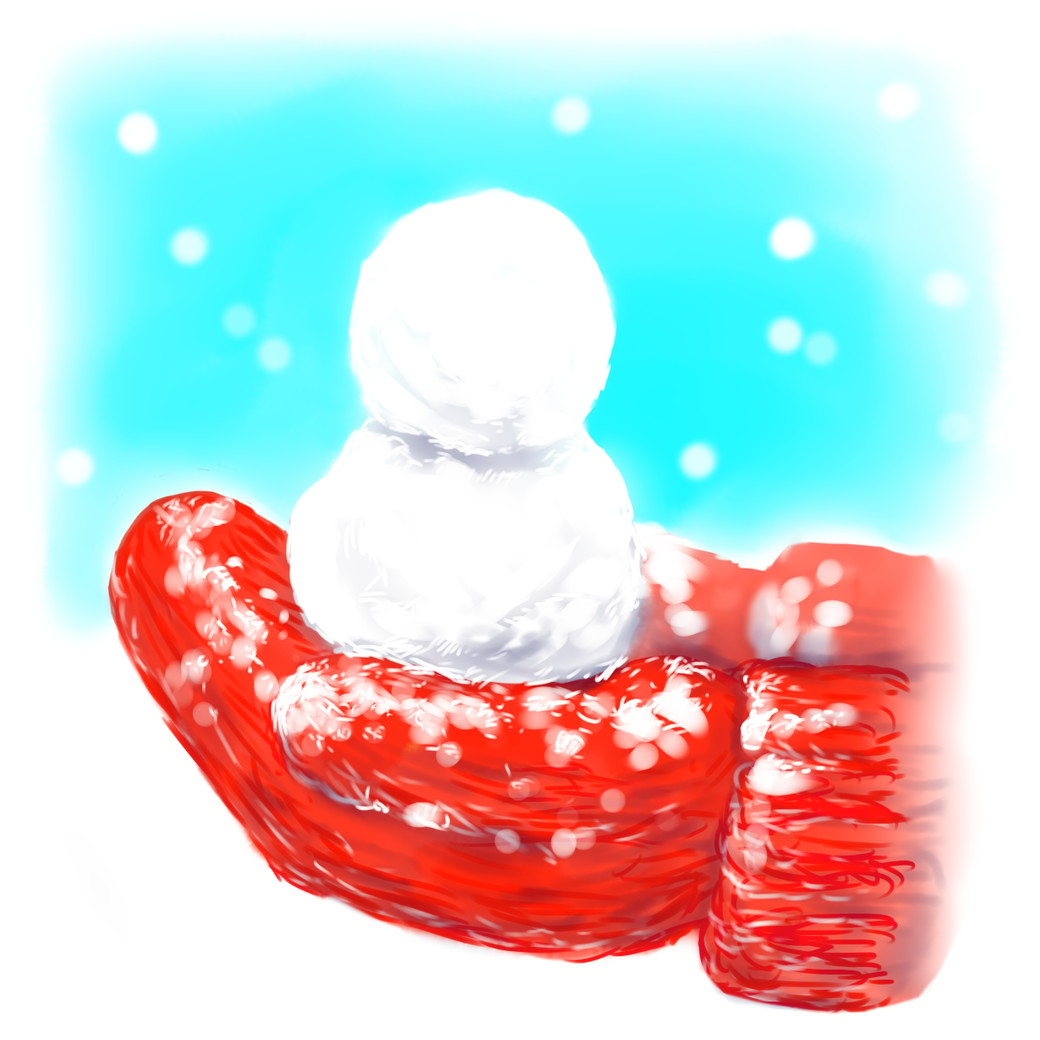
「登場人物の名前も年齢も職業も違うし、セリフも全部取っ替えてるけど、リフォームしても間取りは変わってない家っていうか、メロディは違うけどコード進行は同じ曲っていうか。そしたら、そのドラマのプロデューサーが舞台見に来てたことがわかって」
「その人に問い合わせしたの?」
「出演者の一人がプロデューサーに頼んで見に来てもらってたから、そいつから本人に聞いてもらおうとしたんだけど、似てるのは雪だるまだけだってそいつが言って。消え行く記憶を押しとどめるように雪だるまを固めるってとこが肝だけど、そんなの誰でも思いつくって。今思えば、プロデューサーとの関係にヒビ入れたくなかったんだろな。けど、そのドラマのサイトにあったプロデューサーのコメントが、俺らの舞台のチラシに書いてた言葉とまんま同じだった」
「なんて書いてあったの?」
「《生きるとは、出会った人の中に記憶を残すこと。それができなくなった人生に意味はあるのだろうか》。一言一句同じでさ。そんな偶然あるわけない。それで再演したら、あのドラマに似てるって感想ばっかりで。なんか、わからなくなってしまって。俺の作品って、なんなんだろ。俺って、なんなんだろって」
モリゾウが押し黙る。ポケットの中でつないだ手が悔しさにギュッと硬くなる。わかるよと言うように麻希もギュッと握り返す。
「俺もエゴサしてた。あの頃」
「うん」
「検索ワードを変えても、俺が探している言葉は見つからなくて」
「うん」
「そもそも何を探しているのかもわからなくて」
「うん」
「雪だるまのシーンがほめられてると、俺が考えたのにって悔しいし、ドラマが酷評されたところで、俺は何も得しないし」
「うん」
「その作品や、それを作ったヤツらが不幸になっても、俺は幸せにはならないんだなって。だったら、呪うより祝うほうがめでたいよなって」
「うん」
そうだね。そう思えたら、ラクになれるかもしれない。
「呪うより祝うほうがめでたい」と麻希はおまじないのように口の中で繰り返す。
「って俺に言ったのはマスターなんだけど」
「マスター?」
「今日、マキマキがバイト行ってたら、マスターがこの話、したと思う」
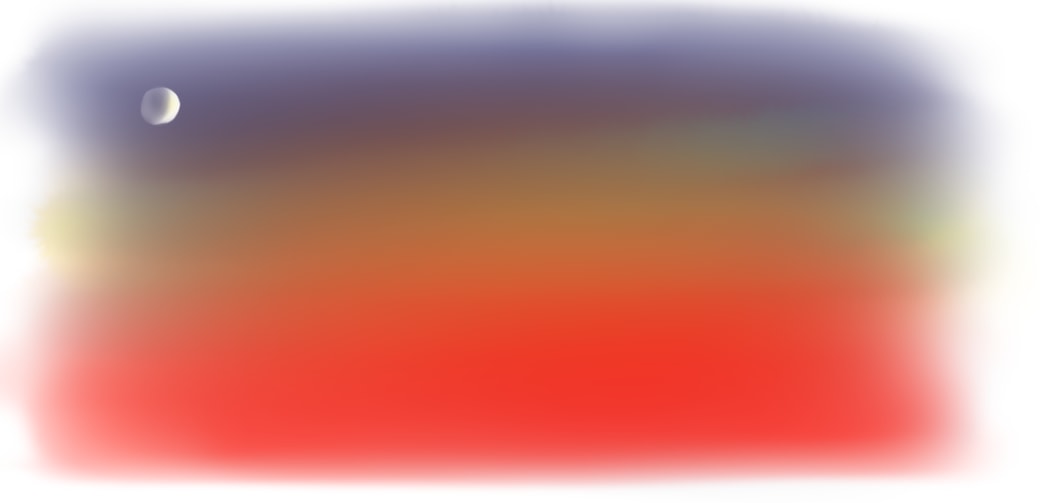
モリゾウが初めて新宿三丁目のカフェを訪ねた日、他の客はおらず、カウンターの中にマスターがいるだけだった。エゴサが止まらなくなっていたモリゾウに「取り替えよか」とマスターが声をかけ、ようやくスマホから顔を上げると、「冷めてしもたやろ」とマスターは口をつけていないコーヒーに目をやった。
2杯目のコーヒーを淹れながら、「なんか、探しもん?」とマスターは聞いた。
誰にも言えなかった話をこの人なら聞いてくれると思った。名もない演劇人の書いたホンを盗まれた悔しさを打ち明けた。
「タダでも、いらんもんは、いらん。盗んででも手に入れたいもんをあんたがこしらえた、いうことや」
話を聞き終えたマスターが、そう言った。
「おめでたいですね」と返したモリゾウに、「そら、呪うより祝うほうがめでたいで」とマスターは言ったのだと、あまり似ていない大阪弁でモリゾウが再現した。
「マキマキは盗んででも手に入れたいものを生み出した。そのことは、祝う価値があると思う」
こぼれ落ちそうになった涙を誤魔化すように「シュークリーム、買いに行こっか」と明るく言って、ポケットの中で握り直したモリゾウの手を引いた。
茜色に染まった空の下をパティスリーに向かって歩く。
そんな簡単に割り切れる話じゃない。モリゾウだって、きっとまだ割り切れてない。だけど、今日のところは、呪うより祝おう。ごほうびのシュークリームを好きな人と買いに行き、一緒に食べ、口に残ったクリームを分け合おう。ケイティの知らないキスをわたしは知っている。ケイティが持っていないものをわたしは持っている。ひまわりバッグの他に。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第103回 佐藤千佳子(35)「そのままのあなたでいいんです」へ。
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!