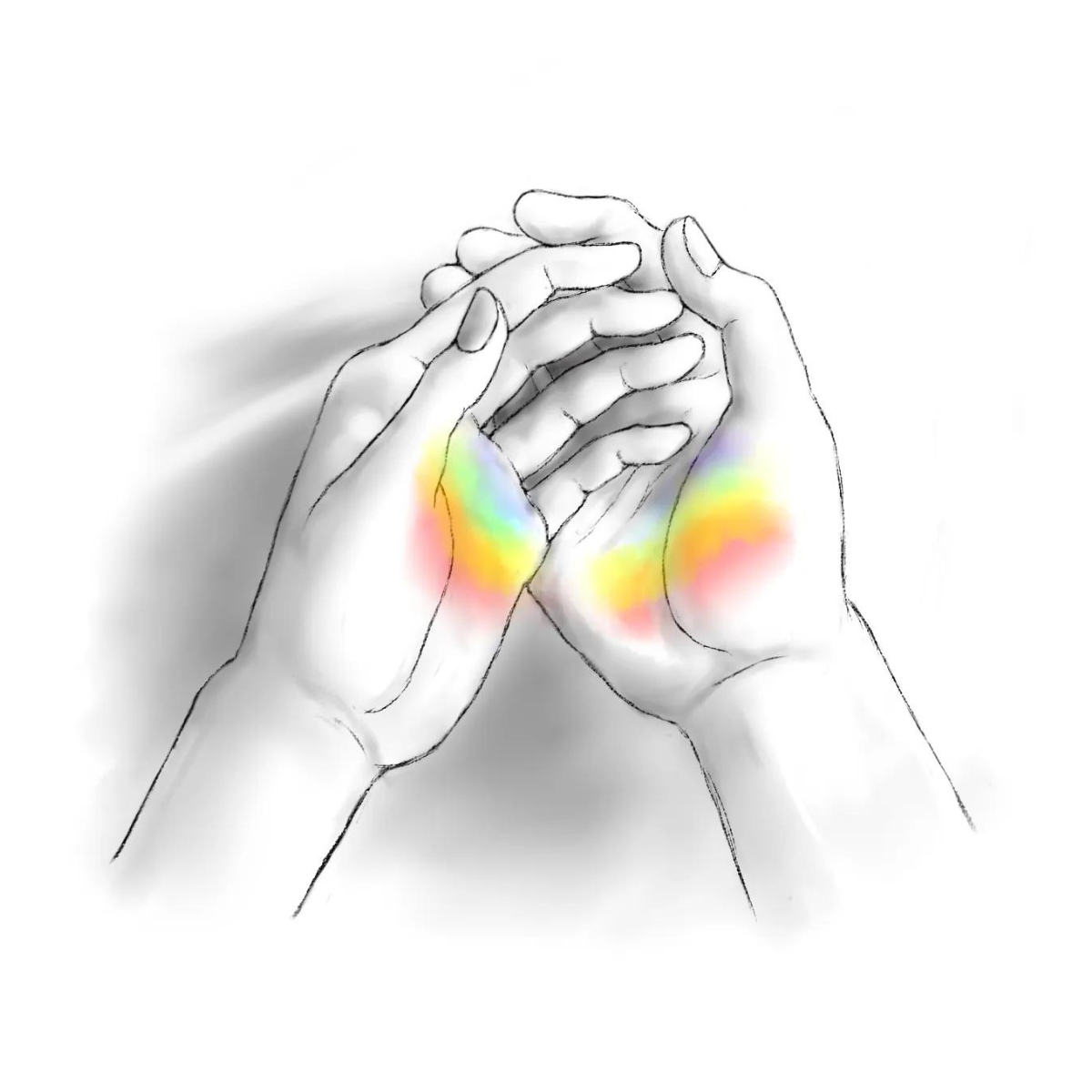第22回 伊澤直美(8) 子どもよりわたしを欲しがってよ
「イザオ、聞いた?」
「聞いた!」
「びっくりだよねー」
1週間ぶりに聞くイザオの声は弾んでいた。もちろん直美の声も。
「マトメにもおめでとうって言っといて」
「直接聞くよ!」
スマホから聞こえるイザオの声がマトメの声に代わったかと思うと、同時にステレオで近づいてきた。振り返ると、イザオとマトメがリビングに現れた。
「ちょっとタイミング良すぎ。うちの前で待ち構えてたの?」と直美が驚くと、
「タヌキ迎えに来たついでにダンナ返しに来た」とマトメがイザオの背中を押し出した。
「マトメ、会いたかったよー」とタヌキがマトメに抱きつく。
「ほらやっぱり酔っ払ってる。帰るぞ」
「まずは乾杯でしょー。ハラミ、私が持って来た泡!」
「それとっくに空いたから。マトメ座って。タヌキにはお茶淹れる!」
イザオとふたりきりになるより、友人の存在がクッションになってくれた。しかも、話題まで提供してくれた。
「このまま結婚しないのかなってイザオと話してたんだよ。長かったよね。つき合って4年だっけ」
「俺らの結婚期間と同じだよ」
「そうだ。3次会の帰りのタクシーでまとまったんだった」
「ハラミとイザオのほうが長いこと煮え切らなかっただろ」
「そうそう。この4人で飲んでて、マトメがけしかけたんだよね。お前ら、いつ結婚するんだよって」
マトメとタヌキに言われて、思い出す。入社してすぐにつき合い始め、イザオが転がり込んだ直美のワンルームで飲んでいた。いつかは結婚するんだろなと思いつつ、その「いつか」が来ないまま、入社8年目の春を迎えていた。
「6月に挙げちゃえよ」とマトメが言い出し、次の週から4人で式場を探し始めた。イザオと直美の結婚にかこつけてタヌキとの距離を詰めようとしたマトメが先延ばしの呪いを解いたのだ。
「あのとき俺がけしかけてなかったら、結婚しないまま長すぎた春が終わってたかもな。感謝しろよイザオ」
「マトメだって、俺らが結婚してなかったら、タヌキとつき合ってないだろ」
「その恩は今回で返した」
「あのねー、恩を返して余りあるよ。人の彼氏んち乗っ取りやがって。イザオ、私たちの結婚パーティーで汗かいてもらうからね。ハラミもだよ」
「もちろん」
「わ、壊れてる!」
テーブルに出したままの「H」と「APPY」をマトメが見つけた。
「俺らのパーティーでも飾ろうと思ったのに。これ、俺がちまちま苔貼りつけたんだよ」
「マトメが? タヌキじゃなかったの?」
「タヌキじゃないよ。俺」
「私も手伝ったよね?」
「タヌキ、致命的に手先不器用だから。ミスキャンパスのプロフィールに趣味刺繍とか書いてたけど、大ウソ」
「マトメ黙れ。唇ふさぐぞ」
「はいはい、帰るよ」
「おんぶ~」
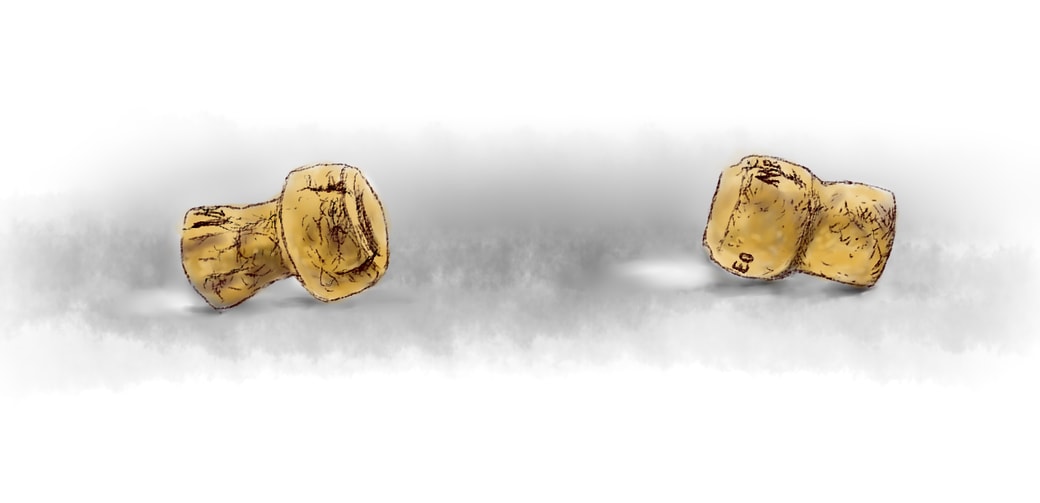
水の音に目を覚ますと、朝だった。ソファで寝てしまっていた。昨夜空けたスパークリングワインのコルクが、向かい合って床に転がっている。マトメとハラミはいなくなっていた。
水の音はキッチンからだった。イザオがワイングラスを洗っている。キッチンに立つイザオを見るのも1週間ぶりだ。
「起きた?」
「おはよう」
「なんか食べる?」
「とりあえずコーヒー」
イザオが淹れてくれるコーヒーを飲みたかった。
「あと甘いもの。タヌキが持って来てくれたピーカンナッツがあったはず」
「あれ昨日食べたよ」
「食べちゃったの?」
「いや、ハラミが食べてた」
「嘘……あれ? 何このにおい?」
においのするほうへ近づくと、接着剤のチューブのふたが開いたまま、テーブルに出ていた。「H」と「APPY」がくっつけられ、つなぎ目から接着剤がはみ出している。
「これやったの、タヌキ?」
「ハラミだよ」
「わたし? 覚えてない」
「だろうね」
「うわー酔っ払いの仕事だ。タヌキとマトメのパーティーで飾るのは絶望的だね」
「その話は覚えてるんだ?」
「うん。幸せそうだったね。タヌキとマトメ」
「あのふたり、似てきたよな」
「思った。今が一番いいときだよねー」
言ってしまってから、ハッとなってイザオを見たが、イザオは聞き流してくれた。
何の気なしに言ってしまうことって、ある。わたしも、イザオも。
いちいち目くじら立てていたら、年中ぶつかってしまう。それは直美もわかっている。だけど、普段は受け流せることがトゲになって、チクチクすることがある。こじらせると、傷口が膿んでジクジクする。
不恰好な「HAPPY」のつなぎ目が、かさぶたに見えた。

接着剤のふたを閉めると、イザオが淹れてくれたコーヒーの香りが届いた。1週間ぶりに夫婦で向き合って、コーヒーを飲む。
「イザオがいない間、うちでコーヒー飲まなかった」
「豆置いてる場所わからなかった?」
「わたしが淹れてもおいしくないし」
一人で飲んでもおいしくないし。
「わたし、自分だけ損するのが許せなかったんだよね」
「うん」
「子どもができたらクロスバイクなんてしばらく乗れないし、コーヒーもお酒もわたしだけ我慢しなきゃいけないし」
「じゃあ俺も我慢する。ハラミが飲めるようになるまで、お酒もコーヒーも飲まない」
「そういうことじゃなかった」
「え?」
イザオに同じ不自由を味わって欲しいわけじゃなかった。子どもを産んだら失うもの。それを恐れる気持ち。だから踏み出せないこと。イザオにわかって欲しかった。分かち合って欲しかった。それだけ。
「子どもか自転車どっちかにしてって言ったけど、子どもかわたしだったんだなって」
産むか産まないか、そのことばかりを気にするイザオに、女として見られていない淋しさを覚えた。「子どもどうする?」の前に、「わたしたちどうなってるの?」とモヤモヤしていた。リフォームを終えたこの部屋に引っ越して来た一昨年の秋、まだ寝室にカーテンをつけてなくて、窓のない廊下で交わった。それが最後。
「子ども欲しがるよりわたしを欲しがってよって言いたかったけど、言えなくて、違うぶつけ方してた」
「ハラミ、そんな可愛いこと思ってたんだ?」
「ハラミって呼ばれるのも、引っかかってた」
「え?」
「孕みって漢字を連想しちゃって、落ち着かなかった」
「あ、ごめん」
「今は大丈夫だけど、それだけ敏感になってた」
ジクジクしていた傷口がかさぶたになって、ヒリヒリしなくなった。またいつはがれるかわからないけれど。
「ずっと女の子なんだね」
「そうだよ」
恋人だったのが夫婦になり、子どもが生まれて父親と母親になって、互いを「ママ」「パパ」と呼ぶようになっても、変わらないものがあることを確かめたかった。ただそれだけのために、すれ違ったり、ぶつかったり、ずいぶん遠回りをした。
「見て! 虹!」
突然、イザオが子どもみたいにはしゃいだ声を上げた。イザオの視線は、窓の外ではなく、ソファの上に向けられている。プリズムを通したみたいに、光が虹色になって落ちている。
吸い寄せられるようにソファに近づき、光の先に手をかざすと、直美の手にも、イザオの手にも、虹が落ちた。
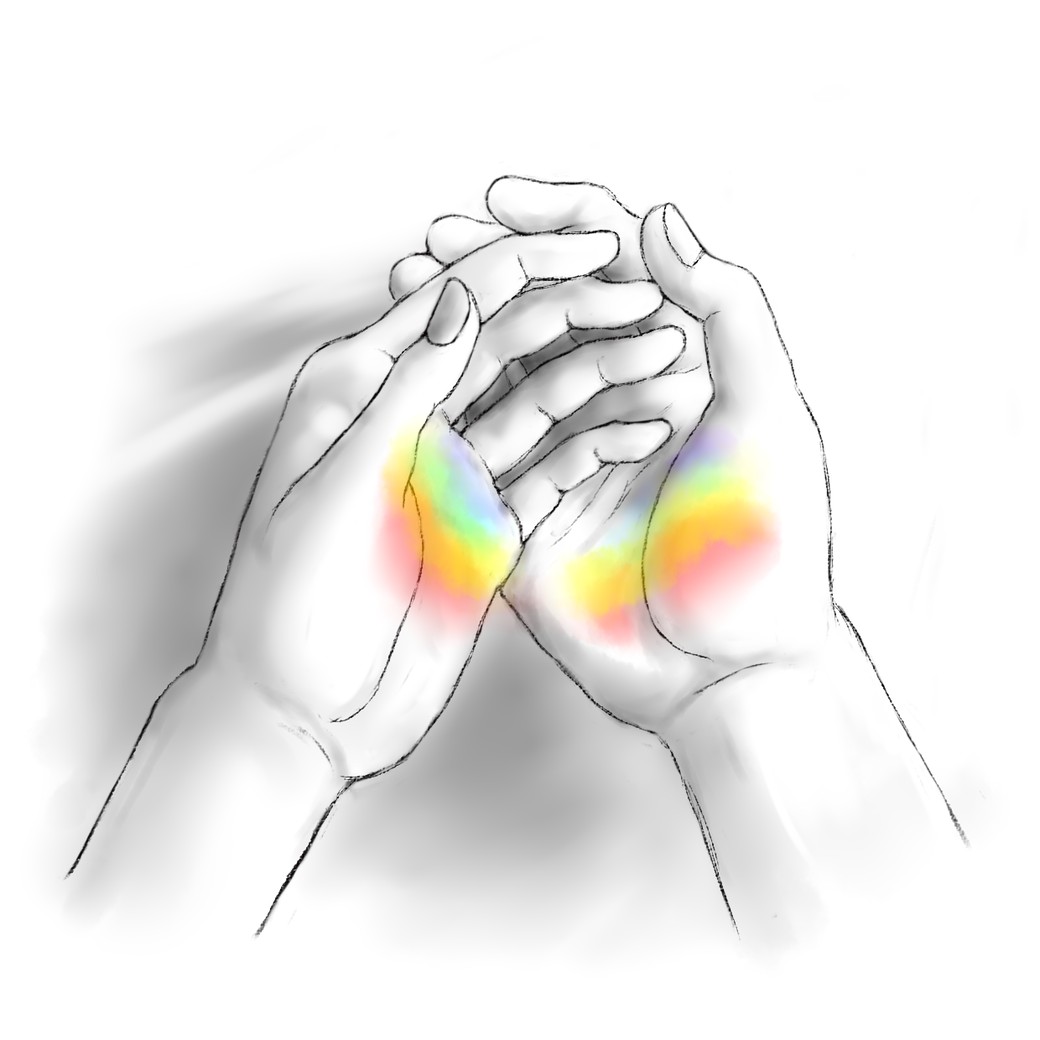
どちらからともなく手と手を取り合う。ふたりの間に虹がかかる。指を絡めて、離れないように鍵をかける。イザオの空いている手に引き寄せられ、
「直美」
名前を呼ばれた。イザオをどんどん好きになった頃の甘酸っぱい気持ちが蘇る。ふたりで会うときは、同期入社組でつけたあだ名ではなく「直美」「伊澤君」と呼び合っていた。
「伊澤君」
「懐かしい」
イザオの生温かい息とコーヒーのにおいが近づいて、直美は目を閉じる。イザオの唇が触れる。まぶたの奥に虹がかかった。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第23回 多賀麻希(7)「最後の恋人によく似た彼」へ。
イラスト:ジョンジー敦子
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!