
第103回 佐藤千佳子(35)そのままのあなたでいいんです
駅前の紅茶専門店で千佳子がサンプルの茶葉の香りを嗅いでいると、自動ドアが開く音がして、コツコツと杖をつく音と足音が入ってきた。白杖をつくカズサさんの姿が思い浮かんで振り返ると、本当にカズサさんだった。
「カズサさん!」
久しぶりで、懐かしさが手伝い、声が大きくなった。
「佐藤さんですか?」とカズサさんが声を頼りに千佳子のほうへ近づいて来た。
「カズサさん、このお店、よくいらっしゃるんですか?」
「はい。ここの紅茶の香りが大好きなんです」
「わたし、初めてなんです。おすすめがあったら教えてください」
いいですよと言って、カズサさんが好みを聞いてくれた。
「柑橘系の香りがするものを」とリクエストすると、
「だったら、いいのがあります。オレンジの皮が入ってるんですけど」
そう言いながら、カズサさんは白杖を持っていないほうの手を棚に沿わせ、目当ての紅茶のある棚を探り当てた。よく見ると、棚に透明なテープが貼られていて、点字が打たれている。それが商品名を示しているらしい。常連客のカズサさんのために用意されたものなのか、配慮のある店だからカズサさんが通うようになったのか、どちらが先なのだろうと千佳子は考える。
パート先のスーパーの商品棚にも点字をつけたほうがいいのだろうか。途方もない点数の商品を思うと、一人では対応できない。
目当ての紅茶のサンプルの茶葉が入った缶をカズサさんが手に取り、ふたを開けると、閉じ込められていたオレンジの香りが放たれた。
「うわあ。オレンジだ」
「でしょ? むっちゃオレンジですよね」
カズサさんはお決まりの茶葉を選ぶと、スマホをかざして決済を済ませた。電子マネーのアプリを呼び出すのにいつもまごついてしまう千佳子よりも手慣れていてスマートだ。
一緒に店を出て、カズサさんに腕をつかんでもらい、バス停に向かって歩き出すと、
「佐藤さん、いいにおい、しません?」
カズサさんが立ち止まった。漂ってくるにおいに千佳子が注意を向けると、甘く香ばしいにおいが鼻腔をくすぐった。
「ほんとだ。こんがり焼けた小麦粉と……あんこのにおい?」
「たい焼きですね」とカズサさんが断言する。
においのするほうへ顔を向けると、「たい焼き」の幟が見えた。

「すごい。形までわかるんですか」
「さすがに形まではわかりませんよ。でも、町なかにあるお店は、丸い回転焼きよりたい焼きが多いかなって」
「たしかに最近ふえてますよね」
「ここも新しいと思いますよ。先月紅茶を買いに来たときは、このにおい、してなかったです」
「カズサさん、におい探偵になれますね」
そんなことを話しながらバス停を通り越して、たい焼き屋に向かい、6組が並んでいる列の最後尾についた。
「並んじゃいましたけど、良かったですか」と千佳子が聞くと、
「このにおいを無視できるほど強くないです私」とカズサさんが言い、ふたりでふふふと笑い合った。
「佐藤さんが一緒で助かりました。一人だと、どこが列の一番後ろかわからなくて。たい焼きのしっぽつかまえる前に、行列のしっぽがつかまらないんです」
カズサさんは冗談めかして言うが、たい焼きひとつ買うのにも壁があるのだと千佳子は知る。知らず知らず順番を抜かしてしまったり、列とは違うところに並んで順番が来なかったり。
「わたしもカズサさんに会えて良かったです。おかげで、いい買い物ができました」
「最近マルフルに行っても佐藤さんの声がしないなって思っていたんです」
「シフトを減らしてるんです。娘が高校受験で」
「それは大変ですね」
「いえ、特にやることはないんですけど、なんとなく落ち着かなくて」
神奈川県の県立高校の入試本番が数日後に迫っている。2学期になってようやくエンジンがかかった文香は、秋から冬にかけて、これまでの人生で最も勉強した。
頑張った分、伸びてはいるが、他の子たちも頑張っている。伸びている。
頑張ってと口にするのもプレッシャーになるので心の中でエールを送る。この頑張りが報われますようにと祈る。あとは、バランスの取れた温かい食事を出す。それくらいしか母親にできることはない。
と思ったが、もうひとつ、できることを見つけた。
お茶をいれること。

香りと湯気とカップ越しに伝わるぬくもり。一杯のお茶にエールを込められる。
学校が休みの日には一日に何度もいれる。緑茶、ほうじ茶、黒豆茶、紅茶、ハーブティー。気分が切り替わるように、フレーバーを変える。
家にある茶葉が切れたので、せっかくならちょっといい茶葉を買って行こうと思い、いつもは素通りしている専門店に初めて入ったのだった。
「カズサさん、紅茶選ぶの手伝っていただいたお礼にごちそうします」
「そんなそんな。私だって、前に口紅選ぶのつき合ってもらいましたし」
「いいんです。ごちそうさせてください。合格祈願で」
「合格祈願、ですか?」
「めでたい結果が出るように」
文香の本命の県立高校は、文香の実力より少し背伸びしたところだ。以前までなら届かなかったが、今は手を伸ばせば届きそうなところまで来ている。自己ベストを出せば合格できる。出せるかどうかは、わからない。でも、その目標に向かって、学習量の自己ベストは更新している。
「じゃあ、ごちそうになります。合格したら、今度は私にごちそうさせてくださいね」とカズサさんが言った。
行列がなかなか動かないと思ったら、店員の女の子が新入りなのか、手こずっている。電子マネーのクーポンを使いたいお客さんの応対で操作を何度もやり直し、ついに奥から上司らしい人が出てきて、操作を代わった。
店員の女の子が「すみません」と小さく言い、身をすくめる。「お待たせしてすみません」と並んでいる客たちにも謝る。
大学生だろうか。うちの文香もあと4、5年経てばあんな感じになるのだ。たい焼き屋でバイトすることだってあるかもしれない。
千佳子は自分の娘を見るようにドキドキして店員の女の子を見守る。クーポンを使いたいお客さんも、その後ろで待たされているお客さんもおおらかで、怒ったり苛立ったりする様子はない。たい焼きを買いに来る人たちは、心にゆとりがある人たちなのだ。
千佳子の番になった。電子マネーのクーポンは使わず、交通カードで支払う。これ以上、あの子を萎縮させてはならないという使命感を胸に交通カードを読み取り機にかざすと、千佳子の心遣いを褒めるように、ピッと電子音が高らかに鳴った。
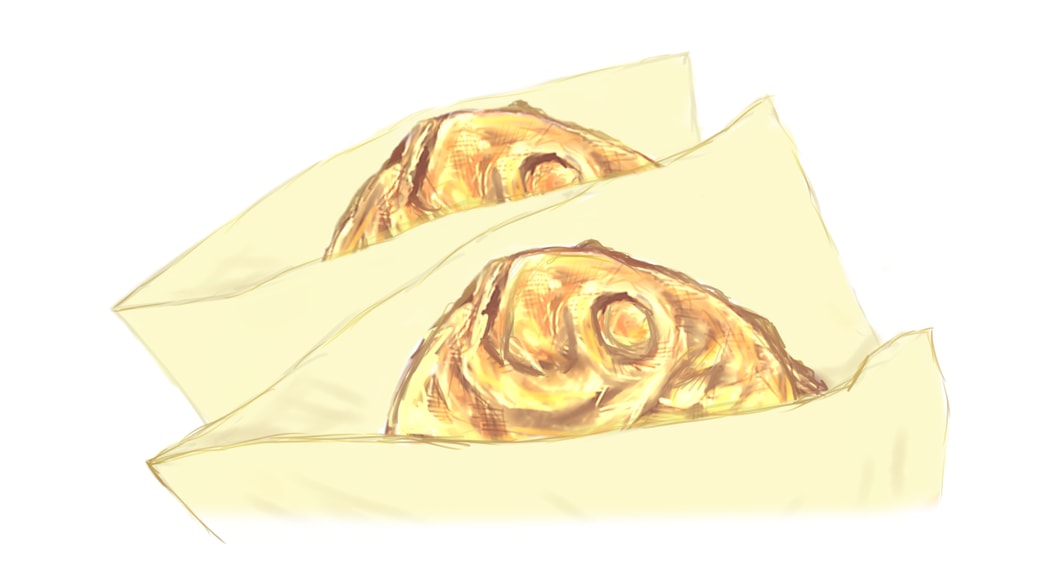
紙袋に一匹ずつおさまった焼きたてのたい焼きが2匹、目の前に差し出されたとき、店員の女の子が真っ直ぐに千佳子の目を見て、思いがけないことを言った。
「このままの私でよろしいですか」
心の中で応援していたのが、彼女にも伝わっていたのだろうか。
「もちろん。そのままのあなたでいいんです」
千佳子が力強く言うと、
「え?」と店員の女の子が戸惑った顔になった。
「え?」と千佳子も聞き返す。
「たい焼きをこのままお渡ししていいですかって言われたんじゃないですか?」とカズサさんが後ろから言った。
カズサさんの後ろに並んでいるカップルがくすくす笑っている。持ち帰り用の手提げに入れなくても良いかと尋ねられていたのだと千佳子は気づき、
「わ、違った! すみません! このままで!」
慌てて手を伸ばし、たい焼きを受け取ったが、今度は「このままのあなたでいいんです」を打ち消してしまったように感じ、取り繕うように「頑張ってください!」と口走ると、
「ありがとうございます」
店員の女の子の目が細くなった。笑っている。マスクの中の口も笑っているのだろう。
サクラサクの笑顔だ。つられて千佳子も口元が緩む。
大丈夫。この店員さんも、文香も。きっと大丈夫。
次の物語、 連載小説『漂うわたし』第104回 佐藤千佳子(36)「せっかく生まれてきたんですから」へ。
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!


















































































































































































































































































































































































































































