
第19回 佐藤千佳子(7) 人妻だって恋をする
「佐藤さん、きれいになったよね」
パート先のスーパーの支度部屋で千佳子がエプロンを外していると、遅番の野間さんが入って来るなり、そう言った。
千佳子よりひとまわりほど年上の野間さんは、本部から来ている社員にも一目置かれている。「わからないことがあったら、なんでも聞いて」と言い、パート仲間の子育てや介護の相談にも乗ってくれる。
「きれい、ですか?」
「お化粧、変わったでしょ」
マスクをしているので赤い口紅は隠れているが、口紅に合わせてアイメイクやチークを入れるようになった。目配りがきく野間さんは、人をよく見ている。
「わかります?」
「わかるよー。顔が明るくなったよね。声にもハリが出てるし。縮こまっていた蕾がほどけて、花開いた感じ」
ハーブのマイさんの真っ赤なコートに憧れ、目に留まった「とびらを開く色」のポスターに惹かれて赤い口紅を買った。あの日から目線が少し上がって、世界がひらけた気がしている。
「実は、いい出会いがあって、霧が晴れたんです」
「やっぱり。春だよね。恋の季節」
「違います! そっちの出会いじゃなくて」
野菜売り場で出会ったハーブのマイさんのことを話して、野間さんの誤解を解いた。
「わたし人妻ですよ」
「人妻だって恋するでしょ」
ダンナさんに叱られますよと言いかけて、千佳子は口をつぐむ。野間さんは去年の春、ダンナさんを亡くしている。定年退職した後、関連会社に2年勤め終えた明くる日の朝に胸の痛みを訴え、その日の夜に亡くなった。「時間はあるようでないから、やりたいことは先延ばししちゃダメ」というのが野間さんの口癖だ。
「人妻のうちに恋をして、ダンナを嫉妬させたかったな」と野間さんは明るく言った。
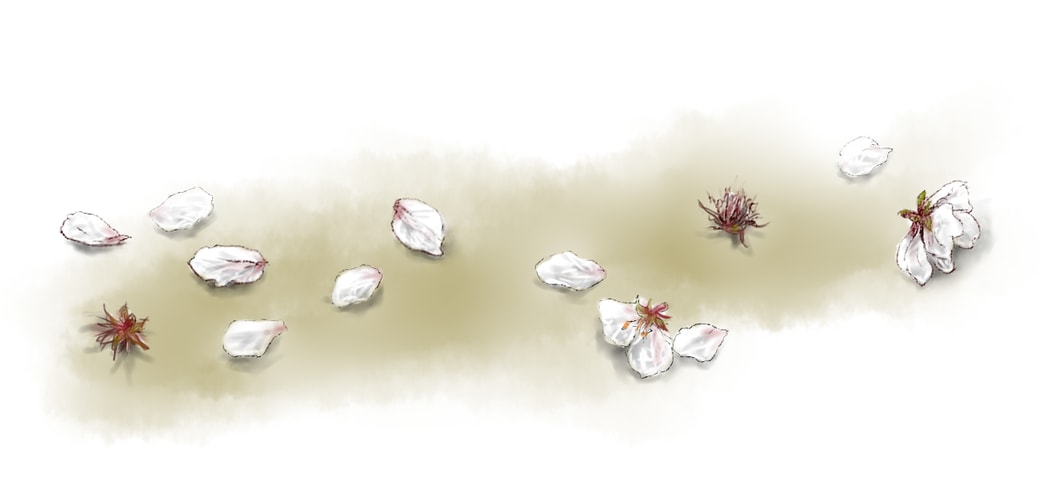
パートの後、買い物を終えて外に出ると、日はすっかり落ちていた。スーパーの前の並木道は、桜の花盛りを過ぎ、地面に落ちた花びらを自転車のライトが白く浮かび上がらせる。花をつけた枝が道に落ちているのに気づいて、千佳子は自転車を停めると、拾い上げた。
持ち帰った桜の枝をドレッシングの空き瓶に活け、キッチンカウンターに置いた。パセリの後、ハーブブーケを活けていたスペースが、一気に華やぐ。
「まだ終わりじゃないよ。もうしばらく咲いてね」
花に向かってかけた言葉が自分に向けられたようで、ドキっとする。
野間さんが変なこと言うから。
邪念を振り払うように、買い物してきた食材を冷蔵庫や棚に納め、夕飯の支度にとりかかる。
そうだ。昨日の続き。
キッチンカウンターに置いたスマホのアプリを起動させ、動画の再生ボタンを押す。聴き慣れた男性の声がルネサンスと大航海時代について解説を始める。
娘の文香が中学2年生に上がるタイミングで動画学習サービスに申し込んだ。部活が忙しくても時間を作って学習できると思ったのだが、文香は見ようとしない。聴くだけでも聴いたらとせっつくと、
「講師の声がダメ」
そう言って、お気に入りの声優の動画を延々と見る。声優もいいなと淡い憧れを抱いていたが、高校生になったらナレーション学校に通いたいと言い出している。
「声がダメってどういうこと?」
「滑舌悪いし、鼻濁音できてないし」
声優の技術を講師に求めるのは、ないものねだりではないか。
「せっかく月額料金を払っているのに、もったいない」
「じゃ、ママが代わりに見といて」
「ふーちゃんが見ないと意味ないでしょ」
「ママが見て、内容教えて。ママの声なら許す」
「許すって何?」
そんなわけで家事の手を動かしながら動画の音声に耳を傾けるようになった。自分が学んで文香に教えようという意気込みからではなく、月額料金の元を取らなくてはという義務感からだった。
わたしは定期テストも受験も関係ないのに。
30年近く前に学んだはずの地理や歴史は、初めて聞く話のようだった。風呂を洗いながら、洗濯物を畳みながら、メソポタミア文明やら平安時代やらに想いを馳せるうちに、遠い記憶が掘り起こされたり、理解が深まったりして、続きが楽しみになってきた。
勉強を楽しいと思ったことなんて、あったっけ。
千佳子の成績は小学校時代から一貫してクラスの平均前後を漂っていた。要領のいい子の何倍も勉強時間を費やして、その程度だった。やらされていると思っているうちは気が乗らないし、身につかない。渋々机にかじりついたところで、ざるに水を注ぐようなものだとサラダのレタスを洗いながら千佳子は思う。その間にルネサンスと大航海時代の講義動画は終わっていた。

次の動画を再生しようとして、他の教科を聴いてみることにした。耳だけでわかりやすい社会を好んで聴いているが、数学はどうだろう。再会したら仲良くなれるかもしれない。講義一覧を開いてみる。連立方程式、一次関数、並行と合同。どれも懐かしさよりとっつきにくさを覚える。
比較的なじみのある「確率」の単元を選ぶと、「ことがらの起こりやすさ」の講義動画があった。
「ことがらの起こりやすさ」
普段あまり見かけないフレーズだが、口にしてみると格調高く、自分が賢くなった気がする。「確率」とは、「ことがらの起こりやすさ」のことらしい。降水確率は、雨が降ることの起こりやすさ。
「人妻だって恋するでしょ」
ふと蘇った野間さんの声にドキッとして、人参を刻む手を止める。
わたしが夫以外の誰かに恋をすることの起こりやすさは、どれくらいあるのだろう。
「恋愛確率」
口にしてみると、意外とさらっとした響きがあった。降水確率と同じくらい引っかかりがない。そもそも夫に恋愛していたのだっけと胸に問いかけ、そういうのを飛び越して結婚したのだと思い至る。
「確率?」
すぐ近くで夫の声がして、ハッと我に返ると、帰宅した夫が立っていた。夫に心の内を読まれたようで焦ったが、
「数学聴くの、珍しいね」
スマホから聞こえる音声で、確率の講義を聴いているのだとわかったらしい。千佳子がこのところ学習アプリの動画を聴いていることは夫も知っている。
「確率、面白い?」
「え?」
「楽しそうだったから」
後ろめたい秘密があるわけでもないのに、夫に見透かされているようでドキドキする。
「数学って苦手だったけど、大人になってから出会うと、なんか新鮮で」
言い繕う自分の言葉に罠が潜んでいるような気がしてしまう。千佳子が黙り込むと講義動画も話し止み、キッチンがしんとした。
「きれいだね」
不意に夫が言った。そんなこと一度も言ったことないのに。「人妻のうちに恋をして、ダンナを嫉妬させたかったな」と野間さんが言ったのを思い出してドギマギする。食器を拭く布巾をつかみ、意味もなく手を拭いてしまう。
「見納めだね」
そう言う夫の視線は、ドレッシングの瓶に活けた薄桃色の花に注がれていた。

「桜だったんだ?」と千佳子が言うと、
「桜だよね」と夫が言った。
乱高下した気持ちをごまかすように人参を切る包丁の音を響かせながら、千佳子は確率について思いを巡らせる。目の前の人に「きれい」と言われて、それが自分を指していることの起こりやすさについて。今日のところは2回のうち1回。確率は2分の1だ。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第20回 佐藤千佳子(8)「真昼の逢い引き」へ。
イラスト:ジョンジー敦子
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!
























































































































































































































































































































































































































































