
第76回 伊澤直美(26)これは満たされてますアピールなのか
童話の原稿を打っているところをイザオに見られ、テスト前に漫画を読んでいるのを親に見つかった中学生みたいに慌てたのは、後ろめたさがあったからだ。
仕事をすると言ってイザオに子守を頼んだのだから、仕事以外のことをしてはいけないのだと。
だけど、と直美は思う。
仕事という理由がなければ、子育てを休んではいけないのだろうか。夫に託してはいけないのだろうか。
それを許す許さないを決めるのは、夫なのだろうか。
直美が子どもを持つことをためらっていた頃から、イザオは「産んだら協力する」と言っていた。その言葉通り、保育園の送り迎えも、おむつ換えも、お風呂に入れるのも、母乳を出す以外のことは分担してくれている。
分担と言いつつ、半々ではない。保育園への送りはイザオ、迎えは直美というのが基本ルールだが、それ以外は直美の手が回らないときにイザオが助けてくれる。料理や洗濯や掃除のように、いつの間にかやってくれているということはないが、頼めば気持ちよく引き受けてくれる。
協力。引き受ける。あくまで主力は直美で、イザオは「いつでも動ける補欠」のような立ち位置だ。
イザオは社内でも「イクメン」で通っているし、直美は「理解のあるダンナさんのおかげで仕事を続けられている」と思われ、うらやましがられ、「感謝しなきゃね」と言われている。
ありがたいと思う。恵まれていると思う。でもなんだかモヤモヤする。
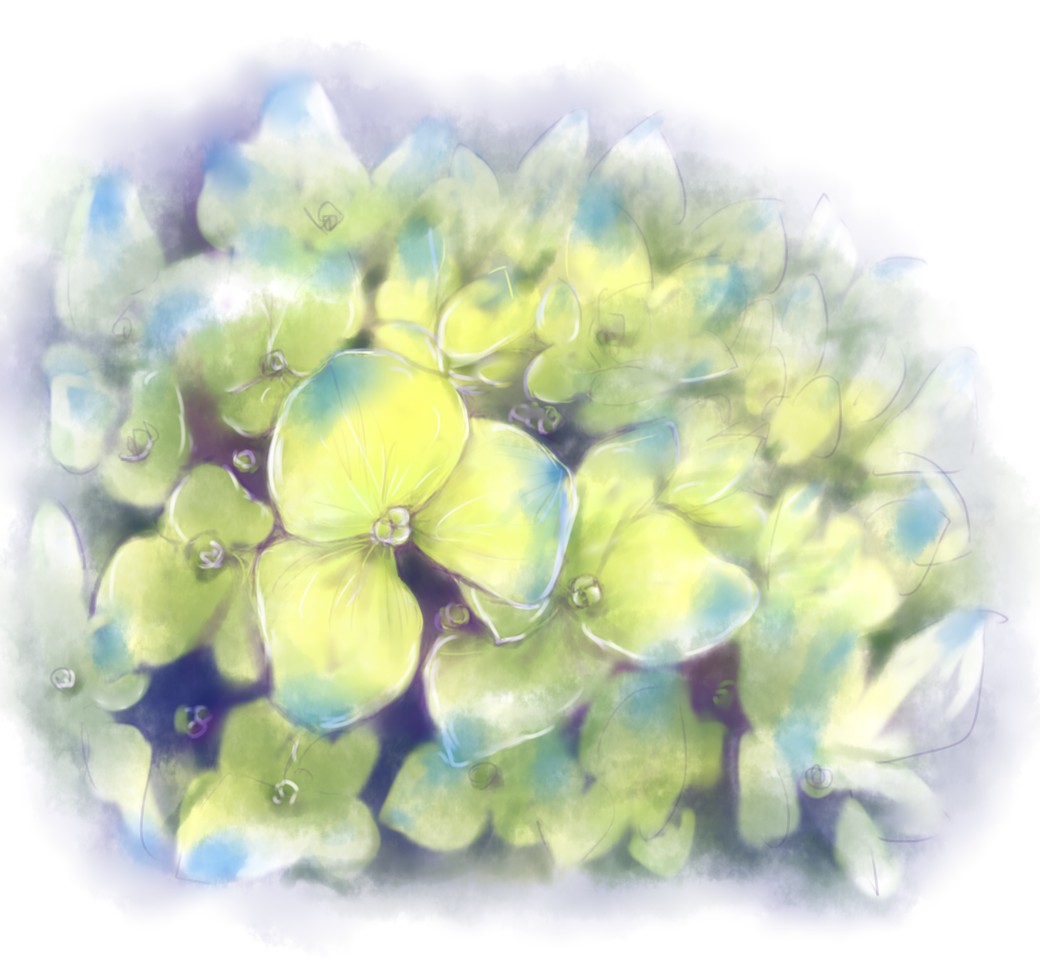
同じことをして、イザオだけがほめられるのは対等じゃない。子育てはふたりでするものなのに。
母親は育児に自分を捧げて当たり前。だから、他のことを優先させると「母親なのに手を抜いている」と理想像からの引き算をされる。一方、ゼロベースの父親は「父親なのによくやっている」と足し算で持ち上げられる。
男女平等やら男女共同参画やら言うなら、まず立ち位置を揃えてくれないと。
少し前に梅雨明け宣言が出ていたが、直美の気持ちは晴れない。心がささくれていると、普段なら受け流せるようなことがいちいち引っかかり、トゲになって突き刺さる。かぶれた肌に衣服がこすれて、悪化してしまうように。
金曜日にあった新商品開発ミーティングのことをまだ引きずっている。
2時から社内で行う予定だったのが、メンバーに在宅勤務の人が多い都合で6時から対面とリモートでの開催となった。
直美は6時までに保育園へ迎えに行けるよう、5時までの時短勤務になっている。会議が時間外になるのは構わないのだが、できれば対面で参加したかった。子どもを見ながらのリモート会議はなかなか集中できない。体はパソコンの前にあっても、頭と心は子どもに持っていかれる。
イザオに優亜の迎えを頼めないか聞いたが、イザオも夕方から打ち合わせが入っていて、「もう少し早くわかっていたら」と言われた。
あのときも「ごめん」と直美は謝った。共働きで、同じ会社で、同じ子を育てているのに、謝るのも感謝するのもいつも直美だ。
5時に会社を出れば、保育園経由で6時には帰宅できる。けれど、リモート会議に出席できる状況になっているとは限らない。大抵はおむつが膨れ上がっているし、汗ばんだ服も着替えさせたい。
プロジェクトリーダーは直美より2期下の相原美帆。当初は「育児中でもプロジェクトリーダーをやれるのに」と戦力外扱いされたような淋しさを覚えたが、リーダーを人に任せたことで、企画に集中できる。任せられるところは任せて、限られた時間を上手に使えばいいのだと割り切った。
職場で旧姓の原口を使っている直美は、頭ふた文字と最後のひと文字をつなげて呼び合う同期入社ルールから「ハラミ」とあだ名がついたが、相原美帆の名前にも偶然「ハラミ」が入っていて、プロジェクトチーム内では「ハラミ1号」「ハラミ2号」と呼ばれている。チームは20代30代の女性中心で、子どもがいるのは直美だけだ。ハラミ2号は「1号さんが商品企画開発ママのロールモデルになってください!」と言ってくれている。

金曜日、蒸し暑さのせいか、保育園を出たときから優亜はぐずり続けた。
「子どもがぐずっているのでミュートで参加します」
とチャットに書き込み、ビデオもオフにして、耳だけ参加することにしたが、優亜に気を取られている間に話が転がり、浦島太郎状態になってしまった。
「廃棄される果物の皮の話って、どこから出てきたんでしたっけ」
チャットにコメントを書き込んだが、拾ってもらえない。直美を置き去りにして、会議は進む。
何の話をしているのかわからないから、会話に加われない。聞き取れない単語が飛び交う外国語の会議に放り込まれたら、こんな感じだろうか。自分の頭の上を通り過ぎる言葉をぽかんと眺めているだけで時間が過ぎていく。他の出席者には自分が見えているのだろうかと心配になる。
「ゆあちゃん、誰もコメント読んでくれないよ」
ようやく泣き止んでおっぱいを飲んでいる優亜に愚痴をこぼすと、
「1号さんすみません!」
まるでこちらの声が聞こえていたかのように、ハラミ2号の反応があった。
「わ、やだ! ミュートになってない!」
気づくと同時に直美が思わず叫ぶと、出席者たちから時差のある笑い声が上がった。
「いつ1号さんが気づくかなーって思ってたんです」
ハラミ2号が言うと、また笑い声が上がった。
「ええっ。早く言ってよ!」
恥ずかしさで顔が熱くなる。ぐずる優亜をなだめる直美の音声が筒抜けになっていた。その間、約30分。
「1号さんお母さんなんだなあって。ほっこりしちゃいました」
パソコン画面の中の顔が一斉にうなずく。口角が上がり、皆笑っている。けれど、直美は笑えなかった。無性に淋しくて、泣きそうだった。
こっちは必死なのに、「ほっこり」されてもねえ。だからリモートじゃなくて会社で出たかったのに。
ハラミ2号も他のメンバーも何も間違っていない。子育て中の先輩社員を温かく見守ってくれる後輩たち。善意の押し売りをする「良かれ教」の人たちとはまるで違う。だけど、あの人たちのありがた迷惑のほうが、文句を言いやすかった。
恵まれているのに「なんか違う」と思ってしまうなんて申し訳ない……。自分を責めてしまい、余計に追い詰められる。
外し忘れのタグが首筋に当たっているような些細な違和感も、それを抱いてしまうことへの後ろめたさも、他の人にはわからないだろう。直美だって知らなかったのだ。こんな気持ちになるなんて。

「やっときますよ」とハラミ2号は言ってくれたが、週末のうちに会議を踏まえた企画書を作っておくと言ったのは意地だった。なのに、パソコンを開くと、『鏡っ子ゆあちゃん』の続きを打ってしまう。
「鏡っ子ゆあちゃん」のことを優亜は鏡に映った自分だとわかっているのだろうか。人はいつから「他でもない自分」を自覚するようになるのだろう。そんなことに興味が湧くのは、直美自身の「自分」が定まっていないせいだろうか。
今まで自分を満たしていたのは、空しい思い込みだったのかもしれない。子どもを産んで失ったものなんてひとつもない。そう自分に言い聞かせていただけじゃないのか。
どこかに穴が空いて、わたしがしぼんでいく。
その穴埋めをしようとしているのだろうか。これは満たされてますアピールなのだろうか。
わたしは何がしたいのだろう。
わからないままに、書いたことのない童話を書いている。原稿用紙のマス目を埋めるように、空白が文字に置き換わっていく。ひと文字、一行、一ページ。コンクールで大賞作品に選ばれたら、プロのイラストレーターが挿し絵を描いてくれ、主催者である出版社から出版されるらしい。受賞のコメントで「子どもを産んで世界が広がりました」と言う自分を想像できる。そこに向かって書いている気もする。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第77回 多賀麻希(25)「閉じていなかった物語」へ。
イラスト:ジョンジー敦子
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!




















































































































































































































































































































































































































































