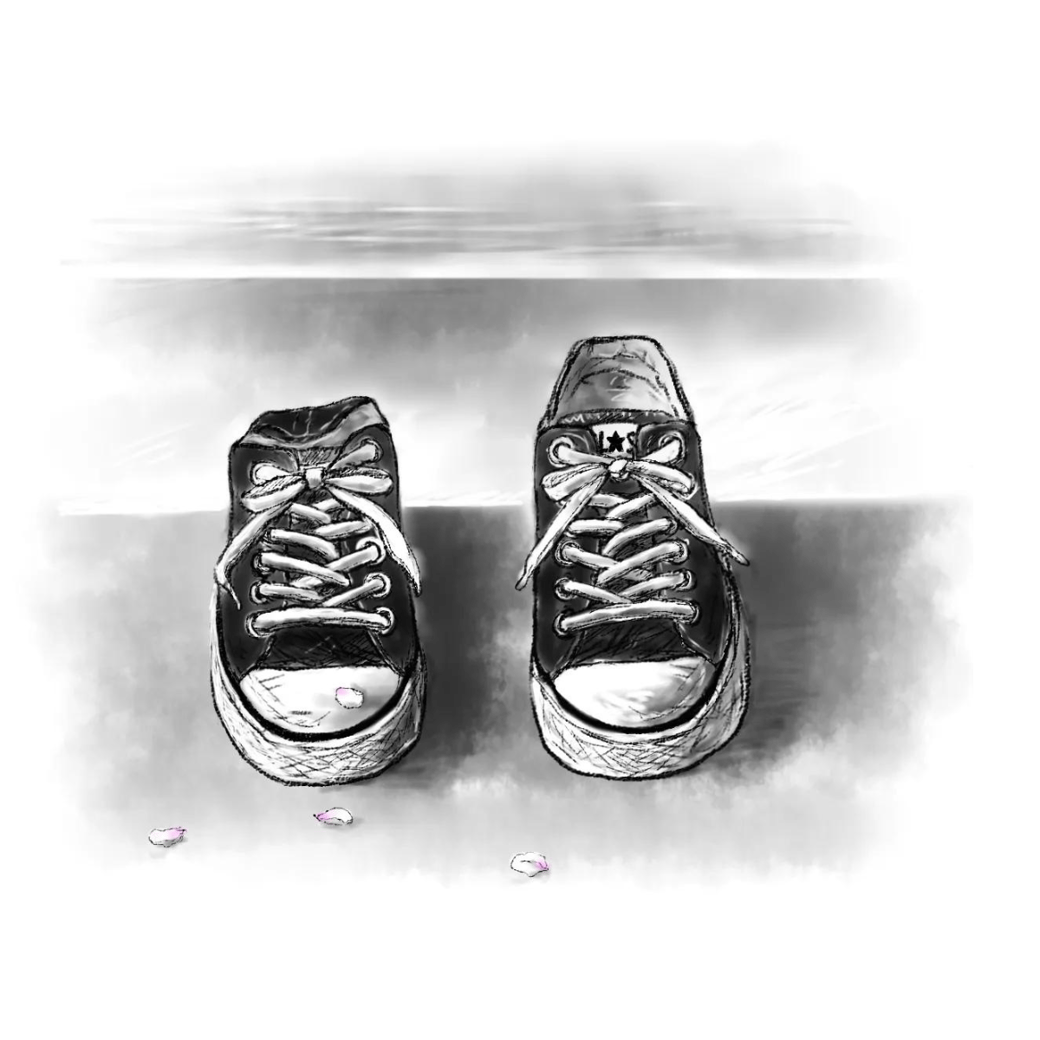第18回 多賀麻希(6) 幸せの合格ラインを下げる
『焙煎珈琲 然』の看板を出しているが、マスターいわく「名前はとくに決まってない」新宿三丁目のカフェでバイトを始めて2週間。モリゾウと出会った日からプラス1日。その間、モリゾウは麻希の部屋で寝起きしている。
わざわざ報告することでもないので黙っていたら、「モリゾウ、マキマキんとこ行ったん?」とマスターに聞かれ、「なんで知ってるんですか?」と慌てた。
「最近ここで泊まってへん感じやったから」
「モリゾウって、ここで寝泊まりしてたんですか」
「せやで。あいつがこっから引き上げたリュックに着替えやら全部入ってるやろ」
確かに、紙皿と箸が出てきたあのリュックには何でも入っている。雨露をしのげる屋根と寝転がれる床があれば、どこででも暮らせる。
「次に行くとこ探してるところに、わたしが現れたってことですか?」
「あいつは拾うんも拾われるんも得意やからな」
モリゾウが誰かの部屋に転がり込むのはよくあることで、彼が拾って来た『焙煎珈琲 然』の看板のように、位置が移動しただけのことらしい。
麻希と入れ違いにモリゾウはカフェでのバイトを辞めた。
「ちょうど忙しなる言うとってな。また舞台やるんとちゃうか」
バイトを始めるのも辞めるのも、あっさりしている。客はほとんど来ないし、留守を任されることもない。マスターと映画や音楽の話をして時給千円をもらっている。
この居心地の良さに甘えていてはいけないと思うのだが、10年ぶりに書いた履歴書をいまだにどこにも出せていない。派遣切りされた39歳の女を欲しがってくれる職場などあるのだろうか。

バイトから帰り、鍵をかけていない玄関のドアを開けると、朝見たのと同じ位置にモリゾウのスニーカーがあった。合鍵を作っていないので鍵を置いて出かけたが、モリゾウはずっと部屋にいたらしい。
玄関を入ってすぐのダイニングに灯りはついているが、モリゾウの姿が見えない。そら豆の形のちゃぶ台の上にカバーをかけた文庫本が伏せられている。と、水を流す音がして、モリゾウがトイレから出て来た。麻希を見て、「おかえりっす」と言う。
麻希が最後に誰かと暮らしたのは10年も前のことだ。20代の終わり、映画製作プロダクションに出入りしていた脚本家志望のツカサ君と9か月だけ暮らした。
ツカサ君は世話を焼くのが好きで、麻希の髪を乾かすのも、爪を切るのもツカサ君の仕事だった。モリゾウはツカサ君とは対照的で、何もしない。居候のお礼に掃除をしたりもしないし、何かするそぶりも見せない。ただただ、くつろいでいる。
レンチンの惣菜とご飯を出すと、「電子レンジって人類最高の発明っすね」と最上級表現で喜ぶ。「今日、肉じゃがの気分だったんすよ。マキマキさんのセンス最高っす」と麻希のチョイスも褒める。悪い気はしないが、勘違いしてのぼせたりはしない。モリゾウはヨイショで場を盛り立てるタイコ持ちの役を演じているのだ。セリフだと思えば、何だって言える。
壁際の床に顔を近づけると、まとまった量の髪の毛が溜まっていた。元々近視なのだが、また度が進んだようだ。モリゾウも時々目を細めるが、二人とも普段は眼鏡をかけていない。近視の男女が裸眼で暮らし、見なくても良いものを見過ごしている。
埃を絡めて溜まっている髪の毛を見られたからといって、モリゾウとの関係で失うものなどない。そもそもモリゾウから何かを得ようなんて期待していない。だから気が楽なのだ。

これまで部屋に上げた男たちに、麻希は期待していた。好かれたい。抱かれたい。もっと知りたい。その先に「結婚したい」があった。それを望めない相手と関係を持つことがふえても、相手に何かしら期待した。奥さんのところに帰らないで欲しい。週末も会いたい。嫌われたくない。よりを戻したい。
「うち行っていい?」と聞かれると、ムダ毛を剃っているかどうかを気にした。男の人を部屋に上げるというのは、脱がされることとセットだった。
なのに、モリゾウに「うち来る?」と声をかけたとき、ムダ毛のことは頭をよぎらなかった。そういうことから遠ざかっていたし、モリゾウにそういう匂いを感じなかった。
便座も浴槽も共有しているのに、生活以上の生々しさがない。麻希が使うものをモリゾウも使う。ドミトリーのユースホステルで共用のトイレやシャワー室を使うのと同じ感覚。
一緒にいる時間が長くなると途端に気安くなったり横柄になったりする男たちと違い、モリゾウは驚くほど変化がない。麻希の体も自分の布団も求めない。リュックを枕に固い床で熟睡し、機嫌よく目覚め、「電気が通ってれば最高っす」と繰り返し、電子レンジや冷蔵庫やエアコンに感謝を捧げる。
「そんなに電気大事?」
「電気があれば何とかなるっす」
「そしたら、たいがいのことは幸せだね」
「幸せの合格ライン、思いっきり下げてるんで。全員合格っす」
幸せな人というのは、幸せの間口が広い人のことなのだ。幸せを受け止めるアンテナがあるのだとしたら、麻希のアンテナは避雷針みたいな棒状で、モリゾウのはパラボラアンテナみたいに全方位からつかまえられるようになっているのだろう。

自分の幸せがこれ以上膨らむことはないと悟ったときから、麻希は他人の不幸を願うようになった。自分より高い位置にいる人が転落することで、自分だけがみじめにならないことを願った。
結婚しました葉書や子どもが生まれました葉書を見ると、祝福の気持ちよりも嫉妬がこみ上げた。人類が分け合う幸せのパイの大きさは決まっていて、誰かが幸せになると自分の幸せが削られるように感じていた。それだけへこたれていたし、病んでいた。
結婚した友人からの年賀状が旧姓に戻っていると、救われたような気持ちになり、すぐ後で強烈な自己嫌悪に見舞われた。他人の人生にいちいち波立つことに疲れた。
衝動のようにこの部屋に引っ越したとき、家族以外に新しい住所を知らせなかった。郵便局にも住所変更届を出さず、これまでの人間関係を清算した。郵便受けにはポスティングのチラシしか入らなくなった。チラシは読まなくても罪悪感がないし、読んだからといって心をかき乱されたりしない。
「マキマキさん、僧侶のバイト募集してますよ」
「僧侶のバイト? 女でもいいの?」
「性別年齢経験不問。食事つき。肉も出るそうっす」
「肉食べていいの? 煩悩あり?」
「煩悩ありっす」
モリゾウはチラシを隅から隅まで読んで面白がる。ポストの中身に笑わせてもらう日が来るとは。わたしって、こんなに笑う人だったんだと麻希は自分の立てた声に驚く。
「肉を食べられる僧侶のバイトって」
布団の中で思い出し笑いした。性別年齢経験不問。派遣切りされた39歳の女にだって僧侶になる可能性があるのなら、仕事なんて、探せばいくらでもあるのかもしれない。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第19回 佐藤千佳子(7)「人妻だって恋をする」へ。
イラスト:ジョンジー敦子
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!