
第65回 多賀麻希(21) 彼の指が見つけたエンダツ
「桜の茎って、鮮やかな緑なんだ?」
モリゾウの声が頭の上から降ってくる。
フローリングに敷いたラグに腰を下ろし、麻希は壁に背を預けたモリゾウを背もたれにして、スケッチの鉛筆を走らせている。
新作の布雑貨のモチーフにと、道に落ちていた桜の花を拾って持ち帰った。麻希の気持ちに季節が追いついたような春。目に映る何もかもが愛おしい。浮かれているというのとは違う。しみじみ噛み締めるような感じ。わたし、良かったねと。
ちゃぶ台に置いた桜の花を指でつまみ、手のひらにのせて、見てみる。3つの花が茎でつながっている。黄緑色の茎が花を引き立てている。
「こんなにまじまじと観察したことなかった」
「俺も」
少し前までなら「俺もっす」と言っていたが、いつの間にか語尾の「っす」が消えている。麻希を呼ぶときも「マキマキさん」ではなく、「マキマキ」と呼び捨てにする。ふたりの体の距離が縮まるとともに、モリゾウの言葉の尻尾も短くなっている。

今の麻希の幸せは、手の中の桜に似ている。そっと拾って、落っこちないように手のひらを丸めて、しばらく眺めていたい。
長い手足で麻希を後ろから包んでいるモリゾウは、右手に文庫本を持ち、左手でページをめくっている。何読んでるのと尋ねると、「わたなべおん」と答えが返ってきた。
「渡辺温」と麻希は頭の中で漢字に変換する。派遣で働いていた出版社で文学全集の校閲をしたとき、その名前を知った。
「『恋』の人?」と麻希が言うと
「『恋』の人」とモリゾウが答えた。
麻希が読んだことのある渡辺温の作品はその一作品だけなのだが、図らずもふたりで口にした「恋」が合図のようになり、どちらからともなく顔を近づけて、短いキスを交わした。
渡辺温は28歳で亡くなったのだったと思い出す。確か谷崎潤一郎の原稿を取りに行く途中に事故に遭ったのだった。28歳。麻希がツカサ君との恋を失った歳だ。今40歳。干支ひとめぐり分の間にずいぶんいろんなことがあったけれど、思い出したくないことのほうが多い。モリゾウに出会う前と後で日陰と日向のように時間の色がくっきりと変わっている。
モリゾウの左手が麻希を抱き寄せた。その左手を麻希の頭に持ってきて、髪を撫でる。
人に頭を触られるのって、なんでこんなに気持ちいいんだろ。自分で触るのと、なんでこんなに違うんだろ。
自分で自分を触ると、触る手と触られる頭の両方の感覚があるから、触られる気持ちよさに集中できないのかもしれない。
モリゾウの手に頭を預けながら、麻希はそんなことを思う。スケッチの手は止まったままだ。
「美容院のシャンプーって気持ち良くて寝ちゃうよね」と麻希が言うと、
「俺、寝れない。あの椅子から足飛び出しちゃう」とモリゾウは言った。
好きになった人の腕の中で、どうでもいい話をする。他愛のない、愛おしい時間。モリゾウの手に自分の好きな自分が掘り当てられ、汲み上げられていく気がする。

ふとモリゾウの手が止まった。
「マキマキ、知ってる?」
「何?」
「ここ」
モリゾウが麻希の手を取り、その手を麻希の後頭部に導く。モリゾウの手に連れて行かれたところを指でなぞると、
「あ……」
髪が途切れているところを見つけた。一円玉くらいの大きさの更地ができている。シャンプーのときに気づきそうなものだが、最近できたのだろうか。
「うわー。やば! エンダツ!」
麻希にしてはかなり高いテンションで、明るく言った。初めてニキビを見つけた女子高生みたいに。
麻希が今気づいたのを見て、「後ろにあるからね」とモリゾウは言った。
「エンダツって4文字に略すと、ミュージシャンっぽくない?」
恥ずかしくてテンションが高くなった人みたいにはしゃいでしまったが、モリゾウに見つけられたこと自体は恥ずかしくなかった。もっと恥ずかしいところを見られている。胆石を診断され、手術で胆のうごと取るかどうか聞かれた診察室で「あってもなくても関係ない」と医師に告げられた胆のうに自分を重ねて取り乱したときのほうが、ずっと恥ずかしかった。
だけど、エンダツには触れられたくなかった。麻希にとって、それは開かずの扉で、開けてしまったら、閉じ込めておいた忌まわしい記憶がこぼれ出てしまう。
高校3年に上がる春。家の裏庭で通学鞄の中身を空け、教科書と参考書を燃やした。焚き火のつもりだった火が勢いを増して広がり、納屋を飲み込んだ。
噂は火よりも速く燃え広がった。麻希は最初から納屋に火を放ったことになっていた。
おとなしい子だと思っていたのに。
おとなしい子のほうが何をするかわからない。
どこに行っても後ろ指を差されている気がした。この町にはいられない。早く出て行きたいという気持ちが募った。引っ越しの話も出たが、父が拒んだ。堂々としていれば、そのうち誰も口にしなくなる、と。
春休みが明け、新学期が始まる頃には、噂は下火になっていた。燃やさなかった通学鞄に新しい学年の教科書と参考書を詰め、あと一年と自分に言い聞かせ、高校までの長い道を通い続けた。
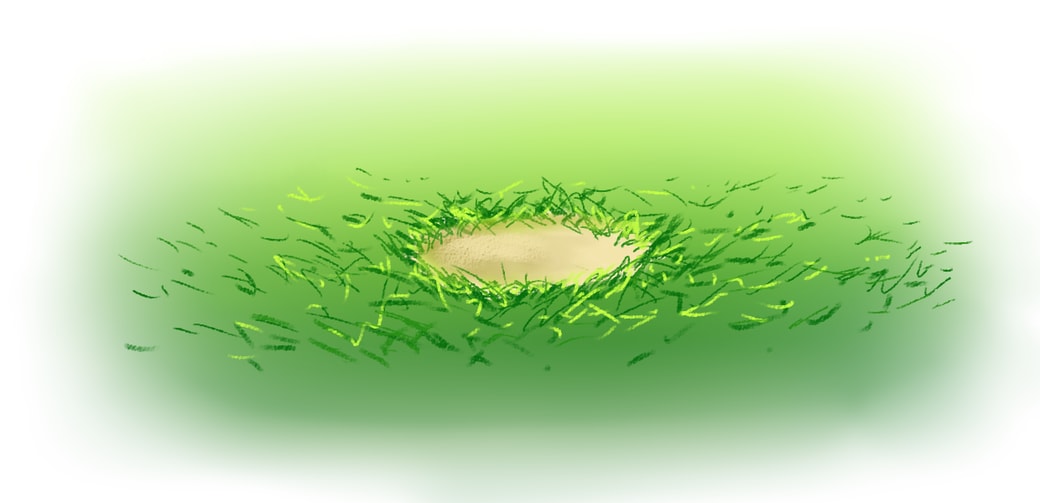
裏庭を更地にしてしまってから4か月ほど経って、麻希の頭に小さな更地が現れた。
あのときは、学校の水泳の授業で同級生に見つけられたのだった。見つかり方も最悪だった。罰が下されたのだと思った。
罰を受け止めるように、更地の感触を何度も確かめた。そのうち秘密を共有する理解者のような親しみを覚えるようになった。更地を触っていると、気持ちが落ち着いた。今度は、あまり触ると新しい髪が生えてこなくなるのではと心配になった。
エンダツは、どん底から少し遅れて現れるのだ。底を蹴って、浮かび上がって、忘れた頃に。
4か月ほど前、秋の終わりに何があったっけと思い巡らす。
無職だと思っていたモリゾウが動画配信サービスの英語講師をやっているのを偶然知ったのがその頃だった。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第66回 多賀麻希(22)「制服のシンデレラ」へ。
イラスト:ジョンジー敦子
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!






















































































































































































































































































































































































































































