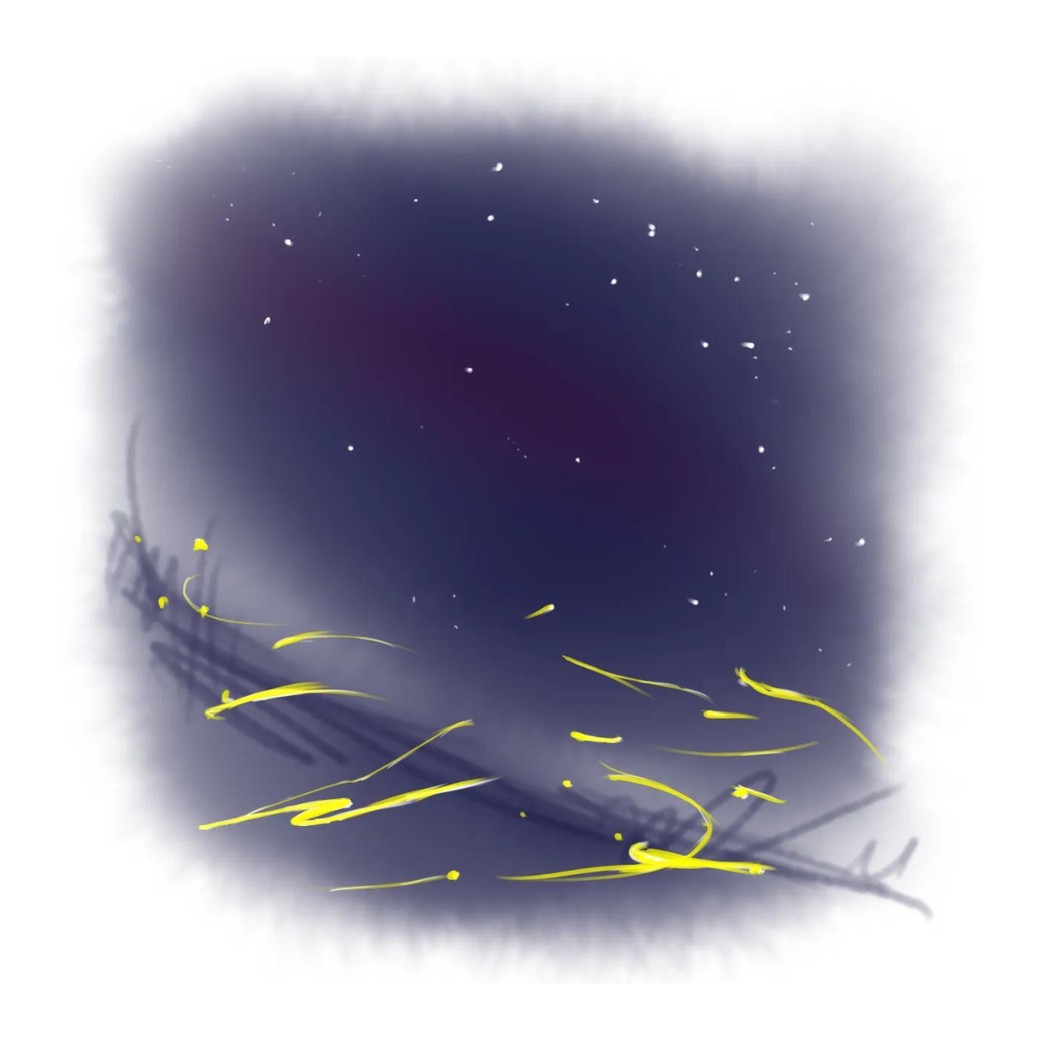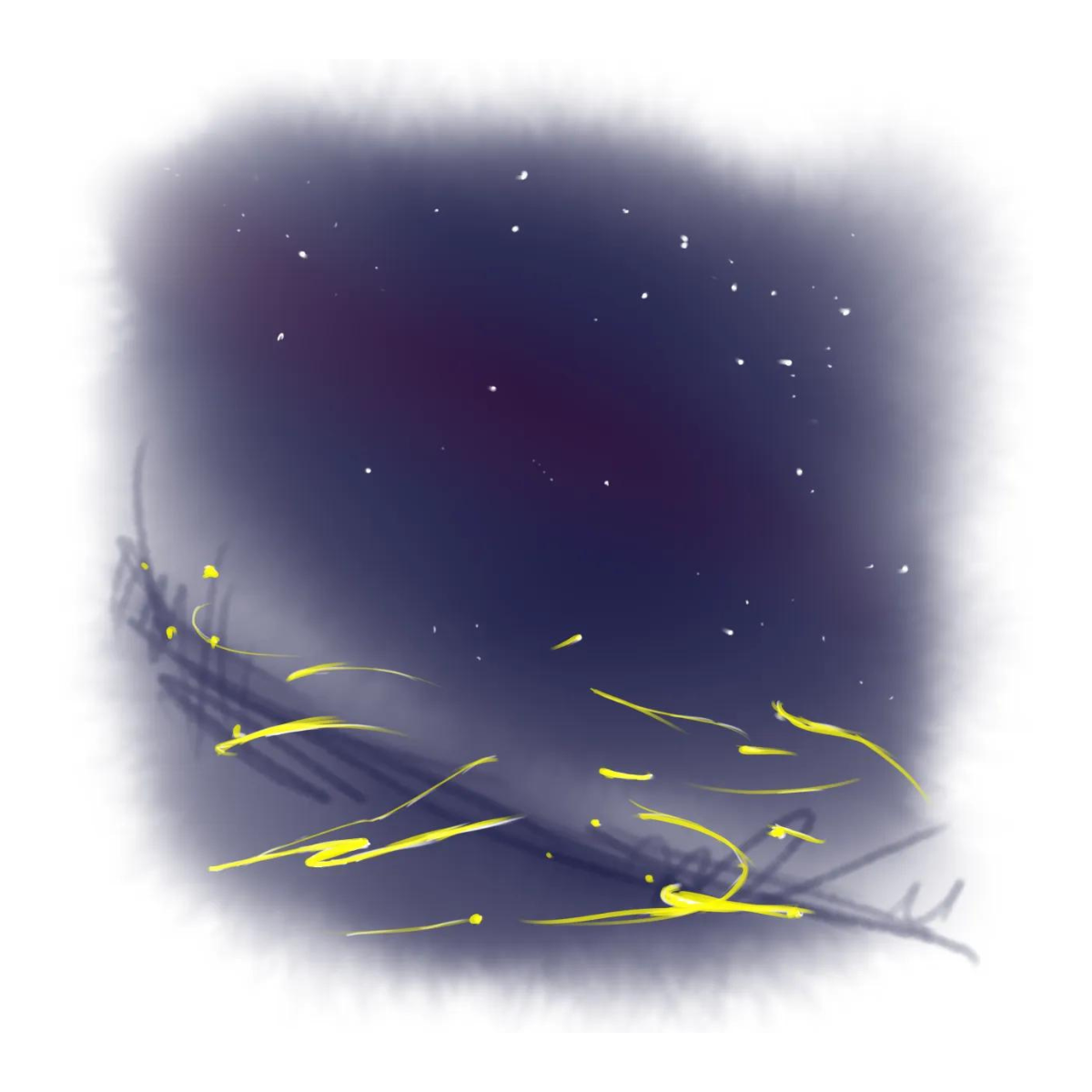第72回 多賀麻希(24)愛せないヒロイン
『それからのルーズソックス』を最後に観たのはツカサ君とだった。ふたりで暮らしていた部屋で、いちごを食べながら。
ツカサ君の思い出は赤と結びついている。いちごの赤。『制服のシンデレラ』の炎の赤。「シンデレラへ」のカードを添えてプレゼントされたのは、赤い靴だった。
そう言えば、新宿三丁目のカフェでモリゾウと初めて会った日、あの靴をはいていたことを思い出し、モリゾウを見ると、目が合った。抱き寄せられ、キスが始まる。これはキスで終わらないパターンだ。
いっときは毎日のように体を重ねていたのに、麻希の頭に小さな更地を見つけてから、モリゾウは手を伸ばして来なくなった。久しぶりにその気になったのは、『それからのルーズソックス』のせいだ。
モリゾウは気づいていたのだと麻希は思う。一瞬ピントが合った25歳の麻希に。一緒に映っている恋人役の青年との仲も、きっと見透かされている。
この人は、わたしがどこにいても見つけて、どんなわたしもくるんでしまうのだ。たくましい腕で。
DVDを流しっぱなしのパソコンから、グラビアアイドル咲良栞子のすねた声が聞こえる。待ちぼうけを食らわせた相手に電話しているらしい。呆れるほど棒読みで滑舌が悪い。声だけ聞いていると、余計にアラが目立つ。
ツカサ君と観たときも途中からキスが始まった。麻希から始めて、終わらせなかった。いちご味のキスを重ねているうちにエンドロールが流れていた。出会った日を思い出して盛り上がったと思っていたが、他のことをしていないと間が持たないほど、映画の内容が薄かったのかもしれない。
咲良栞子の唇が乾かないように、しょっちゅうグロスを塗り直していたのだけが妙に印象に残っている。ヘアメイクだと思っていた女性は、マネージャーだった。それほどお金のない現場だったのだ。
咲良栞子の待望の初主演映画とうたっていたが、間延びしたプロモーションビデオみたいな仕上がりで、話題にもならず、パッケージ化もされなかった。麻希の手元にある関係者用完パケDVDは希少な素材だ。
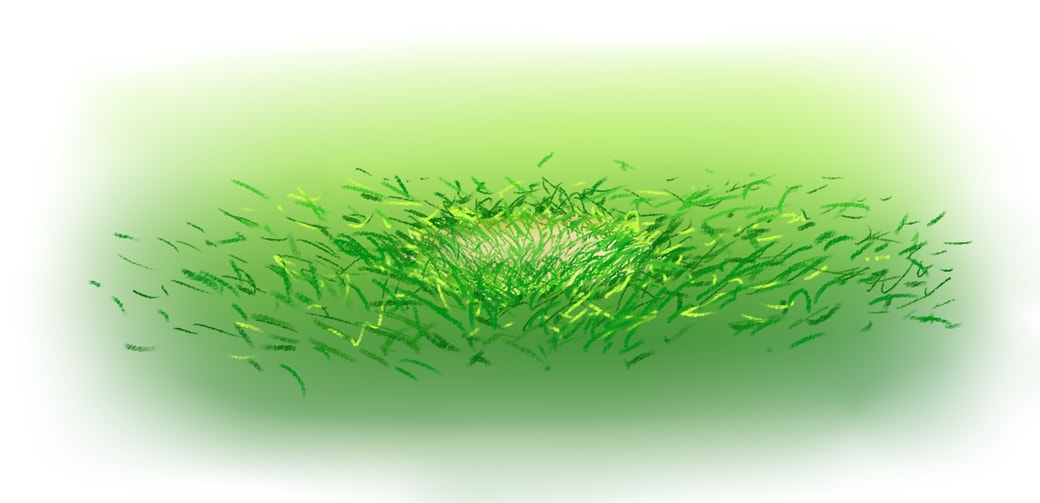
『それからのルーズソックス』の後、咲良栞子はどうなったのだろう。
25歳だった麻希にも、17歳だった彼女にも同じだけの時間が流れている。同じだけ歳を重ね、同じだけ重力に引っ張られ、同じだけ紫外線を浴びている。
撮影から15年の間に、麻希は職場をいくつも変わり、胆石をたくさん溜め、恋をふたつした。勤めていた映画製作会社はなくなり、派遣社員の身分を失い、かつてロケ地があったカフェでバイトをしている。
成長しているのか、同じところをぐるぐるしているだけなのか。
ひとつだけ確かなのは、今の自分が15年前の自分より好きだということ。そう思える安らぎをくれた彼の大きな手が麻希の髪を撫でる。
「ほよほよしたのが生えてきたね」
モリゾウの低い声が麻希の耳をくすぐる。
頭の小さな更地に柔らかい毛が生えてきた。エンダツに遅い春がやって来た。
高校生だった麻希が更地にした裏庭も、根絶やしにされたわけではなかった。やがて土を割って小さな芽が顔を出し、広がり、地面の色を変えた。
あの庭にクローバーは生えていなかったと思う。斑入りの四つ葉のクローバーは、麻希が刺繍でよく使うモチーフだ。モリゾウに勧められて始めた布雑貨のオンラインショップ。ひと針ひと針運んで四つ葉のクローバーを描いたポーチやバッグに、会ったことのない人がお金を出してくれる。40歳の自分が25歳の自分より幸せになっているなんて想像しなかった。
明け方の夢に出てきたクローバーは、麻希が失いたくない今の穏やかな生活の記号なのだろう。ツカサ君の記憶が赤と結びついているなら、モリゾウとの今は明るい緑に彩られている。

『制服のシンデレラ』を読み返したくなったのは、答え合わせをしたくなったからだった。いちごパフェと同じように、思い出にトッピングをしてしまっている可能性がある。
ツカサ君がコンクールに応募した原稿の控えを取ってあった。ツカサ君が部屋を出てから10年あまり。ダブルクリップのサビが出て、茶色くなっている。
主人公の女子高生は連続放火事件の犯人という設定だった。教科書を燃やしたら家の裏庭を焼き払ってしまった麻希より、たちが悪い。
《きっかけは、偶然だった。その日、あたしは、生まれて初めて、タバコを買った。クラスメートたちの話題に入っていけないあたしは、せめて、彼女たちと同じ冒険をしたかったのかもしれない。なんとなく立ち止まった目の前に、自動販売機があった。人生で最初の1本を吸う場所にあたしが選んだのは、さびれた印刷所の跡地だった。背伸びしたくても、クラスの女の子たちみたいに大胆になれない。先生の目が怖くて口紅さえ塗れないあたしには、駅のトイレで隠れて吸う勇気なんてなかった》
震える手で火をつけたタバコを落としてしまい、「あたしは、タバコ1本ちゃんと吸えないダメなヤツだ」と女子高生は落ち込む。その火が燃え広がってしまった。
バレたらどうしようと怯える一方で彼女は興奮を覚える。自分のつけた火が、消防車を走らせ、渋滞を引き起こし、人だかりをつくったことに。以来、炎の誘惑にとりつかれる。
《数学の時間。あたしは確率を計算する。放火がバレて、つかまる確率。つかまらない確率。火をつけるたび、誰かに見つかる確率は高くなる。あたしが安全でいられる確率は低くなる。だけど、火遊びはスリルがなきゃ、つまんない》
『制服のシンデレラ』は最終審査に残り、真っ先に落とされた。それが一番いいところまで行ったツカサ君の応募作だった。麻希が知る限りは。
「主人公にまったく感情移入できない」という審査員の講評をツカサ君と読んだ。
その通りだ。愛せないヒロイン。彼女は、どうしようもなく麻希自身だ。描かれている事件は実際の出来事とは違うのに、描かれている女子高生の屈折ぶりは、麻希以上に麻希だった。
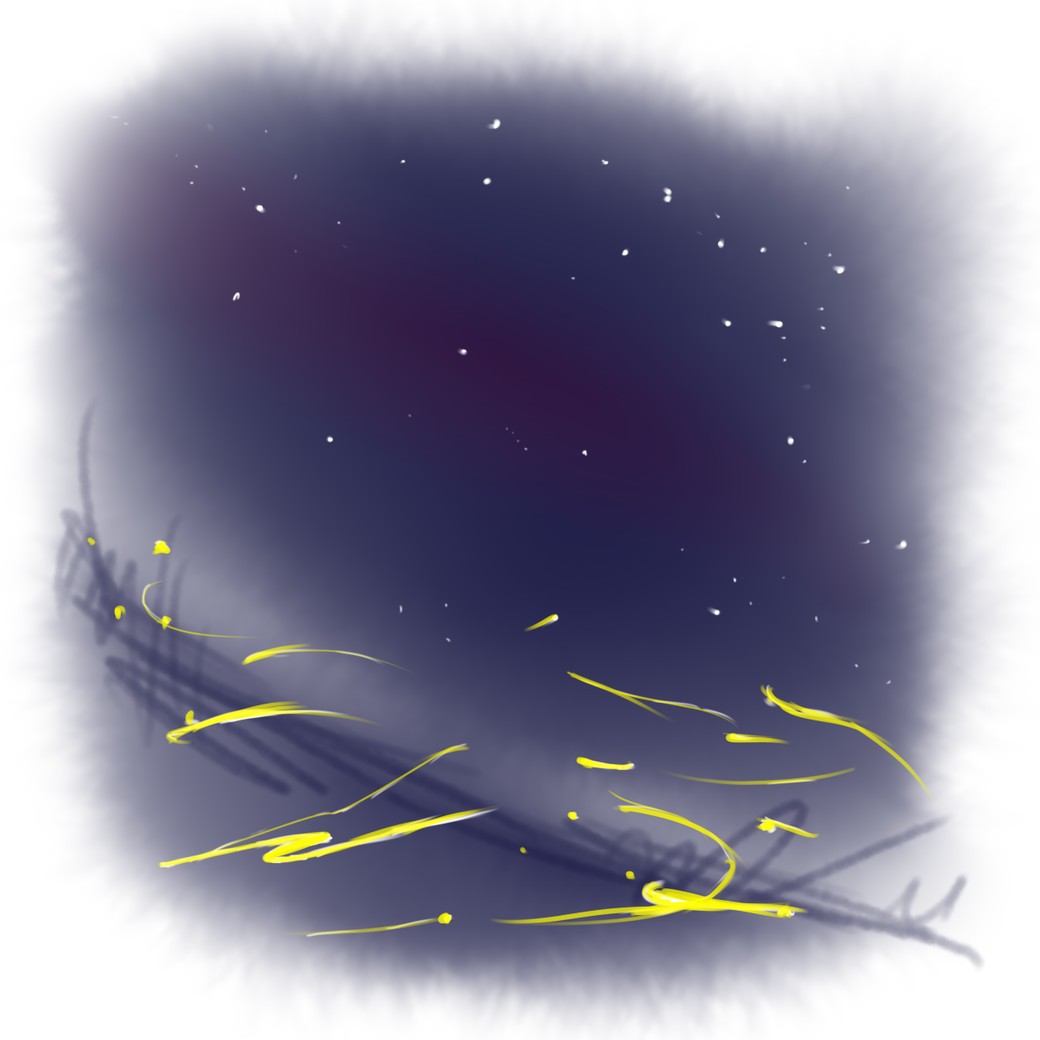
「読んで欲しいものがあるんだけど」と麻希が原稿を差し出すと、モリゾウがタイトルを読み上げた。
「制服のシンデレラ」
モリゾウに「シンデレラ」と呼ばれたみたいでドキドキする。
モリゾウなら、読めばわかるだろう。これは、わたしの物語だと。わたしと作者との関係も。それを知ったとき、モリゾウはどんな顔をして、どんな言葉を口にするのだろう。何も言わず、抱き寄せるだろうか。
「星屑蛍」
モリゾウがツカサ君のペンネームを読み上げた。
線が細くて自信がなくて、はかなげなツカサ君に似合っている。脚本家というよりファンタジーノベル作家みたい。大賞は取れないけれど佳作2編に引っかかりそうな名前だった。
ツカサ君は、『制服のシンデレラ』の後、何本か書いただろうか。いくつか恋をしただろうか。今も書き続けているだろうか。恋をしているだろうか。
「ほしくず、ほたる?」
モリゾウが繰り返した。
「どうしたの?」
「この名前、知ってる」
次の物語、連載小説『漂うわたし』第73回 佐藤千佳子(25)「同じ景色を見ていると思っていたのに」へ。
イラスト:ジョンジー敦子
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!