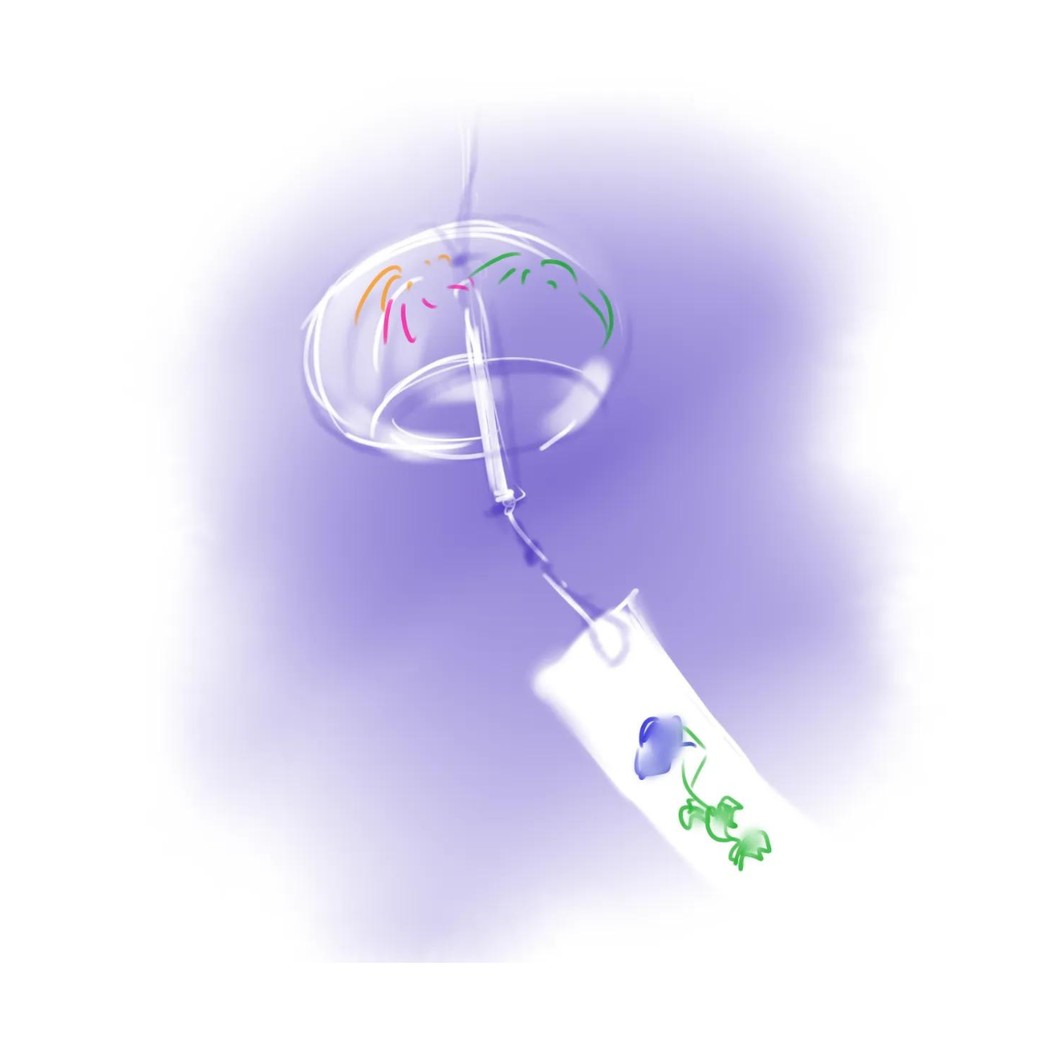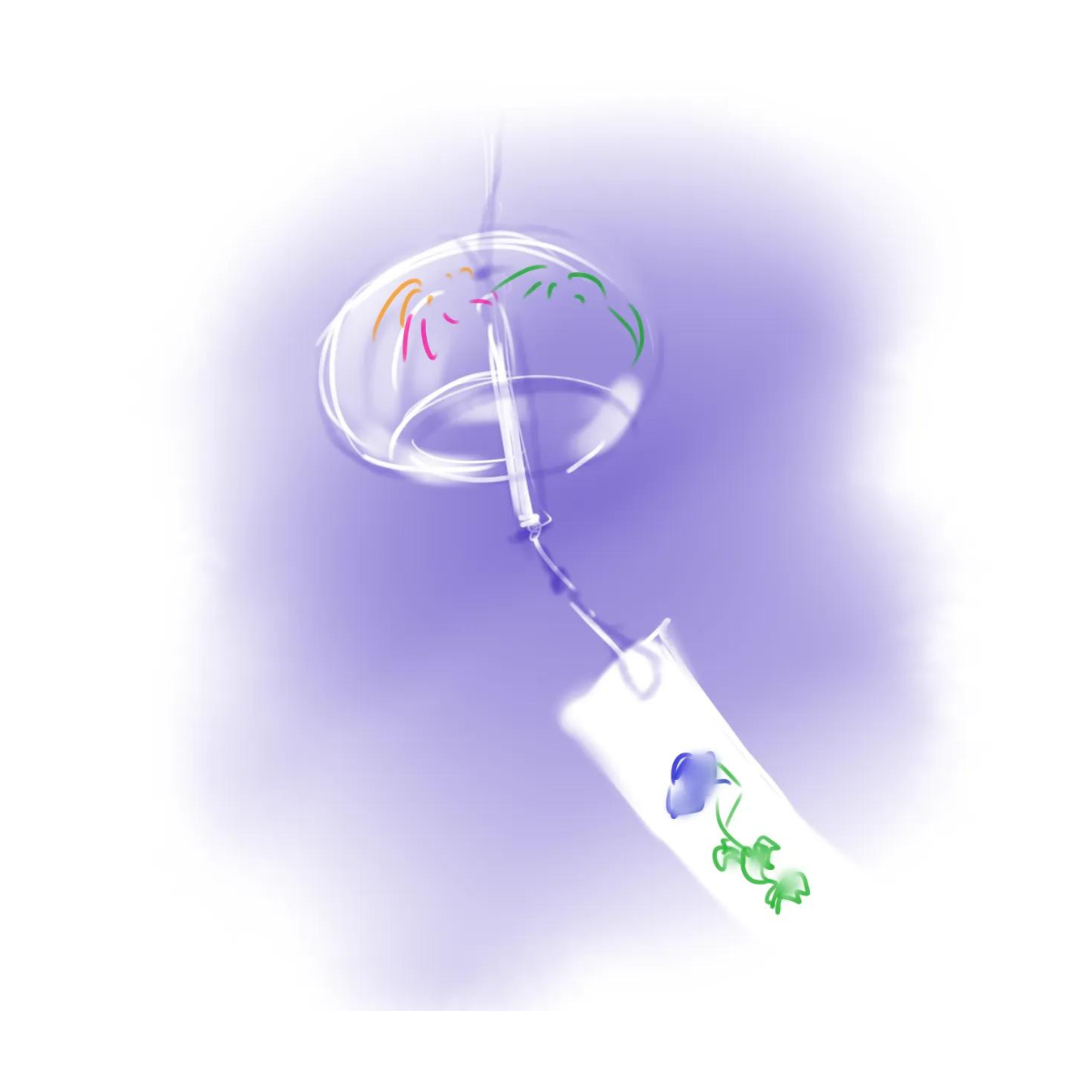第80回 佐藤千佳子(27)振り上げたこぶしの下ろし方
ノマリー・アントワネットの庭をのぞむ野間さんの家のテーブルで出されたデザートは、バニラビーンズが入ったアイスクリームだった。
「やっぱり、これでしょう」と野間さんが言い、
「やっぱり、これですよね」と千佳子はうなずいた。
相手の言うことを繰り返すだけで通じ合える。何もつけ足さず、差し引かず、捻じ曲げず。打てば響くような野間さんとの会話を取り戻せたようで、「やっぱり、これだよね」と千佳子は胸の内でつぶやく。
そのアイスクリームが野間さんと千佳子のわだかまりを溶かしてくれた。いや、アイスを買った「セイギさん」の正義感あふれる勘違いが、と言うべきか。
バニラビーンズを知らなかったセイギさんは、黒い粒々を砂だと思い、クレームを入れた。野間さんはいつものように言い返さず、セイギさんの気が済むのを待っていたが、「何を笑っているんだ!」とセイギさんが突然怒り出し、店長が割って入る事態となった。
あのとき、野間さんは「私、勘違いしてた」と放心したように言った。その意味を千佳子も勘違いしていた。
野間さんはセイギさんの中に自分を見たのだろうと千佳子は思っていた。自分だけが正しいと思い込み、声高に主張する人の滑稽さと空しさを。
だが、野間さんが「勘違いしてた」と言ったのは、店長のことだった。

声を荒げたセイギさんの怒りを鎮めてくれたのは店長だった。「パセリにリボン巻いてるヒマがあったら従業員教育をしっかりやりなさいよ」と息巻くセイギさんに、「パセリにリボンを巻いたのは私の責任です」と言い切った。
「あの対応はさすがでしたね。店長を見直しました」
「それはそうなんだけど。いや、それも関係してるんだけど、私、根本的に勘違いしてた」
野間さんの歯切れが悪い。千佳子と目を合わさず、どこか遠くを見ている。こんな野間さんをつい最近見たと千佳子は思い起こす。セイギさんのクレームを受けていたときの野間さんだ。
「根本的に勘違いしてたって、どういうことですか?」
「店長が私たちの手柄を独り占めしたって話」
そこまでさかのぼるのかと千佳子は驚く。
「今の店長の手柄にされてるけどいいのって、本部に戻った前の店長が連絡くれたんだけど、そんな事実はなかったの」
店長が本部に提出した店舗紹介写真の一枚が、パセリのクリスマスツリーが並ぶ野菜売り場だった。その写真には「パート店員の発案でパセリをクリスマスツリーに。本部から支給のクリスマスリボンを活用」と注釈が添えられていた。
野間さんがそのことを知ったのは、悔しさのあまり本部に乗り込んで自主プレゼンをした後だった。パセリのクリスマスツリーは店長ではなくパートが発案、実行したことをアピールし、パートが活躍して輝ける会社であることを発信してブランドイメージを上げていきましょうという提案で、野間さんが考えた「マルフルネス」というスローガンを掲げていた。
「本部の反応が鈍くて、この会社はダメだ、変わる気がないんだって失望して、佐藤さんに長い愚痴メール送っちゃったけど、店長が手柄を独り占めにした事実がなかったわけだから、口うるさいパートのおばさんが言いがかりつけてるみたいになっちゃった」
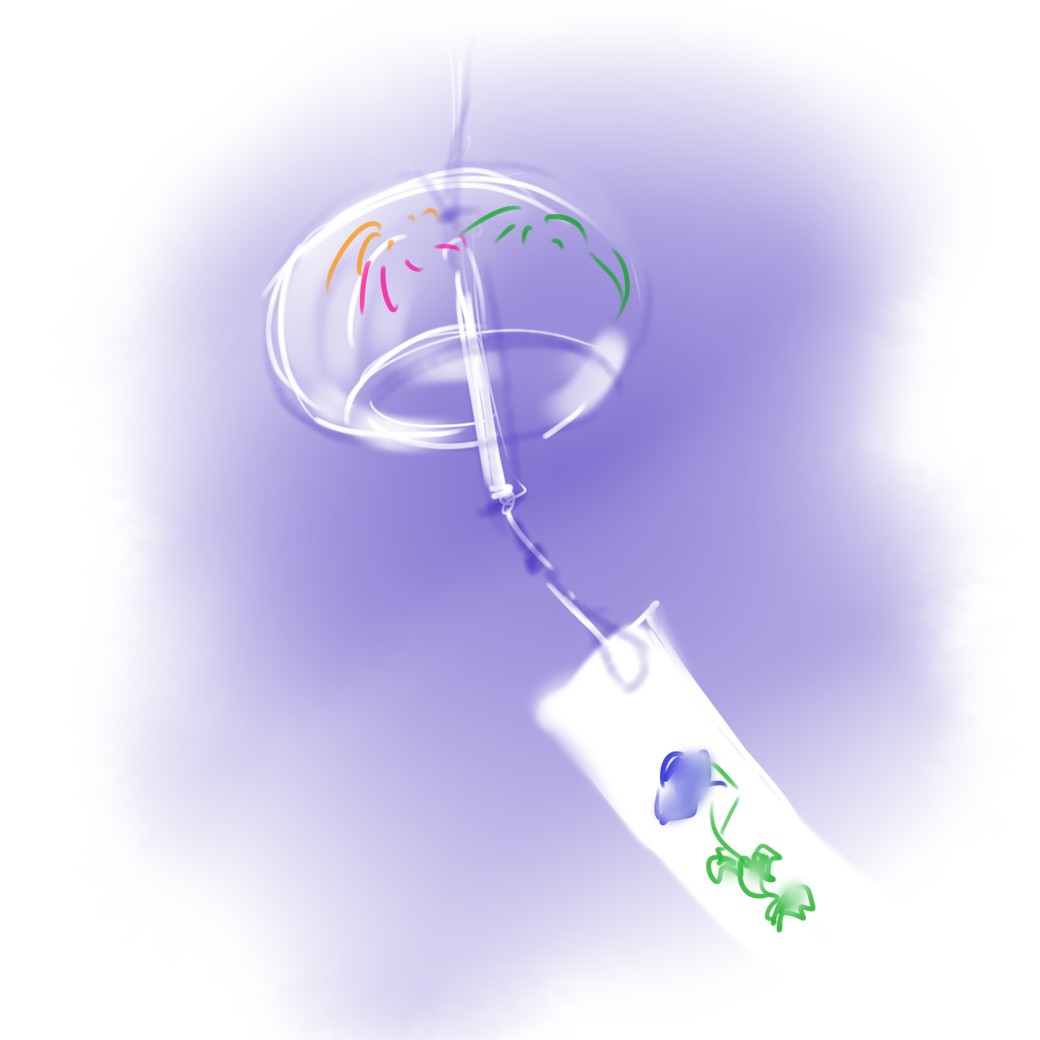
「その通り」と相槌を打つように、タイミング良く通り過ぎた風が窓辺に揺れる風輪を鳴らした。
「前の店長の勘違いだったってことですか?」
「勘違いじゃなくて、わざと私の耳に入れたっぽいんだよね」
「どういうことですか?」
「私を敵に回したら、今の店長がやりにくくなるじゃない? あの二人、同期入社らしいから」
前の店長は体育会系で威勢が良い。本部の上層部に取り入るのもうまそうだが、調子の良さでのし上がってきたようにも見える。後任の今の店長になってから店舗の売り上げが伸びているのを知って、店長の力量差だと思われては困ると焦ったのかもしれない。
「前の店長って口がうまいじゃない? 野間さんはパートにしとくのもったいないってよく言ってくれてて。今思えば、機嫌取ってただけかもしれないけど。今の店長はお世辞言わないし、頼ってくれないし、私のこと過小評価してるって思ってたの。それで私もムキになってたかもしれない。私ほんとはこんなとこでレジのおばちゃんやってる人じゃない。今も広告代理店にいて、本部にプレゼンしてたかもしれないんだぞって」
前の店長は千佳子には素っ気なかった。こいつは利用価値がないと思われていたのだろう。
「人のせいにしたくないけど、利用されたんだと思う。前の店長が今も私のこと気にかけてくれてるってうれしくなって、鵜呑みにしちゃった私がマヌケだったって話」
アイスをスプーンで口に運びながら、野間さんは話を続けた。
「そもそもパセリのクリスマスツリーが本部に評価されたわけでもなかった。紹介されたってだけ。手柄って呼べるものでもなかったんだよね」
「パセリにリボン巻いただけですからね」
「なんだ、佐藤さんのほうがよっぽどよく見えてる。やんなっちゃう」
野間さんは大きなため息をついた。
「悔しいってのは、期待と現実に開きがあるってことだからね。自分のことを過大評価してたら世話ないよね」
野間さんが自分を引いて見られるようになって、千佳子はほっとする。野間さんだって間違える。だけど、間違いに気づいて、認めて、振り上げたこぶしを引っ込められるやわらかさを持っている。
「画期的な発明でしたよ。わたしにとっては」
「そうだね。私たちにとっては」
「それでいいじゃない」と二人の声が重なった。
リボンを巻きたくなる日々を分かち合える関係は素敵だ。ほどいたリボンを巻き直せる関係は、もっと素敵だ。

ノマリー・アントワネットの庭から持ち帰った朝顔を空瓶に活けて、キッチンカウンターに飾った。夏空のような明るい青が眩しい。
「害虫だと思っていたのが益虫だった、みたいな話だなあ」
セイギさんがきっかけで野間さん問題が決着したことを報告すると、夫は食品工学の研究員らしい感想を言った。
店長のことを勘違いしていたと野間さんが確信するに至ったのは、セイギさんが野間さんを追い詰め、店長の出る幕ができたからだ。「パセリにリボンを巻いてるヒマがあったら」とセイギさんが引き合いに出したおかげで、いざというときは店長が矢面に立ってパートをかばってくれることもわかった。野間さんの勘違いは見事にひっくり返された上に、店長を見直すというおまけがついた。
もちろんセイギさんは何も知らない。いつものようにクレームをつけただけだ。
「どうするの? パートやめたいって言ってたけど」
答えはわかっているという口ぶりで夫が聞いた。
「もうしばらく続けてもいい?」
「僕が許可することでもないでしょう」
夫は涼しい顔で言った。
夫の収入の足しにと始めたパートだが、パートをやめたら家計が回らないというわけでもない。妻の意思を尊重し、好きにさせてくれるこの人は理想的な夫と言えるのだろうと千佳子は思うが、関心がないだけではないかと不安にも駆られる。
もう何年も夫に触れられていない。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第81回 伊澤直美(27)「創作って埋め合わせだから」へ。
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!