
第8回 佐藤千佳子(4) パセリが主役になる日
ピッ。《人参》。
ピッ。《じゃがいも》。
ピッ。《玉ねぎ》。
カレーかな。
ピッ。《豚の細切れ》。
カレーじゃなくて、肉じゃがかも。
ピッ。《糸こんにゃく》。
ピッ。《絹さや》。
やっぱり肉じゃが。うちも肉じゃがにしようかな。
パート先のスーパーで商品のバーコードをレジに通しながら、千佳子はその材料から作られる献立を想像し、今夜の献立の参考にする。娘の文香がバスケ部の練習で遅くなる火曜から金曜の午後2時から6時にシフトを入れ、帰りに夕飯の材料を買う。
パートを始めて半月。ピッ、ピッと規則正しいリズムでバーコードを読み取りながら頭の中では別なことを考えられるくらい、仕事には慣れた。右から左へ商品を動かすだけの単純作業。会計は「何番でお願いします」とセルフレジに誘導すればいい。
ピッ。《生ハーブ》。
肉じゃがに生ハーブ?なんか意外。
「やっぱりやめるわ」
心の声を聞かれたようで、千佳子はハッとなって顔を上げる。ピッ、ピッのリズムが止まった。
お客さんは白髪を上品な紫に染めた小柄な女性だった。以前、セルフレジの使い方がわからず困っていたときにお手伝いしたことがあった。千佳子の夫の母に雰囲気が似ているので印象に残っている。「ごめんなさいね」と言う物腰がやわらかい。
キャンセルされたのは、コップに水挿ししたハーブだった。数種類のハーブを花束のように束ねている。
品物を棚まで戻しに行くと、向かう先の野菜売り場からよく通る声が聞こえてきた。
「食べられる生ハーブブーケ、いかがですかー」
モスグリーンのエプロンを着けた女性が、千佳子が手にしているものと同じ商品を手にして、声を張り上げていた。ハツラツとした声の印象そのままに、ハツラツとした表情をしていた。
わたしと同い年ぐらいかな。肌にも声にもハリがある。ハーブを食べていると、あんな風になるんだろうか。
「これ、お花のブーケみたいに、このまま飾れるんです。これがあるだけでキッチンが華やかになります。ハーブの彩り、取り入れてみませんか?」
「彩り」という言葉に、晴翔くんママの家でのランチ会が蘇る。自分は隙間を埋める彩りのパセリのような存在なのだと割り切っていたけれど、途中からは彩りにさえなれていないように思え、干からびていくパセリのようなわびしさまで味わった。
「彩り」と聞いて、もうひとつ思い出すのは、娘の文香の言葉だ。文香が小学5年生のとき、発育の早い子がブラをつけ始めた。自分もつけたいと言う文香に、必要ないでしょと千佳子が告げると、
「関係ないの!いろどりなんだから!」
唇を尖らせて文香は言い張った。機能ではなく彩りが必要なのだと訴える真っ直ぐさに、うたれた。千佳子がどこかに置いてきて、娘がどこかから拾ってきたもの。そして、今も千佳子に欠けているもの。文香の言う「彩り」と晴翔くんママが言った「女は先っぽに宿る」は、同じ意味なのだろう。
「お客様、今、目が合いましたね。合っちゃいましたね」
ハーブの人の声に、自分が呼び止められたのかと思い、千佳子はギクリとなる。ハーブの人の目の前を通り過ぎようとした学生っぽい若い女性が足を止めた。
「生ハーブ、ぜひ、味方にしてみてください!お料理のレパートリーが、ぐんと広がります。ミニレシピもつけてます。これ、私が書いて、自分で印刷してるんです。お買い上げいただけます?ありがとうございます!」
千佳子は自分がその若い女性になったような気持ちで成り行きを見つめる。
あの人はどうするだろ。わたしだったら断れない。
若い女性は生ハーブブーケを買い物カゴに入れた。
あの勢いに押されて、紫の髪の女性も品物をカゴに入れ、レジで思い直したのだろう。あの学生っぽい女性はどうだろうとレジへ向かう背中を目で追うと、無事会計を済ませてくれ、ほっとする。
ハーブの人とわたしは、何の関係もないのに。
張り切ってハーブを売り込んでいるその人の目の前で棚に戻すのは、気が引けた。自分で買って帰ろうかと思って値段を見ると、思っていたより高かった。この値段でレタスを2玉買える。ハーブの人が持ち場を離れるのを待って、千佳子は商品をそっと棚に戻した。
そのとき、パセリが視界に入った。バジルやオレガノやルッコラと並んで、ハーブコーナーに置かれていた。今まで意識していなかったが、パセリもハーブなのだろうか。
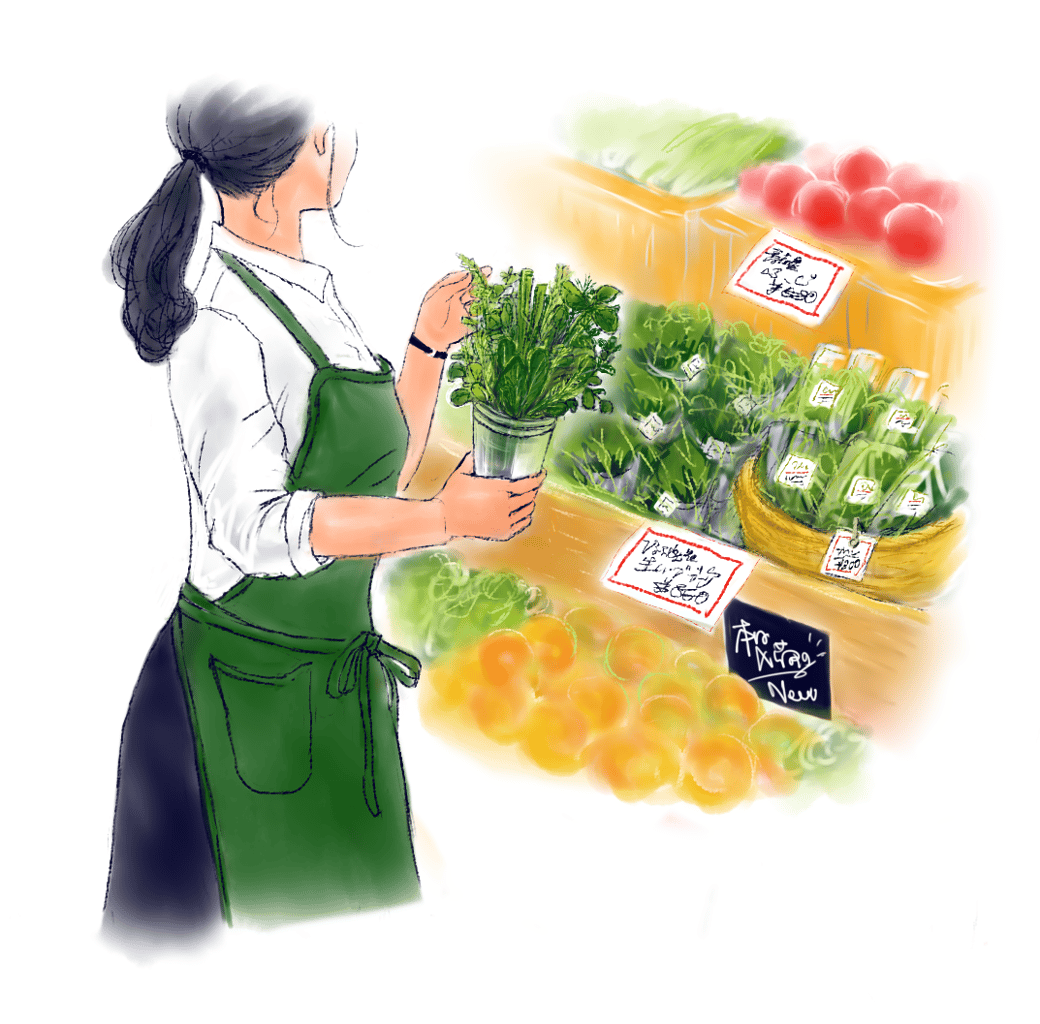
「ママー、晩ご飯何?」
バスケ部の練習でおなかを空かせて帰宅した文香が、パセリを刻む千佳子の手元をのぞき込む。
「パセリバターで鶏肉焼いてみようと思って」
「それパパ絶対うなずくやつだね」
「うなずくかな」
「うなずくよ」
夫は口数が少ないが、好みの味のものを口にするとうなずく癖がある。肉で一番好きなのは鶏で、バターやチーズといった乳製品も好む。
「何これ?花瓶にパセリささってるんだけどー」
ドレッシングの空き瓶に挿したパセリに文香が目を留め、爆笑した。
「パセリの花束。可愛いでしょ」
「花束ぁ?なんでパセリ?」
「ハーブブーケっていうのを売り場で見て、真似してみたの」
「ママ、ウケるー」
「もう、ふーちゃん笑い過ぎ!」
文香につられて千佳子も笑い出したところに夫が帰宅した。夫は結婚以来、外で食べて来ることがめったにない。つき合いの薄い職場なのか、誘われても断っているのか。家族3人揃って8時から食べ始める。
鶏のパセリバター焼きを口に運んだ夫が、予想通り首を大きく縦に振ってうなずき、千佳子と文香は顔を見合わせて笑った。
「え?何?」
「何でもない」
「何でもないよねー」
「何だよ」
夫は首を傾げながら、また鶏を口に入れ、またうなずき、それを見て、千佳子と文香はまた顔を見合わせて笑った。
「そうやって笑うと、似てるね」
母娘のにやけた顔を見て、夫が言い、千佳子の「やったー」と文香の「やだー」が重なり、今度は家族3人で笑った。
家族の顔が似てくるのは、同じものを食べているからという説があるが、同じ食卓を囲んで、同じ瞬間を共有しているからなのだろう。夫婦も。親子も。今、わたしたち3人は、よく似た顔で笑っているに違いない。

その夜の食卓で、パセリは添えものではなく人気者だった。テーブルの真ん中に躍り出て、話題をさらった。
キッチンカウンターに置いた瓶挿しのパセリに、千佳子は目をやる。食洗機を諦めた代わりにこだわった天然木の天板に鮮やかなグリーンが映え、キッチンが明るく見える。
パセリの花束にどんなストーリーがあるのか、娘は知らない。瓶挿しのパセリにすら気づいていない夫は、もちろん知らない。
パセリだって主役になれるという手応えは、千佳子の自己満足でしかない。
「自己満足でいいじゃないの。満足って、満ち足りるってことなんだから」
「ママ、なんか言った?」
「なんか聞こえた?」
「独り言が増えるのって老化なんだって」
「せめて熟成って言って」
「ハムかよ。ウケるー」
ハムと組み合わせるなら、文香の好きなポテトサラダをパセリマヨネーズで作るのはどうだろう。グラタンにしてもいいかも。ガーリックバタートーストにハムをのっけてパセリを散らすのは、夫がうなずきそうだ。
自分がやりたいことは思いつかないけれど、家族が喜びそうな献立は次々と思い浮かぶ。指先をネイルで彩るより、パセリで食卓を彩るほうが、わたしは楽しい。
無理して他の何かを見つけなくたっていいじゃない。わたしには、パセリの花束が似合うんだから。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第9回 伊澤直美(3)「子育てより仕事のほうがラク!?」 へ。
イラスト:ジョンジー敦子
※表示価格は記事執筆時点の価格です。現在の価格については各サイトでご確認ください。
























































































































































































































































































































































































































































