
第108回 多賀麻希(36)わたしの顔を見に来た彼女
ドアが開く音に麻希がスケッチブックから顔を上げると、パンツスーツの女性が一人で入ってきた。スーツやドレスを折り畳んで持ち運ぶテーラーバッグを肩からかけている。手足が長く、首も長く、立ち姿が美しい。内側からしっかりしたものに支えられている。体幹なのか、自信なのか、愛なのか。
待ち合わせの相手ではないと思ったが、彼女は空いているテーブルではなく、人がいるテーブルを探し、そこにいる人待ち顔の麻希を見つけた。
「makimakiさん、ですか?」
「……はい」
「ご連絡を差し上げたミューです」
アカウント名のMYUはミューと読むらしい。
向かいの席に着いた待ち人は、ケイティが吹き飛ぶほど美しい人だった。ほとんど色をのせていないナチュラルメイクなのに、華がある。何も足す必要のない顔。
「いつも持ち歩かれているんですか?」
麻希が表紙を閉じたスケッチブックにMYUさんが目をやった。まつ毛まで胸を張っている。
「ちょっと……」と麻希は誤魔化す。不用意にこちらの手の内を見せないほうがいい。ドアチェーンをかけたままドアの隙間から来客をうかがうように相手を見る。MYUさんは麻希の飲みかけのコーヒーを見て、「お待たせしちゃいました?」と屈託なく言う。
「早く着いてしまって。すみません。お先に」
「ぜーんぜん。私もコーヒーにしようかな。焙煎珈琲って表の看板に書かれてましたよね」
「ブレンド、お淹れしますね」とカウンターの中からマスターが声をかける。
「聞こえてました? お願いします」
何を言っても明るく清潔感がある。日当たりのいい庭で風に吹かれている白シャツのようだ。だけど、ドアチェーンを外すのはまだ早い。熊本から東京に出て来た18歳の春、原宿で声をかけてきたエステの勧誘員もイヤミのない美人だった。のこのこついて行ったら、高額のプランを契約させられそうになった。
「会っていただけて良かったです。警戒させちゃいました?」
麻希が思わず「はい」と答えてから「すみません」と謝ると、「やっぱり怪しいですよね」とMYUさんは歯並びのいい歯を見せて笑った。歯の健康ポスターにして飾れそうな笑顔だ。
「実は私、結婚を控えてまして」
「へ?」
「おめでとうございます」と言うべきところだが、間抜けな声が出てしまった。
ひまわりバッグのことで話があるのだろうと思っていた。味方なのか、警戒すべき相手なのか、見極めようとしていたら、全然違う方向から話が飛んできた。メインディッシュを肉か魚のどちらにしようかと迷っていたらデザートが出てきた、そんな展開に頭が追いつかない。
「コーヒーが来る前に、見ていただきたいものがあるんですけど」

MYUさんがテーラーバッグを開いて取り出したのは、ウェディングドレスだった。麻希は自分のコーヒーカップを隣のテーブルに移し、ドレスを見る。手仕事と思われる刺繍が施された繊細なレース。なめらかな手触りが見た目から伝わってくる。
「サイズはぴったりなんですけど、ところどころシミになっているんです」
桜色にネイルした指で茶色くなっているところを指し示すと、MYUさんがドレスから顔を上げて麻希を見た。
「こちら、お預けしていいですか」
「え?」
「送らせていただいたほうがいいですか」
「えっと……」
これは何かの罠だろうか。美人局という言葉があるが、ウェディングドレスを押しつけて、後から高額の請求をされるとか。
「結婚式が延びたんです」とMYUさんが続けた。「それで、実家を片づけていたらこれを見つけたんです。母が結婚するときにあつらえたドレスで、写真では見たことがあったんですけど」
「はぁ」
「式がのびてなかったら、見つけてなかっただろうし、これを着なさいってことかなって。ちょうどその日、makimakiさんのショップを知って。どれも素敵で。とくに四つ葉のクローバーの刺繍シリーズが好きです。針運びが丁寧だなあって。この人なら、このドレスにどんな刺繍をしてくれるんだろうって」
喜んでいいのだろうか。でも、できすぎた話だ。チェーンを外してドアを開けた途端、なーんてねとドレスを引き上げられるのではないだろうか。優しそうなおばあさんが差し出したおいしそうな林檎に毒が塗られていたりするのだ。
「あ、お金の話がまだでした」
麻希の沈黙の理由をMYUさんは勘違いした。この人には裏なんてない。表しかない。
「あの……MYUさんはわたしのこと、どこまでご存じですか」
「どこまで、と言いますと?」
どこから話せばいいのだろうと麻希は言葉を探す。まだ知らないのなら、知らないままでいてもらったほうがいい。でも、いずれ知られるなら早いほうがいい。
「ケイティさんがよく似たひまわりバッグを出されていること、ですか?」
MYUさんがスパッと本題に切り込んだ。
「ご存じ、でしたか」
「はい。それでmakimakiさんのショップを知ったんです」
「そうなんですか?」
「でも、もしかしたら今、誰にも会いたくないかもしれないって思って。会ってもらえなかったらご縁がなかったって諦めるつもりで、メッセージを送ったんです。単純に作った人の顔を見てみたかったってのもあるんですけど」
「え?」

「makimakiさんは、本を読んで、作者に会いたくなったこと、ありませんか」
「……あります」
「それと同じです」
「……会って、がっかりしませんでしたか?」
「私、こういう勘は結構当たるんです」
「……ありがとうございます。でも、いいんでしょうか。お母様の形見のドレスをお預かりして……」
「生きてます」
「え?」
「生きてます。母」
「あ……すみません」
MYUさんが吹き出したのにつられて、麻希も笑う。笑うと力が抜けて、肩に力が入っていたのがわかる。なんでそんなストーリーを作ってしまったのか。でっち上げた美談ではないかと身構えたせいだろうか。
「母は元気ですけど、このドレスは生き返らせてあげてください」
「生き返らせる……」
その言葉が自分とショップにも向けられているようで、麻希は鼻の奥がツンとなる。
「それで、まずは手付金といいますか……」
「いえ、お金なんて……声をかけてくださった、そのお気持ちだけで……」
「マキマキ、受け取っとき」
MYUさんがドレスをバッグにしまうタイミングを見計らってコーヒーを運んできたマスターが麻希をあだ名で呼んだ。MYUさんが「ん?」という顔になったのを見て、麻希が目で咎め、マスターは口を「あ」の形にして固まった。
「こちら、よく来られるんですか」
「あ、はい。実は……ここでバイトしているんです。しばらく休んでて、今日久しぶりに来たんですけど」
「そうだったんですね。さっきから保護者の目で見てらっしゃるなって思ってました」
「保護者の目?」
麻希がマスターを見ると、マスターが「役者にはなれんなあ」と苦笑いした。
「申し遅れました」とMYUさんが名刺を出した。麻希がよく知っている社名だった。
「アイタス食品。レンチンシリーズでお世話になってます」
「この名刺だって作れちゃいますけどね」
ふふっと企みを共有するように笑い合う。何を信じていいのかわからないことばかりだけど、この人を信じていいという直感は信じられる。だから、顔を見て、声を聞いて、同じ時間、同じ空気を分かち合う。
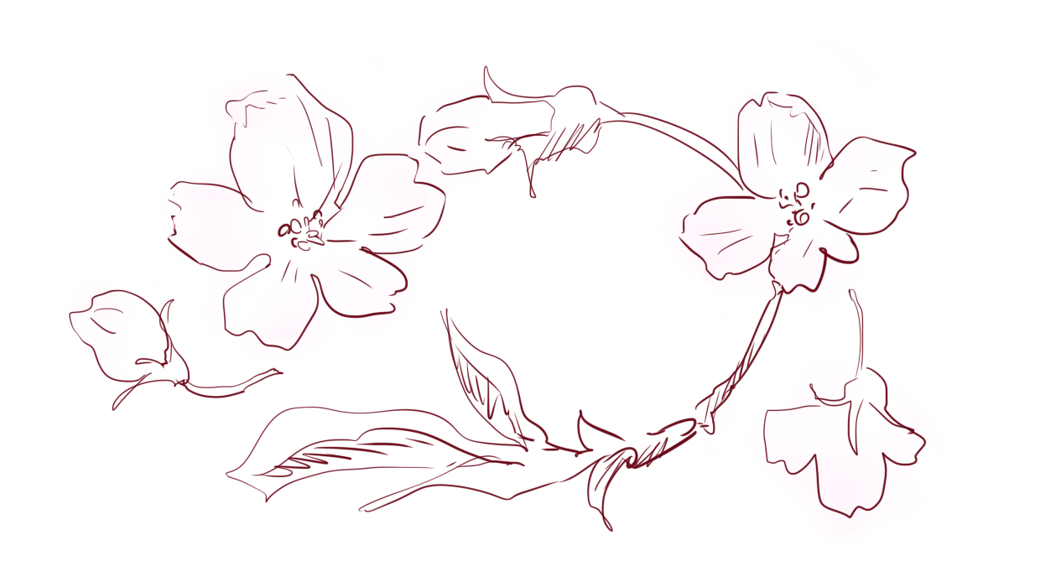
マスターの助けが必要になったら表紙を開くと合図を決めていたスケッチブックの出番はなかった。
カウンターの桜をスケッチしていたのは、手持ち無沙汰だったから、だけじゃない。もし、ひまわりバッグのデザインについて相手が何か言ってきたら、これを見せようと思っていた。わたし、自分でデザイン画起こしてますよと証明するつもりだった。ガチガチに警戒していたのに、差し出されたのは、春の陽射しのように明るくやわらかく胸を膨らませてくれるものだった。
名もなき作家への信頼を寄せたドレスと手付金と名刺を残し、MYUさんあらため田沼深雪さんは去って行った。
「ケイティの身内かと思たけど、違ったな」
ふたり分のカップを下げながらマスターが言った。
それは彼女を見たときからわかっていた。ケイティは自分を霞ませるような人をそばには置かないはずだから。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第109回 佐藤千佳子(37)「埋蔵主婦を卒業します」へ。
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!






















































































































































































































































































































































































































































