
第128回 佐藤千佳子(44)子ども服はタイムカプセル
フリマアプリを開くと、ひまわりが目に飛び込んだ。
ひまわりの形をしたバッグだ。ハダカのひまわりのことを手紙に書いていた野間さんの顔を千佳子は思い浮かべ、飛びつきそうになったが、1万円という値段に思い止まった。
同じものが他に出品されていないかを調べてみる。すると、すでに売れたものを含めて、10件ほどあった。値段は1万円前後。新品未使用で2万円をつけているものもある。元は3万円近くするらしい。
花そのものをバッグにしてしまう大胆なデザインは、野間さんから贈られたチューリップバッグを思わせる。こんな個性的なバッグ見たことないと思っていたが、こういうのが流行っているのだろうか。もしかしたら同じブランドなのだろうか。
商品説明には「ケイティさんのオリジナルブランド」と書いてある。「ケイティ」でアプリ内検索すると、ひまわりの形のポーチや財布も出品されていた。他に「ケイティさん愛用」をうたった化粧品やアクセサリーがヒットした。ケイティという人は、タレントか何かだろうか。
「ケイティ」について検索しかけて、何やってたんだっけとなり、アプリを開いた目的を思い出す。文香の子ども服を出品しようとしていたのだ。

この夏、岩手に帰省する予定が急遽取りやめになった。
千佳子のパートと夫の仕事と文香の部活の休みが重なる土日を挟んだ3泊4日を予定していたのだが、出発の前日になって「来ないほうがいい」と電話があった。
同じ町内に住む老夫婦の家に東京在住の息子一家が帰省していたのだが、「例の病を置いて行った」のだと言う。息子一家が帰った後に両親が相次いで発症し、息子と会食した同級生たちからも感染報告が相次ぎ、4年ぶりの夏祭りが中止になってしまった。千佳子たちの帰省とちょうど重なっていたその夏祭りが楽しみでもあったのだが、「祭りもなくなったし、今帰ったら目立つ」という理由での「来ないほうがいい」だった。
まだ完全に終わったわけではないとは思っていたが、やはりまだ続いているのだ。マスクを外してもご近所の目という締めつけは追いかけてくる。
「やめとく」と伝えると、電話の向こうで、母の声はホッとしていた。千佳子たちだって、せっかく4年ぶりに帰省して、夏祭りを取り上げられた恨みの矛先を向けられてはかなわない。
そういうわけで、延び延びになっていた子ども服の整理をする時間ができたのだった。
小学校の読み聞かせボランティアをやっていた頃、上が男の子で下が幼稚園児の女の子という人がいて、おさがりを定期的にもらってくれていた。だから120センチ前後の服はほとんどはけたのだが、その前後がどっさり溜まっていた。文香が小学校を出た後の140センチサイズ以上と、2、3歳の頃に着ていた100センチ前後。衣装ケース2段分。
古着屋でまとめて引き取ってもらおうと、試しに10点ほど持ち込んだところ、値段がついたのは2点だけだった。示された査定金額を見て「2着で600円」だと思ったら「2着で60円」だった。ブランド物だが、文香が着ていたのは10年余り前だ。以前古本を買い取りに出したときも落差に驚いたが、古着に比べたらまだ良い値段がついていた。
さすがにその金額ではと引き上げ、フリマアプリに出すことにした。
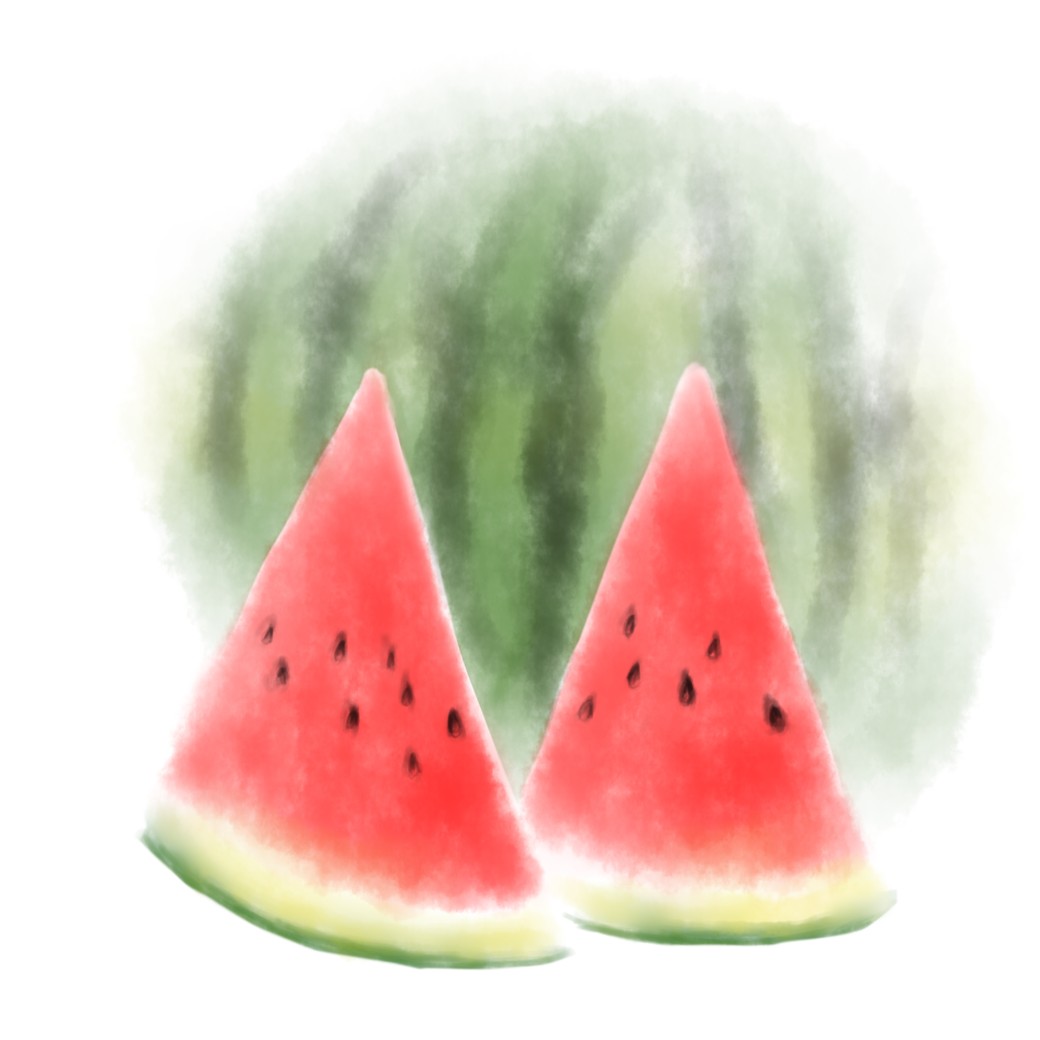
比較的状態の良い、値段のつきそうなものをより分けていると、
「これも出すの?」
高校1年の2学期が始まった文香が帰宅し、ワンピースを手に取った。
「出さないよ」
「出すとしたらいくら?」
「出さないって」
「ばあばが悲しむから?」
ワンピースは夫の母から贈られた。ブランドのタグはついていない。息子の結婚が決まって間もなく、「孫に着せたい」と一目惚れして購入したが、出番のないまま箪笥の奥で眠っていたという。
いつもは距離を保っている義母が、このワンピースのことにかけては熱心だった。文香がまだ歩き始めたばかりの1歳過ぎの頃、そろそろ着せてやってはどうかと言われた。千佳子はまだ早いと思ったが、案の定、裾を引きずった。義母は満足げにうなずき、涙ぐみ、「やっと着てもらえた」と声を詰まらせた。
不妊治療をやめて間もなく妊娠がわかったとき、「そんなもんよ」と義母は言った。まだかと催促されたことは一度もなかった。なのに、ワンピースと一緒に何年も待たせていたのだ。そのことを口にしなかったのは、気を遣ってくれていたということだ。
「重いな」と思った記憶がある。「お義母さん、その思い入れ、余計です」と五七調で浮かんだ言葉を口にはしなかったが、顔には出ていたかもしれない。
「ふーちゃん、これ着てたときのこと覚えてる?」
「覚えてないけど、写真こればっかだし」
季節を問わず、よく着ていた。冬は中にセーターを着込んで。それでもまだ生地はしっかりしている。深みのある緑と茶色という配色は、地味で子ども服らしくないと当時の千佳子は思ったが、着せてみると、どんな服よりも文香を愛らしく見せた。

16歳になった文香の体にワンピースを当ててみると、かつて引きずっていた裾が太ももの辺りに来た。
「ワンピースは大きくならないけど、ふーちゃんはどんどん大きくなるね」
「ワンピースが成長したらホラーだってば」
この服を何度着せて、脱がせて、洗って、干したことか。
古着の値打ちは歳月が経つと目減りするけれど、思い入れは降り積もる雪のように時間の分だけ重くなる。
このワンピースはお金には換えられない。誰か大切な人に受け継いで欲しい。できれば、孫とか。
まだ見ぬ孫がこのワンピースを着て裾を翻しながら走り回る姿を思い浮かべて、涙が出そうになる。
孫? ふーちゃんの娘?
何言ってるの? まだ高校生なのに。
生まれてくる孫が男の子か女の子かわからない、孫が生まれるかどうかもわからないときからワンピースを用意していた夫の母の気持ちが今ならわかる。
「ふーちゃんに女の子が生まれたら着せてあげて」なんて不用意なことを言ってしまわないように、いっそ手放したほうがいいのかもしれない。
「ママ、何ブツブツ言ってんの?」
「子ども服はタイムカプセルだなって」と千佳子がしみじみと言うと、
「博物館みたいにガラスケースに入れて飾っちゃう?」と文香がからかい、続けた。
「子どもは生きてるタイムカプセルだよ」
文香の言葉の面白さに気づかせてくれたのも、このワンピースだったと千佳子は思い出す。
家族で植物園に行ったとき、木立の枝と葉とワンピースの色が同化し、文香が隠れた。「あれ? ふーちゃんがいない」「どこ行ったのかなー」と今よりずっと若かった千佳子と夫は、親になるまでやったことのない芝居口調と仕草で辺りを見回した。すると、文香が言ったのだ。
「ふーちゃん、いま、もりになってる」
今、森になってる。
自分にはない感性を持ち合わせた、まったく別な生き物が自分から生まれ出て、育っているのだとそのとき千佳子は感じ入った。
あの日の眩しさもワンピースは閉じ込めている。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第129回 伊澤直美(43)「今がいちばん可愛い」へ。
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!




















































































































































































































































































































































































































































