
第41回 多賀麻希(13) 自分で自分に値段をつけるのって難しい
「1万円だともらいすぎかな」と麻希が言うと、
「2万円でも安いっすよ」とモリゾウは言った。
モリゾウの演劇仲間の古墳王子に頼まれて作った古墳型のバッグの値段。もし向こうから金額を聞かれたら何と答えようかとモリゾウに相談していた。
「2万円もらったって、時給にしたら千円切ってますよ」
「でも、刺繍とパッチワークは頼まれたわけじゃなくて、わたしの趣味だし」
「材料費だってかかってるし、俺だったら3万もらいます」
グリーンの布は古墳王子から託されたが、留め具と吊り紐はバッグに合ったものを調達し、それなりの出費になった。材料費込みで「2万」と言ってみて、反応を見てみることにした。
「うわー、素晴らしいです! イメージ通りですよ!」
麻希のバイト先の新宿三丁目のカフェに現れた古墳王子は、古墳バッグに歓声を上げた。テーブルにバッグを広げ、コーヒーカップと並べてアングルを探り、写真を撮ると、続けてスマホを操作する。麻希からは見えないが、インスタに上げているのだろう。「古墳王子」のハッシュタグをつけて。気に入ってもらえて良かったとホッとしつつ、やはり2万は高いだろうかと迷っていると、
「麻希さんに頼んで良かったです!」
王子はバッグをつかむと席を立ち、爽やかな笑顔を残して店を出た。
お金の話は出なかった。バッグの代金は、グリーンの布と一緒に渡されたシュークリーム2個ということか。
「コーヒー、飲んでいかんのかいな」
カウンターの中から見ていたマスターがぼやいた。王子はコーヒー代も置いて行かなかった。

「コーヒー代、バイト代から引いといてください」
写真の背景だけに使われたコーヒーのカップを下げながら麻希が言うと、「マキマキが出すことはないて。いつものことや」とマスターは言った。
以前、古墳王子が撮影で店を借りたいと言ってきたときも、当然のようにお金を出さなかったのだという。
「王子って、モリゾウに貸しでもあるんですか?」
「そら、ずっと住ませとったわけやから」
「え? モリゾウと王子って一緒に住んでたんですか?」
「せやで。聞いてへん?」
初耳だった。マスターによると、モリゾウが古墳王子の下宿に転がり込み、住みついたらしい。
「学生の頃からて言うてたから、十年じゃきかんか」
「そんなに?」
「けど、モリゾウがおられんようになって、王子の部屋を出ることになったんやて」
恋愛がらみだろうか。王子に恋人ができて、モリゾウの居場所がなくなったのだろうか。それにしても、あの二人が十年あまりも同居していたとは。代官山のカフェでモリゾウから古墳王子を紹介されたとき、どちらかといえば、よそよそしさを感じたが、同居解消のゴタゴタを引きずっていたのかもしれない。
「金の切れ目が縁の切れ目やったんやろな」
マスターは恋愛がらみとは違う事情を想像している。
「モリゾウ、金入れてなかったんとちゃうやろか」
「お金って、家賃とか?」
「家賃やら光熱費やら食費やら」
モリゾウが幼い頃、家の電気を止められた話を麻希は思い出す。今もお金はないが、学生時代から苦労していたのかもしれない。
「古墳王子としては、貸しを返してもろてるつもりなんやろな。モリゾウとマキマキは別やのに」
マスターはそう言うが、モリゾウの借りの幾らかを手作りのバッグで返せたのだと思うと、悪い気はしない。それに、
「麻希さんに頼んで良かったです!」
さっき古墳王子に言われた言葉の甘い響きが、耳の奥に残っている。1万円札2枚のときめきには負けるけど、お金にかえられないお礼を受け取った。
でも、そう思うのは、強がりなのかもしれない。お金のためになんかやってないというポーズ。好きでやっていることだからお金は二の次なんて言っていると、つけ込まれる。本当は受け取れたほうがいいに決まっている。

「モリゾウが王子の部屋を出たのって、わたしが初めてこのお店に来た頃ですか」
「せや。モリゾウがここで寝泊まりしとって」
「ちょうどわたしがいたときに、荷物取りに来たんですよね。絶妙なタイミングで」
「まぁ、僕が呼びつけたからな」
「え?」と麻希は思わず聞き返す。
「マスターがモリゾウを呼び出したんですか」
「せやで。マキマキと気ぃ合いそうやなて思て」
「そうだったんですか」
「まさかその日から住みつくとは思わんかった」
麻希だって意外だ。今でも、なぜこんなことになったのか不思議に思う。あの日、モリゾウと一緒に店を出て、なんとなく新宿三丁目駅に向かって歩き出し、なんとなく麻希の電車にモリゾウも乗り込み、なんとなく麻希が降りる終着駅までついて着て、そのまま引き返さず、麻希の家に向かった。
なんとなく。
麻希はそう思っていたけれど、モリゾウは違ったのかもしれない。店に置いてあったリュックを担いで、あの日、モリゾウは店ではないどこかに泊まるつもりだった。キャンプにでも行きそうな大きなリュックの中には、着替えもタオルもコップも歯ブラシも入っていた。
住所を持たないモリゾウは、人なつこい猫が軒先に居場所を見つけるように、出会った女性の懐にするりと入り込み、部屋に上がり込み、寝床を確保することを繰り返してきたのだと思っていた。麻希はモリゾウの人生と交差する何人ものうちの一人で、同居は一時的なもので、長くは続かないのだと。
麻希の予想に反して、モリゾウは麻希の部屋に居着き、半年が経った。相変わらず電気がつく生活に感謝し、炊きたてのご飯に感激し、それ以上のものを求めない。フローリングの固い床では背中を痛めてしまうからと麻希がマットレスと枕を買い、寒くなってきたので毛布も買ったが、モリゾウは寝るとき以外は布団を畳み、私物を散らかさず、大柄な体の割には場所を取らないし、主張しない。その代わり、麻希の気持ちの中ではモリゾウの占有面積が日に日に大きくなっている。
「マキマキに悪いことしたかなて思っててん」
「なんでですか」
「モリゾウに住むとこ紹介するつもりはなかったんやけど、結果的に古墳王子の穴埋めさせてしもて。モリゾウ、マキマキにも金入れてへんやろ?」
「まぁ、ない袖は振れないですから」
「いくらかは入れてもろたほうがええんとちゃう?」
「いつかモリゾウが儲かったら、ドカンと返してもらいます」
「返してもらう」と何気なく言ってから、わたしもモリゾウに貸しがあると思っているのだろうかと麻希は自分の言葉にドキッとする。
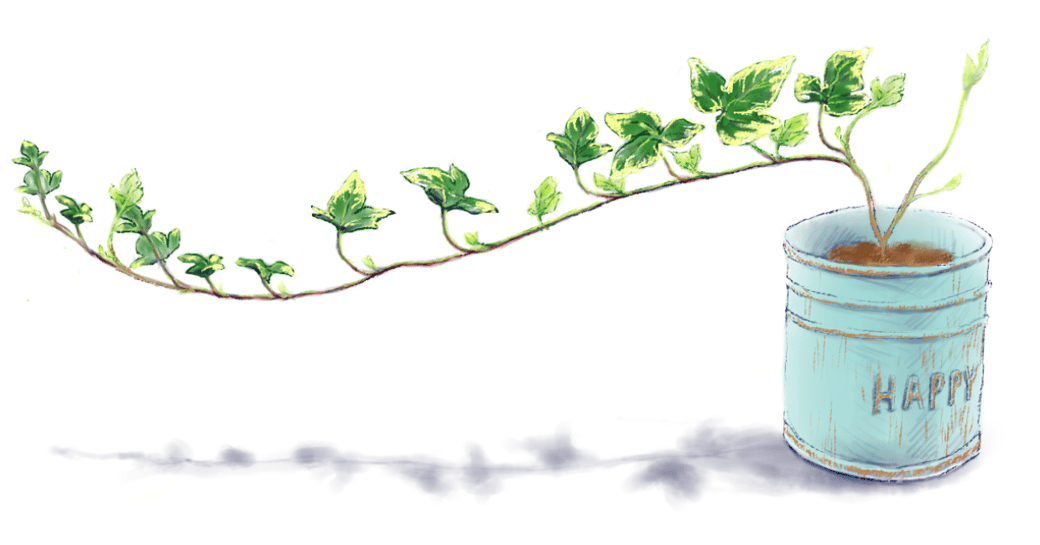
お金の話は出なかったとモリゾウに報告すべきかどうか迷った。どうだったと聞かれたら、なんと答えればいいのだろう。考え過ぎかもしれないけれど、古墳王子の部屋に身を寄せていたことにモリゾウはあまり触れられたくないのではないか。
答えの出ないまま帰宅し、ドアを開けると、「マキマキさん、待ってたんすよ」とモリゾウが明るい声で言った。
「マキマキさんの作品、ネットで売りません?」
次の物語、連載小説『漂うわたし』第42回 多賀麻希(14)「作家と呼んでくれた彼のシナリオ」へ。
イラスト:ジョンジー敦子
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!


















































































































































































































































































































































































































































