
第35回 多賀麻希(12) あなたには嫌われたくない
米を炊く土鍋の底に当たるコンロの火を眺めながら、麻希はモリゾウに聞いた話を思い出していた。幼い頃、家の電気を止められ、ロウソクでご飯を炊いたという。ロウソクを束にすると、中火ぐらいの火力が出るらしい。
もしガスが止まっても、ロウソクがあれば土鍋でご飯が炊けるんだなと安心し、炎を見て安らぎを覚える自分を意外に思う。勢い良く燃える炎が苦手だった。じっと見ていると、東京に出て来る前の消したい記憶が呼び覚まされるのだ。
土鍋は映画製作プロダクション時代の同僚だった美優ちゃんの結婚式の引き出物だ。美優ちゃんの出身地の窯元で作られたもので、家族ぐるみのつき合いだという窯元の人も列席していた。老舗和菓子店の重量感ある羊羹とともに持ち帰ると、腕に紙袋の持ち手の跡が残った。
とにかく重かった。引き出物も美優ちゃんの幸せも。
今の部屋に引っ越す前の大断捨離で、炊飯器と土鍋のどちらを残そうかと考えたとき、土鍋を残したのは、土鍋のほうが場所を取らなかったというだけの理由だった。
炊飯器を手放して、初めて土鍋でご飯を炊いた。思いのほかおいしく炊き上がり、こっちを残して正解だったと満足した。だけど、土鍋の肌にこびりついた米粒を洗うのが面倒だった。もっぱらレトルトのご飯で済ませ、ときどき土鍋を引っ張り出した。なじみの店から足が遠のくように、土鍋ご飯が疎遠になっていった。
流しの下にしまわれっぱなしだった土鍋がコンロと流しを行き来するようになったのは、モリゾウが転がり込んでからだ。自分一人のためにわざわざ土鍋で炊くのは燃費が悪い気がするが、二人分ならレトルトご飯より土鍋ご飯のほうが経済的だ。
何より、モリゾウが喜んだ。「こんなにうまい米は食べたことがないっす」と最上級表現で土鍋ご飯をほめた。

土鍋を洗うのが面倒だと思わなくなった。モリゾウが来て、土鍋のポジションが変わったのだ。
土鍋も炊きたてのご飯もコンロの火も、以前とは違って見える。まさか30代の最後の年に、世の中の見え方がこれほど変わるとは思わなかった。初めて双眼鏡をのぞいた昔のお殿様もこんな驚きを覚えたのだろうか。
人は変わる。人生は変わる。ほんのちょっとしたきっかけで。美優ちゃんは離婚してシングルマザーになり、わたしは引き出物の土鍋でご飯を炊いている。
土鍋のふたを取ると、湯気とともに炊き立てのご飯の香りが立ち上った。
うん。今日もうまく炊けてる。
土鍋を洗うのが苦にならなくなると、ついでにご飯を炊くコンロの横でおかずを作るようになり、長年愛用していたアイタス食品のレンチンシリーズの出番が減った。裁縫と同じように、使える材料を組み合わせて何かを作り出す作業は好きなのだ。
モリゾウは全身を歓喜させ、これまた最上級のほめ言葉でおかずを歓迎する。
「こんなにおいしいポテトサラダは生まれて初めてっす」
「きんぴらって、こんなにうまい食べ物だったんですね」
などと言われると、また作ろう、次はアレンジを加えて、もっと唸らせてみよう、あれも喜んでくれるのではと腕が鳴る。
誰かに必要とされたい気持ちは誰でも持っているが、それが人一倍強いのだろうと麻希は自覚している。体を求められて、断れなかったのもそのせいだ。

モリゾウは相変わらず、麻希を求めて来ない。土鍋ご飯と手作りのおかずで満たされているのかもしれない。モリゾウの舌に触れ、口の中に吸い込まれるご飯やポテトサラダやきんぴらを目で追いながら、わたしと彼があんな風に交わることがあるのだろうかと麻希は思い巡らせ、なんて想像をしているのかと慌てる。
「マキマキさん、どうしたんすか?」
麻希の箸が止まっていることにモリゾウが気づいた。
「ちょっと、考えごとしてた」と咄嗟に言い繕い、「モリゾウがご飯をロウソクで炊いた話、思い出してて」と誤魔化し、とくに興味があるわけでもないのだが、「ロウソクだと、時間かかるの?」と聞いた。
「強火じゃないから、結構かかったんじゃないかな」とモリゾウは記憶をたどる。
「あー、かかりましたね。ロウソクがどんどん短くなって、途中で足したんすよ。そしたら、うまく立ってなかったみたいでロウソクが倒れて、火がうわって床に広がって」
麻希はハッと息をのみ、身構える。モリゾウが見てないことを願ったが、
「あ、いや、火事にはならなかったっすよ。床がちょっと焦げたくらいで」
モリゾウが麻希を安心させるようなことを言った。ということは、麻希が怯えたのを見て取ったのだ。
ロウソクが倒れて、床に火が燃え広がった。確かにハラハラする話だが、身を強張らせた麻希の反応は大げさに見えたことだろう。
「咄嗟に、なんかかぶせて消したんすよね。けど、危なかったっすよね。下手したら、ボヤ出すとこでした」
わたしは出したよと麻希は心の中でつぶやく。
東京に出て来る前、高校生だったとき。
教科書に火をつけたら、その火が燃え広がって。
立ちすくんで動けなくなっているわたしをお父さんが弾き飛ばして、火を消してくれた。
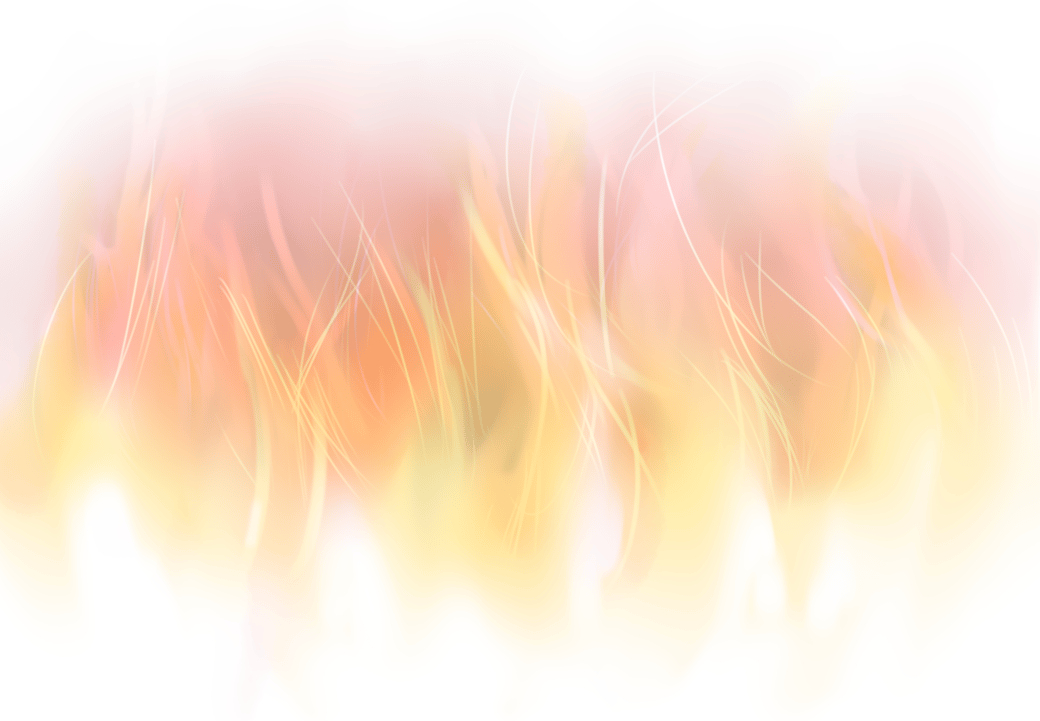
家族の他に知っているのは、ツカサ君だけ。ツカサ君は話を聞き終えて、「シンデレラだね」と言った。それから、髪を撫でてくれた。
「きれいな話にしないでよ」と言いながら、教科書を燃やしたことも、ボヤを出したことも、ツカサ君には許されたような気がした。そのままツカサ君に体を許した。どうしようもない過去を埋め合わせるように、交わった。ボヤの話をしなかったら、ツカサ君は男友達で終わっていたかもしれない。
あの話をして、ツカサ君を試したとも言える。離れていく人なのか、残ってくれる人なのか。
今、モリゾウに聞きたいのも同じことだ。だけど、モリゾウには知られたくない。ツカサ君には話せたのに。あの頃から歳を重ねた分、守りに入っているのかもしれない。人は、人生は、何歳からでも変われるのだとモリゾウの登場で教えられたが、こんな出会いがそうそう転がっていないこともわかっている。だから、しがみつく。この人を失いたくない。この人に嫌われたくない。忌まわしい過去を呼び覚ます炎に安らぎを覚えるようになった今の暮らしを壊したくない。
「じゃあ、ロウソクでご飯炊くのは、やめとこ。ここ賃貸だから、床焦がしちゃったら大変」
「もしやるときは、下に不燃性のもの置くのがいいっすよ」
「だね」
脳裏で燃え盛る炎を忙しく消しながら、動揺を悟らせずに軽口を叩けるぐらいには大人になった。
あの話をしたら、モリゾウもわたしを抱くのだろうかと麻希は想像する。モリゾウがどんな反応をするのか興味がある。知って欲しい気持ちと知られたくない気持ちがせめぎ合う。
「今はまだ」
言葉が音になって飛び出し、モリゾウの耳に届いた。
「今はまだ?」とモリゾウに聞かれ、
「なんでもない」と誤魔化す。
口に放り込んだ梅干しが、ことのほか酸っぱい。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第37回 佐藤千佳子(13)「空っぽってわけじゃない夏」へ。
イラスト:ジョンジー敦子
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!




















































































































































































































































































































































































































































