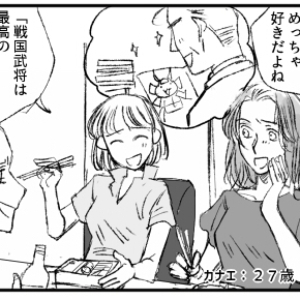第6回 多賀麻希(2) 39歳の再就職活動
書き終えた履歴書を携え、麻希はハローワークへ向かった。景気づけに赤いパンプスを履いて行ったが、自動ドアをくぐったところで足が止まった。あなたを必要としているところはありませんと、これ以上誰にも言われたくなかった。
回れ右して駅まで引き返し、気がつくと新宿三丁目の雑居ビルの前に立っていた。20代の10年間を過ごした映画製作プロダクションが入っていたビルだ。
今思えば、無茶苦茶だけど楽しかった。低予算映画ばかり作っている会社で、給料も安かった。セリフが一言二言だけの役は社員にやらせて役者の出演料を浮かせた。社長はドラッグクイーンになったり、校長先生になったりしていた。
3階を見上げると、壁面に店の看板が取りつけられ、かつての職場はネイルサロンになっていた。壁面に店の名前が出ていた。エレベーターがないので階段で上る。幅が広くなったと思ったら、通路を塞いでいた荷物がなくなっているせいだった。社内では「倉庫」と呼んでいた。「ちょっと倉庫からあれ取って来て」と社長に言われると、撮影の小道具や季節ものの電化製品を取りに行った。非常時の避難経路でもあるんですから空けておいてくださいと何度も消防署の指導を受けていた。
3階まで行き、ドアを開けようとして、やめた。中を見なくてもわかる。ヤニで黄ばんだ壁紙も、壁一面に積み上げられていた台本や資料も、すっきりと片付けられ、いい香りがして、ヒーリング音楽なんか流れているのだろう。階段を降りる麻希の背中で、サロンからの明るい笑い声が弾けた。

オムライスやカレーやコーヒーの出前を取っていた1階の喫茶店は、ピンクのサーフボードに『モニカ』と店名を水色でペイントした看板が目印だったが、『焙煎珈琲 然』という一枚板の看板が立てかけられていた。ガラスをはめ込んだピンクのドアは重厚感のある木のドアに新調されていた。
誘われるように真鍮の取っ手を引いてドアを開けると、客はおらず、天井の灯りは落ちていて、カウンターの上の裸電球だけが灯っていた。どう見ても開店前だ。カウンターの中でグラスを拭いているマスターと目が合った。
「あ、まだやってないですか?」
麻希が引き返そうとすると、
「今からやりましょ」
関西弁のアクセントでマスターは飄々と言い、天井の灯りをつけた。
「お好きなとこどうぞ」と促され、カウンター席のスツールに腰を下ろすと、マスターと向かい合う形になった。
歳は50前後だろうか。黒縁の眼鏡。短髪に短いあごヒゲ。無精髭なのか、伸ばしているのか。不潔な感じはなく、色気がある。ライブハウスでベースを弾いているミュージシャンのような雰囲気。どこかで会ったような親しみと懐かしさを覚えた。
「何にします?」と聞かれたが、テーブルにも壁にもメニューらしきものが見当たらない。
「あの……メニューは?」
「なんでも言うてみてください」
「じゃあコーヒーを」
普段はカフェオレ派だがブラックにしてみた。「焙煎珈琲」と看板に謳うからには自信があるのだろう。
「『ゼン』って読むんですか」と話しかけると、「ゼン?」とマスターが聞き返した。
「自然のゼンかな、と」麻希がドアのほうを指差すと、外の看板のことだと気づいたらしく、
「ああ。自然のゼンやね。天然のネンでもあるけど」
「あ、確かに。シカって読み方もありますね」
「シカ?」
「然りのシカ」
「ああ、シカ。そうとも読みますね。きっと、そのどれかなんやろね」
他人事のようにマスターが言うので、麻希は「あれ?」となる。
「ここのお店の名前ですよね?」
「あれ、うちの看板いうわけやないんですよ。バイトの子が拾て来て、あそこ置いてるだけで」
「拾って来て」ではなく「拾(ひろ)て来て」。製作プロダクションの社長も同じ話し方だった。「使って」は「使(つこ)て」。「洗って」は「洗(あろ)て」。マスターに懐かしさを覚えたのは、関西弁が醸し出す雰囲気のせいかもしれない。
「じゃあ、お店の名前、別にあるんですか?」
「いや。とくにないです」
「名前がないと不便じゃないですか」
「けど、みんなが同じ名前で呼ばんかてええと思うんです」
そんな話をしていると、コーヒーが入った。麻希の勝負靴とコーディネイトしたような光沢のある赤のカップ。看板は違うと言いながらコーヒーはしっかり自家焙煎だった。

「お酒もあるんですね」
マスターの背中の棚に並んだボトルを見て言うと、
「飲みます?」
「飲んじゃおっかな」
「ビールも冷やしてますけど」
「じゃあビールで。食べるものもありますか?」
「適当に、なんか作りましょか」
適当と言って出されたものが驚くほどおいしかった。しめじを網焼きしてレモンと塩を振っただけのもの。薄く切ってトーストしたバケットとレバーパテ。初めて見るボトルの黒ビールと笑ってしまうほどよく合った。
「このレバーパテ、無茶苦茶おいしいんですけど」
「それ材料3つ、ミキサーでガーって混ぜるだけ。鶏レバーの醤油煮とクリチと無塩バター」
「クリチ?」
「クリームチーズ」
関西人の社長が何でも3文字に省略していたのを思い出した。マクドナルドはマクド、ミスタードーナツはミスド。アイスコーヒーは冷やしたコーヒーでレイコ。クリームソーダはクリソだった。クリームをクリと略すのは関西人の定番なのかもしれない。
銀行から借りたお金を返せなくて、夜逃げした社長。麻希を含めて4人いた社員の給料は3か月分支払われていなかった。「いつか払う!」と短いメールが来た。いつものように「。」ではなく「!」で終わっていたから、社長本人からだろうと社員たちは無事を確認し合った。
いつか給料を支払われる日は、きっと来ないだろう。だけど、不思議と恨みも怒りもない。当時は途方に暮れたが、今は懐かしさだけが残っている。いつか社長に会えたら、クリームソーダでもおごってもらおう。
「なんか、ええことあったんですか」
とマスターに聞かれて、麻希は「え?」となる。
「いいことないですよ。失業しちゃって」
「へーえ」
「へーえ、なんですか?」
「ちゃんと定職についてはったんやなぁて」
「正社員じゃなくて、派遣ですけどね」
「正社員とハケンて、ちゃうんですか」
「ちゃうんですよ」
関西弁アクセントを真似すると、「あれ?関西の人?」と言われた。10年間、社長の関西弁を浴びていたせいだろうか。外国語を耳で覚えるというのも正しいのかもしれない。
こういう他愛のない、自分も他人も傷つけない話を誰かとしたかった。マスターと話せば話すほど力が抜けていって、力が入っていたんだと麻希は気づく。派遣切りに遭ってからずっと張り詰めていたのが、いい感じに緩んで、久しぶりにお酒がおいしい。
「このお店、バイト募集してないですか?」
軽くなった口から飛び出した言葉に、自分で驚いた。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第7回 佐藤千佳子(3)「ママを引いたら何が残る?」へ。
イラスト:ジョンジー敦子
※表示価格は記事執筆時点の価格です。現在の価格については各サイトでご確認ください。