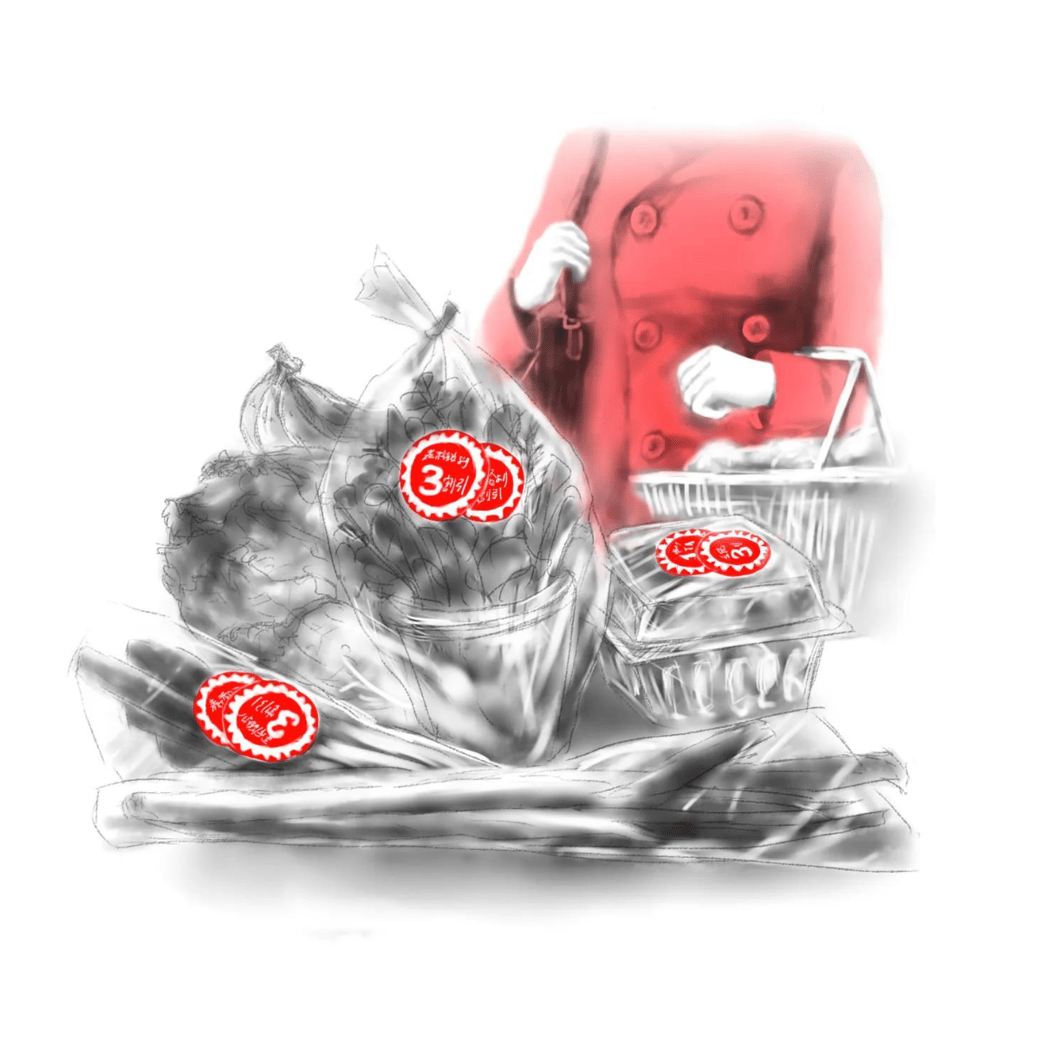第13回 佐藤千佳子(5) ママと『きれい』は二択じゃない
千佳子がドレッシングの瓶にパセリを活けてから3週間。買った日にチキンのパセリバター焼きを作るのに1本使い、あとは観賞用にした。
最初の1週間、パセリは青々としていた。その後、1本また1本と紅葉するように葉っぱが黄色くなり、水気を失ってチリチリとなり、茎も白くふやけていった。
燃えるゴミの日の朝、最後の3本になったパセリをゴミ袋に移していると、制服に着替えた娘の文香が自室から出て来た。
「ママ、今何時?」
「7時40分」
「やった! 7時50分だと思ってたから10分トクしちゃった」
つい引き算してしまう千佳子とは逆で、文香は思考回路が足し算になっている。
「パセリ、まだいたんだ?」
「いたよ。十分元取ったよね。消費税込み138円で3週間。1日あたり7円。パセリはえらい」
「ママって幸せを見つける天才だね」
文香の言う「天才」は、「えらい」と同じくらいの重さしかない。固い瓶のふたを開けただけでも「天才」と言われる。
「娘を生んで、わたしは天才になった」
「ママ、また独り言漏れてるよ!」
その日も文香は元気に中学校へ向かった。成績は中の上くらい。友達関係もうまく行っている。悩みもない。問題もない。心配がなさ過ぎて心配になるくらいだった。
その電話が来るまでは。

「文香さんのことで確認したいことがあります」
早口で語尾を短く切る切羽詰まった話し方。電話は担任の喜代美先生からだった。鈴木先生が2人いるので下の名前で呼び分けられている。文香によると「ママより10歳くらい年下。私生活は謎」らしい。
「確認したいこととおっしゃいますと?」
「将来の夢の作文のことです」
「将来の夢?」
文香の誕生日を家族で祝った日の宿題だ。覚えている。あの夜、お皿を洗いながら交わした会話とセットで。
「ママは何になりたいの?」
「何言ってるの? ママはママになってるじゃない」
「そうじゃなくて。ママってやりたいことないの?」
もうひとつ思い出したのは、文香が小学2年生のとき、夏休みの宿題の読書感想文をクラスの代表作品としてコンクールに応募したいと担任の先生から連絡があった。また何かに選ばれたという知らせだろうか。
「娘の作文が、何か……?」
「まだ書けていないんです」
千佳子のおめでたい想像とは違った。
「文香さんから何も聞いていらっしゃいませんか?」
「すみません。娘からは何も」叱られているような気持ちになり、つい謝ってしまう。「キヨミンって、言葉が鋭角なんだよね」と文香が言っていた。先生の専門は数学だ。
あの夜、千佳子が答えを探している間に、文香は「作文やらなきゃ」と言って、自室に引っ込んだ。だから、書いたものだと思っていた。
「あの……まったく書けていないんでしょうか」
「最初は白紙ではなかったです」
「最初は?」
「将来の夢と、それを実現するためにどんな努力をしているかを書かせる宿題だったんですが、文香さんの作文は未定とだけ書いてありました」
「未定、ですか」
「普段の文香さんは欄からはみ出して記入することが多いので、どうして書かないのかと問いただしたところ、未定までも消してしまい、白紙になりました」
「白紙……?」
「何か、どうしても書きたくない事情でもあるのではと思いまして」
先生の言葉に心当たりがあるとしたら、千佳子が文香の質問に答えられなかったことだ。なりたいもの、やりたいことがない。夢のない母親に失望して、夢を持てなくなったのかもしれない。
あの日以来、千佳子は、このままじゃダメなのかと悩んだり、ママ友と自分を比べて焦ったりした。今さら何かを目指さなくてもいいじゃないと吹っ切れたのは、花束みたいに瓶に活けたパセリがきっかけだった。パセリが色あせるまでに、さらに時が流れた。千佳子の気持ちが沈んだり浮いたりする間、文香の作文は止まったままだった。
白紙なんて、あの子に似合わないのに。
色鮮やかなパセリが映えて明るくなったキッチンで久しぶりに味わった爽快感には、パセリと同じく賞味期限があったのだろう。

上の空でレジを打ち、小さなミスを重ねた。客に声をかけられて気づかなかったり、期間限定で配布している5%割引券を渡しそびれたり。4時間のパートを終えてエプロンを脱ぐと、千佳子は野菜売り場へ向かった。
もう一度パセリを活けてみたら。
パセリを活けたって文香が作文を書けるわけではないが、せめてキッチンは明るくなる。気持ちも多少は晴れる。すっきりしない日も、主婦はキッチンに立たなくてはならない。
野菜売り場の端、パセリが並ぶ棚の前に立つと、見切り品のワゴンが目に入った。ニラやねぎに混じって、生ハーブブーケが残っていた。水挿しのカップごとビニール袋に入れ、赤地に白い文字の値引きシールが貼られている。
「表示価格から1割引」に重ねて「表示価格から3割引」のシールを貼ったのは千佳子だ。1割引にしても3点が売れ残っていた。3割引になって2点が売れたらしく、最後の1点になっている。
3割引なら、買ってみようか。
ふとワゴンの反対側から視線を感じた。生ハーブブーケをじっと見ているその女性に、どこかで会った気がする。
「あの……こちら買われますか?」
「いえ、どうぞどうぞ。ありがとうございます」
ハツラツとしたその口調と、お礼を言われたことで思い出した。
「もしかして……こちらでハーブの販売されていた方ですか」
「はいっ。そうですそうです。マイハーブのある暮らしを広めたい、ハーブのマイです!」
いきなりキャッチコピーつきで名乗られた。こんな風に自己紹介する人、アイドルか選挙の立候補者くらいじゃないのかと千佳子は面食らう。
ハーブのマイさんは、今日は緑のエプロンではなく、真っ赤なコートを着て、買い物かごを提げている。客としてハーブの売れ行きを見に来たらしい。

「すみません。この値引きシール、わたしが貼りました」
「こちらでお勤めなんですね? 謝らないでください。お仕事なんですから」
「生ハーブブーケ、実は気になっていたんですけど、ちょっと手が出なくて。3割引なら買えるかなって、見てたんです」
「わかりますわかります。きっかけ、大事ですよね。私もハーブとの出会いは値引きシールでした」
「そうなんですか?」
「はい、見切り品大好きです!」
ハーブのマイさんの買い物かごに目をやると、値引きシールのついた餃子の皮が3袋入っていた。
「そしたらご縁があって、その見切り品で買ったハーブの会社で働くことになったんです。今ではもうハーブのない暮らしなんて考えられません。朝から晩まで何にでもハーブを使ってます。お料理にもお菓子にもお茶にもお酒にも子どもたちのお弁当にも」
「えっ、お子さんいらっしゃるんですか」
「いますいます」
「全然見えないです。ママなのに、きれいにされているんですね」
「ママだから、きれいでいたいんです」
さらっと言われたその言葉に、ハッとした。母親であることと「きれい」であることは二択じゃない。真っ赤なコートを着て、値引き品の餃子の皮を買ったっていいのだ。
「女は40過ぎてからが面白いってココ・シャネルも言ってます」
友達みたいな身近さでココ・シャネルが出てくる。「女は先っぽに宿る」とファッション誌の見出しのようなセリフを口にした晴翔くんママといい、手をのばしやすい位置に置いてある調味料のように、すっと取り出せるところに「女」があるのだ。
娘の将来の夢が白紙なのは自分のせいかもしれないと朝から思い詰めていたのに、ハーブのマイさんと話している間、千佳子はそのことを忘れていた。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第14回 佐藤千佳子(6)「口紅のとびらを開けて」へ。
イラスト:ジョンジー敦子
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!
※表示価格は記事執筆時点の価格です。現在の価格については各サイトでご確認ください。