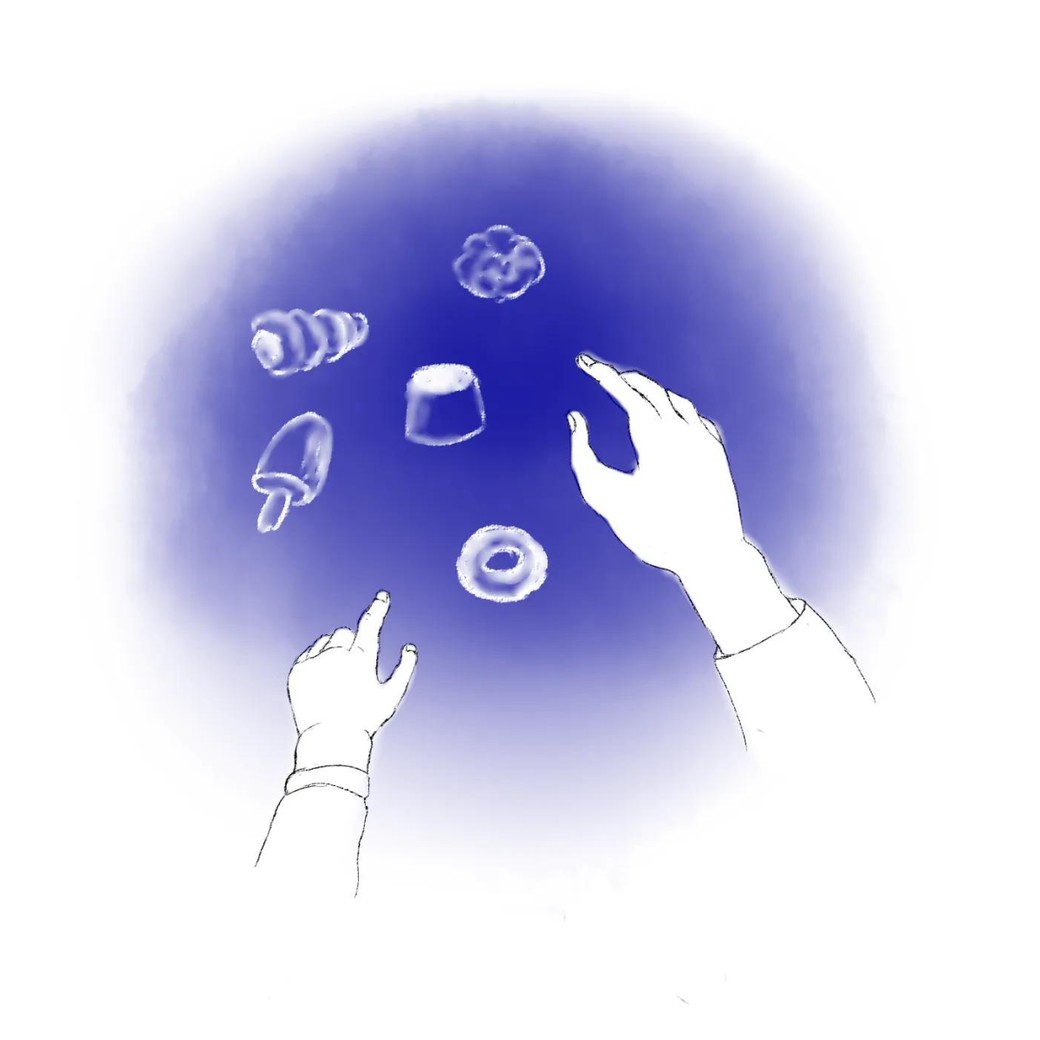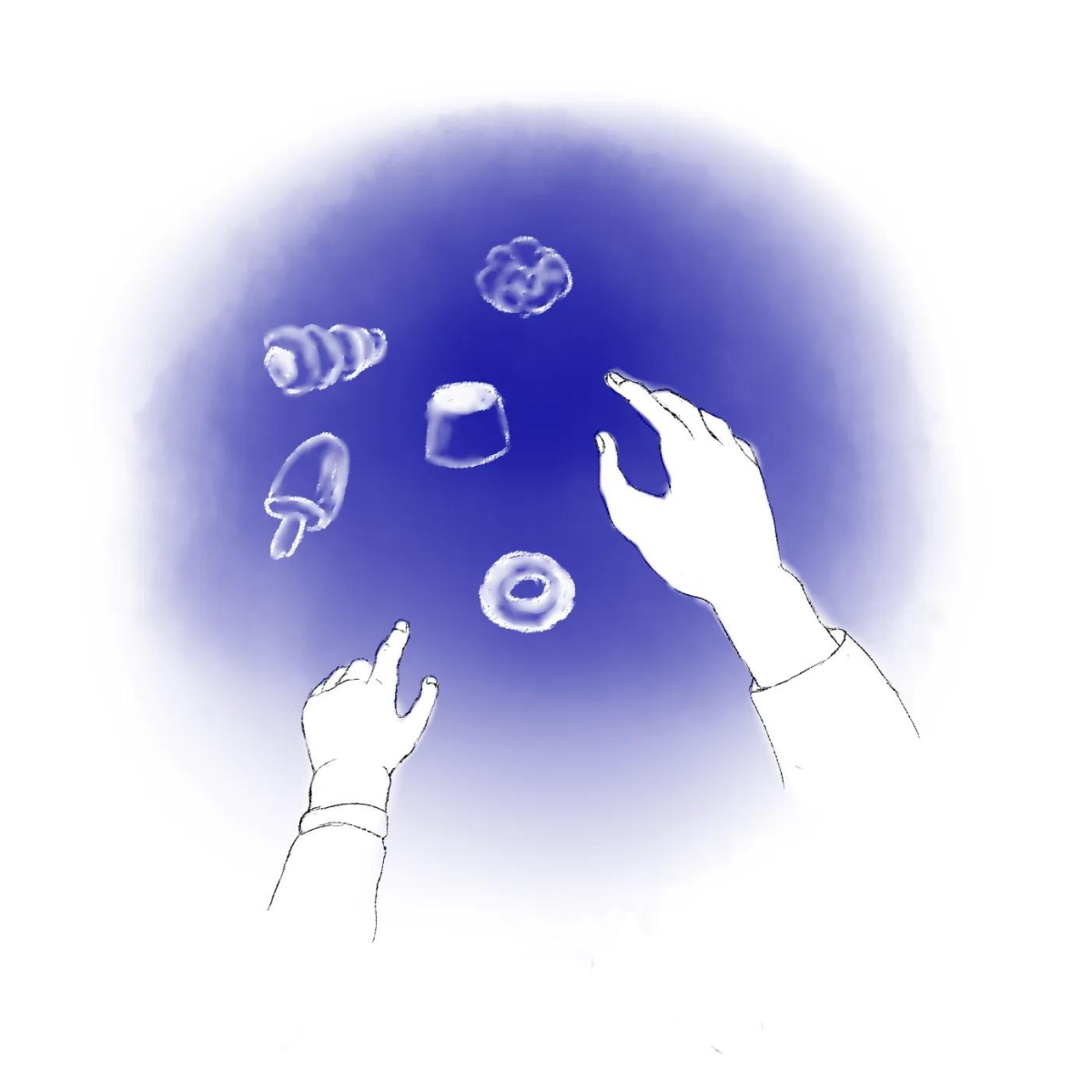第38回 佐藤千佳子(14) かいじゅうが不安を食べた夜
「ふーちゃん、地震のときのこと覚えてるの?」
「覚えてるよ」
どこまで覚えているのだろうと千佳子は考える。横浜も激しい揺れに見舞われた当時、文香は3歳だった。
「ママ、ジュース持ってたよね」
「そんなこと覚えてるんだ?」
「うん。冷たかった」
1リットル入りのオレンジジュースの紙パックの記憶が差し込まれるように蘇る。あのときも、この部屋にいた。自宅の2階にあるリビング。テーブルに置いたコップにジュースを注いだとき、グラッと揺れ、ジュースがこぼれた。左手に持ったジュースの紙パックの口を咄嗟に閉じ、右手で文香を抱き寄せた。

文香の両手が千佳子のウエストのあたりをギュッとつかんだ。しばらく立ったまま揺れに耐え、こぼれたジュースがテーブルの上で面積を広げるのを見ていた。家のあちこちからカンカン、ガンガンといろんなものがぶつかり合う音がした。そうだと思い出してテーブルの下に入った。ストロボを焚いたようにくっきりと記憶に刻まれた一瞬一瞬をつなげると、数分の出来事のように思えるが、ほんの数秒のことだったかもしれない。
床の上にへたり込んで、文香をひざにのせ、揺れがおさまるのを待った。その間、棚から飛び出した絵本は次々と落ちて床を打った。
花瓶から飛び散ったオレンジのガーベラと水。本棚から落ちた絵本。当時のイメージの残像が、明け方の夢に現れたのかもしれない。
あのとき、千佳子は左手でジュースの紙パックをつかんだまま、ひざの上に文香を座らせ、腕を回して小さな体を抱き留めていた。文香は唇を固く結び、凍りついたように千佳子の腕にしがみついていた。強張った体に冷蔵庫から出したばかりの紙パックが当たる、その冷たさを文香が覚えていたとは。
「地震のときの話、ママとしたことなかったよね」
「ふーちゃんが怖いこと思い出すかなと思って」
「私、怖がってた?」
どうだったかなと千佳子ははぐらかし、忘れていてくれたほうがいいよと願う。
大きな揺れがおさまってテーブルの下から出た後も、文香は千佳子から離れようとしなかった。故郷の家族と連絡がつかず、携帯電話の連絡帳に入っている片っ端から電話をかけたが、どこもつながらず、不安が募るばかりだった。
テレビのニュース映像を食い入るように見ていて、ふと、さっきまでしがみついていた文香が離れていることに気づいた。振り返ると、床に画用紙を広げ、おとなしく絵を描いていた。ホッとした次の瞬間、ギョッとした。文香は黒いクレヨンで紙を塗りつぶしていた。クレヨンの背丈が短くなって、指先でつまんでいた。あわててテレビを消し、文香を抱き留めると、ひざにのせた。そのまま、離さなかった。
夫の携帯電話も勤務先の電話もつながらなかったあの長い夜、晩ご飯をどうしたのか、食べたのかどうかも覚えていない。
「天井を食べたよね」と文香が言う。
「天井?」と千佳子が聞き返すと、
「そういう遊び。天井食べるごっこ」
その遊びを千佳子は覚えていなかった。
「天井に手を伸ばして、パンみたいにちぎって、あむあむって食べて、なんの味がするか言うの。プリンの味とか、アイスクリームの味とか」
そう言いながら、文香が天井をちぎり、口に入れる動きをやってみせる。そこまで聞いても、やはり千佳子は思い出せない。本当にそんな遊びをしたのだろうかと思いながら、天井をちぎっては食べる文香の動きを眺め、同じ仕草をしていた3歳の文香を思い浮かべる。それから、文香をひざにのせていた、今より十歳若い自分を。天井に向かって手を伸ばすと、関節がカクッと小さく鳴った。
天井を食べるごっこのいいところは、上を向くところだ。多分、当時のわたしも同じことを思っただろう。
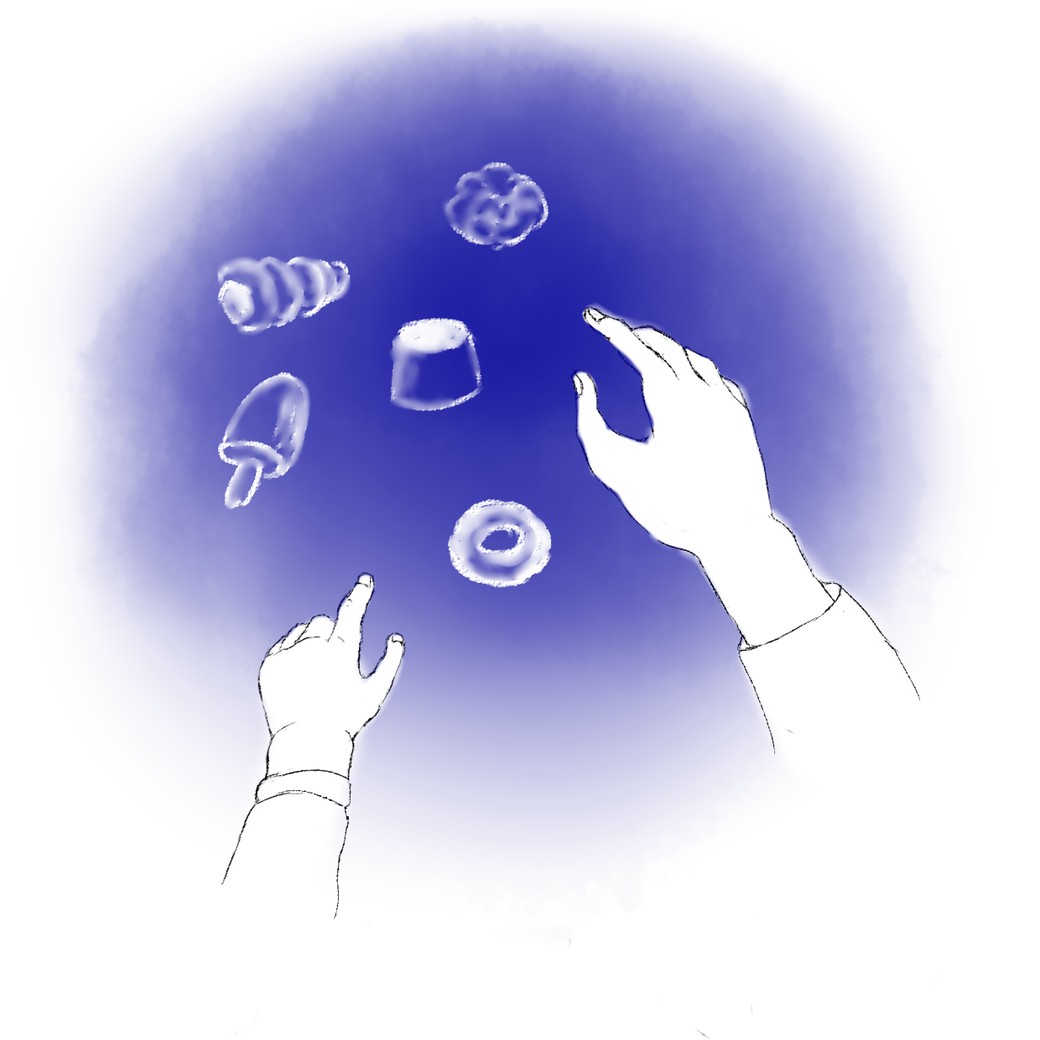
「ママとかいじゅうの話、作ったよね」
「かいじゅう?」
「地震を食べるかいじゅうの話」
文香に言われ、遠い記憶が浮かび上がる。
グラグラと揺れる町。
眠れない子どもたち。
そこにやって来る、おなかをすかせたかいじゅう。
余震が続いて眠れない夜、文香と一緒に「おはなし」を作った。そのひとつが、地震を食べるかいじゅうの話だった。
《いつもグラグラゆれている町がありました。その町の子どもたちは、なかなか眠れませんでした。そこに、おなかをすかせたかいじゅうがやって来ました。かいじゅうの大きな体を満足させるだけの食べものは、町にはありません。「おなかがすいたぞー。なにか食べさせろー」。そのとき、町がグラグラとゆれました。すると、かいじゅうは「これこれ、こういうの」と言って、グラグラをムシャムシャと食べました。「グラタンよりおいしいぞ」と大よろこびしました。その町のグラグラを食べつくすと、かいじゅうは満足して、グーグー眠りました。町の子どもたちもグーグー眠りました。》
そんな話だった。「グラタンよりおいしい」のくだりは、文香のアイデアだったと思う。
「あー、そんな話。ママの話聞いて、思い出した」
「なんだ、どんな話だったか覚えてなかったの?」
「うん。でも、ママのひざは覚えてるよ」
「ママのひざ?」
「ここにいれば安心って思った。怖かったって記憶が残ってないのは、ママが守ってくれてたからなんだよね」
いきなり面と向かって告白されたようでドギマギとして、「喉渇いちゃった」と千佳子は冷蔵庫へ向かう。
違うよ。逆だよ。
パートの先輩の野間さんが手作りしたジンジャーシロップを炭酸で割りながら、千佳子は思う。文香がいてくれたから、ぎりぎり持ちこたえられた。文香を抱きしめ、一緒に話を作ることで、波立つ気持ちをなんとか落ち着かせていた。地震を食べる「かいじゅう」に不安も食べさせていた。
地震の話を避けてきたのは、文香に怖い記憶をぶり返させたくないというより、あのときの追い詰められた苦しさを思い出すのが怖かったからかもしれない。
シュワシュワと弾ける炭酸の音が文香に届いたらしく、「私も飲む!」と元気な声が飛んできた。
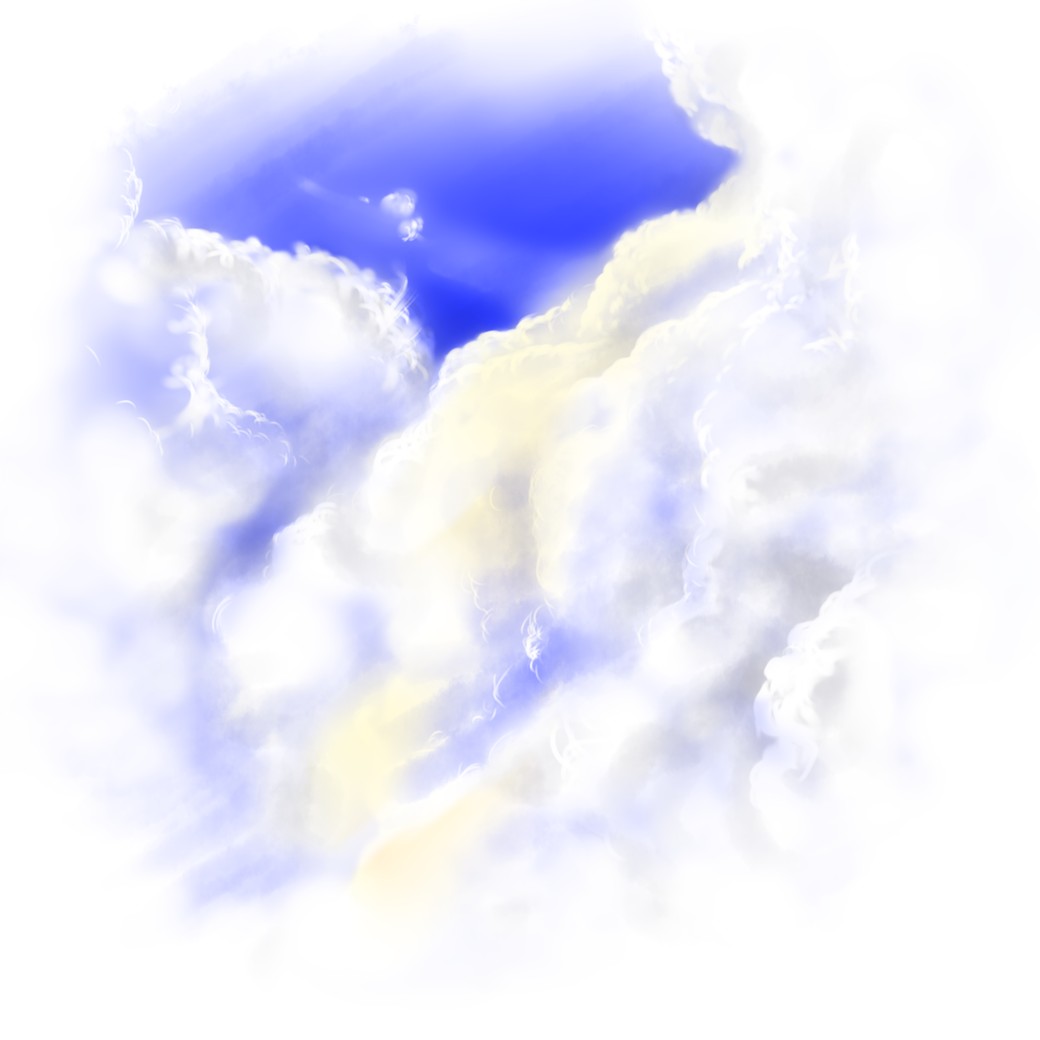
窓の外の青空に入道雲が膨らみ、蝉が鳴き立てている。今日も暑くなりそうだねと文香と言いながらジンジャーシロップの炭酸割り、通称「ノマリーサイダー」を飲んでいると、起きてきた夫が「おはよう」と背中から声をかけた。
「おはよう」と千佳子が先に振り返り、後から文香が「パパおはよ」と振り返ると、「そっちがふーちゃんか」と夫が意外そうに言った。
「二人並んでると、どっちがママで、どっちがふーちゃんか、わかんなかったよ」
「パパ、それって失礼じゃない?」と文香が笑いながら抗議し、パパの分も作ろっかと千佳子はキッチンに向かう。
今日の一行日記に文香は何を書くのだろう。『ふーちゃんの夏休み』の絵本は、どんな話になるのだろう。
夫のノマリーサイダーを作ると、ジンジャーシロップの瓶が空いた。夢の中で揺れていたキッチンカウンターの定位置の花瓶は、澄ました顔で立っている。野間さんに分けてもらった白いミニバラがシャンと胸を張っている。なんでもない愛しい一日が始まる。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第39回 伊澤直美(13)「一人目もまだなのに二人目ですかお義母さん」へ。
イラスト:ジョンジー敦子
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!