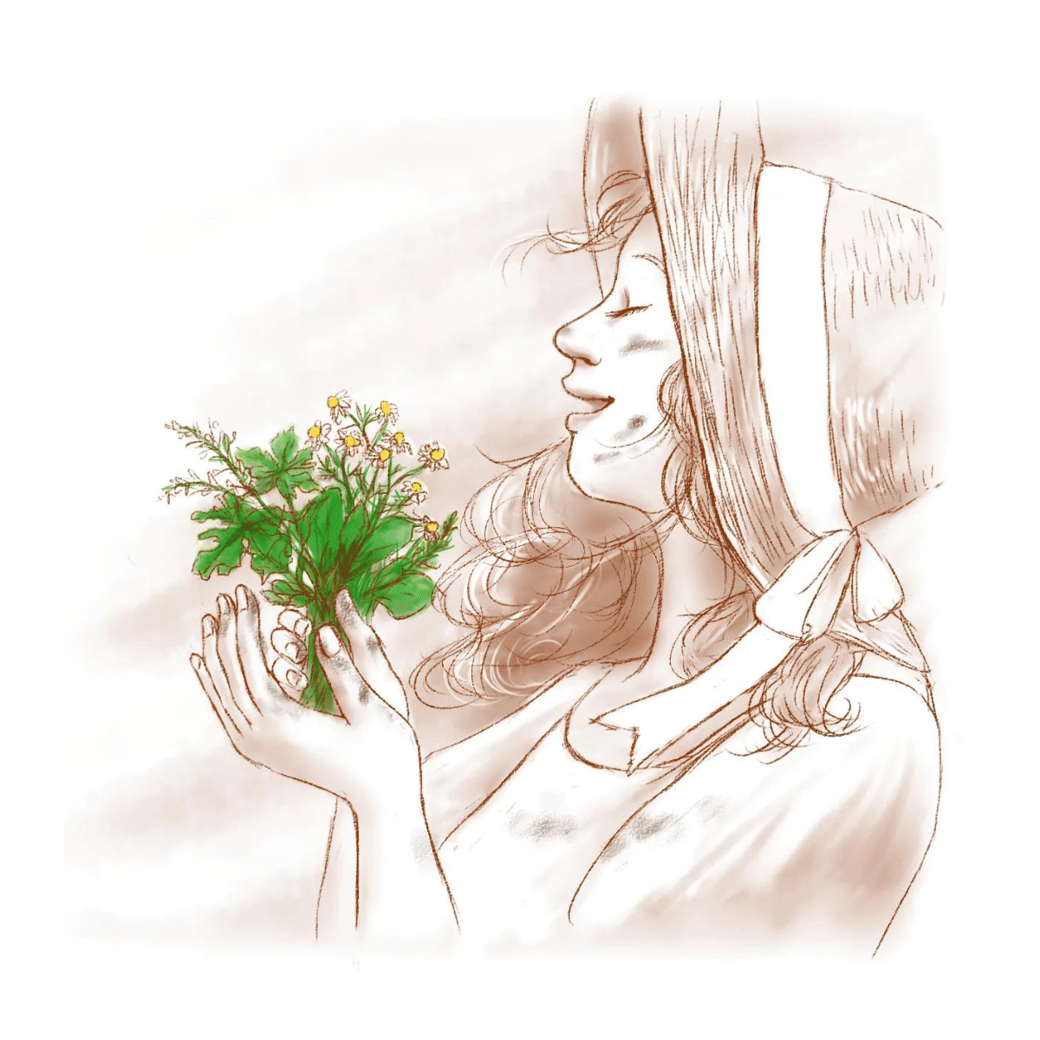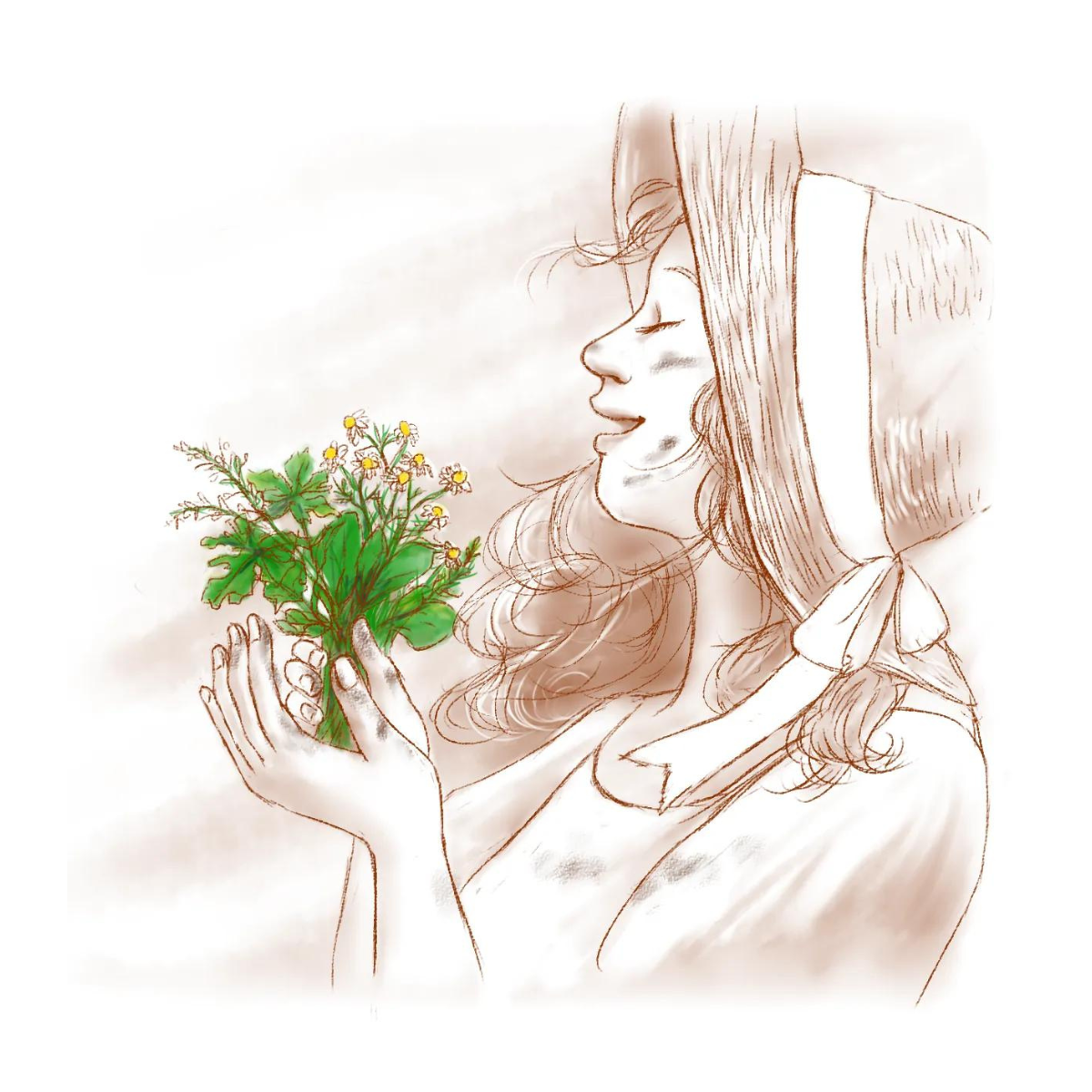第26回 佐藤千佳子(10) 「奥様」でもなく「お母様」でもなく「私」を生きる
「これ、水やり大変じゃないですか」
「それ、うち来る人に必ず言われる」
シフトの休みが重なった平日の午後、パートの先輩の野間さんの一人暮らしの家にお邪魔している。リビングのドアを開けると、ジャングルだった。壁際にずらりと並べられた鉢植えの観葉植物が葉を茂らせ、天井からはポトスやアイビーがぶら下がっている。
摘みたてのミントとレモンバームでハーブティーを淹れてもらい、開け放ったサッシ戸の向こうの庭を眺める。ピンクやオレンジのつる薔薇がフェンスをつたって伸び、その下はトマトやベビーリーフやハーブが育つ菜園になっている。
「うちに来ない?」と野間さんが誘ってくれた理由がわかった。こんなに花と緑があふれた空間でお茶できるのなら、わざわざ出かける必要はない。
「それで、話って何?」千佳子の手土産のガレットブルトンヌをひと口かじって、野間さんが聞いた。
「こないだ、久しぶりに『お母様』って呼ばれたんです」
「文香ちゃんに?」
「いえ、オジサンです。携帯電話の料金プランを相談したショップの店員さんで」
夫婦なのに夫は「ご主人様」、妻は「お母様」という呼び方に違和感を覚えたこと、そのちぐはぐさが世の中の夫と妻の扱いの差なのだと思い至ったことを話した。
「これって日本独特なのかなって、誰かに聞いてみたくて。そしたら、野間さんがお客さんを英語で案内してるのを見かけて」
「なーんだ。そういうこと?良かったー。てっきり、パート辞めたいって相談かと思った」
自宅に誘ってくれたのは、込み入った話ではという気遣いもあったようだ。

「私さ、『お母さん』の通過儀礼を免れているんだよね。ダンナの転勤でアメリカについて行って、向こうで産んだから」
野間さんが英語を話せる理由がわかった。男の子を二人産み、上の子が小学校に上がる前に帰国したと言う。
「『お母さん』を押しつけられたって思ったことはなかったな。ベビーシッターに子ども預けて、夫婦で映画観に行ったりして、子育てしながら好きなことやれてた気がする」
「子どもが泣き出して、黙らせろって怒鳴られたこと、ないですか?」
「なかったよ。日本人やアジア人が嫌いって人には、ちょくちょく出くわしたけど。『犬のウンチ踏んじゃうこともあるよね』って声かけてくれた人がいて、そっからは、理不尽なこと言われたら、犬のウンチだって思うようになった」
「いいですね。それ」と千佳子が言い、笑い合った後、「でもね、日本に帰ったら、『お母さん』の壁にぶち当たった」と野間さんは真面目な顔になった。
「前にいた会社に戻ろうとしたら、夫の許可が下りなくて。子どもたちが日本の環境に慣れるまで待ってくれって。で、上の子が中学校に上がるときに、今から戻れますかって会社に聞いたら、ブランクあるし無理でしょって言われちゃった。ブランクったって、新入社員よりは即戦力だっての。お茶、もう一杯どう? コーヒーにする?」
コーヒーのドリップを待ちながら、野間さんは話を続けた。
「でね、中途採用やってる会社いくつか受けてみたら、笑っちゃうぐらい引っかからなくて。履歴書の職歴がさ、アメリカ行く前で終わってるじゃない?
それ見て、何もやってなかったんですねって言われたの。面接で。子育てして、PTAの役員やって、時間やりくりして翻訳ボランティアも引き受けて、それ全部なかったことにされた気がして」
「何もやって来なかった」という言葉が千佳子の胸の奥を刺す。「ママは何になりたいの? ママって、やりたいことないの?」と娘に聞かれ、「わたしからママを引いたら、何が残るのだろう」と思いわずらった。その「ママ」の部分さえ引かれてしまったら……。
お母さんって、空しい。
「採用されても蹴ってやるって思ったら、結局不採用でさ。『月刊ウーマン』の見開きで取材されたこともあるのに、私のどこ見てるんだって頭に来て、しばらくその会社の商品買うのやめた。一人不買運動。あれね、アイタス食品のレンチンシリーズ」
千佳子は『月刊ウーマン』を知らないが、アイタス食品なら知っている。パート先のスーパーで商品を扱っている縁で、少し前にオンラインインタビューを受けた。新商品開発のヒントを探るために主婦の声を聞きたいという募集を知って手を挙げたのは、赤い口紅をつけ始めた頃だ。

「結局、夫が引退するまで働きに出ることはなくて。私に30 年尽くさせたから、これから 30 年かけて返すって言ったの。あの人。何歳まで生きる気だよって笑ってたら、あっけなく死んじゃって」
「ご主人様が亡くなられて、パート始められたんでしたっけ」
何気なく口にしてから、千佳子はハッとなる。先日から引っかかっていたのに、そのことで野間さんに相談しに来たのに。野間さんを見ると、ニヤリと笑われた。
「つい言っちゃうよね。ご主人様って」
「言っちゃいますね」
「奥様、お母様も、つい使っちゃってる人が多いんだと思う。佐藤さん、最初にオジサンって言ってたしね」
「あ、確かに」
「私なんて今、呼び名がなくって大変。未亡人なので奥様じゃないんですって言うと、相手は困っちゃう。代わりの呼び方がないんだよね」
問題なのは、呼び方よりも、セットでついて来る決めつけや押しつけなのだろうと千佳子は考えが整理されていく。
「娘に話したとき、どうでもいいって、言われちゃったんです」
「それは、『奥様』でも、『お母様』でも、ママはママってことなんじゃないの?」
「そうなんですかね」
「私、花の名前覚えられないし、間違っちゃうことあるけど、何と呼ばれようと、私は私だって胸張って咲いていればいいんだよね」
そう言って、野間さんが庭のバラに目をやる。
「ほんとすごいですよね。野間さんのお庭」
「ノマリー・アントワネットって呼んで」
「ノマリー?」
千佳子は首をかしげる。歴史の教科書で見たマリー・アントワネットの肖像画からは、土の匂いがしない。野間さんともつながらない。
「マリー・アントワネットって、ファッションやインテリアだけじゃなくて、庭にも力を入れてたらしいの。農村まで作ったんだって。牧場があって、魚を釣れる池があって、水車小屋があって、菜園があって。そんな理想の田園風景を村ごと作っちゃったの。それ税金でやられちゃったら、庶民は怒るけど。私の頭の中では、マリー・アントワネットは麦わら帽子かぶって、コットンのワンピース着て、土いじりしてる」
ほっぺたに泥をつけて笑っているマリーアントワネットを千佳子は思い浮かべる。口角を上げた横顔が野間さんに似ている。
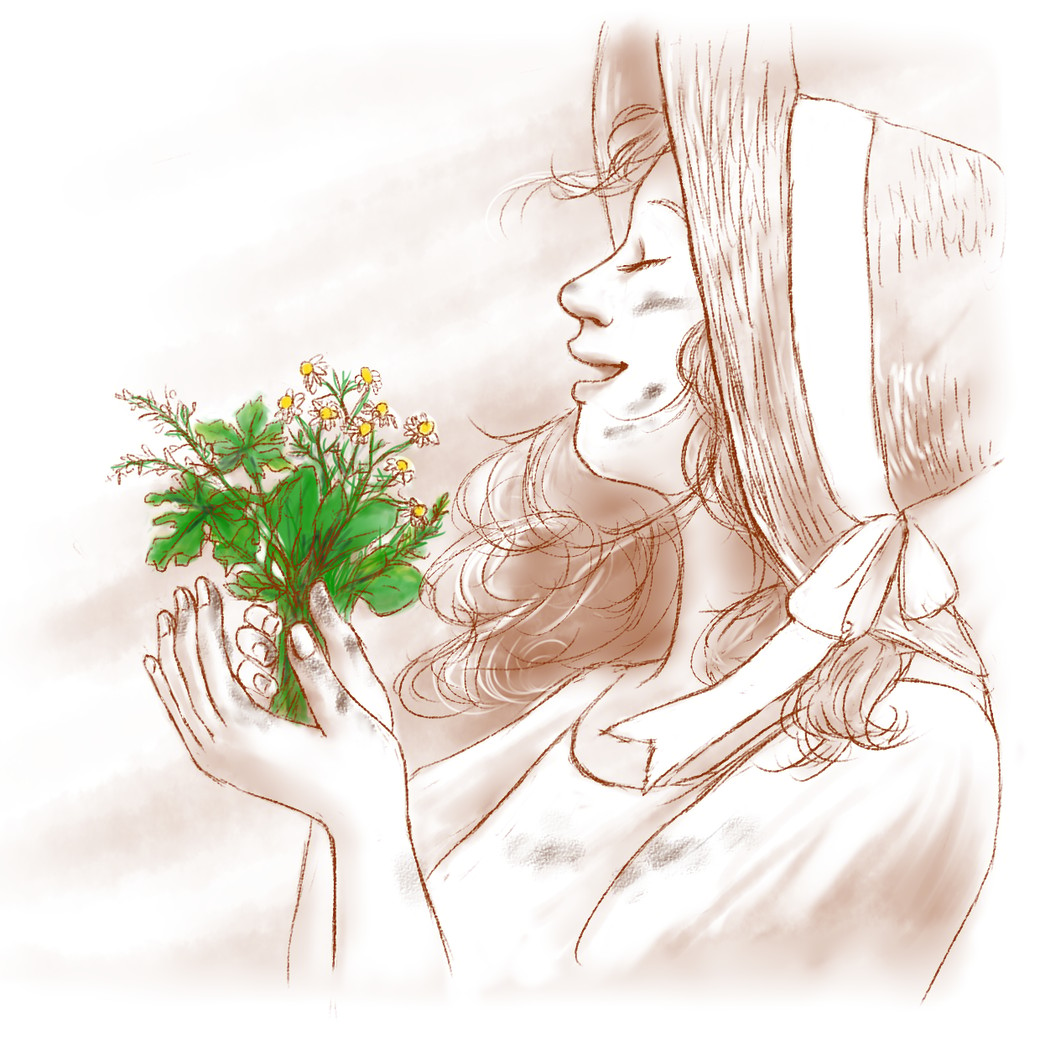
「野間さんって、話題が次々と出て来て、ティッシュペーパーみたいですね」
「ティッシュペーパー?」
「すみません! わたし、余計なこと言っちゃうんです。ママ友とのおしゃべりでも、けっこう滑ってます」
「ううん、私は好き。私もよく言うもん。トイレットペーパーみたいに長いメールとか。スクロールしても永遠に続くやつ」
「あはは。いいですね、それ」
野間さんと話していると、余計な力が抜けていく。野間さんが好きだし、野間さんと話している自分が好きだ。
「マリー・アントワネットみたいに財力も広い土地もないけれど、自由だけはある。奥様でもお母様でもなく、私は私を生きればいい」
ノマリー・アントワネットに拍手を贈りながら、千佳子は考える。
わたしはわたしを何と呼ぼう。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第27回 伊澤直美(9)「あの嫁なんで旧姓使ってるんだ問題」へ。
イラスト:ジョンジー敦子
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!