
第190回 伊澤直美(64)そうでないほうの人
直美の知らないカタカナの名前を挙げて、亜子姉さんとmaikimakiさんは意気投合している。イラストレーターだか映画監督だかジャンルすらわからないが、その人の作品にひまわりが登場するらしい。
テーブルに着いている3人が「つくる人」と「そうでない人」に分かれている。話の内容は聞こえるけれど話題に加われない。見えない膜が張られているみたいに。
亜子姉さんはこういう話がしたいのだなと、守備範囲の及ばない直美は申し訳なくも淋しくも思う。亜子姉さんが感じているであろう物足りなさが直美のささやかな自信とプライドを小さく引っ掻く。
普段は意識しない気後れを覚えるのは、自分にないものを人が持っていることを自覚させられたときだ。英語を話せなくても不自由していないのに、話せる人と一緒にいると、あるべきものが備わっていない心もとなさを感じてしまう。
直美が『鏡っ子ゆあちゃん』という童話を書いてコンクールに出して一次選考にすら引っかからなかったとき、亜子姉さんは仕事で描いたひまわりの絵が売れ、そのお金でひまわりバッグを買った。
わたしはわたし。亜子姉さんは亜子姉さん。わかっているけれど、引き算で自分の価値を目減りさせてしまう。
「うらやましい」と「面白くない」は風にあおられるレースのように表にも裏にもなる。応援したい気持ちがひっくり返ると、足を引っ張るほうに働く。
亜子姉さんのように創作にぶつけるパワーも才能もなく、匿名掲示板にひまわりバッグのことを書き込んで指一本で波紋を起こそうとしたが、結果は沈澱した気持ちが攪拌されて、水が濁っただけだった。

「会うべき人に会える確率は1分の1だよ」
亜子姉さんにそう言われたのは、ひまわりバッグの縁で面白い出会いがあったと話したときのことだ。
優亜を連れて出かけた電車の中で言葉を交わした母娘がいた。母親が持っていたバッグを見て、咄嗟に「makimakimorizoですか?」と声をかけたのは、母娘が電車を降りたときで、返事を聞く前にドアは閉まったが、一期一会かと思ったその人とは、すでに出会っていた。消費者調査のオンラインインタビューで「パセリの花束」という印象的なエピソードを聞かせてくれた人だった。
その人、佐藤千佳子さんのほうも後から直美のことを思い出したらしく、アイタス食品の試食会に来てくれ、子ども服をくれ、交流がつながった。
佐藤さんがパート先のスーパーマルフルでやろうとしていたハーブマルシェにも声をかけてもらったのだが、企画の詰めが甘く、社内に持ち帰って検討できる内容ではなかった。数か月後にkirikabuで偶然再会したときには、ハーブマルシェは予想通り棚上げになっていたが、佐藤さんの娘の文香ちゃんに優亜はすっかり懐き、そのとき覚えた語尾の「たね」を気に入って、「やったね」「たのしかったね」などと連呼していた。
そう言えば、ハーブマルシェの企画書のイラストを描いたのがmakimakiさんだと聞いていた。チューリップバッグの縁だという。スーパーマルフルの同僚だった人がアムステルダムで暮らすことになり、日本を発つ前に佐藤さんにチューリップバッグを贈ったのだが、その同僚は以前にもチューリップバッグを購入していて、留守宅の管理をmakimakiさん夫婦に託すことになったのだった。その家をひまわりバッグの持ち主の亜子姉さんと代理で購入した直美が訪ね、作者とお茶をしている。幼い娘たちまで連れて。その娘たちはクローバーが生い茂る庭で四つ葉を探している。
クローバーとひまわりとチューリップが根を伸ばし、つながっている。
世の中にはこれだけ人がいるのに、会うべき人とはいつか会うようにできているし、何度でも会うようになっている。
それは素敵なことのはずなのだけど。
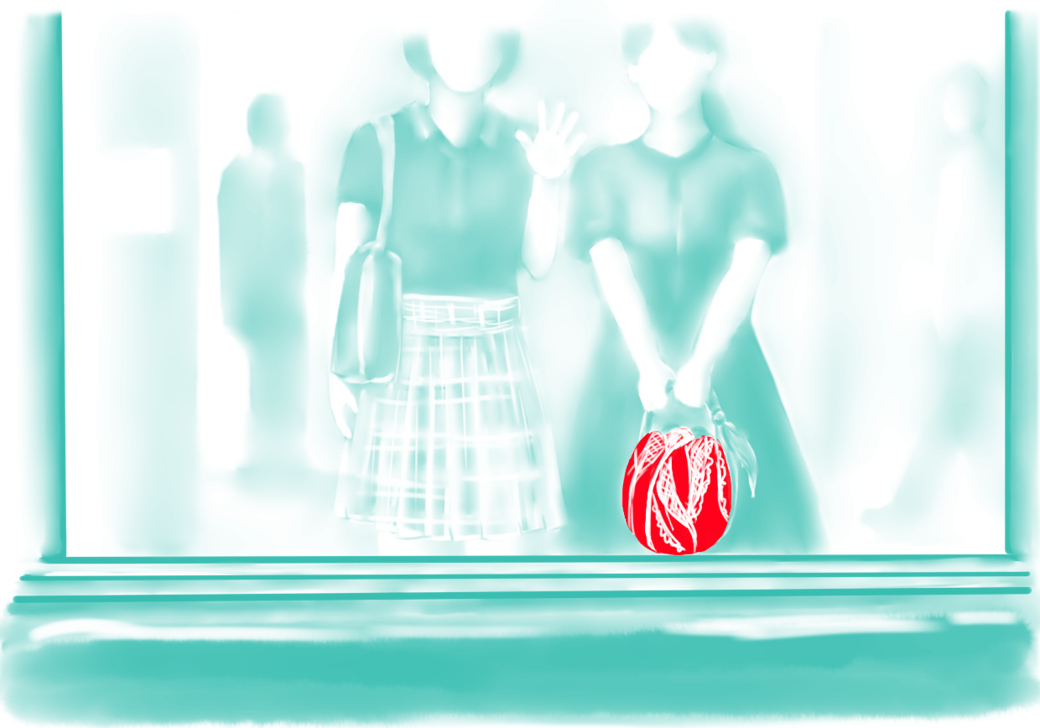
《あしたは ぼくのおやつ
きみに ぜんぶあげる
ぼくが おやつのゆめを みたら
きみに ぜんぶあげる
きみが おばけのゆめを みたら
ぼくが ぜんぶたべる》
優亜と結衣が歌っている。直美は初めて聴く歌だ。結衣が優亜に教えたのだろうか。
テーブルの大人3人と庭の子ども2人、あわせて5人がふたつに分かれていることも直美は自覚する。今ここを楽しんでいる4人と、居場所を見つけられずにいるひとり。
気後れの理由は他にもある。
同期で同じ部署のタヌキが昇進した。後輩のハラミ2号も昇進した。同じプロジェクトを立ち上げ、一緒に進めた直美の昇進は見送られた。時短勤務やリモート勤務で迷惑はかけているけれど、結果は出している。そう思っていたのは自分だけだったのか。
仕事があって、子どもがいて、十分充実しているはずの毎日なのに、時々どこかに穴が空いて、空しくなる。空気を入れても入れても抜けてしまう自転車のタイヤみたいに。
四つ葉のクローバーを見つけてはしゃぐ子どもの素直さがあれば、子育てをしながら仕事を続けられているだけでありがたいと素直に喜べるのだけど。
「直美ちゃん、あれ持ってきてくれた?」
亜子姉さんに呼ばれた。ようやく話題が途切れたのだろう。
家を出る前に電話で「あれ持ってきて」と頼まれ、ひまわりバッグを持ってきた。外に出すのは、タヌキに貸して以来だ。その前は、亜子姉さんと母娘ふた組で出かけたときだった。直美が持っても亜子姉さんが持ってもさまにならず、着るものを選ぶバッグだと実感したが、優亜が持つと意外としっくり来た。
亜子姉さんが紙袋からひまわりバッグを取り出したのを見て、makimakiさんが戸惑った表情になった。
連絡を受けたメールに返品の意向があれば応じる旨が書かれていたことを直美は思い出し、亜子姉さんはどういうつもりなのかと見守る。
「はい、里帰り」
亜子姉さんがmakimakiさんにひまわりバッグを差し出した。

里帰り。
親である作者に顔を見せに帰って来たということだろうか。
亜子姉さんは独特の表現をする。幼稚園を2回変わることになった幸太の制御の難しさを「超能力」と呼んでいたっけ。幸太が小学校に上がった年に亜子姉さんは仕事を再開した。幸太は5年生になったから、仕事を再開して5年目ということになる。
両手でひまわりバッグを受け取めたmakimakiさんは、しばらく何も言わなかった。再会を味わっているようにも見えるし、感想の言葉を探しているようにも見えた。
「何年ぶりですかね?」
亜子姉さんから声をかけた。
2年は経っていると直美は頭の中で計算する。購入したのは、いま2歳3か月の優亜が1歳になるより前だったから。
「一度手を離れた作品をもう一度手に取る機会って、なかなかないので」
makimakiさんがしみじみと言った。同じデザインのものは作っていない。一点ものということは、作者にとってもただ一つなのだ。
「ありがとうございます」
対面を味わったmakimakiさんが両手を伸ばし、亜子姉さんにバッグを差し出した。
「いえ、ここに置いていてください」
「え?」と驚く直美とmakimakiさんの声が重なった。
「里帰りって言ったじゃないですか」

次回6月7日に多賀麻希(63)を公開予定です。
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!
























































































































































































































































































































































































































































