
第88回 伊澤直美(30)母とわたしと犬とレモン
インターホンを鳴らしてみたが、応答はなかった。
「レモンの木、前からあったっけ」とイザオが聞く。
「あったよ」と直美は答える。
門からのびるブロック塀の上、シンボルツリーのように立つレモンの木が枝を広げている。枝は塀を越えて道路側にせり出し、大ぶりの実を垂らしている。
もう何年になるだろう。飼っていた犬のトトが死んでしまい、骨になったトトを埋めたところに母はレモンの苗木を植えた。トトは直美が小学生だったときに両親にねだって飼い始めた。『オズの魔法使い』に出てくる子犬にちなんで名前をつけたのも直美だった。
部活や勉強が忙しくなり、トトは後回しになっていき、トトの世話は少しずつ母に移っていった。あるときから母はトトのことを「ぴーちゃん」と呼び始めた。どこからその名前が降ってきたのかはわからないが、母が突拍子もないことを言うのは珍しいことではなかった。いつもの気まぐれかと思ったが、母はその名で呼び続け、レモンの木の根元に「ぴーちゃんの木」と手書きした札を立てた。
ひよこ色したレモンのほうがぴーちゃんという名前が似合うと当時の直美は思ったし、今も思う。植えたときはトトよりも背が低かったレモンの木は、ぐんぐん伸びて、ブロック塀から顔をのぞかせる背丈になった。

もう一度インターホンを鳴らしてみる。家の中でピンポーンと間延びしたように音が鳴る。その音が消えると、家は黙り込む。人の動く音がしない。人のいる気配も感じられない。
「出ないね」
「出ないね」
イザオが言った4文字を直美は繰り返す。予想していたことではあったけれど、一人だったら、この沈黙を深刻に受け止めてしまっただろう。「出ないね」と確かめ合える相手がいるだけで、気持ちが楽だった。
母に会えるとしても、会えないとしても、ひとりよりふたりが心強い。
それと、もうひとり。
イザオに縦抱っこされた優亜はまだ寝息を立てている。もしかしたら今日、母に孫娘の顔を初めて見せることになるかもしれないと思い、出産祝いで贈られたブランドものの長袖を箱から出し、着せてきた。
「電気は来てるってことだよね?」とイザオが言う。
「あ、そっか」と直美は応じ、電気が来ているということは、今もここに住人がいるということだと理解し、安堵する。インターホンのついた門の脇のポストに刻まれた名字は「原口」のままになっている。住人は変わっていないということだ。
たまたま今留守なだけかもしれない。電話が通じないのは、固定電話をやめて携帯電話にしたからかもしれない。考えうる中でいちばん楽観的な可能性を想像し、何の根拠もないのにほっとする。でも、中で住人が倒れていようと電気は通うのだと思うと、不安に駆られる。
「原口さん? いますか?」
「お母さん」ではなく名字で呼びかけてみるが、家の中はしんとしている。
父が出て行った後も母は旧姓に戻さなかった。籍は入ったままなのだろうか。離婚して夫婦の縁は切れたが、慣れ親しんだ名前だけは使い続けているのだろうか。
父と母がどうなっているのか、聞けていない。父にも母にも聞くのが申し訳ないし、自分のせいで両親が溝を深めたのではという負い目もある。両親が言い争うのは、いつも直美のことだった。わたしがいなければ、この家はもっと平和だったのに。生まれてきてごめんなさいと思い詰めたこともあった。だから、早く家を出たかった。
心残りはトトのことだったが、トトはすっかり母のぴーちゃんになっていた。直美が大学生になった頃、トトは徘徊が始まっていた。トトが弱れば弱るほど、母はより熱心に世話を焼いた。娘よりも犬のほうが手のかけ甲斐があると気づいたのだろう。
ぴーちゃんを喪った後、ぴーちゃんに注いでいた時間と情熱を母は「ぴーちゃんの木」に注いだ。ぴーちゃんがお腹を冷やさないようにと毛糸で編んだ腹巻きを木の幹に巻きつけ、冬の寒さから守った。ぴーちゃんの生まれ変わりのようにレモンの木を愛した。
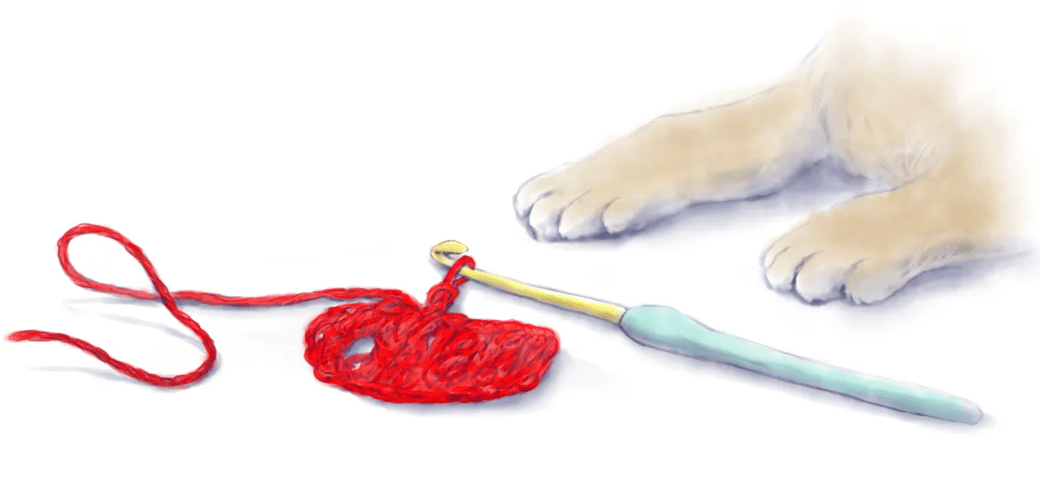
娘とわかり合えない母の虚しさをぴーちゃんが埋め、ぴーちゃんを喪った悲しみをぴーちゃんの木が埋めてくれた。そう考えると、目の前のレモンの木に感謝の気持ちが湧く。わたしの代わりにお母さんを受け止めてくれてありがとう、と。
レモンは年によって豊作の年と不作の年があり、ひとつも実らない年があったかと思うと、何十個も実をつける年もある。今年は豊作の年のようだ。
収穫せずに実りっぱなしになっている実の重みで枝がたわんでいる。実の大きさに対して、支える枝は細く、頼りなく見える。お母さんが重かったわたしも、受け止めるだけの丈夫さや図太さが足りなかったのかもしれないと直美は思う。
イザオが門に手をかけると、開いた。数歩先に玄関のドアがある。
「ハラミ、鍵持ってないの?」
「置いてきた」
「そっか」
イザオは鍵を「忘れてきた」という意味に取ったが、ひとり暮らしすることになって家を出たときに置いていったのだ。この家には帰らないという意思表示のつもりで。
「あれ? 違うか」と直美は記憶の答え合わせをする。
何度か荷物を取りに帰ったとき、母に鍵を開けてもらった。やっぱり鍵を持っていたほうがいいと思い、荷物と一緒に鍵を持ち帰ったのだったと思い出す。
だが、その鍵はもう使えなくなっていた。母が鍵をつけ替えていたのだ。
たまたま鍵をなくしたのか、空き巣対策で破られにくい鍵にしたのか、何か理由があったのかもしれないが、家を出て行った夫と娘を締め出すためだと直美は理解した。
わたしだけが離れて行ったんじゃない。母も自分から距離を置いた。それなのに、わたしたちの結婚パーティーには出たいと言い、席を用意したのに、結局来なかった。連絡も寄越さずに。
そうだ。結婚パーティーのあの日、母が会場に向かう途中で倒れたのではないかと心配した。地元に残っている同級生のお母さんに連絡して、家まで見に行ってもらって、母の無事を確認してもらい、ほっとして気が抜けると同時に怒りが込み上げ、結婚パーティーのおめでたさを2割ほど削がれた。
この歳になって、親になっても、まだ母に振り回されている。夫まで巻き込んで。

「どうする? もう少し待つ?」
直美はどうでもいいやと投げやりな気持ちになる。元来た道へ視線を向けると、こちらに向かってくる人影が見えた。
「お母さん?」と目を凝らすと、近づいてきた女性は母ではなかった。歳は母と同じぐらいに見えるが、顔つきが全然違った。母はきつい顔立ちで、ネジで締めつけたような緊張感が皺になって刻まれていたが、その女性は重力に任せたような肌の緩みが、人を警戒させない柔らかな表情を作っている。母とは別な時間の積み方をしてきたことが顔に現れていた。
女性は直美の家の前まで真っ直ぐ近づいて来て、レモンの木の前に立つ直美たちに、「こんにちは」と声をかけた。顔から想像した通りの明るい声だ。
「こんにちは」と直美とイザオも明るい方向に引っ張られた声で応じる。その声につられて、笑顔になる。赤ちゃんを抱っこしているし、不審者には見えないだろう。
女性はこの家に用があるのだろうか。母を訪ねて来たのだろうか。母のことを何か知っているのだろうか。何からどう切り出そうと直美が考えあぐねていると、女性が先に口を開いた。
「レモン、好き?」
思いがけない質問に、直美は「え?」となる。どうやらレモンを物欲しげに見ていると思われたらしい。
「ちょっと待っててね」
女性は門を開けて中に入ると、インターホンのついたポストの後ろ側のドアを開け、中から園芸用のハサミを取り出した。そのハサミでチョキンチョキンと枝を切り、レモンの実を2つ収穫し、「どうぞ」と直美に差し出した。
初めてではない。慣れている。人の家のレモンを勝手に採っていることへの後ろめたさは感じられない。母は知っているのだろうか。母の知り合いだろうか。
直美がレモンを受け取ろうとしないので、女性が「どうぞ」ともう一度言った。
「あの……これ、うちのレモンなんですけど」
「もしかして、直美ちゃん?」
「もしかして、レイコさんですか?」
咄嗟に口から出たのは、父と暮らしている女性の名前だった。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第89回 多賀麻希(29)「世渡り上手の駆け引き構文」へ。
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!
























































































































































































































































































































































































































































