
第29回 多賀麻希(9) 結婚しましたハガキが重かった頃
「使いものにならんのやったら、取ってしもて、ええんとちゃうん?」
動かなくなった電化製品をゴミに出すように、マスターは言った。麻希の胆のうのことだ。胆石だらけになった胆のうを取り除く手術をするかどうか、最後の客が帰ったカフェで相談している。
「でも、あっても邪魔にならないかなって」
使いものにならない胆のうに自分を重ねて反論すると、「マキマキの答えは出てるやん」とマスターに言われた。手術を受けたくない気持ちは、はっきりしている。ただ、それでいいんだよと誰かに言って欲しかった。
「モリゾウは何て言うてるん?」
「手術やるなら、立ち会うって」
「ふうん」
マスターの相槌が意味ありげに聞こえた。ふたりの仲が進展したと受け取られたかもしれない。
「モリゾウとは、ただの同居人ですから」
「それやったら、まぁ、ええか」
マスターの言い方が引っかかり、それだったらってどういう意味ですかと麻希は聞いた。
「マキマキ、全身麻酔やったことある?」
「ないです」
「コテンて効いて、次に目ぇ覚ましたときは手術終わってるねん」
「マスター、やったことあるんですか?」
「若い時分にな。麻酔が覚めて、意識がほわほわしてるときに、いらんこと言うてしもて」
「いらないこと?」
「一番好きな人の名前」
マスターが呼んだのは、手術に立ち会っていた人とは違う名前だったのだろう。そして、それを口にしたことで、その人との関係が変わってしまったのだろう。歪んだか、壊れたか。同じことが麻希とモリゾウに起きたらと心配してくれたが、「ただの同居人なら、まぁ、ええか」ということらしい。
わたしはツカサ君の名前を呼ぶのだろうかと麻希は考える。モリゾウが聞いたら、どう思うだろう。「ツカサって誰だ?」と気になるだろうか。そう聞かれたら、何と答えよう。
前に勤めていた映画製作プロダクションの社長が撮影現場に連れて来て、エキストラで恋人役を演じた人。麻希と同い年で、当時は脚本家を目指していて、コンクールは一次審査止まりで、結局夢は叶わず、故郷に帰った人。「シンデレラへ」のメッセージを添えた赤い靴と、古墳バッグになったボタンのいっぱいついたシャツと、麻希をモデルにした脚本と、消えない思い出を残して。
過去のことをわざわざ知ってもらう必要はないが、うっかり伝わるならいいのかもしれない。そう思うのは、モリゾウの過去に興味が湧いているせいだろうか。古墳王子への屈託。「人は死にますよ」と言ったときの目。小説の続きが気になるように、その先のモリゾウを知りたくなっている。

「マキマキの部屋、物だらけやろ?」
「なんでそう思うんですか?」
「あっても邪魔にならん、いうんは、物が捨てられへん、いうことや」
「あはは。バレました?」
そういうことにしておいた。たしかに、物を捨てられなかった頃の麻希の部屋は、場所を取らないからという理由で溜め込んだモノたちであふれ返っていた。
それが、衝動的に引っ越そうと決めたとき、自分でもびっくりするほど、どんどん手放せた。45リットル入りのゴミ袋が次々と満杯になるのが快感だった。捨てた分だけ気持ちが軽くなっていった。
過去を断ち切るための引っ越しだったから。
ツカサ君と別れた後、映画製作プロダクションの社長が夜逃げして無職になったときに、同僚だった事務の美優ちゃんから披露宴の招待状が届いた。
披露宴当日、新郎新婦の見送りを通り抜けたところで、麻希は泣き崩れた。まわりの人は「良かったね」のうれし涙だと受け止めてくれたが、悔し泣きだった。自分はこんなに踏んだり蹴ったりなのに、なんであの子は幸せになるのと恨めしかった。
結婚しましたハガキに加えて、産まれましたハガキが年々増えていった。こちらは幸せにやっていますが、そちらはどうですかと笑顔に迫られているようで気が滅入った。とくに書くことがなかっただけだとわかりつつ、「お変わりありませんか」の手書きメッセージに傷ついた。世間の平均的標準的な幸せ達成度と自分との差が開くにつれ、幸せ報告ハガキが重くなっていった。
だから、引っ越すことにした。引っ越して、新しい住所を知らせなければ、ハガキは追いかけて来ない。
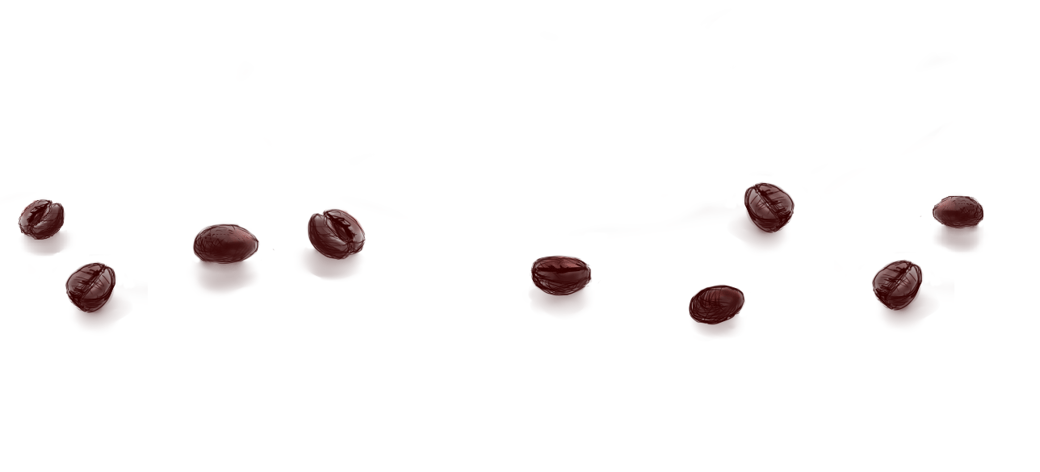
アパートに戻り、ポストを開けたとき、「違う」と思い出した。
引っ越しを決めたきっかけになったのは、結婚しましたハガキでも生まれましたハガキでもなかった。
届いたのはハガキで、送り主は美優ちゃんだったが、幸せ報告ハガキではなかった。結婚式から何年か経って届いた「引っ越しました」のハガキ。差し出し人の名前が、旧姓に戻っていた。
一人に戻ったんだ。
美優ちゃんに何があったかを心配するより先に、麻希はほっとした。幸せをつかんでも、ずっとつかんでいられるわけではない。見放されたのは、わたしだけじゃなかった。救われたような気持ちになったすぐ後に、吐き気のような強烈な自己嫌悪がこみ上げた。
ハガキを裏返すと、スーツ姿の美優ちゃんが七五三の着物姿の女の子と写っている写真に「母娘仲良くやっています」と書き添えてあった。
一人じゃなかった。七歳には見えないから三歳なのだろう。「生まれました」もその後の成長も年賀状で知らされていたはずだが、覚えていなかった。見たくなかったのか、忘れたかったのか。三歳になった美優ちゃんの子が突然現れたように思えた。
お母さんになった美優ちゃんは、麻希と働いていた頃より体つきも顔つきも丸くなっていた。ちっとも淋しそうじゃなかった。麻希の心配も同情も必要なかった。一瞬浮き上がった分、勢いづいて突き落とされた。
ハガキ一枚にいちいち波立つことに疲れた。だから、ハガキが追いかけて来ないところへ逃げた。
もちろん美優ちゃんには引っ越し先を知らせなかった。「年賀状が戻って来ちゃったんだけど、住所変わったかな?」と美優ちゃんの声が留守番電話に残されていたが、かけ直さなかった。
最後の恋人の名前をうっかり口にしてモリゾウに聞かれても構わないが、美優ちゃんからのハガキに浮き沈みしたことは知られたくない。知られたら、きっと、モリゾウに嫌われる。
そのことを恐れ始めている自分に気づいて、麻希は立ち尽くす。
麻酔から覚めたとき、名前を呼んでしまうのは、ツカサ君ではなく、もしかしたら……。

集合ポストの奥に伸びる通路を十歩も歩けば、麻希の部屋があり、鍵のかかっていないドアを開ければ、いつものようにモリゾウがいる。
いつものようにそのドアを開けられるだろうか。
いつものようにモリゾウの顔を見られるだろうか。
いつものようにモリゾウと話せるだろうか。
今わたしは、どんな顔をしているのだろう。
モリゾウからは、どんな風に見えるのだろう。
足がすくんで、動けない。
わたしの家なのに。
モリゾウは、ただの同居人なのに。
ドアを開けると、豆の形をしたちゃぶ台の前にモリゾウがいて、振り返った。そして、ちゃぶ台を挟んで、もう一人。
「お父さん」
次の物語、連載小説『漂うわたし』第30回 多賀麻希(10)「今さら孫の顔が見られるわけでもないし」へ。
イラスト:ジョンジー敦子
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!






















































































































































































































































































































































































































































