
第130回 伊澤直美(44)母娘の残像
「どこで会ったのかなー」
ランチのミラノ風カツレツを食べながら、直美は同期のタヌキに東急線で会った母娘のことを話している。
あの日、直美の向かい側の席に並んで腰を下ろしていた母娘は、直美の膝に座っている優亜に目を留め、可愛いねと言い合っていた。「いくつぐらいかな」と娘が言い、母親が「80ぐらい?」と答えたのは、服のサイズだった。
電車を降りようと立ち上がったとき、母親が手にしたバッグの全容が見え、真っ赤なチューリップが現れた。
「makimakimorizoですか?」
咄嗟に口走ったブランド名に発車ベルの音がぶつかった。
「え?」と母親が聞き返したのと、先にホームへ降りた娘が「ママ早く」と急かしたのが同時で、「すみません」と直美と母親の声が重なった。
電車を降りた母娘は、さっきまで自分たちが座っていた座席の上の窓の向こうに現れた。娘が優亜に手を振ってくれたが、直美の目は母親に吸い寄せられた。
落ち着いた色合いとゆったりしたラインのワンピースに真っ赤なチューリップが異彩を放っていた。唐突に放り込まれたような赤に記憶の隅を引っかかれた。
あの人、どこかで会ったことあるかも。
それがどこだったのか思い出せない。チューリップバッグの赤を手がかりに記憶の地層を掘り返しているのだが、これだという答えにまだ辿り着けていない。
「タヌキと一緒に会った人かも」
「じゃあ仕事関係? トマト農園か、ケチャップ関係か」
「唐突な赤じゃないよね?」
「じゃあ、夜道の郵便ポスト? 違うか。トンネルを抜けたら彼岸花?」
「それって、どういう出会い?」
タヌキが思いつくまま赤いものを挙げるが、大喜利みたいになっている。
「わかった。銀世界に血だまり」
「その状況で会ってたら、さすがに覚えてる。あー。ダメだ。思い出せそうで思い出せない」
「歯の間にブロッコリーが詰まって取れない感じ?」
タヌキは笑って、つけ合わせのブロッコリーを口に放り込む。
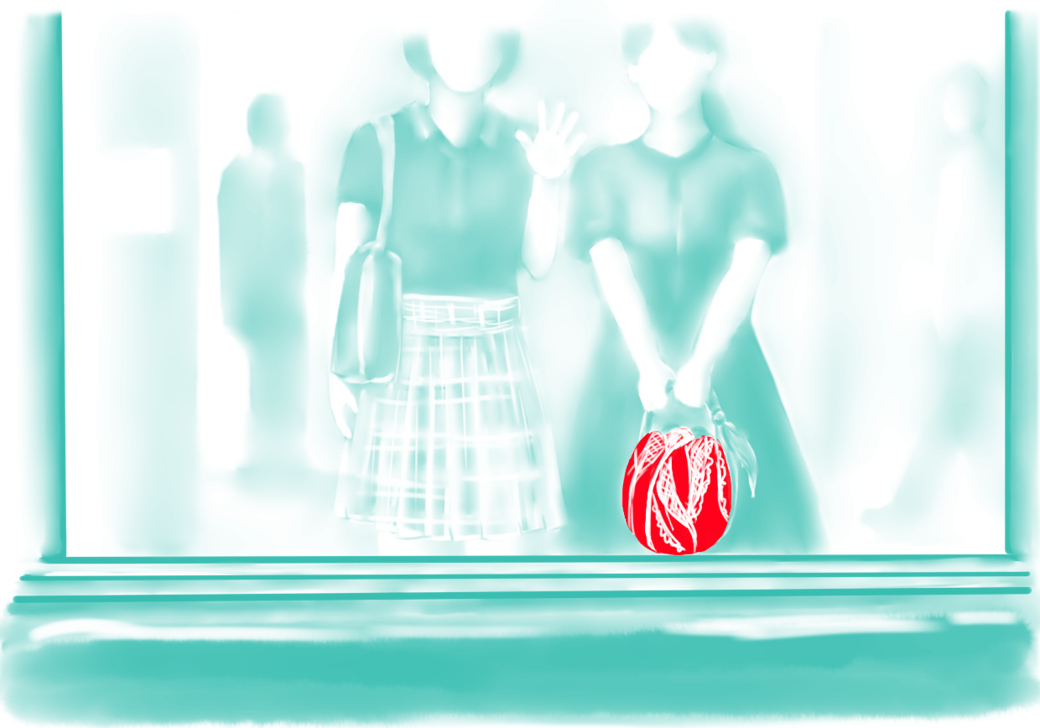
「ハラミって、思い詰めると、そのことばっかり考えちゃうとこあるよね」
タヌキに言われるまでもなく、自覚はある。十分すぎるぐらいに。
イザオとふたりで初めて映画に行った日、ヒロインが誰かに似ていると気づいた直美はストーリーを追うどころではなくなってしまった。観終えた後のランチでイザオにそのことを話すと、
「ああ、レンチンパンだろ」
あっさり答えを言われた。勤め先のアイタス食品で出しているレンチンシリーズのキャラクター。レンジでチンするも良し、鍋で温めるも良しでレンチンパン。イラストのチンパンジーが親指を立て、ニカッと歯を見せているデザインだった。
「サルでも調理できるというのは消費者をバカにしている」とケチをつける消費者とそれに賛同する無責任な消費者が現れ、パッケージに印刷されるレンチンパンはどんどん小さくなり、ついには消えてしまった。
違う。掘り出したいのはサルじゃない。でも、かすっている気がする。
最後に観た映画ってなんだっけど思い出そうとしたが、いつが最後だったのかすら思い出せない。子育てをしていると時間が溶ける。記憶が溶ける。脳みそが溶け出しているんじゃないかと思う。知らない間にタイヤに穴が開いて空気が漏れている自転車みたいに。
唐突な赤。映画。イザオ。自転車。
掘り起こされたのは、真っ赤な自転車だった。
六本木まで自転車で出かけて、映画を観て、パエリアを食べながら感想を言い合い、独身時代のデート気分を味わった帰り、輸入ブランドの自転車ショップの前でイザオが足を止め、勧められるまま試乗した。
最初のひと漕ぎの軽さに驚いた。東京タワーにぐんぐん近づくスピードが、いつもの自転車の倍ぐらいに感じられた。翼が生えたような乗り心地を味わいつつ、妊娠したらこのスピードで走れなくなるのだと直美は淋しさを覚えたが、イザオはその自転車を買う気になった。

この人は何もわかっていないと失望した。妊娠はできないけれど、できることはやるから子どもが欲しいと涙ぐんで訴えたくせに。
「名前も連絡先も知らない。手がかりはバッグだけ。恋愛ドラマだったら、再会して恋に落ちるやつだね」
タヌキの声で妊娠前に巻き戻されていた意識が現在のランチに戻る。カツレツがあとひと切れ残っている。
「大丈夫。会うべき人には、会えるようになってるから」
ひまわりバッグを見て高校生の頃に見た映画『幸せのしっぽ』を思い出し、作者に会いに行ったタヌキが言う。
母親がかつて着たウェディングドレスを押しつけられていたタヌキは、ひまわりバッグの作者にドレスを託した。ドレスは裾に一面のクローバーの刺繍を施されて返ってきた。
結婚パーティーでタヌキは『幸せのしっぽ』の話をした。入社したときからタヌキに何度も振られたマトメとタヌキが一気に近づいたのは、公開時に全国で2万人しか観なかったこの映画をマトメも観ていたからだった。
映画とドレスのつながりについては話さなかったが、舞台裏を知っている直美には、私は私らしく、私が見つけた人と幸せになるんだというタヌキの宣言に聞こえた。
その日、タヌキの母親は姿を見せなかった。
直美とイザオも同じレストランで結婚パーティーを開いたのだが、直美の母親は、当日まで来ることになっていたのに、姿を見せなかった。
どこかで会ったことがあるのではなく、あの母娘に叶わなかった過去を見たのかもしれないと直美は思う。唐突な赤が引っかかった理由は謎のままだけど。
服のサイズで優亜の大きさを想像した母親は、あんな頃があったなと懐かしんでいたのだろう。「なんでサイズ?」とツッコミを入れた娘は、80センチの服を着ていた頃のことを多分覚えていないだろう。それでも笑い合える。育てた時間、育てられた時間を慈しみ合える。直美と母の間にはなかった穏やかな肯定感が眩しかった。
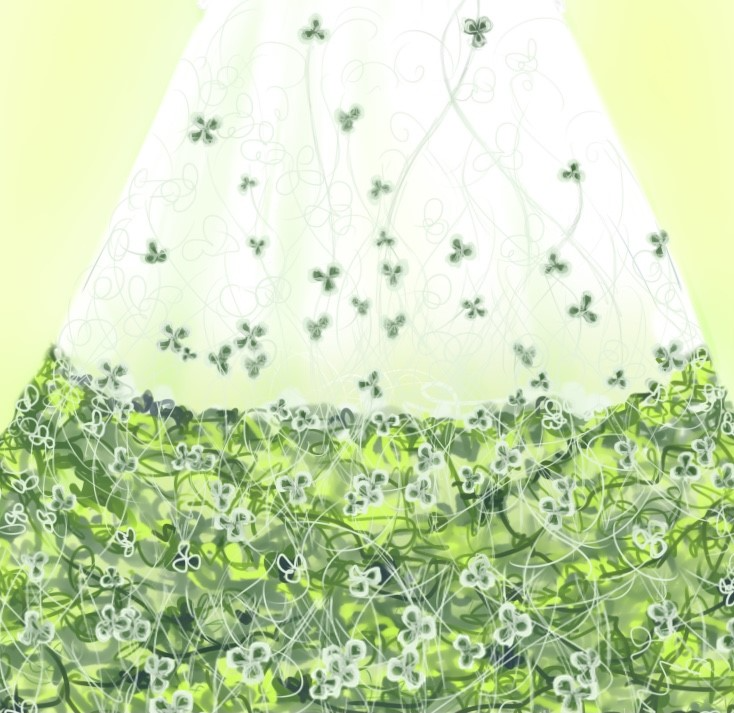
「思い出した」と直美がつぶやくと、
「どこで会ってた?」とタヌキが身を乗り出した。
「チューリップバッグの人じゃなくて、最後に観た映画。『幸せのしっぽ』だ。タヌキとマトメの結婚パーティーの前の晩」
「イザオと観たの?」
「一緒だったっていうか、一緒じゃなかったっていうか」
唐突な赤。映画。イザオ。自転車。すれ違い。
赤い口紅。
ツルハシの先にコツンと手応えを感じたかと思うと、イルミネーションがバババッと端から点灯して光がつながるように記憶の断片が一気に結びついた。
「タヌキ、思い出した! タヌキと一緒にオンラインインタビューした人!」
「どの人?」
「中学生の娘がいるって言ってた人! 2年前だから、今は高校生になってるかも」
「ハラミが『月刊ウーマン』で話した、パセリの花束の人?」
「そう!」
「赤じゃなくて、緑じゃん」
直美に口紅の衝撃を残したその人は、タヌキにはパセリの印象を残した。子育てが天職のようなその人に直美は気後れした。自分はこの人のようになれないと思った。一方、歳を重ねることを恐れていたタヌキは、日々のささやかな幸せを積み上げる生き方に背中を押され、プロポーズを受け入れる決意をした。
赤い自転車を巡るケンカがこじれ、イザオが家出してマトメの一人暮らしの部屋に転がり込み、直美を訪ねてきたタヌキから結婚すると聞き、そこにマトメがイザオを連れて来て、タヌキを連れ帰ったあくる朝、イザオと取り合った手に虹が落ち、おなかに優亜が宿った。
口紅もバッグも唐突な赤のあの人は、ふた組の夫婦を動かしていたのだった。本人の知らないところで。
引っかかりの正体はこれだったかと直美はカツレツの最後のひと切れを口に運ぶ。揚げたての熱はすっかり冷め、切り口からとろけ出したチェダーチーズは固まっていたが、ようやく味を感じられた。
あ、イタリアンパセリ。
ヒントは最初からテーブルに出ていた。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第131回 多賀麻希(43)「棺に入る分だけ残しなさい」へ。
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!






















































































































































































































































































































































































































































