
第54回 多賀麻希(18) 回りくどい女が欲しかった一言
「わたしって、つくづく男運がないんだよね」
刺繍の針を止めたまま、麻希は自分語りを続ける。
「好きって言って」と囁いたら、「黙ってろ」と言われた。寝ているところを起こされて、寝ぼけている間に事が終わっていたこともあった。
「目が覚めたときに、昨日のは夢だったのかなって思ったら、口を丸めたコンドームがゴミ箱に捨ててあって。自分を見てるみたいで、泣けてきちゃった」
「マキマキさん、それって……」
モリゾウが割って入るのを「わかってる」と麻希は遮った。
わかってる。そんなのつき合ってるって言わない。はけ口にされていただけ。最近になって、Me tooだ何だと声を上げている女の人たちが男の人にされたことを読んだら、過去に自分がされていたことだった。
「お金まで吸い取られて、もう笑っちゃうよね。フツーは、こっちがお小遣いもらうほうなのに」
いかにも平気だよ傷ついてないよという明るい口調で麻希は言い、モリゾウを試す。
むしり取られた過去を笑い話にするような女なら、遠慮なくむしり取れる?
それとも……?
「フツーがどうだか知らないけど」
モリゾウはボソッと言った。
「俺だったら家賃に上乗せして払いますよ。マキマキさんと暮らすの楽しいし。金があったらの話だけど」
金があったら。
よく言うよ。
モリゾウが転がり込んでからの家賃と光熱費と食費を折半するとしたら、いくらになるだろうか。月に10万としたら、百万近くになる。そのお金がないわけではないのに、麻希を通り越して、別なところに落ちている。麻希よりも価値のある何かに使われている。その何かに麻希は嫉妬し、みじめになる。
麻希の布雑貨を作品と呼び、麻希を作家と呼び、のぼせ上がらせたモリゾウ。わたしには価値があると思わせてくれた人が、同時に、お前には価値がないと残酷な形で示している。
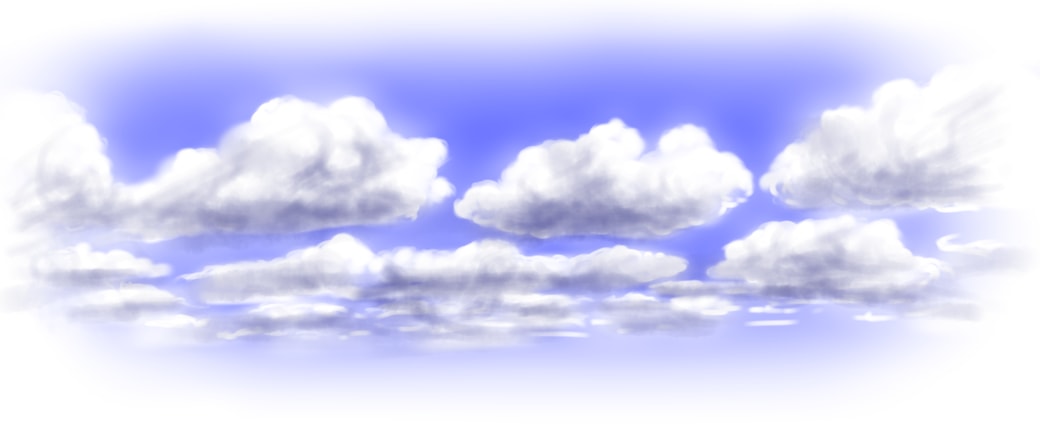
「モリゾウは普通の人とは違うもんね」
イヤミを込めて言ってから、いや、ここは乗っかっちゃいけなかったのではと思う。普通か普通じゃないかの問題で片付けてはいけない。麻希の何倍も稼いでいるくせに、「お金があったら」なんて平気で言うモリゾウが問題なのだ。
「いや、俺もフツーの男っすよ」
モリゾウの眼光と声色が尖ったような気がして、麻希はドキッとする。あぐらをかいていたモリゾウが正座の形に座り直し、麻希に向き直った。
「ちょっと脳内実況していいっすか?」
麻希の返事を待たず、モリゾウの口から言葉がほとばしった。
「冷静に聞いてられないっすよ。マキマキさんがどんな風に吸い取られてたか想像しちゃう俺に戸惑うわけですよ。情にほだされるって、よくあるパターンで、ありふれすぎて既視感しかなくて、こんなの脚本に書いたら笑われちゃいますけど、今ここはマキマキさんに覆いかぶさって口塞ぐのが真っ当な展開だなって、その気になっちゃってる俺がいるんすよ。それをやめとけって囁くもう一人の俺がいるんすよ。それやったらもうここにいられないって。で、マキマキさんはどんなつもりでこういう話、してんだ? 誘ってんのか? 焚きつけてんのか? いや、俺に何を期待してんだ? こっちは頭ん中ぐるぐるしてんのにフツーじゃないとか勝手に決めつけて、俺、安全地帯に入れられてますけど、フツーに今すごく変な気持ちになっちゃってるんすよ。けど、これって変なのか、俺がマキマキさんを抱きたいってこの瞬間思うことは、イケナイことなのかって今俺の脳内で起こっているボクシングをいつか脚本に書いたらどうなんだ、ウケるのか、すべるのかって創作論に置き換えて、起爆装置にブレーキかけてるんすよ」
麻希の自分語りを上回る文字数と熱量が返ってきた。こういう一人芝居を演じたことがあるのかと錯覚させるような澱みのなさだった。滑舌がいいなと内容とは関係のないところに麻希は感心した。芝居がかっているけれど嘘っぽさはなく、出口を求める本音が瞬時にセリフに翻訳されて声に乗せられているようだった。いつも以上に響く重低音で放たれるモリゾウの言葉の激流を浴びながら、自分のために彼がこれほど感情を爆発させてくれたことへのうれしさと、それを引き出すために彼を挑発したことへの申し訳なさが麻希の中でせめぎ合う。モリゾウの怒りが告白のように聞こえ、体が熱くなる。

モリゾウは一気にしゃべって、不意に黙った。
「起爆モード、おさまった?」
「解除しました」
「解除しなくても、良かったのに」
「マキマキさん、怒りますよ」
すでに怒っているのに、怒りますよとモリゾウは言い、「何なんすか」と立ち上がり、壁のハンガーにかけたジャケットを取り、靴を引っかけると外に出た。
麻希は呆然と、自分一人のために演じられたモリゾウ劇場を振り返った。
「どんなつもりでこういう話、してんだ?」とモリゾウは言った。それは、まさに麻希がモリゾウに聞きたいことだった。
自虐な自分語りを繰り広げる麻希の口をキスで塞ごうかと思ったモリゾウは、「それやったらもうここにいられない」と自制を働かせた。
モリゾウはここにいたいのだ。ここから追い出されるようなことはしたくないのだ。
その言葉を聞けただけで麻希は満足だった。
自分のことをどう思っているのか。どういうつもりで居候を続けているのか。直接ぶつければ済む話を、ギャンブルの自己開示なんて回りくどいことをしないと聞き出せない性格が我ながら面倒くさい。愛想を尽かされて当然だし、そうなるように麻希のほうから仕向けた。
壁に背中を預け、膝を抱え、バカだねと声に出して言い、わかってるよと答えた。
39歳って、もっと大人だと思っていたのに。
何かしていないと落ち着かなくて、四つ葉のクローバーの刺繍を再開した。古墳王子のバッグを作った余り布は使い切り、ストックしてあったギンガムチェックの布で新しいポーチを作ることにした。裁断を終えた布を縫い合わせる前に刺繍を入れる。幸運のクローバーなんて気分じゃないのに。こんな気持ちで刺繍された四つ葉に、ご利益なんてなさそうだ。かえって悪い念が宿ってしまうかもしれない。
売り物じゃなくて、今は自分のために針を動かすのだと心の中で言い訳する。手元に集中していると、とっちらかった頭の中が整理されていく。モリゾウには麻希にお金を渡せない事情があって、時期が来たら話そうと思っているのかもしれない。
祈る気持ちで針を動かしていると、ドアが開いた。鍵を持たずに出て行ったモリゾウが、そのドアを抜けて帰って来た。
「おかえり」
「ただいまっす」
モリゾウは靴を履いたまま、玄関に突っ立っている。
「どうしたの?」
「入っていいんすか?」
「もちろん」
モリゾウは遠慮がちに靴を脱いで、部屋に上がると、
「どこにも売ってなくて」
そう言って、ジャケットの左右のポケットからひとつずつ袋入りのコンビニスイーツらしきものを出すと、ちゃぶ台に置いた。
シュークリームだった。
シュークリームがご褒美の単位だったという話をモリゾウにしたのは、随分前だ。
「覚えてたんだ?」
一人になったときは自己嫌悪が優って泣く気にもなれなかったが、不意打ちの涙がぶわっとせり上がった。
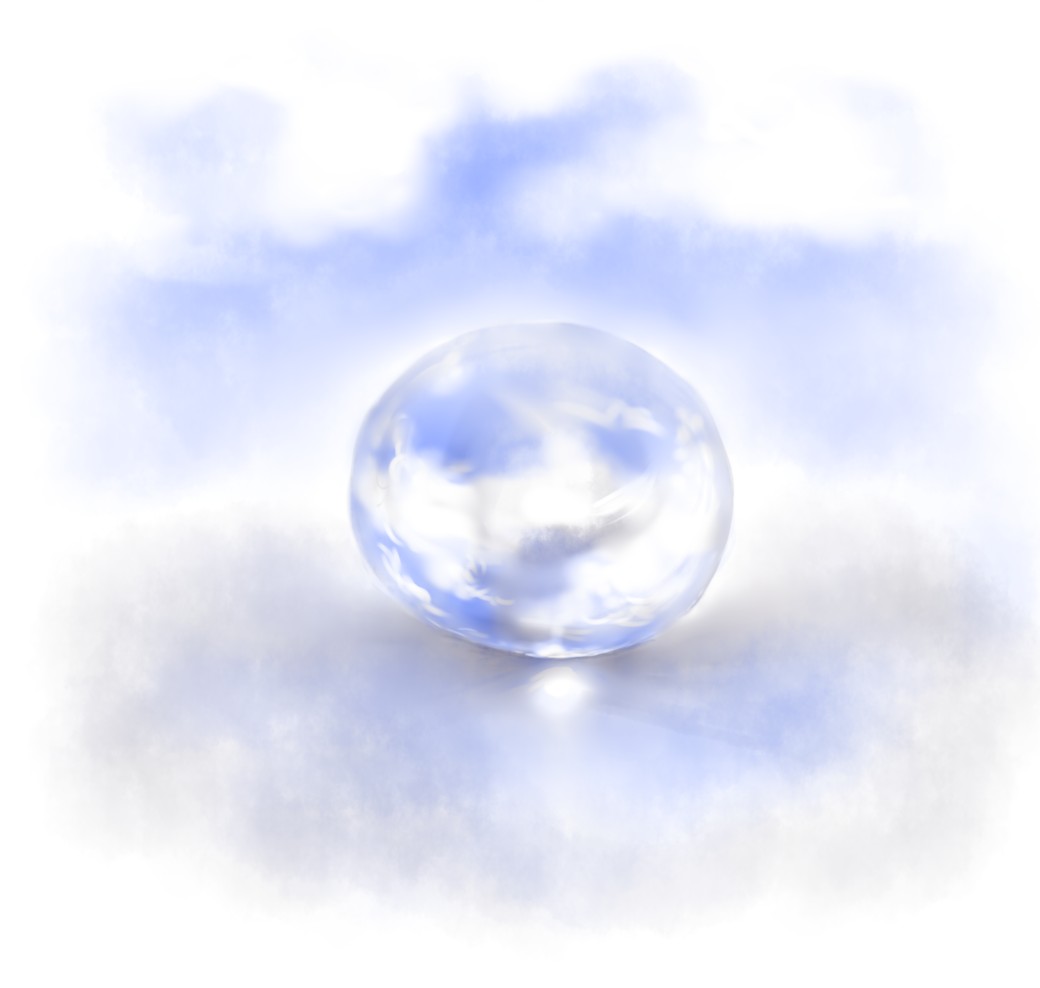
「マキマキさん?」
「だって……もう帰って来ないかもって思ってたら、シュークリームと帰って来たから……」
モリゾウの顔が近づいた。
キスされると思ったら、ぺろっと涙をなめられた。
「しょっぱい」とモリゾウは笑った。
「しょっぱい?」と麻希が聞き返す。
「涙は世界で一番小さな海だから」
モリゾウは芝居のセリフみたいなことを言った。
頬を伝い落ちてきた涙を麻希が人差し指で絡め取ろうとすると、その手をモリゾウが取った。
モリゾウの顔がもう一度近づき、ひんやりした唇が麻希の頬に押し当てられた。
麻希の涙を含んで濡れた唇が麻希の唇に重なった。
「しょっぱいっすか?」
「しょっぱいっす」
モリゾウの口調を真似して、ふたりで笑い合うと、また涙が押し寄せる。その涙をモリゾウが受け止め、麻希の口へ運ぶ。モリゾウの唇がだんだん温かくなる。
キスとは温もりを伝え合うものだったのかと今はじめて知ったような、思い出したような、ふわふわした心地を味わいながら、麻希の頭の中にシュークリームが増えていく。いくつあるのか、数えきれない。
次の物語、 連載小説『漂うわたし』第55回 佐藤千佳子(19)「母と娘のロウバイの季節」へ。
イラスト:ジョンジー敦子
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!






















































































































































































































































































































































































































































