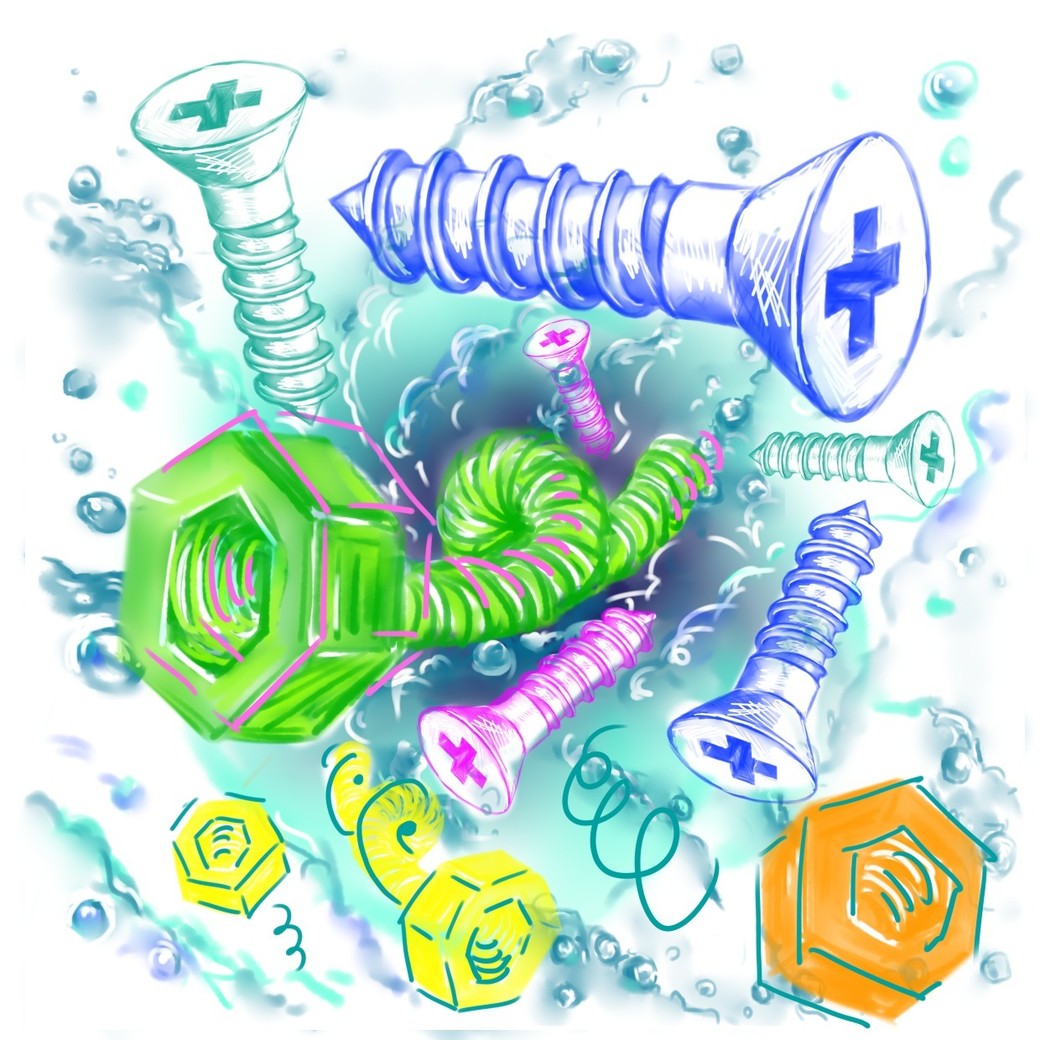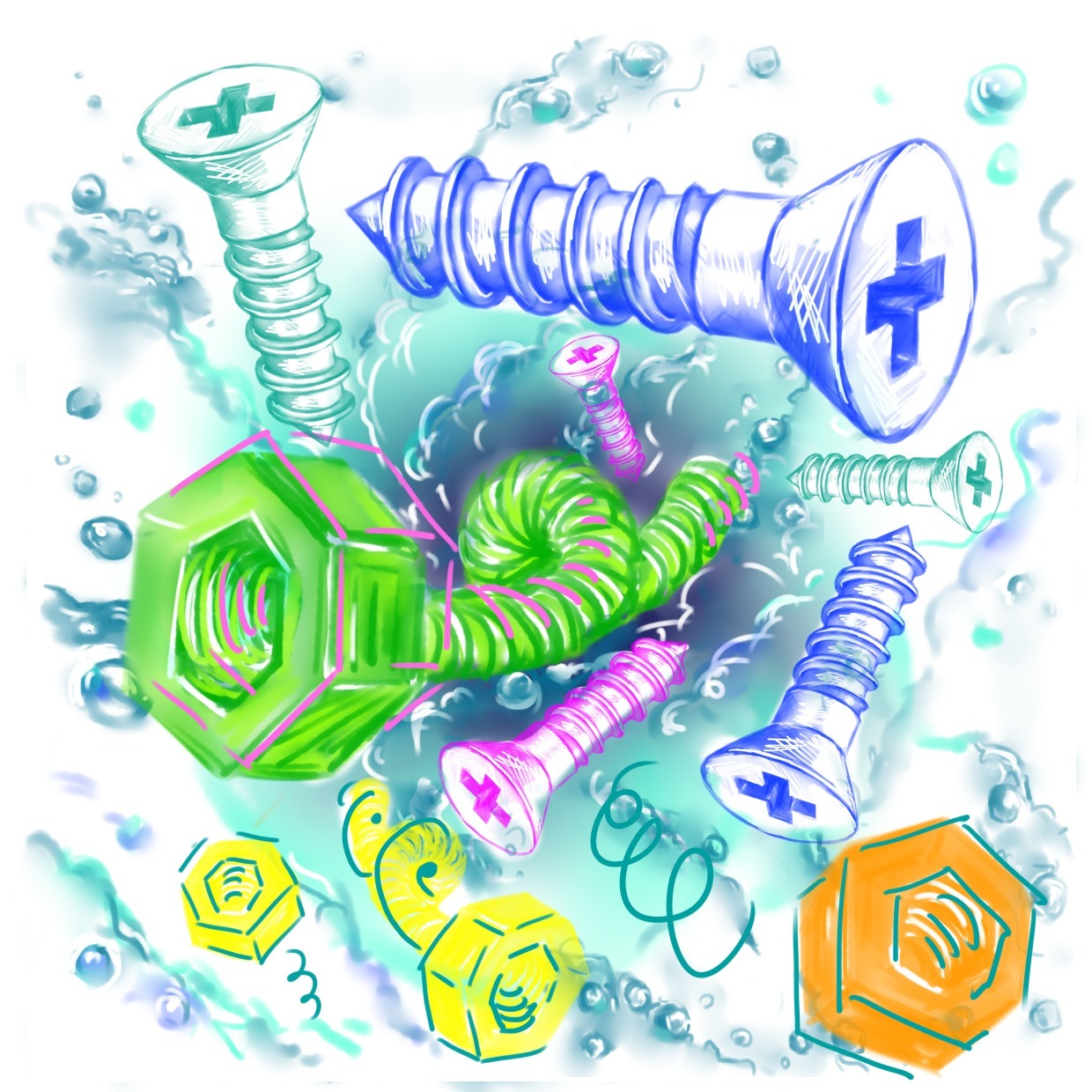第138回 多賀麻希(46)いつか誰かのねじを巻く
色とりどりの野菜と果物と花びらを食べ終え、宴の名残のように、皿にはシューサレに立てていた旗だけが残った。
「マスター、この旗、持って帰っていい?」
「持って帰ってどないするん?」
「記念に」
「百均で売ってるやつやで」
マスターはそう言うが、2本の旗の大きさは微妙に違い、「M」と手書きされている。
モリゾウのMと麻希のM。
モリゾウは武田唯人だから「T」なんだけどと麻希は思い、マスターはモリゾウの本名を知らないかもと想像する。麻希の名字も伝えていない。ハローワークへ行くつもりだったあの日、バッグには履歴書を入れていたけれど、提出は求められなかった。
多賀麻希から武田麻希になるのか。
だったら名字のイニシャルはTのままだ。それともモリゾウが多賀唯人になるのだろうか。どちらにせよ、ふたりともイニシャルは変わらない。
「やっぱりTとMにしてもらったら良かったかな」
考えていたことが口から出て、隣のモリゾウとカウンターの中のマスターに聞こえた。
「ああ、これって俺らの名前のイニシャルなの?」とモリゾウが旗に目をやる。
「じゃないの?」
「この店の名前。やったらどうする?」とマスターが言った。
「この店、Mって名前だったの? マスターのM?」
「やったらどうする、言うただけ」
はぐらかされっぱなしだ。意味を求めることに意味はなく、根拠とか正義とか、しがみつくものなんてなくていいんだと言われている気がする。そう言えばマスターの名前も聞いていない。
「マスターって、モリゾウの舞台観てたんでしたっけ」
「観たり観んかったりやな。最後に観たんは、ねじのやつやったっけ」
ここで会ったとき、モリゾウからチラシを受け取った『寝ぼけ眼のねじを巻け』のことだ。すでに公演は終わっていた。それ以来、モリゾウは演劇に関わっていない。
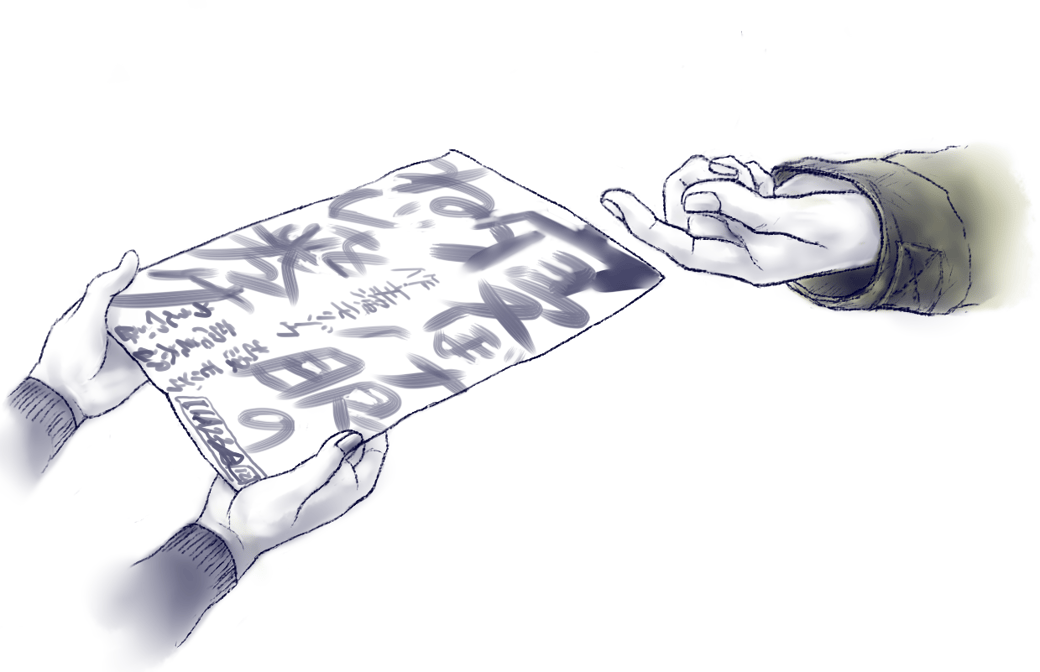
どんな話なのかとモリゾウに聞いたことがある。互いにねじを巻き合うが、実際にねじが出てくるわけではないという答えだった。
「今巻いたねじが、いつかどこかで何かを動かす、いう話やったけど、ようわからんかった」
そう言ってマスターが出した2皿目も野菜とシューだった。マッシュポテトの上にローストポークをのせ、シュー皮が斜めにかぶった帽子のように添えられていた。デザートまで野菜とシューで行くのだろうかと期待が高まる。
皿にぐるりと丸を描いた鮮やかな緑のソースは手作りのジェノベーゼで、バジルもマスターが畑で育てたという。
緑の円から麻希は古墳を連想する。
この店で初めて会った日、モリゾウは麻希のバッグを見て、「古墳みたい」と言った。それが縁で、モリゾウの演劇仲間の高低差太郎、自称「古墳王子」のバッグを作ることになった。彼に高低差太郎という役者名をつけたモリゾウのほうが、古墳タレントとして活動している彼よりも古墳に詳しく、古参だった。
古墳王子にバッグを納品したのも、この店だった。
イメージ通りだと歓声を上げ、バッグとコーヒーカップを並べて写真を撮ると、爽やかな王子スマイルを残して彼は立ち去った。コーヒーには口をつけず、お金の話もせず。
事前に値段をいくらにしようかモリゾウに相談し、「2万」と言って反応を見てみることにしたのだが、バッグを注文したときに渡したシュークリーム2個で支払いは済んでいるかのような態度だった。
古墳王子はコーヒー代も置いて行かなかったが、以前、撮影で店を借りた時も当然のようにお金を出さなかったのだと麻希より彼とつき合いの古いマスターは言った。モリゾウが古墳王子の家に長い間住ませてもらっていたことを、そのときに聞いた。

ローストポークとシューの組み合わせは、軽やかなパイ包みのようだった。マッシュポテトとジェノベーゼをシュー皮でぬぐい、2皿目もきれいに平らげた。
3皿目はベーコンとブロッコリーのペペロンチーノだった。たっぷりのベビーリーフがパスタを覆っているが、シューの姿はない。と思ったら、フライドオニオンに見えたトッピングが、カリカリに揚げたシュー皮だった。
「ベーコンも自家製な」とマスターが言うと、
「どこから?」とモリゾウが聞いた。
「さすがに豚育てるとこからは無理やわ」
マスターが燻したベーコンの香りと脂を吸ったパスタは、ねじのような形をしている。モリゾウを見ると、同じことを思ったらしいモリゾウと目が合った。
井戸を掘ったとマスターが言った。畑は千葉の山奥にあり、片道2時間かかるので、定休日の日曜の週1回しか行けず、自動給水機で井戸から水を汲み上げ、畑に撒いていると言う。
「井戸って、掘ったら水が出るものなの?」
「何メートルぐらい掘ったんすか?」
麻希とモリゾウがかわるがわる聞いた。
「この辺掘ったら出る、いう当たりをつけて、掘るんや。15メートル掘ったら海の底で、それより深いとこまで、22メートルやったかな」
「そんなに?」と麻希。
「自力で?」とモリゾウ。
「さすがに業者に頼んだわ」とマスターは言った。海底より深く掘ったら、海水が混じるのではと麻希は思ったが、「昔、海底があったとこで、今は塩が抜けてる」らしい。
「井戸掘ったら、貝殻がぎょうさん出てきてな。縄文の昔は貝塚があったんかなあ。あんな山奥に」
「ずいぶん内陸まで海が来てたんすね」
「当たり前やけど、下に行くほど、どんどん時代が古なっていって。まさか令和の時代にドリルで掘り返されるて思てなかったやろな」
「地層は時間が折り重なったものですからね」
「それや。時間のミルフィーユや」
「マスター、詩人じゃないですか」
「水かてそうや。地下の深いとこを流れてたのが汲み上げられて、畑にまかれて、野菜やら果物やら育てて」
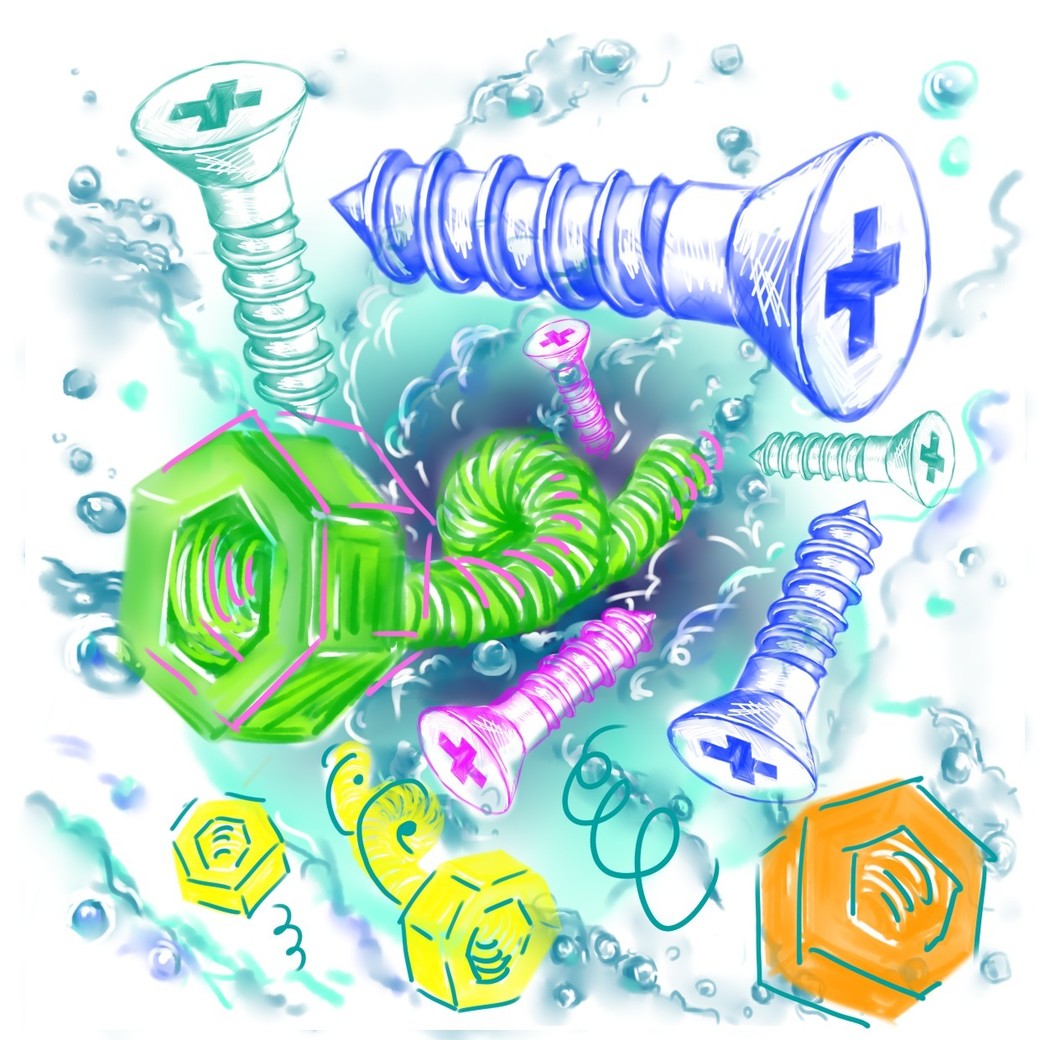
パスタの皿の野菜に目をやったマスターが、思いついたような顔になる。
「今巻いたねじが、いつかどこかで何かを動かすて、そういうこと?」
「マスターから今、井戸の話を聞けたのが、いつかのねじの巻き返しですよ」
「はあー。やっとわかったような、わからんような。これ頭のねじ締めてるん、緩めてるん、どっち?」
「頭に井戸を掘ってるんすよ」
「はあー。頭に井戸なー。深いなー。井戸だけに」
モリゾウとマスターの会話を聞きながら、麻希は映像製作プロダクションで働いていた20代の頃を思い出す。
映画の撮影現場で知り合ったエキストラの子が出ている舞台のノルマチケットを買わされ、観に行くと、人数が埋まらなかったかドタキャンが出たかで打ち上げに誘われ、ついて行った居酒屋で知らない人たちに囲まれ、今観た舞台や近頃の演劇界について延々と繰り出される話を聞いた。
皆には麻希の姿が見えていないのではと思うほど、話題は麻希を通り過ぎ、通り抜けた。チューハイのジョッキが空いた人に「次何にします?」と聞くときだけ、透明人間に輪郭がついた。
今もモリゾウとマスターの会話には割って入れないけれど、居心地の悪さを感じないのは、透明人間にされていない安心感があるからだろう。
あのテーブルだったっけと麻希はカウンター席から振り返る。
古墳王子からバッグの代金を受け取れなかったあの日、重い足取りで帰宅すると、モリゾウはオンラインショップを準備して待っていた。麻希が手がける布雑貨のことを「作品」、麻希のことを「作家」と呼び、詩のような紹介文をつけ、世に送り出してくれた。
あの古墳バッグがなければ、makimakimorizoは生まれず、39歳で青春が始まることもなく、ひまわりバッグも生まれなかった。ケイティと再会し、服飾専門学校時代の古傷をえぐられることもなかったが、ひまわりバッグがなければ、ケイティの代わりに描いた衣装のデザイン画が採用された映画『幸せのしっぽ』を高校生のときに何十回も観たという花嫁に見つけられ、ウェディングドレスを託されることもなかった。
クローバーで上書きしたそのドレスをモリゾウと見届けに行かなければ、帰り道のプロポーズもなかったかもしれない。そしたら今夜ここでマスターの手料理に祝福されることもなく、ねじの形をしたパスタを食べながら井戸の話を聞くこともなかった。
記憶の井戸が掘り起こされ、頭の中で水飛沫が上がる。わたしも、ねじを巻かれている。そして、ねじを巻いている。
知らず知らず、いつか、どこかの、誰かに向かって。
次回12月2日に佐藤千佳子(47)を公開予定です。
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!