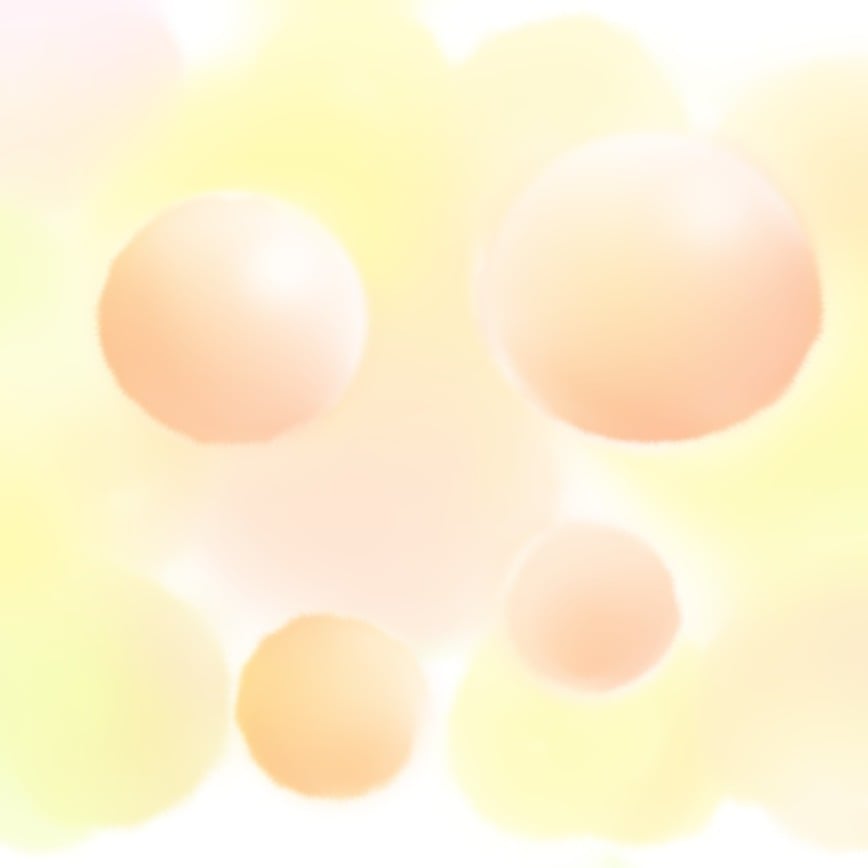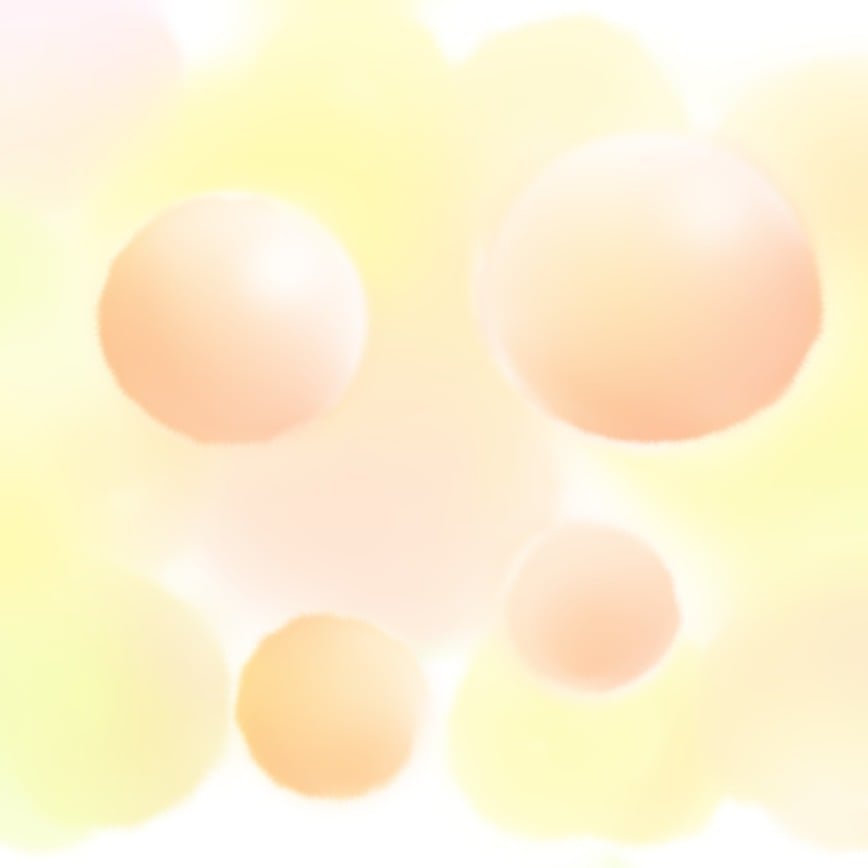第171回 伊澤直美(57)生まれた日の記憶
「なんのうた?」
直美を見上げる優亜に聞かれて、自分が歌っていたことに気づいた。
保育園帰りにスーパーで買い物し、キッチンでエコバッグの中身を空けながら鼻歌を歌っていた。
ヘンデルの『私を泣かせてください』。
歌詞は知らない。あるのかどうかも知らない。優亜を産んだとき、産婦人科の部屋で流れていた曲だ。
好きな曲を聴きながら産んでいいよと先生に言われ、スマホに取り込んで持って行った。『私を泣かせてください』はオーボエ奏者がクラシックの定番曲を演奏するアルバムに入っていた。出産間近の重いお腹を抱えてイザオと近所のスペインバルへ食べに行ったとき、客として来ていた奏者が演奏を始め、居合わせた客たちが投げ銭代わりにCDを買い求めたのだった。
CDのデータを取り込むときにセロファンの外装の封を切ったが、まだ聴いてはいなかった。プレイリストを一巡し、2巡目に入っていたが、1巡目のときは記憶になかった。音楽はずっと流れていたのだが、耳に入ってはいなかった。体を内側から殴りつけていた陣痛が去り、優亜の産声を聞き、ほっとしたとき初めて、オーボエの音色が聞こえてきた。パニックに近い極限状況から解放され、音楽の入る場所がようやくできた。
繊細で美しい旋律がしみた。音のひと粒ひと粒に労いと祝福がこもっていた。演奏はオーボエだったが、直美の頭の中でパイプオルガンの音色に置き換わった。大聖堂の高い天井へ伸びるパイプ。ステンドグラスを通り抜けて大理石の床に降り注ぐ虹色の光。世界史や美術の教科書に出てくる中世の宗教画のような荘厳な情景が瞼の裏に浮かんだ。

全身が疲れ切り、消耗し、あちこちが痛いのに、酔いしれるような恍惚感があった。耐久レースを終えてゴールテープを切った選手も、気が遠くなる寸前の朦朧とした意識の中で幻覚のような風景を見るのかもしれない。
なんと厳かで誕生の場面にふさわしい曲なのだろう。
鼻の奥がツンとした。イザオを見ると、顔をくしゃくしゃにして泣いていた。先に泣かれてしまい、直美は泣きそびれた。
その後は忙しかった。臍の緒をハサミで切り、ゴムチューブみたいな弾力に驚き、出産が終わったと思ったのに胎盤を産む後産が残っていて、ゴールテープを切った後にもう一周と言われたような気持ちなり、出てきた胎盤を食べてみるかと聞かれたが食欲が湧かず、辞退した。
『私を泣かせてください』はあちこちで使われている。テレビ番組のBGMだったり、街角のスピーカーから流れてきたり。この曲に再会すると、優亜を産んだ日のことを思い出す。
今日はスーパーから家に帰る途中、不意打ちで聞こえてきた。信号待ちで聞こえてきた着信音が『私を泣かせてください』の出だしのメロディだったのだ。
信号が変わり、すぐに気持ちが切り替わったが、メロディの端っこが引っかかっていて、キッチンで鼻歌になってこぼれ出たのだった。
「なんのうた?」と聞かれた直美が、
「ゆあが生まれた日の歌だよ」と答えると、
「ゆあちゃん、うまれたねっ」と優亜が言った。
「うん。生まれたね。生まれてきたね」
「きたねーっ」

夏の終わりに訪ねたパンケーキ屋で覚えた、文を「たね」で終わらせる遊び。秋になっても飽きずに親子で言い合っている。優亜の「たね」の後には小さい「つ」が入って、スタッカートみたいに弾む。
「たね」「たねっ」
「たね」「たねっ」
直美がやめない限り優亜は「たねっ」を返してくる。放り投げられたボールを何度でもしっぽを振って取りに行く子犬のように、単純な繰り返しをいつまでも面白がる。幼い頃の自分にもそんな真っ直ぐな無邪気さがあったのだろうかと直美は想像し、あの母親はそんな遊びにつき合ったりしなかっただろうと現実的な答えを見出す。
それとも忘れてしまっただけだろうか。
優亜も大きくなったら忘れてしまうのだろうか。
隙間風のように入り込んだ淋しさを吹き払うように、さっき鼻歌で歌った『私を泣かせてください』の出だしのメロディに歌詞をつけて即興で歌ってみる。
「♪ゆ~あ~ちゃんが~う~ま~れた~ひ~ ゆ~あ~ちゃ〜んが~で~てき〜た~よ~」
「ゆあちゃんがうまれたひのうた、あったねっ」と優亜が目を丸くする。
歌詞がついていると言いたいのだろう。行き当たりばったりでつけた何のひねりもない歌詞なのに、自分のことが歌になっているのがよっぽどうれしいらしい。
「そうだね。歌あったね」
「あったねっ」
今できたのだ。母親は歌詞も作るし歌も歌う。メロディがないときは作曲もする。
「ゆあちゃんがうまれたひのうた、うたって」
優亜にせがまれて、もう一度同じフレーズを歌ってみる。
「♪ゆ~あ~ちゃんが~う~ま~れた~ひ~ ゆ~あ~ちゃ〜んが~で~てき〜た~よ~」
短いからすぐに終わってしまう。そしてまた「ゆあちゃんがうまれたひのうた、うたって」とせがまれる。
「じゃあ、次は、ゆあが歌ってみて」と言うと、「いいよ」とあっさり返事して、歌い出した。
「ゆ~あ~ちゃんが~う~ま~れた~ひ~ ゆあちゃんが~でてきたよ~ トントンも〜でてきたよ〜」
音程もリズムもだいぶ違う。元のメロディがわからない。そして、歌詞が増えている。
トントンも出てきたよ。
「トントン」とは、優亜の言葉で「おっぱい」のこと。おっぱいが欲しいとき、優亜がドアをノックするようにトントンと叩いてきたので、おっぱいを欲しがることを「トントンする」と直美が先に言い出した。やがて優亜の言葉が追いついて「トントン」と口にするようになり、「トントン」がおっぱいの愛称になった。
ぬいぐるみに話しかけるように優亜は「トントン」と呼びかけ、今もそう呼ぶ。ずっと一緒にいるお友だちのような感じ。
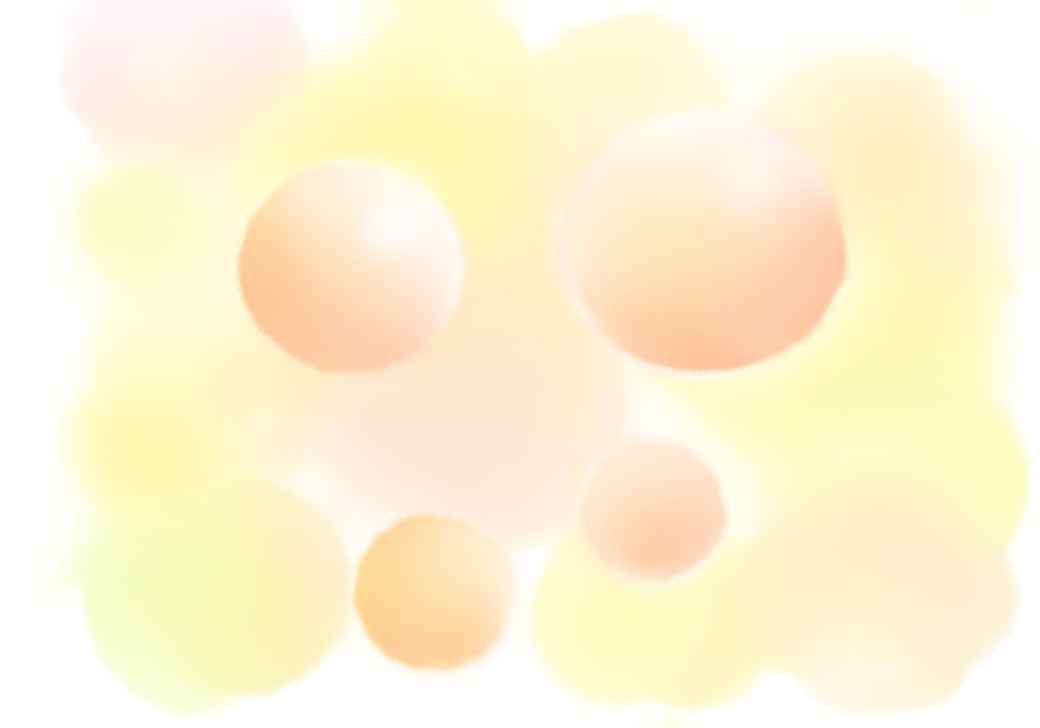
「トントンは最初からママのとこにいたよ」と直美が言うと、
「ゆあちゃんといっしょにでてきたのっ」と優亜は言い張る。
「え、そうなの? ゆあと一緒に出てきたの?」
直美は笑って首を傾げつつ、「おっぱいという栄養飲料貯蔵庫になったのは優亜が生まれてからだから、優亜と一緒に現れたと言えるのかも」と思ったりもする。
2歳児との何気ない会話に哲学を感じる。
「ゆ~あ~ちゃんが~う~ま~れた~ひ~ ゆあちゃんが~でてきたよ~ トン〜トンも〜でてきたよ〜 ちいとんも〜でてきたよ〜」
歌詞がさらに長くなっている。
ちいとんはトントンの子ども。優亜の体についている小さなトントンのこと。ちいとんも優亜にとっては体の一部というより友だちのような分身のような存在で、モノではなく人格を持っている。少し前、残業で直美の帰りが遅くなり、イザオと留守番して待っていた優亜がぐずって泣いた日があった。
玄関のドアを開けると、優亜がしがみついてきた。
「ママが帰るまで寝ないって頑張ってた」とイザオがあくび混じりに言った。
「遅くなってごめんね」と直美が謝ると、
「ゆあちゃんないたよ」と優亜は言ってから、
「ちいとんもないたよ。ママがいいようって」と続けた。
こんな風に淋しさを訴えられるようになったのかと驚いた。悲しみや辛さを「胸が痛い」と表現するのは、小さな胸で受け止めるこの感覚から来ているのかもしれない。
優亜が生まれた日、直美という母親も生まれた。トントンとちいとんと一緒に。
あれから2歳9か月。あと3か月足らずで優亜は3歳になる。

次回11月2日に伊澤直美(58)を公開予定です。
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!