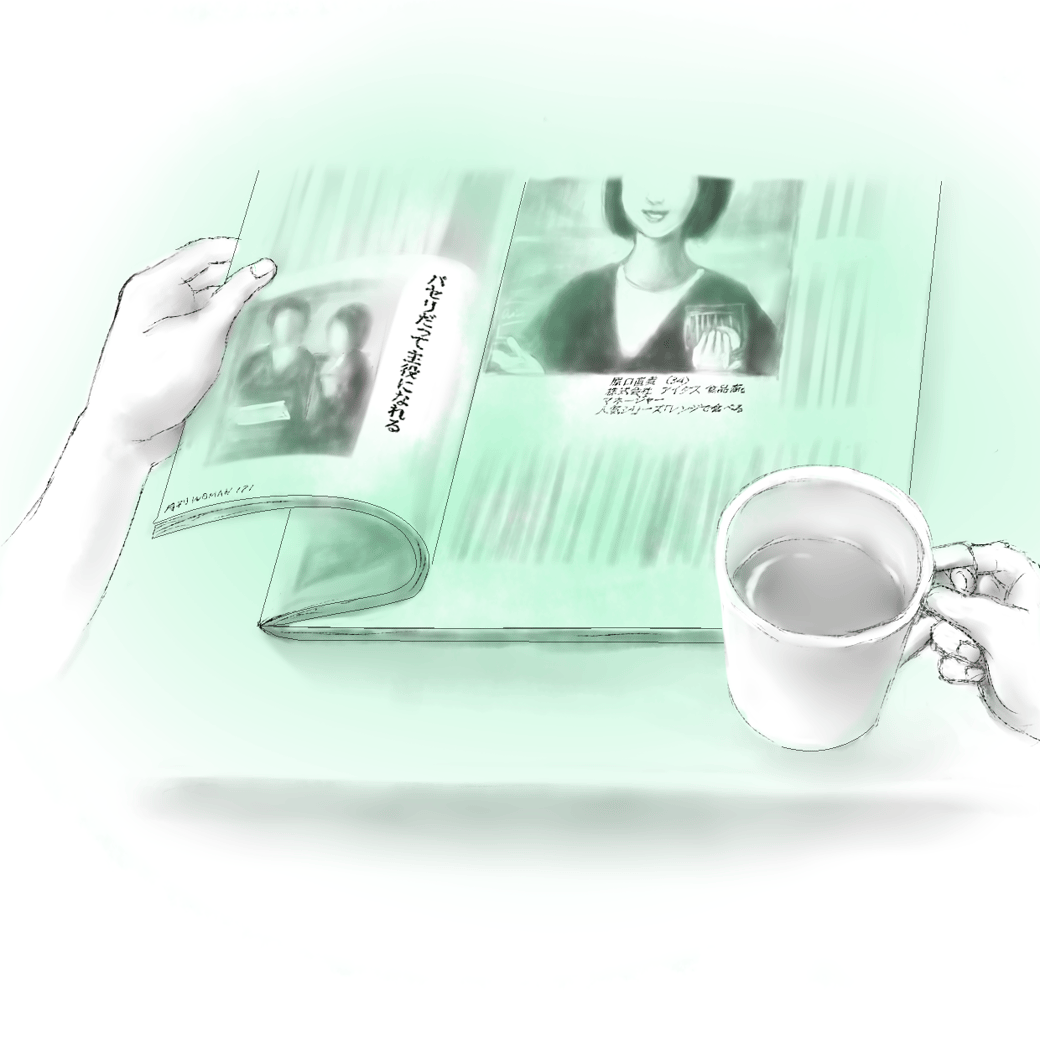第31回 佐藤千佳子(11) わたしが主人公になった日
パート帰りに買い物をしていたら、野菜売り場で「お久しぶりです」と声をかけられ、顔を上げると、ハーブのマイさんの笑顔があった。冬に会ったとき、真っ赤なコートが眩しかったマイさんは、夏を連れて来たような爽やかなグリーンのワンピースを着ていた。
「ミントみたいな色ですね」と千佳子が言うと、
「そうなんです! ハーブカラーだって思って買っちゃいました!」とマイさんは声を弾ませ、続けた。
「前にお会いしたときと、雰囲気変わりましたね。何か始められました? エステとかサプリとか?」
「ちょっとメイクするようになったんですけど」
「前はメイクしてませんでしたっけ。すっごくいいですよ。メイク教えてもらわなきゃ」
「メイク、下手くそですよぉ」と千佳子は謙遜し、「こちらこそ、マイさんのきれいの秘訣を聞きたいです」と言うと、
「ハーブの力です!」
マイさんは謙遜せず、言い切った。
「やっぱりハーブですか。わたし、もう40過ぎているんです」と千佳子が言うと、
「余裕です」
マイさんは力強く言った。
誰が、それとも何が、どう余裕なのだろう。主語がわからない。けれど、「余裕です」という潔い言い方は都会の人っぽいなと千佳子は思う。
「余裕っていいですね」
「余裕、大事です。私はハーブティー飲んで、呼び戻すんです」
「取り戻すんじゃなくて、呼び戻すんですね?」
「そうです。おーい、帰っといでって」
両手をメガホンの形にして、マイさんは言った。
「じゃあハーブ買って帰ります。今日は値引きシールのついてないやつ」
千佳子が生ハーブブーケをカゴに入れると、マイさんは「ありがとうございます。私はこっち」とパセリを2束、買い物カゴに入れた。パセリもハーブだと夫に教えてもらったのを千佳子は思い出す。

「パセリ、よく料理に使うんですか」
「今日は花束みたいに活けてみようと思って」
「それ、わたしもやりました。生ハーブブーケをヒントにして」
「そうなんですね。実は、同じことを考えた方がいらして、食品メーカーさんの消費者インタビューで話してくれたんです」
数か月前に受けたオンラインインタビューの記憶が蘇る。偶然だろうか。
「もしかして、アイタス食品ですか?」
「そうです。月刊ウーマン、読まれました?」
「月刊ウーマン?」
その名前を最近聞いた。パートの先輩の野間さんが広告代理店で働いていた頃にインタビュー記事が載ったというビジネス誌だ。そのことをマイさんに話すと、
「そうなんですね。私も映画配給会社で働いていたときに載りました」
全国発売の月刊誌に取材されたことのある人に立て続けに会うとは。こんなとき、都会に出て来たんだなと千佳子は実感する。
「月刊ウーマンに、パセリの花束の記事が出ていたんですか?」
「あれ? 読まれてないんですか?」
「はい」
「でも、さっき、アイタス食品って」
「そのインタビューに答えたの、わたしなんです」
マイさんが大きな目を見開いて、千佳子を見た。
「マイさんの影響なんです」と千佳子が続けると、マイさんの目がさらに大きくなった。
「マイさんの赤いコートを見て、赤い口紅を買って、つけてみたら、新しい扉が開いたような気がして。そんなときに、アイタス食品のインタビューに答えられる人誰かいないって従業員に呼びかけがあって、やりたいですって手を挙げたんです」
「じゃあ、パセリの花束の記事が世に出たのは、私も一枚噛んでるってことですね?」
「はい」
「千佳子さんがきれいになったのも?」
「なってたらうれしいです」

帰り道にある書店に立ち寄り、月刊ウーマンを見つけた。ページをめくり、「パセリだって主役になれる」という見出しで手が止まった。レジで会計を済ませ、店の前に停めてある自転車に戻ろうとして、書店の上にあるファミレスに向かった。家に帰り着くまで待てなかった。
《パセリを花束みたいに活けている話をすごく楽しそうにされた方がいたんです。花束は主役、パセリは脇役ってイメージがありますが、パセリが主役になるんだって新鮮な驚きがありました。私たちが手がけるお惣菜シリーズは、副菜と呼ばれるものが多いんですが、もしかしたら、盛りつけ方や使い方で主役になることもあるのかもしれません。毎日を楽しく彩るのは、なんでもないことに光を当てる想像力なんだと教えられました》
自分のことが書かれているくだりを何度も読んだ。それから、原口直美という女性についての見開き記事を端から端まで読んだ。オンラインで見たとき以上にプロフィール写真はキリッとしていた。キャリアウーマンの自信が顔つきに現れている。同期入社の夫と結婚してもうすぐ5年。子どもはまだいないが、手がけた商品が子どものような存在だと語っている。
スーパーで働くようになって、商品が店に並ぶというのはポジションの取り合いなのだと千佳子は学んだ。売り場面積も棚の数も決まっている。売れる商品は幅を広げ、売れない商品は追いやられる。それが生産量にはね返る。売れる商品は増産されてますます売れ、売れない商品は製造中止に追い込まれる。
買い物客の立場で見ていたときは「新しい商品が出たな」「あの商品が消えたな」ぐらいにしか思わなかった。だが、商品を並べる側になり、それぞれの商品に「親」がいることを知った。親の思いを背負って生まれた「子」たちを、できればみんな並べてあげたい、場所を作ってあげたいと情が湧くようになった。
原口直美によると、新商品を企画し、世に出すまでには妊娠期間以上に時間がかかることもあるらしい。子どもは産んでから社会に出すまでに家庭で育てるが、商品の場合は、生まれた途端、世に送り出すので、いきなり晴れ着を着せて、鳴り物入りでお披露目することになる。その商品がヒットしたら、自分の子が愛されているようでうれしいし、売れ行きが悪くて棚を確保できなくなったら、「こんなに可愛い子なのに誰からも必要とされていないのか」と無念を味わう。
「できる限りのことをして送り出してあげたいんです」
原口直美の言葉は、親が子を想う気持ちそのものだ。
「それでも子どもと商品は違うけどね」
思ったことが声になって出たが、まわりのテーブルには届かなかったようで、誰も振り向かなかった。そろそろ娘が部活から帰って来る。夫が仕事から帰って来る。夕飯の支度をしなくては。

ファミレスにいたのは30分ほどだった。店を出るとき、以前、娘が泣きわめき、「黙らせろ」と男性客に怒鳴り込まれた店の系列店だと思い出した。当時は店のロゴを見るだけで動悸が激しくなったが、今ではすっかり反応が鈍くなった。
あのときの男性にも事情があったのかもしれない。
ふとそんなことを思った。たまたま虫の居所が悪かったのかもしれない。仕事で追い詰められていたのかもしれない。子どもの甲高い声がどうしても耐えられないという人もいる。自分から見えているのは物語の一部分であって、全部ではない。そんな風に思えるようになるまでに、十年余りかかった。
「余裕です」
ハーブのマイさんの口調を真似して、呟いてみた。娘に泣かれて、オジサンに怒鳴り込まれて、隅っこの席でオロオロしていたあの日のパセリに言ってやりたい。十年後、その系列店で、あなたは、自分が主役になった記事を読んで、ちょっぴり誇らしい気持ちで店を出るよ。
ファミレスのハーブティーで、余裕だけじゃなくて、いろんなものを取り戻せた。アイスクリームも頼めば良かったなと思いながら、千佳子は軽やかな足取りで階段を降りた。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第32回 佐藤千佳子(12)「バズらせるってどうするの?」へ。
イラスト:ジョンジー敦子
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!