
第40回 伊澤直美(14) お母さんの人生、返して
イザオの母を笑い飛ばしてカラッとしていた空気が途端に湿って重くなった。
「お母さんには……まだいいかな」
直美が言うと、「そうだね」とイザオは短く言った。イザオも母には懲りている。できるだけ距離を置いていたいのだ。
イザオの母は自分の価値観を押しつけるが、幸せの基準が明快で、わかりやすい。可愛い息子の幸せが第一で、息子の嫁である直美には、その実現のために夫を支え、子を産んで欲しいと願っている。それが直美の幸せでもあると信じている。だから、言葉に刺激はあるが、言っていることにはブレがない。
だけど、うちの母は……。
「直美は幸せになんかなれない」
5年前、イザオとの結婚を報告したとき、母はそう言った。
8年もつき合っていたのに、親に紹介できないような相手と結婚して、うまく行くわけがないと言い切った。
だって、会わせたら、お母さん邪魔するじゃない?
そう言い返したいのをこらえた。何か言えば、それ以上にえぐられることを思い知っていたから。
中学1年の夏休み、初めて男の子と二人で出かけることになった。けれど、約束の場所に、彼は現れなかった。直美が行けなくなったと母が勝手に連絡していたのだ。お互いを誤解したまま、何も始まらないうちに関係はしぼんだ。
行かせたくないなら直接言えばいいのに。
それ以上に不可解だったのは、母が普通に直美を送り出し、待ちぼうけを食わされた直美が帰宅したときも、何も言わなかったことだ。
相手が来ないことがわかっているのに、どうして?
その頃、母と父はギクシャクしていた。きっかけは、直美の中学受験だった。受験させたい母と、させたくない父。よくあるすれ違いだ。母が押し切って受験はしたものの、直美は母の期待に応えられず、地元の公立中学校に進んだ。
「お父さんを勝たせたね」と母は言った。直美はただ試験に落ちただけだったのだが。
母の言葉は、雨に濡れて肌に貼りついたシャツのように、じっとりとまとわりつく。その気持ち悪さを直美はしばらく引きずり、やがて忘れた。母も、受験のことは思い出したくないのか、話題に出さなかった。
卒業式で撮った写真と入学式で撮った写真を並べてみたことに、大した意味はなかった。それを母に見せたのも、たまたまだった。校門の前の同じ場所で母と直美が並んでいる写真。3年の間に直美は背が伸び、大きめに作った制服がちょうど良いサイズになっていた。母も3年前と同じスーツを着ていた。
入学式のときも卒業式のときも直美は笑顔で、母の顔は笑っていなかった。父は、いつの間にか家に帰っていた。
「本当だったら、この学校に行ってなかったのにね」と母はため息まじりに言った。まだそんなこと言っているのと直美は驚き、「わたしは楽しかったよ」と明るく言った。
「お母さんの人生、返して」
暗い目で写真を見つめたまま、母が言った。何のことを言っているのか、理解が追いつかなかった。
わたしがお母さんの人生を奪ったってこと?
お母さんから人生の何を奪ったの?
時間? それとも……?
入学式から卒業式の間に、母にも直美にも同じ時間が流れたはずだが、母の顔には直美以上の時間が刻まれているように見えた。老けたなというより、人生に疲れてるなと直美は思った。
わたしが吸い取ってしまったんだろうか。
お父さんがお母さんによそよそしくなったのも、わたしのせいなんだろうか。
少なくとも、お母さんはそう思っている。
「お母さんの人生、返して」
それって、わたしが幸せを諦めるってこと?

高校に入ってからは、母の前で楽しそうな話をするのをいっそう避けるようになった。母に邪魔されないように、つぶされないように。
毒親関係の本は何冊も読んだ。当たっている部分もあれば、違うなと思う部分もあった。母は子どもに過剰な期待を寄せ、子どもを思い通りに操ろうとするタイプとは違った。価値観を押しつけるわけでもなかった。中学受験には熱心だったが、高校受験には無関心だった。
飼っていた犬の世話は、機嫌良くやっていた。直美が小学生だったとき、両親にねだって飼ってもらった犬だ。直美は「トト」と名前をつけていたが、あるときから母は「ぴーちゃん」とまったく違う名前で呼んでいた。理由はわからない。「ぴーちゃん」とトトに呼びかける母の声は穏やかだった。トトが歳を取り、弱るにつれ、母はますますトトに優しくなった。
直美が大学生になった頃には、トトはおばあちゃん犬になり、最後はぼけて徘徊するようになった。室内犬だったが、そこかしこに排泄するので、おむつを当てていた。
一人暮らしを始めた直美に、母はトトの様子をこまめに知らせてきた。トトが死んだときは、声をあげて泣いた。慟哭とはこういう泣き方をいうのだろうなと直美は冷めた目で見ながら、トトはわたしの代わりだったのだろうかと考えていた。
子どもを持つことになかなか踏み出せなかったのは、母の存在も重しになっていたと思う。母のようには、なりたくない。子どもの幸せを妬まずに喜べる母親になりたい。けれど、そうなったわたしを、母は歓迎してくれないだろう。そこで思考は止まってしまい、その先を考えるのがしんどくなっていた。
「あなたは幸せになれない」と言いつつ、母は結婚パーティーには出席すると言った。だが、当日、姿を見せなかった。出席はしなかったが、直美の心を波立たせ、爪痕を残した。
なんで来なかったのとは聞かなかった。来て欲しくなかったでしょと言われるのは見えていた。
忘れていた母の言葉が蘇り、せっかく乾いたシャツがまたじっとりと貼りつき、体の芯から冷えるような感覚に見舞われる。おなかを冷やさないようにと産婦人科の先生に言われているのに。
「お母さんのこと考えてる?」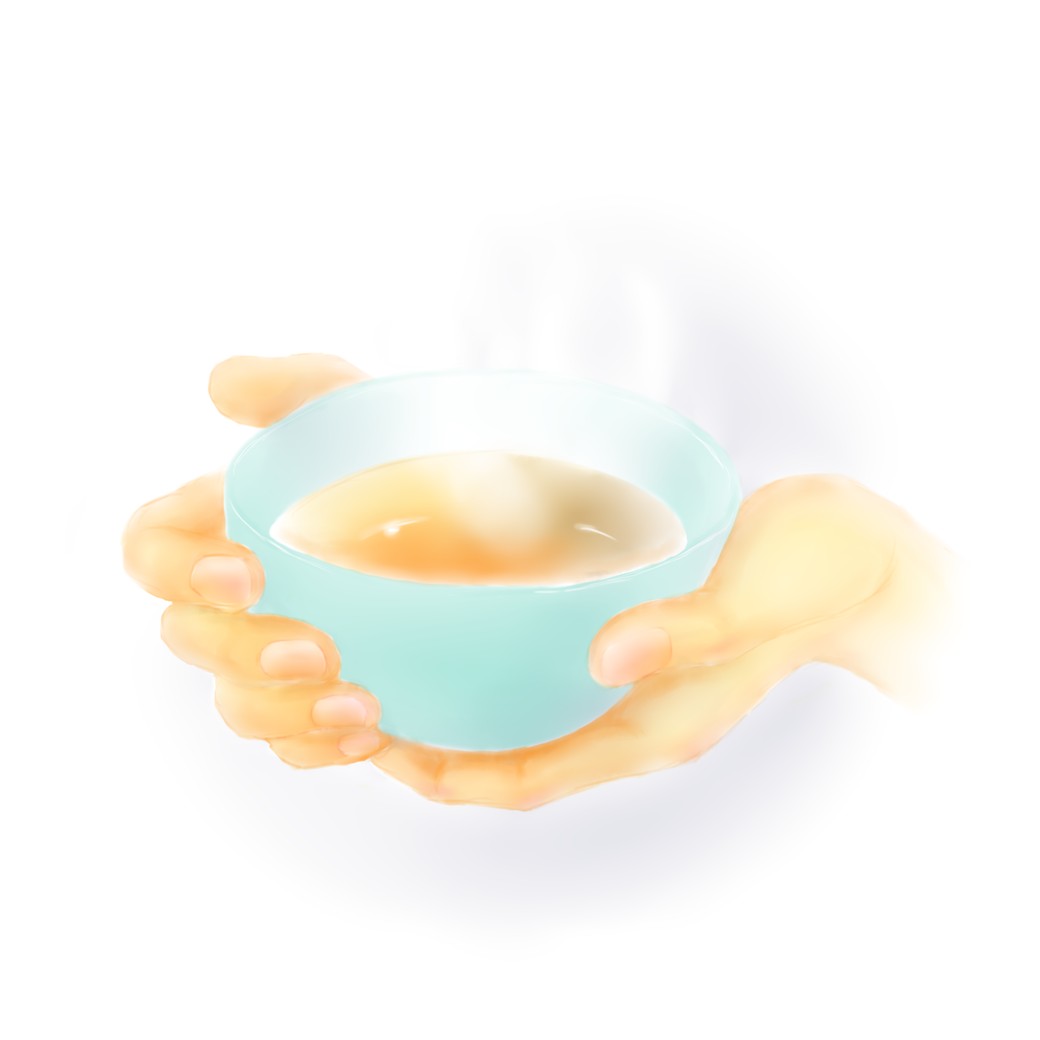
イザオの声で我に返ると、ハーブティーの香りがした。イザオが淹れてくれたらしい。
カップに添えた手のひらで熱を受け止め、ハーブティーを飲む。穏やかな温かさが体にしみ渡る。
「お母さんの人生返してって言われたんだよね」
「お母さんに?」
「うん。中学校の卒業式の日」
この話をイザオにしたのは初めてだった。深刻にならないカラッとした口調で言ったつもりだったが、イザオは黙り込んだ。しばらく受け止める間があって、「きっついな」と言った。
「返せって言われても、返しようがないんだけど」
何をどう返せばいいのかわからないし、何をどう返しても母は満足しない。親に注がれたものを、子どもは幸せにかえて、返すものではなかったのか。
卒業式の日の写真の不服そうな母の顔が思い浮かぶ。その顔は、今の直美が不機嫌なときの顔に似ている。直美の年齢が当時の母に追いついたのだ。
「どうしよう。お母さんみたいになったら」
できるだけ明るく言ったつもりだったが、言い終わらないうちにイザオが遮った。
「ハラミとお母さんは別だから」
わかってる。わたしはわたし。母は母。
母と自分を、今の生活を、できるだけ切り離そうとしてきた。けれど、自分の中に命が宿り、母親になろうとしている今、これまでになく母のことを考えている。
生まれる前、母のお腹にいた頃があったのだなと思う。その9か月間を想像する。母の中で守られて、無事に生まれて、大きくなって、イザオと出会い、新しい命が宿った。母の人生と自分の人生が確かにつながっているのを感じる。
「今はまだ言わなくていい」がそのうち「今なら言ってもいい」に切り替わるのだろうか。そのとき、母はどんな顔をするのだろう。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第41回 多賀麻希(13)「自分で自分に値段をつけるのって難しい」へ。
イラスト:ジョンジー敦子
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!






















































































































































































































































































































































































































































