
第59回 多賀麻希(19) 長い夜が明けるまで
キスで口移しされた自分の涙は温かかった。
こうなることを望んでいたはずなのだが、モリゾウのペースに乗せられてしまっている気もする。コンビニのシュークリームとキスでうやむやにされてしまっていいのと咎める冷静さがまだ残っている。
うやむやにされることに麻希は慣れていた。慣れすぎていた。
結婚しているなんて知らなかった。結婚するなんて知らなかった。別な派遣社員の子とも関係を持っているとは知らなかった……。
「知らなかった」を知ってしまった後は、そのことを相手に問いただすべきなのか、知らないふりをしておくべきなのか悩んだ。はっきりさせようと心を決めると、今度は、いつどうやって切り出そうか悩んだ。
相手は麻希が悶々としていることに気づきながら、とぼけ通した。麻希が切り出そうとするとキスで口を塞がれた。そのままいつものように体を重ね、事が終わるとさっさと服を着て、麻希の部屋からいなくなった。酒やコーヒーを飲みたいと言われたことはある。そのときの麻希は女ではなく部下に戻っていた。
モリゾウのキスも麻希に余計なことを言わせないためのものなのだろうか。
モリゾウと暮らすようになって、もうすぐ一年になる。手を伸ばせば届く距離で何度も食事を共にして、お酒も飲んで、その気になれば一瞬で越えられたのに、唇が重なるまでに一年もかかった。きっかけを作ったのは麻希の自己開示ギャンブルで、それがなかったら、たぶん今こんなことにはなっていない。
一旦体を離して、話をしたほうがいい。聞きたいことを聞いたほうがいい。服を着ているうちに。頭ではわかっているくせに、麻希はモリゾウの背中に手を回す。

モリゾウがオンライン配信の学習講座で英語講師をしていることを偶然知ったあの日、自分だけが浮かれた夢を見ていたのだと思い知らされた。長い夜が明けたように見えていた世界は再び色を失った。
モリゾウはどういうつもりで、ここに居続けているのだろう。
モリゾウにとって、わたしは何なのだろう。
モリゾウにしか答えられない問いを抱え、思考はぐるぐると巡り、螺旋階段を降りていくように下へ下へと引っ張られた。モリゾウが部屋に来てからの時間を物語る水挿しのアイビーが何食わぬ顔して伸び続けているのも恨めしかった。
前からモリゾウを知っているバイト先のカフェのマスターやモリゾウと暮らしていた演劇仲間の古墳王子にも聞けなかった。聞くことで余計なことを知らせてしまう恐れがあった。そう言えば、古墳王子とやる舞台の衣装を麻希に頼むと言っていた話はどうなったのだろう。
さっきモリゾウがシュークリームを買って帰って来たのを見てあふれた涙は、うれし涙だったのだろうか。それとも、出口を求めていた感情が押し出され、涙となって放たれたのだろうか。
涙の味は消え、ふたりの唾液が混ざり合う。体の奥で凝り固まっていたものが、キスの熱に溶かされていく。琥珀色のドロップが溶け出すイメージが脳裏に広がる。
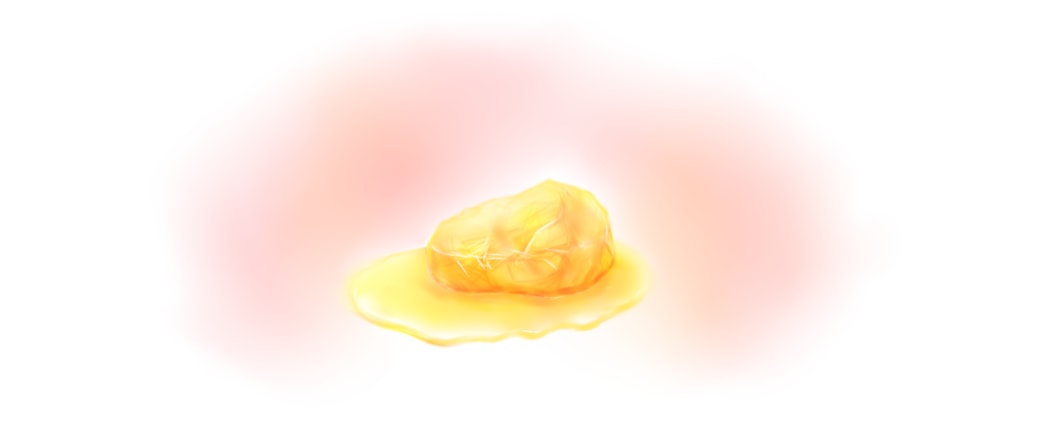
胆石の診断を受けた診察室で見せられた色とりどりの胆石を思い起こす。ボタンのようだと麻希は思った。モリゾウはきれいだという感想を持った。
診察に付き添ったモリゾウは麻希の夫を演じ、その芝居は完璧なほど自然で、すんなり通用した。モリゾウは役者なのだ。仕事も貯金もない貧乏演劇青年を演じることだってできる。
12月の終わり、今日が誕生日だとモリゾウに言えないまま40歳の誕生日を迎え、30代が終わった。胆石の症状は40代以上の女性に多く見られると診断した医師に言われたが、いよいよ胆石ゾーンに突入したこのひと月あまりで、さらに胆石を育ててしまったと思う。
麻希は40歳になったが、モリゾウは何歳なのだろう。年下だとは思うが、いくつ下なのか見当がつかない。うんと年下かもしれないし、案外近いのかもしれない。出身地も知らない。最終学歴は東大中退。それだって本人の口から聞いただけで、本当かどうかはわからない。わからないことだらけだ。そんな男と出会った日から一年近く寝起きを共にしてきたのは、部屋に上げた男といきなり関係を持つより軽率だったかもしれない。
彼が警察や組織から追われている危険人物かもしれないのに。
生活費よりも匿ってくれる協力者が必要だったのだとしたら、友人も知人もほとんどおらず、家族とも滅多に連絡を取り合わない麻希はうってつけだった。となると、モリゾウと麻希をつなげたマスターも共犯なのだろうか。
そこまで想像を巡らせて、逃亡者は舞台に立ったりオンライン講座で顔出ししたりしないかと打ち消したが、どうせなら、実は追われていると知ったほうが心穏やかだった。どこにでも行けるのに家賃も光熱費も食費も入れずに居候を続けられるより、他に行くところがなくて頼ってくれるほうがいい。そんな風に考えるなんて、どうかしている。
モリゾウの体を両手で押し返すようにしてキスを止めた。どうしたのとモリゾウが聞いた。
「電気、消していい?」
聞くべきことはそんなことじゃない。だけど。
スイッチに触れ、天井の灯りを消す。アパートの前の街灯の光が室内をぼんやりと照らす。初めてこの部屋に来た日、電気があれば十分だとモリゾウは言った。後になって、子どもの頃に電気代の未払いで電気を止められた話を聞いた。あの話も本当だろうか。そういう過去も含めて貧乏演劇青年を演じていたのだろうか。
この人のことを何も知らない。だから。

カーテンの隙間から射し込む光が朝を知らせた。キスしていたら夜が明けた。服を着たまま、キスだけしてた。キスというものを初めて覚えたティーンエイジャーみたいに。
ちゃぶ台の上に置かれたシュークリームに朝日が当たる。モリゾウが買ってきたコンビニのシュークリームがふたつ仲良く並んで、スポットライトを浴びているように見える。
「シュークリーム、忘れてたっすね」
モリゾウがシュークリームに手を伸ばし、ひとつを麻希に手渡した。
袋からシュークリームを取り出し、食べる。
幼い頃、父に買ってもらったごほうびのシュークリームを思い出す。口数が少ない父の代わりに、シュークリームが麻希をほめた。
この部屋でモリゾウと鉢合わせたとき、父はモリゾウの仕事や学歴は聞いたが、名前を聞かなかった。その必要を感じなかったのだろう。麻希もモリゾウの名前を聞いていない。けれど、知っている。動画配信でクレジットされている講師名が本当の名前だとしたら。
「武田唯人さん?」
シュークリームにかぶりついた姿勢でモリゾウの動きが止まった。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第60回 多賀麻希(20)「どこにも行かないでと彼が言った理由」へ。
イラスト:ジョンジー敦子
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!






















































































































































































































































































































































































































































