
第63回 伊澤直美(21) 消えた赤ちゃんと現れた母
直美が深い眠りに落ちて、次に目を覚ますと朝だった。見覚えのない天井とカーテン。「ここはどこ?」という混乱に見舞われた後、いつもの癖で手を当てたお腹が小さくなっていることに気づいて、産んだんだったと思い出した。
ベッドから体を起こし、床に敷いた小さな布団に目をやる。おくるみに包まれた赤ちゃんはまだ眠っていた。昨日まで自分の中にいた命が、外に出て、息をしている。
規則正しい呼吸を数える。
生きている。生きている。生きている。
わたしの一部だった命が、わたしを離れ、自分の人生を歩み出している。子どもを育てることは、親から独り立ちさせることなのだ。誕生の喜びに、早くも淋しさが入り混じる。この子はどんどんわたしの手を離れていくのだと思うと、胸が締めつけられる。
産後はホルモンの関係で感情の起伏が大きくなると両親学校で教わった。当社比200パーセントくらいセンチメンタルになっているのは、そのせいだろうが、それだけではない。この子がどうしようもなく愛おしいのだと直美は気づく。そんな気持ちが湧き上がっていることに驚く。ほんの一年ほど前、子どもを産むことをあんなにためらっていたわたしと、同じわたしなんだろうかと。
赤ちゃんの寝顔を見ると、あと何時間か眠り続けそうな顔をしている。産道に押し潰されそうになりながら、もがき進んで出口にたどり着いたのだから、わたし以上に疲れているはずだと思う。
「シャワー浴びてくるね、なかちゃん」
眠っている赤ちゃんに声をかけ、入院室を出て、シャワー室へ向かった。
お腹の中にいるから「なかちゃん」。もしもしギアをお腹に当てて赤ちゃんに話しかけるとき、名前があったほうがいいねとなり、イザオとつけた呼び名だ。

覚悟はしていたものの、空気の抜けた風船みたいにシワシワにしなびたお腹を見たショックは大きかった。時間が経てば元に戻ると亜子姉さんは言っていたが、折り畳めるほど伸びきった皮が果たして元通りになるのだろうか。
人が一人、入っていたんだもんね。
シャワーを浴びる間、気になって、ついついお腹の皮を指でつまんでしまった。こじ開けられた股の部分に湯が当たるとヒリヒリする。擦り傷になっているのがわかる。
身体は思ったより軽い。羊水と赤ちゃんと胎盤を合わせた重みが離れ、身体の自由がきく軽やかさが戻ってきた。マタニティビクスの成果が出ているのが感じられる。赤ちゃんを抱っこして報告に行き、後に続くビクス仲間を励ますのが楽しみだ。
先輩たちの「軽かったよ」の言葉を鵜呑みにしていたが、「終わってみれば」「意外と」軽かったのであって、産んでいる最中は「こんなに大変だなんて聞いてない!」だった。
シャワーで出産の名残を洗い流すと、産前から産後に切り替わったように感じた。シャワー室にいたのは、着替えを含めて10分ほどだったと思う。入院室に戻って来ると、床に敷いた布団が空になっていた。
赤ちゃんが消えていた。
直美が部屋を出るとき、確かにそこにいたのに。
イザオが来たのだろうか。こんな朝早くに。時計を見ると、まだ6時過ぎだ。
イザオに電話すると、呼び出し音が鳴り続けた。電話を切ろうとしたとき、「ハラミ?」と寝ぼけた声が出て、「いま何時?」と聞かれた。
「赤ちゃんが……」
「どうした? 何かあった?」
続きを言わずに電話を切った。
イザオではないとしたら、誰が?
誰かにさらわれた?
思い浮かんだのは、母の顔だった。
誰かが赤ちゃんを連れ去るとしたら、母しかいない。

お医者さんは病院と同じ敷地内にある自宅に戻ったが、出産に立ち会った看護師さんが泊まり込んでいるので、何かあれば声をかけてくださいと言われていた。寝ているところを起こしてしまうのは申し訳ないが、宿直室のドアをノックすると、すぐに返事があり、ドアが開いた。看護師さんもすでに起きていた様子だ。
「おはようございます伊澤さん。よく眠れましたか?」
「母が来ませんでしたか?」
看護師さんの言葉を遮るように聞いた。
「誰も来ていませんが」
母ならインターホンを押さずに入って来るかもしれない。
「入口の鍵はかかってましたか?」
「伊澤さん、何があったんですか?」
「赤ちゃんが消えたんです!」
「消えたって、どういうことですか?」
「シャワーを浴びている間に、いなくなっていたんです!」
話していると、どんどん悪い想像が膨らみ、涙がこみ上げる。
せっかく産んだのに。産んだばかりなのに。
看護師さんと一緒に入院室に戻った。ドアを開けると、布団の上に赤ちゃんが戻っているかもしれない。姿が消えたのは、出産の疲れで見た幻だったのだと信じたかったが、やはり布団は空のままだった。
「ここに寝かせていたんです」
声が震えた。
「いないですね」
看護師さんの声は震えていない。他人事だから落ち着いていられるのだと恨めしく思う。
と、部屋のどこかから衣擦れのような音が聞こえた。
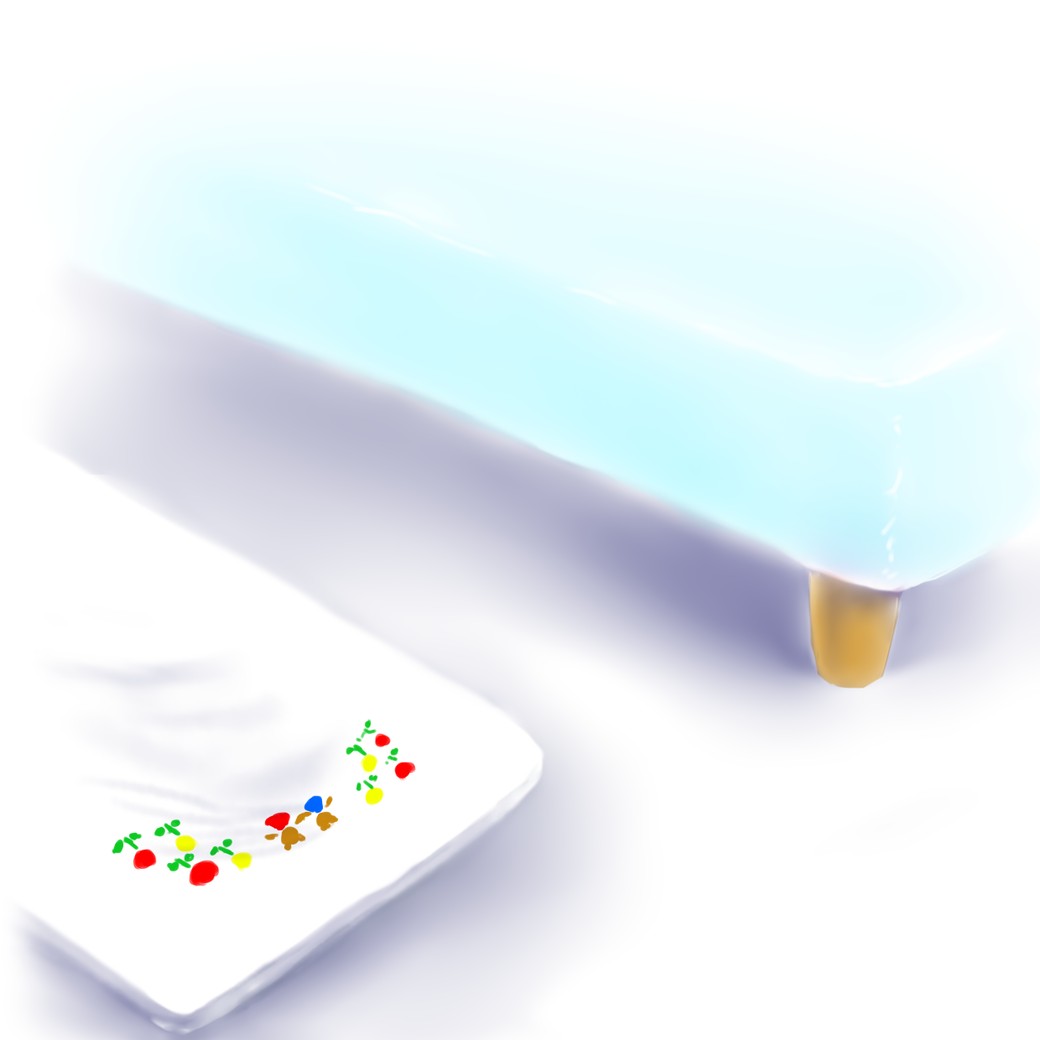
看護師さんが腰を落としてしゃがみ、
「いました」
と告げた。
看護師さんの視線の先、ベッドの下に目をやり、直美は思わず「え!」と声をあげた。
そこに赤ちゃんがいた。
布団の上で眠っていた赤ちゃんが、ベッドの下に移動していた。
「かかとで床を蹴って、頭の方向に進んだんですね」
看護師さんが淡々と言う。
「そんなことできるんですか」
身長50センチ、生後1日、ハイハイもできない赤ちゃんにそんな離れわざができるのだろうか。
「お腹の中で泳いでいますからね。生まれたばかりの赤ちゃんって、結構キック力あるんです」
赤ちゃんの体の下に両手を差し入れ、ベッドの下からそっと引き出し、抱き寄せた。ほっとしたら、さっきとは違う温度の涙がこみ上げた。
「人生最初の迷子ですね」
看護師さんに言われ、ほんとだ、と泣き笑いになる。
「この子がお腹に入る少し前まで、わたし、子どもを持つのをためらっていたんです。子どもが生まれたら、手放さなくちゃいけないものがたくさんあるって。でも、今はこの子を手放したくないです」
「案ずるより産むが易し、ですね」
看護師さんと笑い合い、一件落着となったが、直美の胸に立った波は消えなかった。
母親が赤ちゃんを連れ去りに来たのではないかという咄嗟の反応が、自分の本心をあぶり出しているように思えた。
幸せになると、母が壊しにやって来る。
それくらい幸せだし、それくらい母を信じていない。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第64回 伊澤直美(22)「名前は人生で最初のプレゼント」へ。
イラスト:ジョンジー敦子
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!






















































































































































































































































































































































































































































