
第77回 多賀麻希(25)閉じていなかった物語
モリゾウが「星屑蛍」を知っていた?
どういうことだろうと麻希は頭が混乱する。
ツカサ君は脚本コンクールに出し続けていたが、結果を出す前に故郷の山形に帰って家業の旅館を継いだ。『制服のシンデレラ』は最終選考に残って真っ先に落とされた。それがツカサ君の応募作がたどり着けた一番高い場所だった。
だから、名前が売れていたわけではない。作品を発表する機会もなかったはずだ。脚本家になりたいと言いながら、映画や演劇を観に行くのは消極的だった。演劇をやっているモリゾウと接点がありそうでないように思える。
似たような名前の別人と勘違いしているのだろうか。
モリゾウに確かめると、「星屑蛍」で間違いないと言う。
「会ったことはないけど、こんな書き手がいるよってめろんに教えてもらって。10年、いや、もっと前かな」
「めろん」とモリゾウが呼ぶのは、一緒に演劇をやっていた「めろんぐらっせ」のことだ。もう一人、「古墳王子」の名前で古墳アイドルとして売り出し中の「高低差太郎」と3人で学生時代から活動してきたが、「めろんは抜けたっす」と以前モリゾウが言っていた。素っ気ない言い方だったから、たぶん円満な別れ方ではなかったのだろう。
「めろんぐらっせって人が星屑蛍とつながってたの?」
「バイト先で一緒になって、演劇やってるってめろんが言ったら、ホンを読んで欲しいって言われたらしくて」
なるほどそういうつながりかと麻希は納得する。と同時に、すごい確率だなと驚く。ツカサ君は、めったにバイトをしなかった。山形からの仕送りもあったし、「お金を払ってでも時間を買いたい」という人だったから。たまにバイトするのは、よっぽどお金に困っているときだった。ひと月に数日、日雇いのバイトを入れていた。足し上げても一年のうち数十日くらいだったかもしれない。
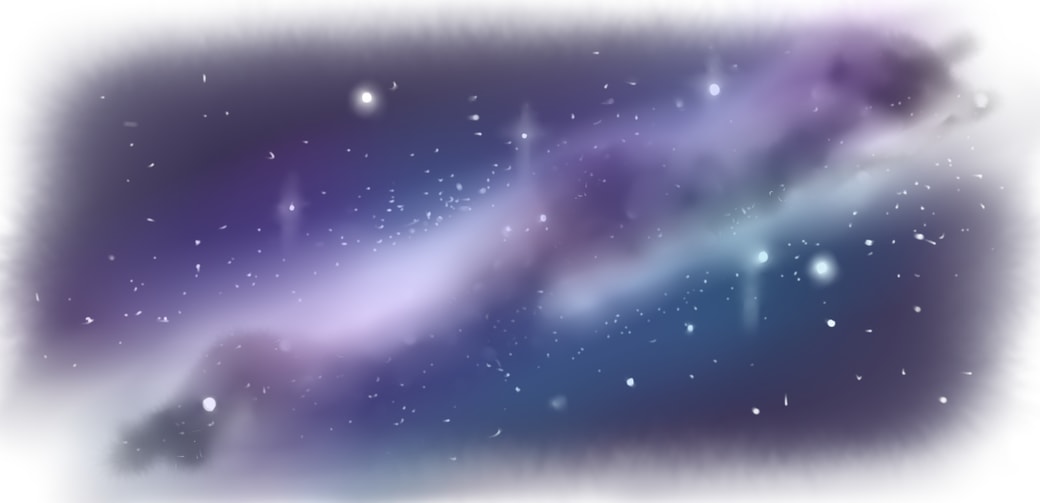
仕送りだけで足りていたとも思えないが、麻希の部屋に転がり込んで家賃を浮かせていた。ツカサ君も麻希から吸い上げた一人ということになるが、そんな風に考えたことはなかった。自分から喜んで差し出したのだ。当時、新宿三丁目の映画製作会社で働いていた麻希は、ツカサ君が脚本家になる夢を一緒に追いかけていた。書くのはツカサ君だけど、ツカサ君が書く時間はわたしが作っているのだという自負があった。
「モリゾウは星屑蛍の書いたものを読んだの?」
「マキマキと星屑蛍は、どういうつながり?」
麻希の質問に、モリゾウが質問で返した。
昔つき合っていた人だと正直に言うべきだろうか。それとも、ぼかすべきだろうか。先入観なしに『制服のシンデレラ』を読んでもらったほうがいい気もするが、先に伝えておいたほうが誠意があるように思う。
「勤めていた会社の社長の知り合い」という言い方もあるし、「『それからのルーズソックス』で共演したエキストラ」も本当のことだ。ただ、15年前の麻希とツカサ君の共演シーンを見たモリゾウは、ふたりがその日をきっかけに付き合うことになったのを察しているように思える。エキストラの共演相手が星屑蛍だと告げたら、交際の事実を告白するのと変わらない。
何と答えようかと麻希が迷っていると、
「ツカサ君って人?」
モリゾウがど真ん中の答えを投げてきた。
「ツカサ君のこと、話したことあったっけ」
「ないけど、呼ばれたことある」
「え?」
「マキマキが寝ぼけてるとき。何度か」
やってしまっていたのか。
「その人、『それからのルーズソックス』にマキマキと出てた?」
「そう、だけど。なんでわかったの?」
「エンドロールでマキマキと並んでる名前がツカサだった」
そうだった。エキストラは出演順にクレジットされ、麻希とツカサ君の名前が並んだ。モリゾウは鋭い。刑事になれる。
映画製作会社の社長はケチだったが、クレジットは出し渋らなかった。名前を載せておけば、いつかパッケージ化されたときに記念に買ってくれるという下心もあったと思う。あの社長のことだから。
結局『それからのルーズソックス』はパッケージ化されなかったが、クレジットはモリゾウが麻希とツカサ君を結びつけるのに役に立った。

もうモリゾウに隠すことはなかった。
「別れてから10年あまり経つけど、脚本家になりたくてコンクールに出してた人で……でも、いつも一次も突破できなくて、それでわたしが裏庭燃やしちゃった話をしたの。そこから膨らませたのが、この話」
「『制服のシンデレラ』」
モリゾウがあらためてタイトルを読み上げる。何度言われてもドキドキする。過去の自分を呼ばれた気がして。
「どうして俺に見せようって思ったの?」
「モリゾウの感想を聞きたくなって」
モリゾウが『制服のシンデレラ』の表紙をめくり、登場人物表で手を止めた。
「あかね 17歳 高校生。燐(りん)太郎 25歳 カメラマン」
あかねのモデルは麻希だ。麻希の実体験では裏庭で教科書を燃やした火が広がるが、あかねは出来心から放火を繰り返す。その現場に毎回現れ、炎の写真を撮る青年が燐太郎だ。
「俺がめろんに渡されて読んだホン、これだ」
「ほんと?」
「でも、タイトルが違った。茜がついた気がする」
「もしかして、『茜色の空の下で』?」
「多分それ」
「最初そのタイトルだった」
『茜色の空の下で』から『制服のシンデレラ』に変えたのは、映画製作会社の社長の入れ知恵だった。
「企画はタイトルが9割。タイトルがつまらんもんは中身もつまらん」
社長にそう言われ、ツカサ君が出した代案が『制服のシンデレラ』だった。過去の自分を「シンデレラ」と呼んでもらえて、消したい過去が上書きされたように麻希は思った。
『制服のシンデレラ』が最終選考まで勝ち残ったのはタイトルのチカラも大きかったとツカサ君も認めていた。だが、最終選考でタイトルだけをほめられて真っ先に落とされると、「タイトル負けした」とツカサ君は悔しがった。
めろんぐらっせに原稿を渡したのはコンクールに出す前だったのだろうか。それとも敗退が決まった後にタイトルを元に戻したのだろうか。
「俺は『制服のシンデレラ』のほうがいいと思うけどな」
「わたしもそう思う」
欠席裁判みたいでツカサ君には悪いなと思いつつ、モリゾウのよく響く声で『制服のシンデレラ』と言われるたびに、過去の自分を肯定された気持ちになる。裏庭を燃やしてしまった自分も、ツカサ君を応援していた自分も。

「めろんは俺が書くわけのわからない話より、こういうストレートなのをやりたいって言ってたんだけど、俺は気乗りしなくて。でも、今読んだらまた違う感想を持つかも」
「読んだら感想聞かせて」
「今、一緒に読まない?」
「一緒に?」
「俺が燐太郎やるから、マキマキがあかねやってよ」
モリゾウが思いがけない提案をした。初見で読み合わせというやつだ。
「無理無理。わたし素人だよ」と麻希が渋ると、
「地でやってくれていいから」とモリゾウは言った。
「いやいや、地でやるったって、高校生と今じゃ、開きがありすぎるんだけど」
「大丈夫。マキマキは地続きだから」
地続き。たしかに、わたしは途切れていない。
10代の痛い体験を20代の頃の恋人が脚本にした。その物語を、30代の終わりに知り合った恋人と、40歳になった今、読み合わせする。七夕が運んできた天の計らいのような巡り合わせ。
ツカサ君が去ってツカサ君との物語は閉じたと思っていたのに、止まっていた時計の針が動き出した。『シンデレラ』も真夜中の12時の鐘が聞こえて舞踏会を去った後からドラマが動くのだ。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第78回 多賀麻希(26)「17歳のわたしの続き」へ。
イラスト:ジョンジー敦子
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!






















































































































































































































































































































































































































































