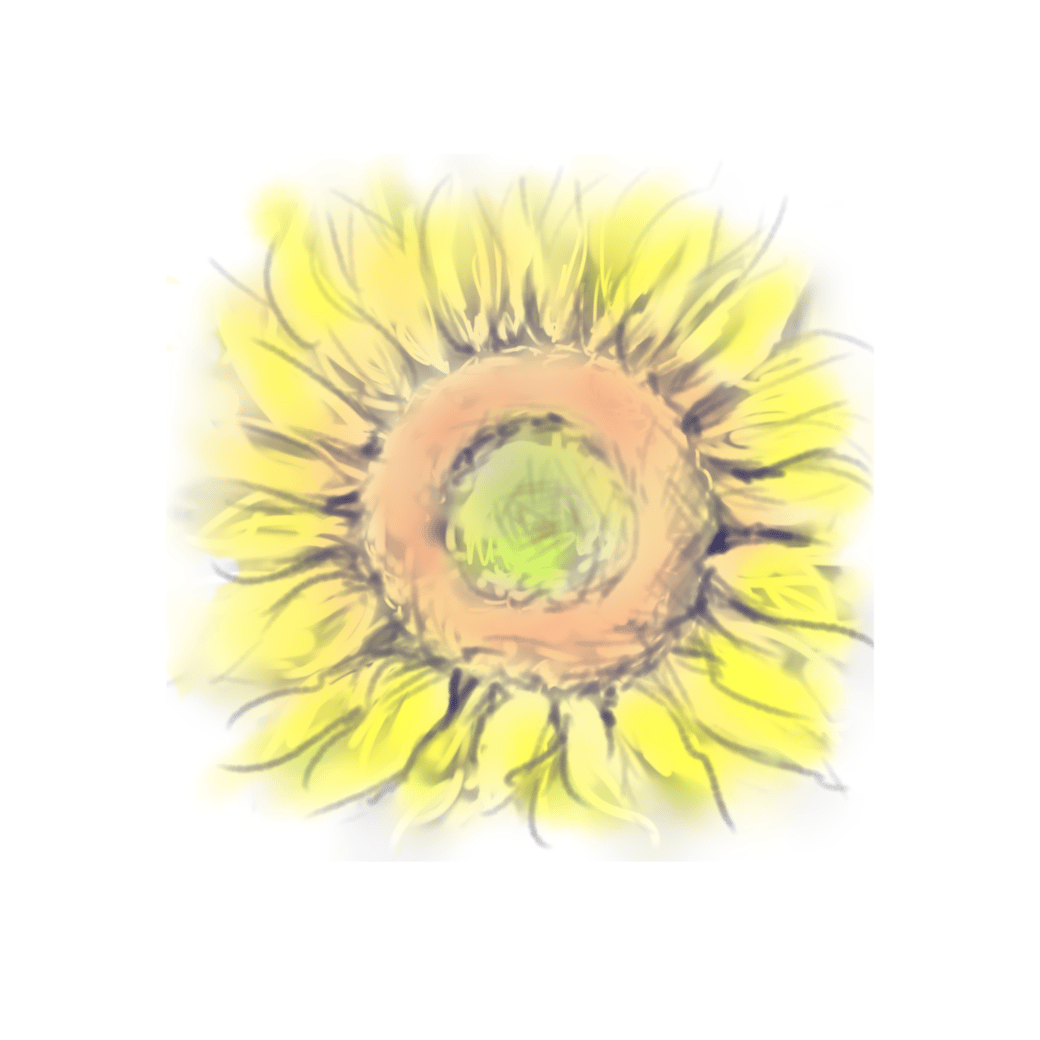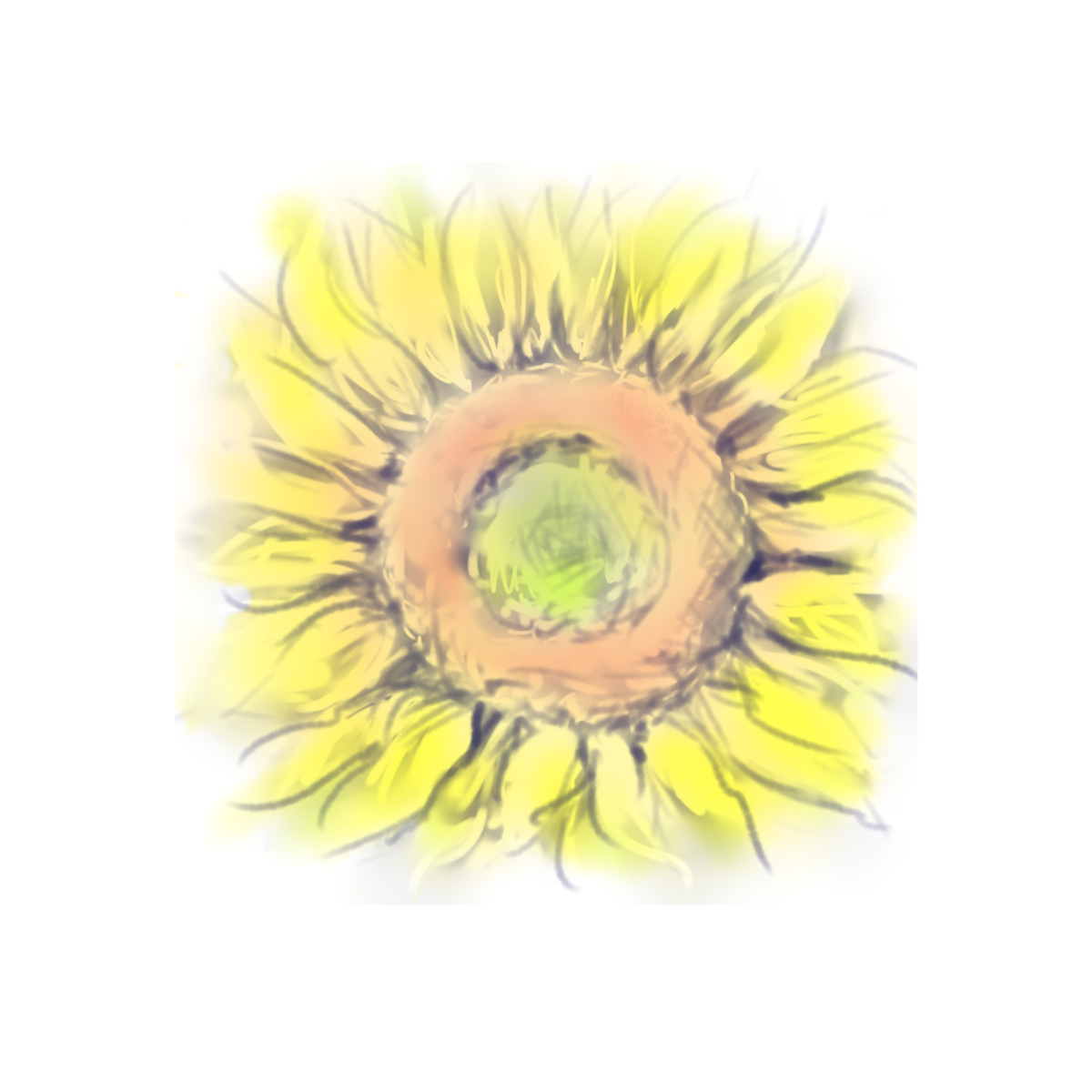第82回 伊澤直美(28)本人に聞けばいいのに
「親は子どもの気持ちがわからないし、子どもは親の気持ちがわからないし」
亜子姉さんの言葉で、母のことを考えていた直美は現実に引き戻された。
亜子姉さんの家のリビング。アイスを食べ終えたカップが目の前にある。「麦茶冷蔵庫にあるから」とさっき亜子姉さんに言われた。夫の姉だから身内なのだが、お客さま扱いされないのが心地良い。亜子姉さんが家に来たときは、亜子姉さんが「麦茶冷蔵庫にあるよね?」と取りに行ってくれる。
ふたりで遊ばせていた優亜といとこの結衣ちゃんは、声が聞こえなくなったなと思ったら、寝息を立てていた。どちらかが先に眠りに落ち、もう一人も眠気を誘われたのだろう。
紙おむつだけはかせて上半身は裸のふたりにタオルケットをかけながら亜子姉さんが話を続ける。
「わからないから推し量るしかないんだけど、結局、自分に都合のいいように解釈しちゃうよね」
亜子姉さん、わたしの心、読んでますか。
それとも、わたし、声に出してましたか。
「結衣がお腹に入って間もない頃、直美ちゃんちに幸太預けたじゃない? あのとき、幸太が描いた絵、覚えてる? 私のお腹の中に赤ちゃんがいて、ちょっと後ろにダンナがいて、みんな笑ってるの。私も、ダンナも、赤ちゃんも。あの絵を見て、産んでいいんだって思ったの」
妹か弟がお腹に入ったよと亜子姉さんに聞いたその日から幸太はおねしょが始まったという。元々変化には敏感な子なのだが、当然喜んでくれると思っていた亜子姉さんは戸惑った。直美とイザオ夫婦が幸太を預かったのは、そんな頃だったのだ。

その絵のことは、もちろん覚えている。あの頃はイザオと「産む産まない」ですれ違っていた。幸太を預かったあの日、子連れが多いスーパーでの買い物も、幸太の相手をするのも、直美にはプレッシャーだった。
お腹に赤ちゃんのいる女の人の絵を幸太が描いたのを見て、イザオは「コータ、いとこが欲しいのかも」と絵に便乗して直美にアピールした。直美は聞いていないふりをして、逃げるように仕事部屋にこもり、パソコンに向かった。直美の背中に幸太が声をかけたが、素っ気ない返事をした。
「でもさ、よく見たら、あの絵、幸太が入ってなかったんだよね。私もお腹の赤ちゃんもダンナも笑ってるけど、そこには幸太はいないの。だから、もしかしたらあの絵は、置いてけぼりでさみしい気持ちを表したものだったのかもしれない」
亜子姉さんはため息のように小さく息をついて、続けた。
「何が言いたいかというと、絵を見る人は、自分に都合のいいように受け止めるってこと」
わかりますと直美はうなずく。幸太が描いた女の人と男の人は、どう見ても亜子姉さんとダンナさんだったが、イザオには自分と直美に見えたのだ。
亜子姉さんがふたり目を身ごもったことを直美夫婦が知ったのは、その日のことで、一人目どうしよう問題に直面していた直美は、さらに追い詰められた。
直美がより強烈に覚えているのは、幸太が残したもう一枚の絵だ。パソコンに向かう直美の背中に「なおみちゃんおしごとがんばってる」とメッセージが添えられていた。「がんばってね」ではなく「がんばってる」だったことがこたえた。一緒に遊んでくれない直美を幸太なりに受け入れようとしている健気さにうたれ、甥っ子に背中を向けた自分の大人げなさに嫌悪を覚えた。
実際幸太がどんなつもりであの絵を、あのメッセージを描いたのかは知らない。
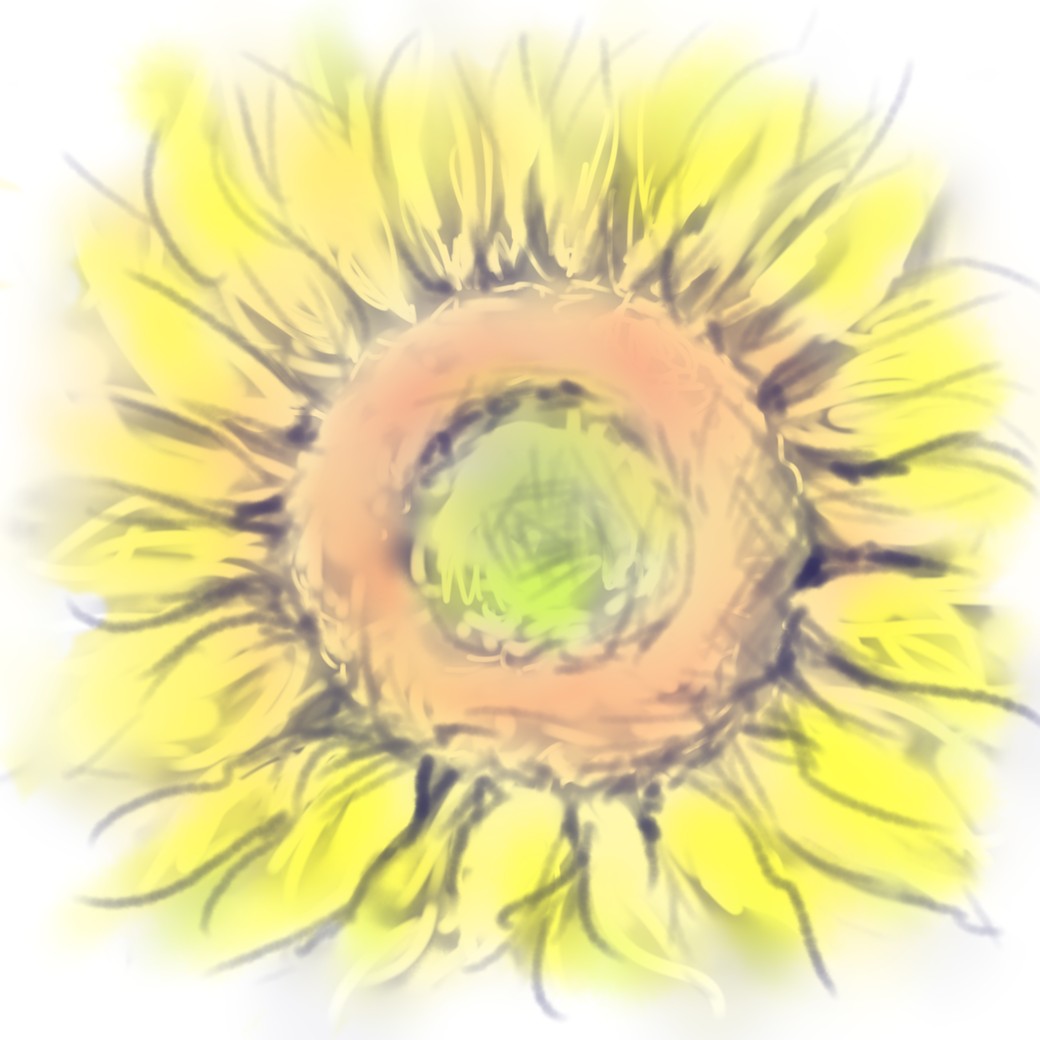
「この季節になると思い出すんだけど、3歳ぐらいかな、クレヨンをグーの手で握ってる私がひまわりの絵を描いてるの。多分それが人生で最初の記憶」
のちに美大に進んで絵を描くことを仕事にした亜子姉さんらしい子ども時代のエピソードだと直美は思う。
「母が隣にいて、私が描き終わるのをじっと待ってるの」
亜子姉さんの母はイザオの母でもある。直美が苦手な義理の母だ。
「そのうち日が暮れてきて、やっとひまわりが描けて、そしたら母が『よく描けたね。お父さんに見せよっか』って言うの」
亜子姉さんの記憶は断片ではなく、まとまった時間が流れている。
「うちの母が私の絵をほめるの、珍しいと思わない?」
「確かに」
「私ね、母にほめられたのがうれしくて、もっと絵を描くようになったの。でもね、こないだ、母がボソッて言ったの。私を連れて家出したことあったんだって」
「家出ですか?」
「ひまわりが咲く季節に」
「ひまわり……」
「どこにも行くあてがなくて、でも、母は父に合わせる顔がなくて、私が描いたひまわりを見せるっていうのを家に帰る口実にした……。多分これが真実。だけど私には母に絵をほめられた記憶だけが残った」
亜子姉さんが「母」と言うたびにドキッとする。亜子姉さんが言っているのは直美が苦手な義理の母だとわかっているのに、自分の母のことを言われているような気持ちになる。
両親の不仲の原因を作ったのは自分だと直美は思っている。元々ヒビは入っていたかもしれないが、亀裂を広げたのは自分だ。一人娘の教育方針を巡って父と母は対立した。中学受験をさせるか、させないか。その選択の根っこには、娘にどんな人生を歩ませたいかがあった。それが決定的にずれていた。
中学受験で進路を絞り込む必要はないと父が言うと、少しでも良い学校に行かせて、将来の選択肢を広げるのだと母は反論した。何になりたいかもわからない小学生に受験させる必要があるのかと父が問うと、何もわかっていないからこそ親がレールを敷くのだと母は断言した。
直美はどちらの肩も持たないようにしていた。両親が自分のことで揉めるのを聞きたくなくて、家の中ではイヤホンを差していた。母親の望み通り受験し、父親の願い通り地元の公立中学校に進んだが、母は「あっちに行っていたら」と3年間こぼし続けた。校舎や運動会や校外学習をいちいち比べては、嘆いていた。比べても仕方ないだろと父親が言うと母は不機嫌になり、わざとガチャガチャと大きな音を立てて食器を洗ったり分別ゴミを分けたりした。

母に理想の未来を押しつけられてきたと直美は思っていた。
だけど、と自分が母親になった今、思う。
母は純粋にわたしの幸せを願っていたのではないか。自分が報われるためではなく、娘の幸せがそこにあると信じて、中学受験を勧めたのではないか。
胸の内に渦巻く母への屈託を亜子姉さんに打ち明けた。イザオにもまだ話していないが、誰かに聞いてもらうなら亜子姉さんだった。
母と折り合いが悪いことは亜子姉さんにも話していた。「うちも大概だけど、直美ちゃんとこも大概だね」と同情を寄せてくれていたが、娘が生まれたことをまだ報告していないと言うと、驚かれた。
「どうして言わないの?」
「なんだか怖くて」
「何が?」
母に幸せを壊されるのが。
本音を口にすると、なんだか嘘っぽい気がして、「タイミングを逃しちゃって」と直美は言った。それも嘘ではない。
「じゃあ今しよ」
「今ですか?」
「ここで電話しよ」
「いつかしよう」の先延ばしの呪いを解くおまじないは、「か」を後ろにずらすこと。
いつしようか。今しよう。
何年ぶりかに自宅の電話番号にかける。もちろん覚えている。
応答したのは母の声ではなかった。
「おかけになった電話番号は現在使われておりません」
次の物語、連載小説『漂うわたし』第83回 多賀麻希(27)「彼と彼女の不完全燃焼」へ。
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!