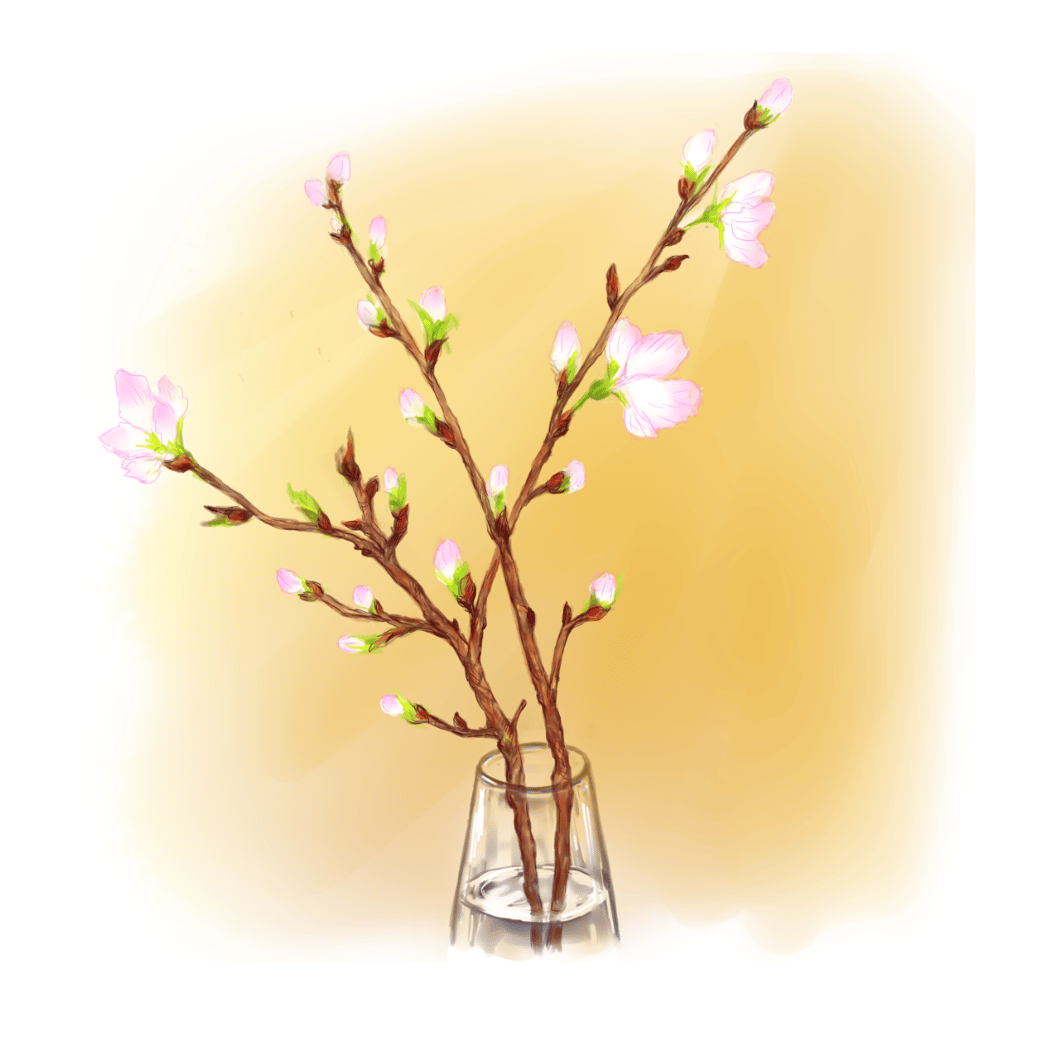第107回 多賀麻希(35)見知らぬ誰かを待ちながら
「マキマキ、なんかサイン決めとく?」
マスターが最後の客のカップを下げながら、一人でテーブルに着いている麻希に声をかけた。
「サインって?」
「助けに入って欲しいときの」
「そんなことになるのかな」
「一応、保険かけといたら?」
「じゃあ、この表紙を開いたら、声かけて」
麻希はモリゾウが「古墳バッグ」と名づけた肩掛けカバンから小ぶりのスケッチブックを取り出し、テーブルに置いた。
5日前、《お目にかかって、ご相談したいことがあります》とショップの問い合わせフォームあてにメッセージがあった。
初めて見るアカウント名からだった。《メッセージでご用件をうかがいます》と返信したのだが、《お会いしたときにお話しします》と返された。
何を相談されるのだろう。
心当たりはあった。
《ケイティさんがご自身のブランドで出されているひまわりの形のバッグが、makimakimorizoというショップの一点もののバッグによく似ています。偶然でしょうか》
ネットの匿名掲示板に書き込まれた投稿を見つけたとき、自分が書いたのかと思った。投稿から2日経っていたが、コメントはついていなかった。「過疎ってる」と呼ばれるやつだ。
投稿から3日後、ようやく最初のコメントがついた。
《見ました。確かに似ていますね。ケイティのデザインが流出したのだと思います。ケイティも心を傷めているはずですが、フェイクの作者さんを気遣って大ごとにしないのは懐が大きいですね》
ケイティの取り巻きと思われる「通りすがり」の人は、真似されたのはケイティのほうであると決めつけていた。

《ケイティさんのデザインが先なのでしょうか》と質問者がコメントを返したのは、それから5時間後だったが、その間に麻希は3回、新規コメントがついていないか見に行った。
《このショップの商品、ひまわりバッグが最後になっていますね。何か事情があるのではないでしょうか》と通りすがりの人がすぐさま返し、
《ショップを閉じていないというのは、やましいことがない証拠ではないでしょうか》と一晩明けて質問者が返した。
一体どこの誰が、わたしに代わって、戦ってくれているのだろう。
真っ先に頭に浮かんだのはモリゾウだったが、違った。もう一人、事情を知っていて、かつ、当事者となる人がいた。
ひまわりバッグの購入者だ。
ケイティが持っているバッグとの関係を問い合わせるメッセージをもらい、《類似したバッグがありましたら、デザインを盗用した模造品です》と返信したが、購入者が納得したかどうかは確かめていない。ケイティが量産品のひまわりバッグを売り出した際には問い合わせがなかったが、こちらからもあらためて説明すべきだったかもしれない。
《もしかして、質問者さんって、ショップの方ですか?》
通りすがりの人のコメントに質問者は沈黙した。このままだと事実として認めたことになってしまう。かといって「ショップの人」本人がしゃしゃり出ては話を複雑にしてしまいそうだ。掲示板をのぞきに行っては動きがないのを確かめ、引き返していたところに《お目にかかって、ご相談したいことがあります》の問い合わせが舞い込んだのだった。
匿名掲示板の質問者か。
通りすがりの人か。
掲示板を見た誰かか。
一人で会うのは怖いけれど、モリゾウを連れて行くのも気が引け、思いついたのが新宿三丁目のカフェだった。あそこならアウェイじゃないし、マスターには事情を伝えてある。
ひまわりバッグのゴタゴタでずっとバイトに行けていないのに、ひまわりバッグのことで頼るなんて、虫が良すぎる。イヤミのひとつでも言われたっておかしくないのだが、
「ちょうどマキマキの顔見たいと思とったんや。来たついでに手伝って行って」
マスターは麻希が戻る場所とコーヒーを用意して、待っていてくれた。
「良かった。元気そうやん」
「元気そうにしてます」
「上出来や」
人と会うときは「元気そう」にできるのだ。自分の中にある元気をかき集めて。そのことをわかった上で、「うまくできてる」とマスターは伝えてくれる。
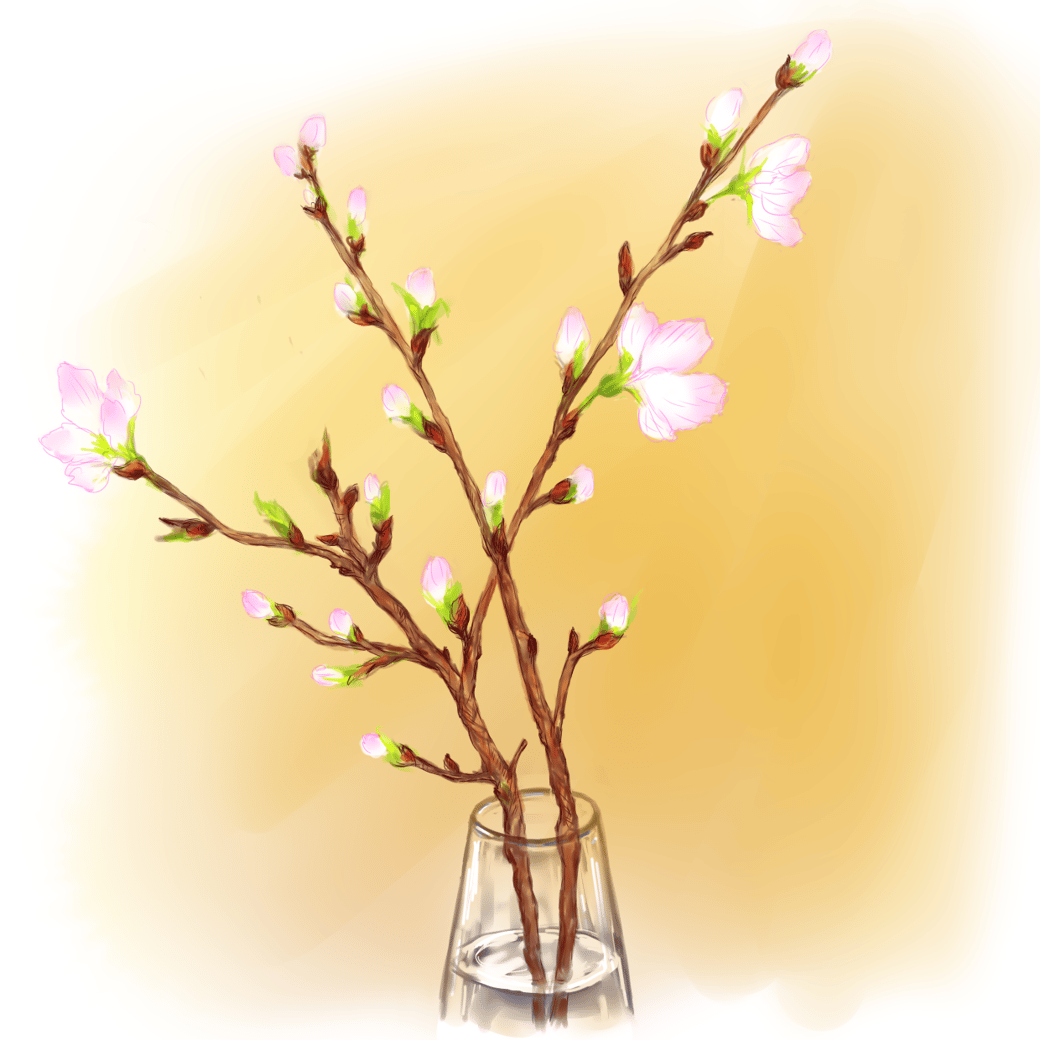
カウンターの隅に置かれたガラス瓶に挿した桜の枝が蕾を開かせている。
「マスター、花なんて飾ってましたっけ」
「ちょうどお客さんが持ってきてくれはったんや。マキマキ、ええときに来た。新宿御苑より早い花見や」
わたしに気を遣わせないために、お客さんが持ってきたということにしているのかも。そんなおめでたい想像ができるのは、自分が受け入れられていると思えているからだ。
待ち合わせの時間まで、あと10分。相手の名前はアカウント名しか知らない。アルファベット3文字でMYU。何と読むのだろう。ミューか、マイユーか、エムワイユーか。あと少ししたらわかることだ。
「手持ち無沙汰やったら、中手伝う?」
「いや、それはおかしいかも」
麻希はスケッチブックを開き、鉛筆を走らせる。手を動かしていると余計なことを考えずに済む。花びらの形や枝のしなり具合を描き留めることに集中する。このラインを刺繍でどう表そうかと考える。
作りたい気持ちが湧き上がってくる。あんなことがあっても作りたい。作ることをやめたくない。ショップに品物を並べたい。それを誰かに手に取って欲しい。
桜は、モリゾウと出会う前の最後の恋人だったツカサ君の思い出も連れて来る。
故郷の山形の桜を一緒に見に行こうと誘われていたのに、うんと言えなかった。ツカサ君の家族に紹介されて、結婚話が持ち上がるのではないかと、まだ20代で白紙の未来を残しておきたかった麻希は身構えた。
せっかく熊本から出てきて東京で恋人を見つけたと思ったら、いつかは田舎に引っ込まなくてはならない期限つきの東京者だったとはとハズレくじを引いたような気持ちにもなっていた。
老舗旅館の跡取り息子で、行く行くは山形に帰ることになるから、その前に脚本家デビューしておきたいとツカサ君は言っていた。打ち合わせのときだけ東京に行ってる脚本家もいるんだよと。デビューしたら自分もそうなれると信じている口ぶりだった。
同じくらい書ける人がいたら、すぐに呼びつけられる人に頼むし、地方に住んでいても仕事が来るのはよっぽどの大物だと映画製作プロダクションで働いていた麻希はわかっていたが、口にはしなかった。

結局、お父さんが倒れてしまい、ツカサ君は脚本家デビューする前に山形に呼び戻された。
あのときついて行っていたら、今頃は老舗旅館の女将さんになっていたのだろうか。
白紙にしておいた未来に描き込まれたのは、思っていたより冴えない日々だった。ついて行っていたらと現実逃避のような想像をしたことは、何度かあった。
だけど、どの道を選んでも、苦労はある。まともに食らうか、よけられるか、乗り越えられるかが違うだけで。
コロナ禍に見舞われて2度目の春、ツカサ君が継いだ旅館のサイトを見に行ったことがあった。毎年花見客で予約が取れなくなると言っていた季節、カレンダーの空室状況はどの日も◯になっていた。
派遣切りに遭っては削られ、胆石を溜め続けた麻希とは違う苦労がツカサ君にはあったのだ。今はどうしているのか、それからは怖くてサイトを見ていない。
踏んだり蹴ったりで無職になり、それでも東京にしがみつこうとしていた30代の終わり、モリゾウとの出会いがあった。
そう、このカフェで。
今思えば、あの日、東京の底を蹴ったのだ。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第108回 多賀麻希(36)「わたしの顔を見に来た彼女」へ。
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!