
第117回 伊澤直美(39)その手をつなぐために空けておく
「スマホ、置いていかない?」
玄関でスニーカーに足を突っ込みながらイザオが言った。
「写真撮ったりしないの?」
直美は屈んで優亜に靴を履かせている。優亜に着せたドレスの裾が手首をくすぐる。ストラップのついた靴も90センチサイズのパーティドレスも優亜の半年前に生まれた亜子姉さんちのふたり目、結衣ちゃんのお下がりだ。
「いくらでも撮ってくれる人いるし」
直美の返事を待たずにスマホを靴箱の上に置いた。俺はそうするよの意思表示のように。
昨夜、タヌキにDVDを借りた『幸せのしっぽ』を観た。一人で観るつもりだったが、ようやく優亜を寝かしつけ、今のうちにと観始めたところにイザオが帰宅し、「何これ?」とDVDのパッケージを手に取った。ヒロインのスカートからキツネのような茶色いしっぽが飛び出し、その周りに黄色い花のアップリケがあしらわれている。
「亜子姉さんのバッグに似てると思う?」と直美が聞くと、
「これ、ひまわりじゃないよね?」とイザオは言った。
イザオとの間では、ひまわりバッグのことを「亜子姉さんのバッグ」と呼んでいる。イザオは「アコネーのバッグ」と呼ぶ。
「タヌキに亜子姉さんのバッグの写真見せたら、この映画の衣装を思い出したんだって。それで、同じ人がデザインしたのかもって思って、ウェディングドレスのリフォームをお願いしたんだって」
「誰に?」
「だからー、亜子姉さんのバッグの人」
「同じ人だったの?」
「それが、後でわかったんだけど、ケイティがこの映画の衣装デザインに関わってるらしくて」
映画に7割ほど気持ちを向けて、残りの3割でイザオと会話をしていたが、どっちも頭に入ってこない。
「ケイティって誰だっけ」とイザオが聞いた。
「だからー、亜子姉さんのバッグによく似たのを出してるインフルエンサー」
「ああ。ジェネリックの人?」
量産のひまわりバッグを「ジェネリック」と呼んでいたことをイザオが思い出した。最初に開発されたものと効用がほぼ同じで低価格な後発薬品に喩え、茶化している。イザオにとっては他人事なんだなと直美は冷める。

「ケイティって人が映画に関わってると、なんか問題なわけ?」
「亜子姉さんのバッグをデザインしたのもケイティの可能性が出てきちゃうじゃない?」
「ハラミは関係なくない?」
関係なくはないよと言い返そうとして飲み込んだ。
亜子姉さんのバッグの話をするたび、すれ違う。この感じ、何かに似ていると記憶を辿ったら、「産む、産まない」話だった。話を打ち切ろうと直美が黙り込むと、ソファが軽く沈み、一人分の距離を空けて、イザオが隣に腰を下ろした。
「え、観るの?」と思った。
迷惑ではないが、歓迎でもない。優亜が生まれてから映画館に行かなくなったし、DVDで観るのも思い出せないくらい久しぶりで、ふたりで横に並んで映画を観るという状況が落ち着かない。
ふたりでいるより一人になりたい。
つき合い始めた頃は、逆だった。なんでもシェアしたくなったし、なんでもシェアしていた。
観たい映画があったら、真っ先にイザオの顔が浮かんで、知らせていた。おいしいものを食べたら。いいお店を見つけたら。明るい話題だけではなく違和感も、イザオならどう思うだろう、なんと言うだろうと、それが聞きたくて、イザオをつかまえた。
いつからだろう。自分のところで止めておくほうがラクになったのは。
優亜についての報告と連絡と相談はしているが、それは一緒に子どもを育てる共同体として必要な情報交換であり、「聞いて聞いて!」と袖を引っ張るような、今だけ、あなただけの気持ちをずいぶん後ろに置いてきてしまっている。
イザオがソファに腰を下ろすときに無意識に空けた一人分の幅が、今の夫婦の距離のようにも思えた。
最後に体を重ねたのは、優亜がお腹に入った日だった。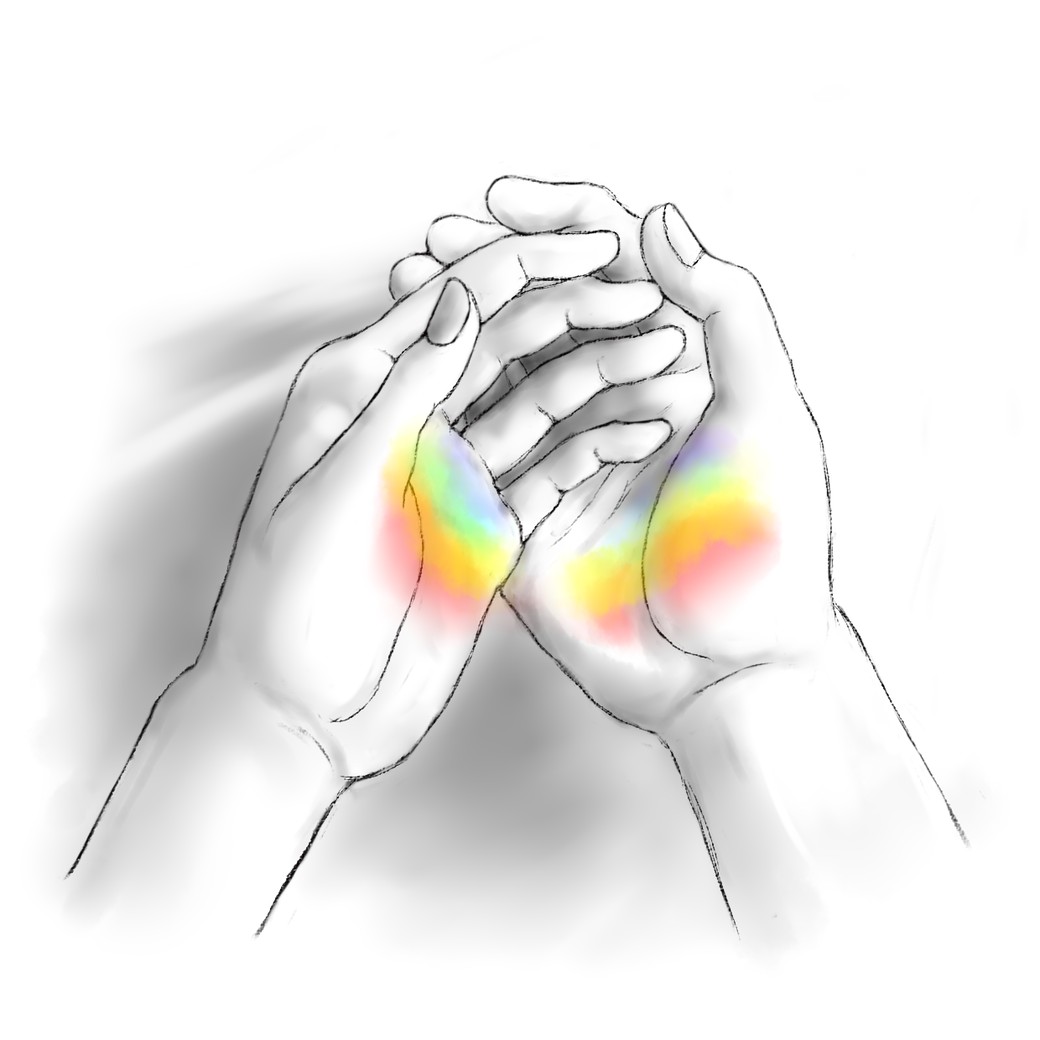
家出したイザオが一週間ぶりに帰って来たあくる朝、手の上に虹が落ちた虹を確かめ合って、仲直りのキスをして、そのまま続けた。このソファで。
最後にキスしたのは、優亜をお腹から出した日だった。
陣痛の痛みを和らげるホルモンが出ると両親学級で言われたのを思い出して、「キスして」と直美から言った。いや、叫んだ。
話の筋がよくわからないままエンドロールがせり上がり、「衣装デザイン協力 ケイティ」のクレジットが目に留まった。イザオも同じものを見ているだろうが、何も言わない。
亜子姉さんのバッグを作った人と、タヌキの思い出の映画の衣装をデザインした人は同じなのか、違うのか。イザオの言う通り、わたしには関係ないのだろうと頭では思う。だけど、巻き込まれている時点で関係している。関係したいわけではないのに、抜け出す方法がわからない。
あの頃と同じだ。
中学受験の結果が母の思い通りにならず、「お母さんの人生返して」と言われた春。母の出す食事を体が受けつけなくなり、やがて何を口に入れても吐き出すようになった。疼く空っぽに何かを詰めなくてはと思い詰め、吐くことがわかっているのに食べものを詰め込んでいた。ぐらつく椅子の脚の下にその場しのぎのダンボールを噛ませるように。
『幸せのしっぽ』に出会った高校生のタヌキは、体重が80キロを超えていたという。吐くか溜め込むかの違いはあるけれど、タヌキも満たされないものを別なもので満たしていた。
そんな話は、イザオにはしない。タヌキの話を聞いて、ますますひまわりバッグの作者とケイティのことを追いかけてしまっていることもイザオは知らない。言ってもわかってもらえないだろうという諦めが、自分のところで止めておくようになった理由かもしれない。それとも分かち合うことをサボるようになったから、わかり合えなくなったのだろうか。
「イカ飯食べたくなっちゃったな」とイザオは感想を言い、立ち上がった。イカ飯なんて出てたっけと広くなったソファで直美は思った。
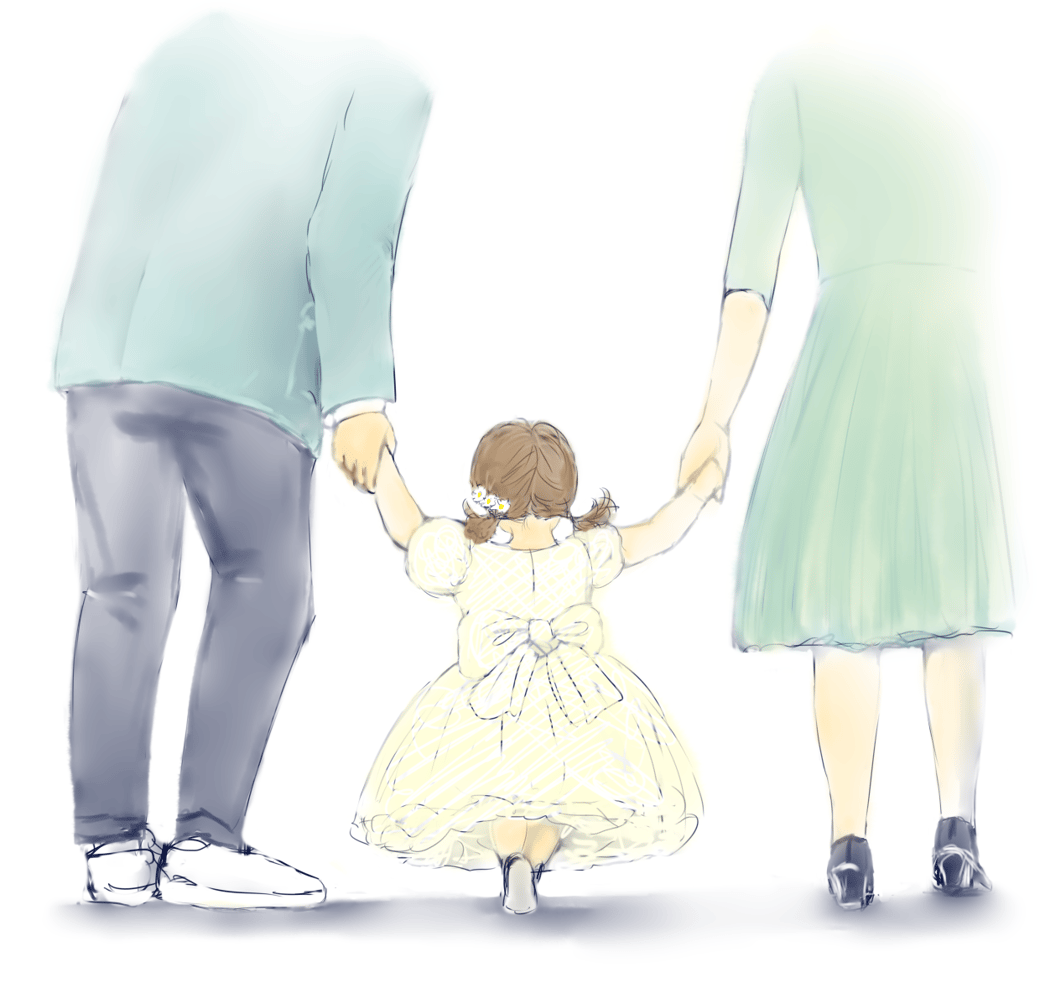
イザオは何も知らない、わかっていないと思っていたから、「スマホ置いて行こっか」と言われて直美は驚いた。
今日はスマホを見ない日にしよう。手元にあると、気になってしまうから。今日の主役の新郎新婦や、目の前の家族そっちのけで、知らなくてもいい他人のアップデートを追いかけてしまうから。ハラミがそうなることを知ってるから。
靴箱の上にスマホを置いたイザオの気持ちが伝わった。
なんだ、気づいてたんだ。
なんでもシェアしなくなったのは、言ってもわからないという後ろ向きな理由だけじゃなかった。わざわざ言葉にしなくても察し合えるから。それだけの時間を重ねてきたから。
同じソファに腰を下ろして、同じ映画を見ていても、頭の中は別々のことを考えている。それでも、同じほうを向いて、同じ時間を過ごして、わかり合えなくても、分かち合う。その先のどこかで、平行線だと思っていたふたりが交わる瞬間が訪れる。
返事の代わりに、直美は黙ってイザオのスマホの隣に自分のスマホを置いた。
スマホを置いて行っても、亜子姉さんのバッグは追いかけてくる。今日、タヌキが着るウェディングドレスには、ひまわりバッグの作者が手を加えている。ひまわりがついているかどうかはわからないけれど。
「どう思う?」の答えをスマホの中に求める代わりに、目の前のドレスを見ればいい。皆の反応を見ればいい。その瞬間に夫婦で立ち会えばいい。
「ママ、はやく」
優亜が手を伸ばしてきた。その手を取り、つなぐ。優亜の反対側の手をイザオが取り、3人が横一列につながる。
自分たちの結婚パーティーの日は、同棲していたアパートから手をつないで会場のレストランに向かったんだっけと直美は思い出す。あのときいなかった優亜がお腹に宿って、生まれて、歩いている。イザオとの間に空いた一人分の幅は優亜の場所なのだと直美は思い直す。
「今日これから行くところ、パパとママが結婚パーティーしたところなんだよ。ごはんがとってもおいしいんだよ」
ひとり増えて、家族が3人になって、思い出の場所で友を祝う。それ以上に大切なことなんて、ない。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第118回 伊澤直美(40)「あの日の花をもう一度」へ。
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!






















































































































































































































































































































































































































































