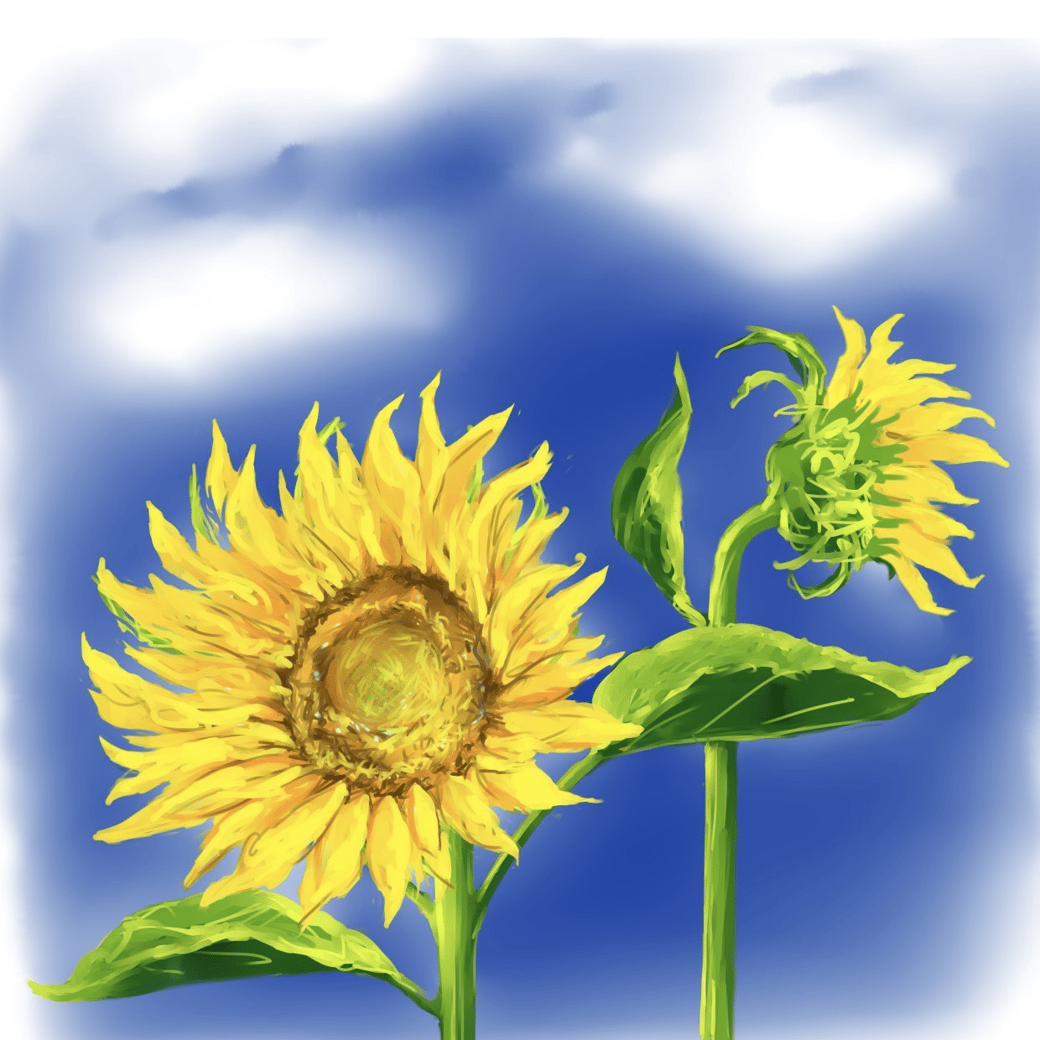第124回 伊澤直美(42)近づきすぎると影が落ちるから
「花が咲いただけ、えらい」
直美の実家の庭のレモンの木の下で、彩子(あやこ)さんはそう言った。
熊木彩子さん。直美が連絡を取り合っていない父のことを、直美よりもよく知っている人。
父が外で会っている女の人がいることに気づいたのは、直美が高校生のときだった。週末になると、父は行き先を告げず、どこかへ出かけた。夜中に寝ぼけた父に「レイコ」と呼ばれたことがあり、それがその女の人の名前なのだと思っていたが、レイコは父が小学生だったときに飼育係で世話をしていたうさぎの名前だった。そのうさぎに彩子さんは似ているらしい。そう父が言ったのだと彩子さんから聞いた。
うさぎのレイコにどう似ているのかは父に直接聞くしかないが、彩子さんは動物に似ているというのが似合うというか違和感がない。自分と他人だけでなく、人間と動物の間にも線を引いてなさそうだし、動物とも普通に話せそうだ。
ケーキを焼きながらお互いの話を聞き合うサークルのようなところで父と彩子さんは出会ったらしい。父が何度か持ち帰ったレモンケーキは、父が隠れて会っている女の人のお手製ではなく、サークル活動の成果物だった。だが、当時は深く聞いてはいけない気がして、何も言わず、食べた。父はどういうつもりでこれを食卓に出すのだろう、母は何をどこまで知っているのだろうと思いながら。
レモンがきついと感じたのは、父の裏切りの端をかじるような背徳感のせいだったかもしれない。誤解だったとわかった今でも、思い出のレモンケーキは酸っぱい。
直美が大学進学を機に一人暮らしを始め、父も家を出た。母の一人暮らしとなった家に今、彩子さんが合鍵を持って通っている。高校生だった直美が疑ったような仲ではなかったとはいえ、父の知り合いだった女性が母と家族のようにつき合っているのは、不思議な関係だ。
そもそも家に居場所のない父がレモンケーキを焼きに出かけなければ、彩子さんと出会うこともなかった。そう考えると、父と彩子さんを引き合わせたのは母とも言える。
父は今、愛媛の今治でレモンを育てている。それも彩子さんが教えてくれた。母が可愛がっていた犬のぴーちゃんが死んでしまった後、この家にレモンの木が届いた。父と母はゆるやかにつながっているらしい。大きくなったその木が作る日陰に、直美と彩子さんが入っている。
この家で初めて会ったとき、「家は、いっときの入れもの」だと彩子さんは言った。だから、人は増えるし、減るし、通り過ぎる。出たり入ったりを繰り返す。

彩子さんと自分の決定的な違いは執着だと直美は思う。手放すことへのためらいがない。
そんな人だから、実家から株分けされたレモンの木がひとつも実を結ばなかったことを直美が報告すると、「花が咲いただけ、えらい」と明るく言い放ったのだった。
「当たりの年とハズレの年があってね。こっちのレモンも今年はほら」
彩子さんは葉っぱだらけのレモンの木を示して、「親子だね」と笑った。
別々の場所で育っているレモンの親木と株分けされた子の木が、同じように花だけで終わった。
「離れていても通じているんですね」と直美が言うと、
「たまたまかもしれないけど」と彩子さんはまた笑って、
「なんだって、つなげようと思えばつながるけど、関係ないっちゃあ関係ないわね」と言った。
「だから、実家から迎えたレモンの木が空振りだったからって、嫌われたって思わなくていいの。ハズレの年の次の年はだいたい当たりになるからね」
「今年は自家製のレモンで作れないですね、レモンケーキ」と直美が言うと、
「口に入っちゃえば、おんなじ」と彩子さんは、カラッと言った。
「彩子さんって、ひなたを見る人なんですね」
「何それ?」
「光が当たっているところだけを見てるっていうか。影が落ちてるところが目に入っていないっていうか。彩子さんの世界には、ひなたしかないのかも」
「どうかな。無責任な立場だから、好きなこと言えるんだと思うよ。ほら、ひとごとって、よそよそしさの距離の分、遠くから眺められるじゃない? 近づきすぎると、自分の影が落ちちゃうから」
彩子さんは深く考えないのではない、深みにはまる前に受け流すのが上手なのだろうと直美は思う。きっと上手になったのだ。レモンケーキを焼きながら誰かに話をこぼしたいものを抱えていた頃だってあったのだ。
家の中から母が優亜をあやす声が聞こえる。何と言っているかは聞き取れないが、母が何か言うたび優亜が笑い声で応じる。文字に起こすと「キャキャキャ」と笑っている。
母の前で最後に笑ったのはいつだろうと直美は記憶を遡る。中学受験で結果を残せなくて、「お母さんの人生返して」と言われた日から、母との間に隔たりができている。コロナ禍に人と人を隔てたアクリル板のようにわかりやすい形と固さと反発性を持ったものではなく、透明の膜のような、ぐにゃりとして、とらえどころのないもの。アクリル板は触ると指紋がつく。引っ掻くと傷が残る。母と直美を隔てる膜のようなものは、汚れも傷も他人からは可視化されず、人知れず澱んでいく。
そんな屈託を何も知らない優亜が無邪気に笑う。わたしの代わりに笑っている。わたしの分も笑っている。

蝉が鳴いている。声がかたまりになって、重みのある熱い空気をふるわせる。
あの日みたいだ。
初めて男の子と二人で出かけることになった中学1年の夏休み。白いリボンのついた麦わら帽子をかぶって、相手を待った。待ち続けた。腕時計を何度も確かめる直美の上で、蝉がうるさく鳴いていた。
「蝉の声を聞くと、思い出しちゃうんです」と彩子さんに打ち明けた。待ち合わせの相手が来なかったのは、直美が行けなくなったと母が勝手に連絡していたからだった。
「母親がやりそうなことね」
彩子さんは、直美の母ではなく、世の中の母親全般を主語にした。
「娘を心配して、じゃなくて、嫉妬っていうか、娘が楽しそうなのが面白くなかったんだと思います。だったら、あっちに電話するんじゃなくて、わたしを引き止めたらいいじゃないですか。普通に送り出して、わたしが帰宅したときも何も言わなくて。ただの嫌がらせですよね?」
「その男の子に言われたの? お母さんから電話があったって」
「2学期が始まる前に、母に言われたんです。なんで今頃言うのって。そういうところも全部、大嫌いでした」
「お母さんにそう言った?」
いえ、と直美が言うと、そっか、と彩子さんも短く言った。言っても無駄だからとは言わなかったが、直美が飲み込んだ言葉を彩子さんはわかっている。その感情を知っている。さっき「母親がやりそうなことだね」と言ったのは、母親全般ではなく、自身の母親のことを指していたのかもしれない。
向かいの家の軒先で、ひまわりが咲いている。
「夏だな」と思ってから、ひまわりを見て、亜子姉さんのバッグよりも先に季節のことを思った自分に驚く。ひまわりバッグのことに囚われて、振り回されていた時期、影を落としていたのは自分だったのだろうか。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第125回 多賀麻希(41)「父を待ちながら」へ。
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!