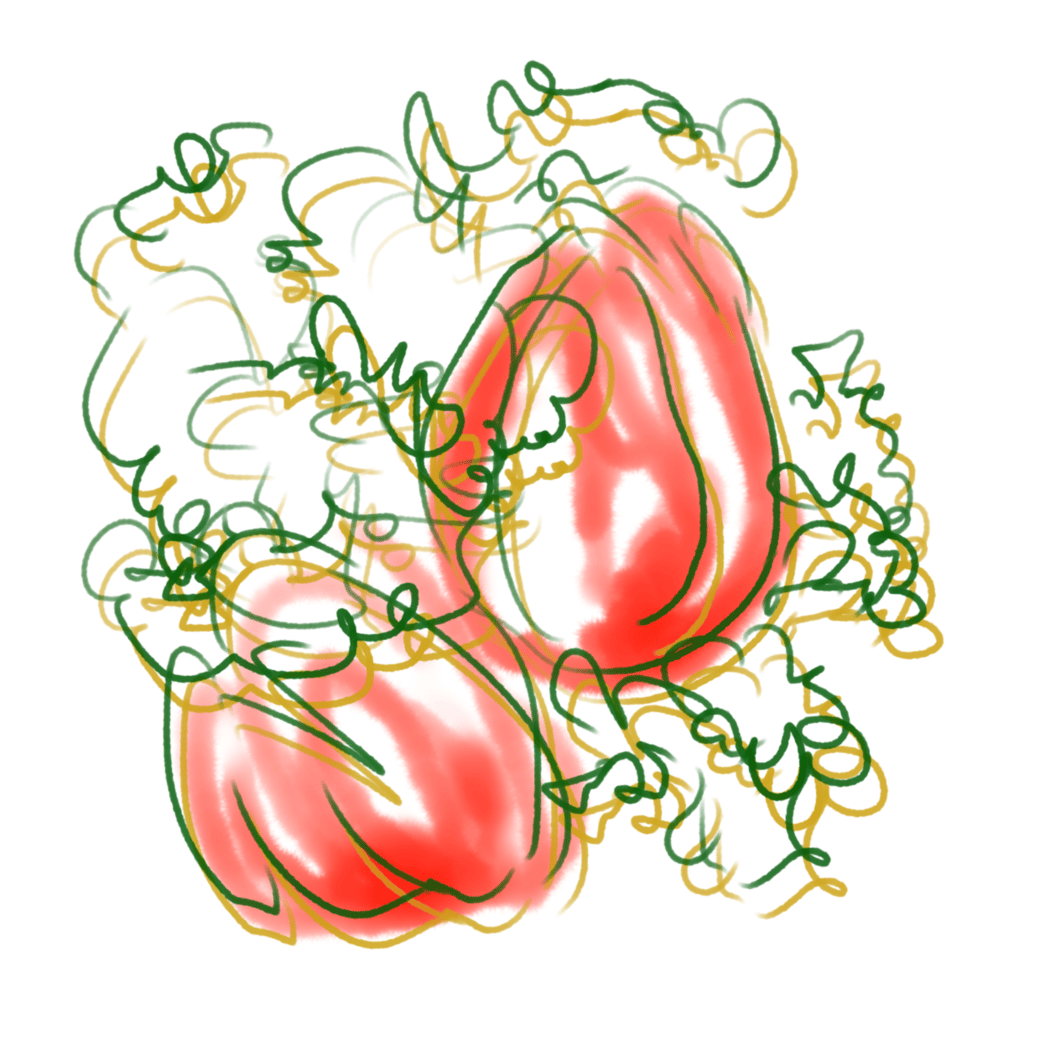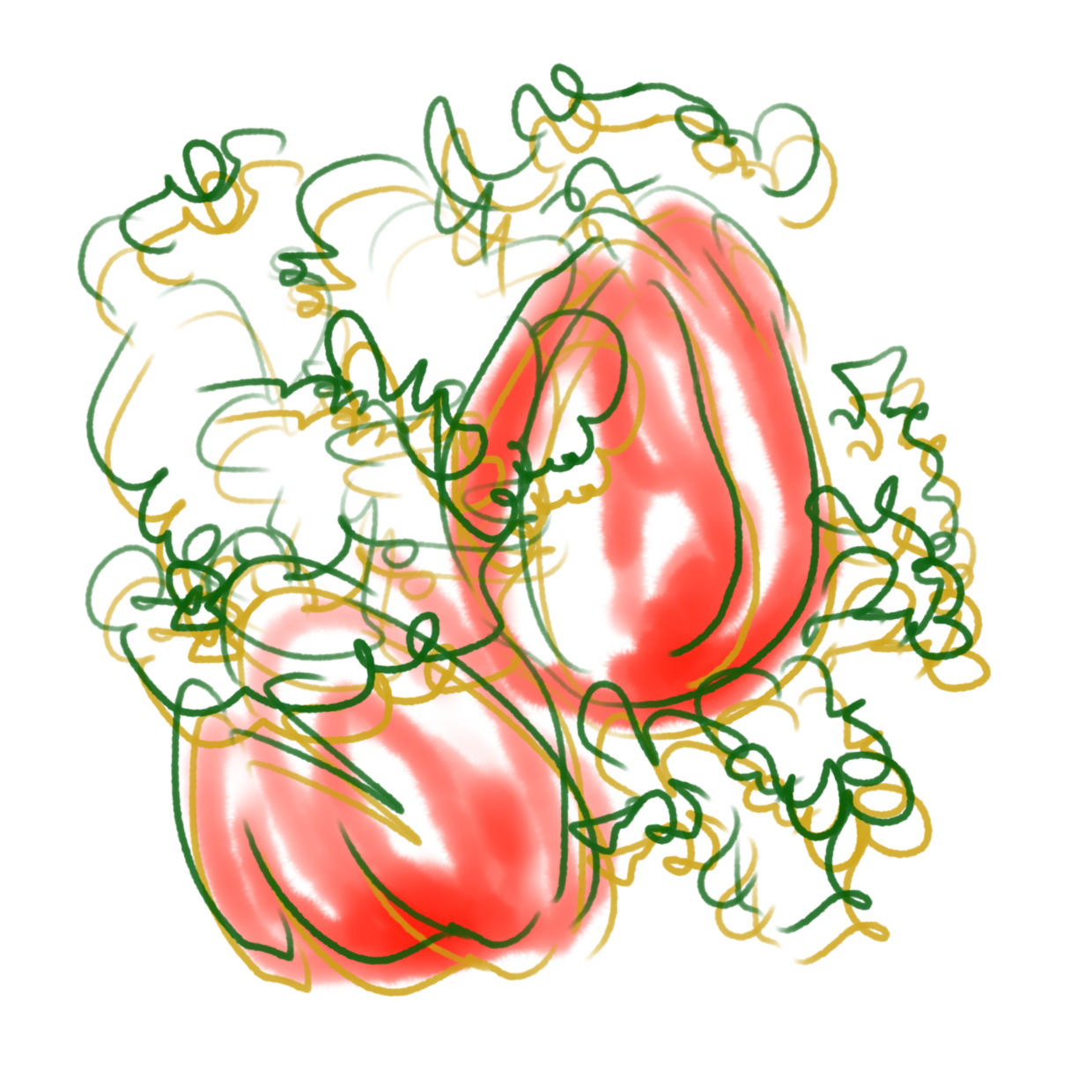第133回 佐藤千佳子(45)母親の旬は過ぎたのか
「オリゾウですか」だっただろうかと千佳子は考える。パート先のレジに商品のバーコードをピ、ピと通しながら。
文香と出かけた帰り、乗り換え駅で電車を降りようとしたときのことを思い出している。小さな女の子を膝に座らせたママから投げかけられた言葉は、発車ベルにかき消され、ほとんど聞き取れなかった。
行き先を聞かれたのだろうか。だが、似た音の駅名や地名は思い当たらない。それとも「オリソウですか」だったのだろうか。でも、席を立った本人に向かって「降りそうですか」と聞くのは不自然だ。
こういうとき、これまでだったら野間さんに聞けた。シフトを終えたバックヤードで。この間こんな親子に出会ってと話し、別れ際の聞き取れなかったメッセージを伝えれば、推理小説の謎を解くように面白がって考えてくれただろう。
あぶくのように浮かんでは消える「ふとした疑問」というものを野間さんが受け止め、打ち返してくれていた。外資系企業出身でアメリカ暮らしの経験もある野間さんは、千佳子のどんな疑問にも「知らなかった」と感心したり、「勉強になった」と感謝したりした。野間さんに聞いて良かったと千佳子も気分が良くなった。
面白がるポイントを見つけ、石ころを光らせられたのは野間さんだからで、誰にでもできることではなかった。そのことに気づいたのは、野間さんがアムステルダムに行ってしまってからだ。
引き受け手のいなくなった疑問は千佳子の中で溜まり、滞っていく。壁際に溜まる埃のように、やり過ごせないボリュームになる。欲しいのは答えではなく、その手前を分かち合える誰かなのだ。答え探しに首を突っ込まなくても、なんだろねと首を傾げてくれるだけでもいい。
野間さんが恋しい。野間さんとパセリにリボンを巻いていた頃が恋しい。ノマリー・アントワネットの庭も恋しい。野間さんの息子さんが世話をしているという庭には今、どんな花が咲いているだろうか。ダンナさんの形見のゴールドクレストは背を伸ばしただろうか。

野間さんの家はスーパーマルフルを挟んで千佳子の家と反対側にある。マルフルからは自転車で10分もかからない。行こうと思えばいつでも行ける距離だが、行ったところでそこに野間さんはいない。帰り道は余計に淋しくなりそうで、様子を見に行けていない。
記憶の中のノマリー・アントワネットの庭が黄金色の光に包まれる。庭の見えるテーブルで野間さんに聞いた話も一緒に飲んだワインもあの部屋で過ごした時間もすべてが遠くに感じられ、千佳子は急に自分が老け込んだような気がして目の前のレジに目をやり、現実にピントを合わせる。バーコードをレジに通す手を動かしながら遠くへ飛んで戻って来れるほど、仕事に慣れたということだ。文香が中学生になったタイミングでパートを始め、文香は今年高校生になった。
やはりソウではなくゾウと濁っていた気がする。オリゾウですか。オに子音がついていたかもしれない。コリゾウですか。ソリゾウですか。トリゾウですか。
「帽子(ぼうし)」と「雄牛(おうし)」、「画家(がか)」と「馬鹿(ばか)」、「おみかん」と「モヒカン」。子音をはっきり発音しないと、母音が同じ他の単語と聞き間違えられてしまう。
「大きな『絵』がありました」が「大きな『へ』がありました」と聞こえ、クラス中に笑われて以来、人前で話すのがますます苦手になった。文香が小学校に入り、母親たちによる読み聞かせグループに誘われたときはもちろん尻込んだが、声をかけてくれた人との関係にヒビを入れるほうが怖くて引き受けた。そこで居場所を見つけるのは、教室で子どもたちに絵本を読み聞かせるよりも思い切りが必要なことだった。
頑張ったんだよ、ママ。
誰もほめてくれないから、自分で自分をほめる。
あの女の子のママがなんと言っていたかが気になるのは、あの母娘が気になっているからだ。80センチぐらいかなと思ったのは、文香が着ていたワンピースのサイズだった。

ママの膝の上でおとなしくしているけれど好奇心旺盛そうな目はよく動いていて、文香が小さい頃に似ていた。文香に似合ったワンピースは、あの子にも似合いそうだと思った。
わが子の小さい頃を重ねてしまったのは、ただのノスタルジーなのかもしれない。「ママ、ママ」と全身で頼られていたあの頃を、同じワンピースを別の子に着せて蘇らせたいだけなのかもしれない。
文香が高校に上がり、親の出番はすっかりなくなった。次は大学受験が控えているが、文香は自分で学校を探し、その学校に入るために必要なことを見つけ、揃えるだろう。高校に入るときがそうだったように。千佳子はいろんな種類のお茶を出しただけだった。元々手のかからない子だったが、その手からも巣立とうとしている。
文香が自転車に乗れなかったとき、千佳子は練習につき合った。後ろの荷台を支えていた両手をそろそろかなと離したら、文香はするすると数十メートル進んだ。
なんだ、とっくに一人で乗れていたんだ。
ぐらつくことなく、危なっかしさのない運転だった。文香はブレーキをかけて自転車を止め、片足ずつ地面につけて、あっけに取られている千佳子を振り返った。
あのときのことを思い出す。自転車だけでなく、親の手はとっくに必要なくなっているのに、親が手を離せないでいることは他にもあるのだろう。そうなるまでにわが子を育てたのは他でもない自分なのだが。
必要とされる時間は思った以上に短い。母親という役割に旬があるとしたら、その時期はもう過ぎてしまったのではないか。四季で言うと、小学校に上がるまでが春で、中学校卒業までが夏で、今は花が終わって実が膨らみ、葉っぱが枯れていく秋辺りだろうか。
まだ40代。こんなに早く、こんな気持ちになるとは思わなかった。
「ママは何になりたいの?」と中学1年生の文香に言われたときは、何かにならなくてはと焦った。今あるのは焦りではなく陰りだ。今日はこれをしようという張り合いがなくなっている。空気の抜けたタイヤ状態だ。
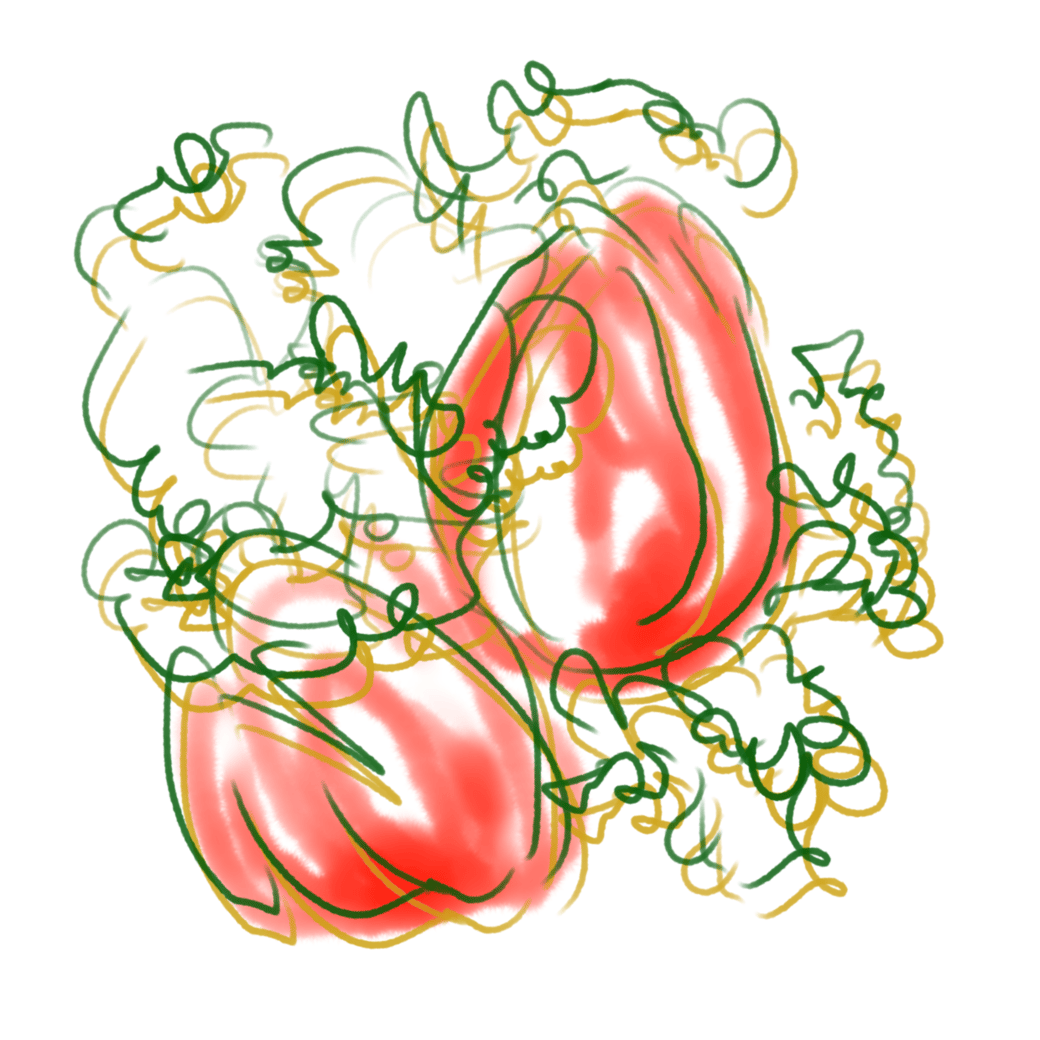
たまたま電車で向かいの席に居合わせた親子ともう一度会う偶然はないだろう。けれど、あの聞き取れなかった質問の中に、再び会うはずのないふたりを繋ぎ止めるヒントがあるのではないか。80センチサイズの女の子のママは、千佳子に何か聞きたいことがあったのだ。
ノリゾウですか。モリゾウですか。
アパレルブランドの名前かもしれない。そう言えば、あのときチューリップのバッグを持っていた。そのブランド名を尋ねたのだろうか。
野間さんにチューリップバッグを贈られたとき、ショップカードを見せてもらったことを千佳子は思い出す。四つ葉のクローバーの刺繍とショップの名前とQRコードが印刷されていた。あのカードは野間さんに返したのだったか、持ち帰ったのだったか。
morizoという字面が蘇った。シフトを終え、帰り支度をするのももどかしくスマホを開き、《morizo チューリップバッグ》で検索すると、見覚えのある名前がヒットした。
makimakimorizo
これだ。公式サイトらしきページを開くと、緑の糸を通した針を白い布に留めたビジュアルに「準備中」の文字が小さくあしらわれていた。
検索結果に挙がった他のページを見てみると、舞台公演のページがあった。衣装で関わった作品だろうかと一応開いてみたが、チラシの写真の若い男女が着ているのは量販店で売っていそうな上下だった。これは違うなとページを閉じかけた手が止まった。
作・演出を担当した劇団の主宰者の挨拶が写真入りで出ていた。
髪は後ろで束ねていないし、千佳子が知っている彼より目尻も口元も5ミリほど引き上がって見え、印象が随分違うが、彼だとわかった。彼が担当する講座を何度も再生して見ている。ひとコマ45分、全部で百を超える講座を。
「パセリ先生」
思わずスマホ画面に向かって呼びかけた。
次の物語、連載小説『漂うわたし』第134回 佐藤千佳子(46)「たちまち色づいたモノクローム」へ。
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。