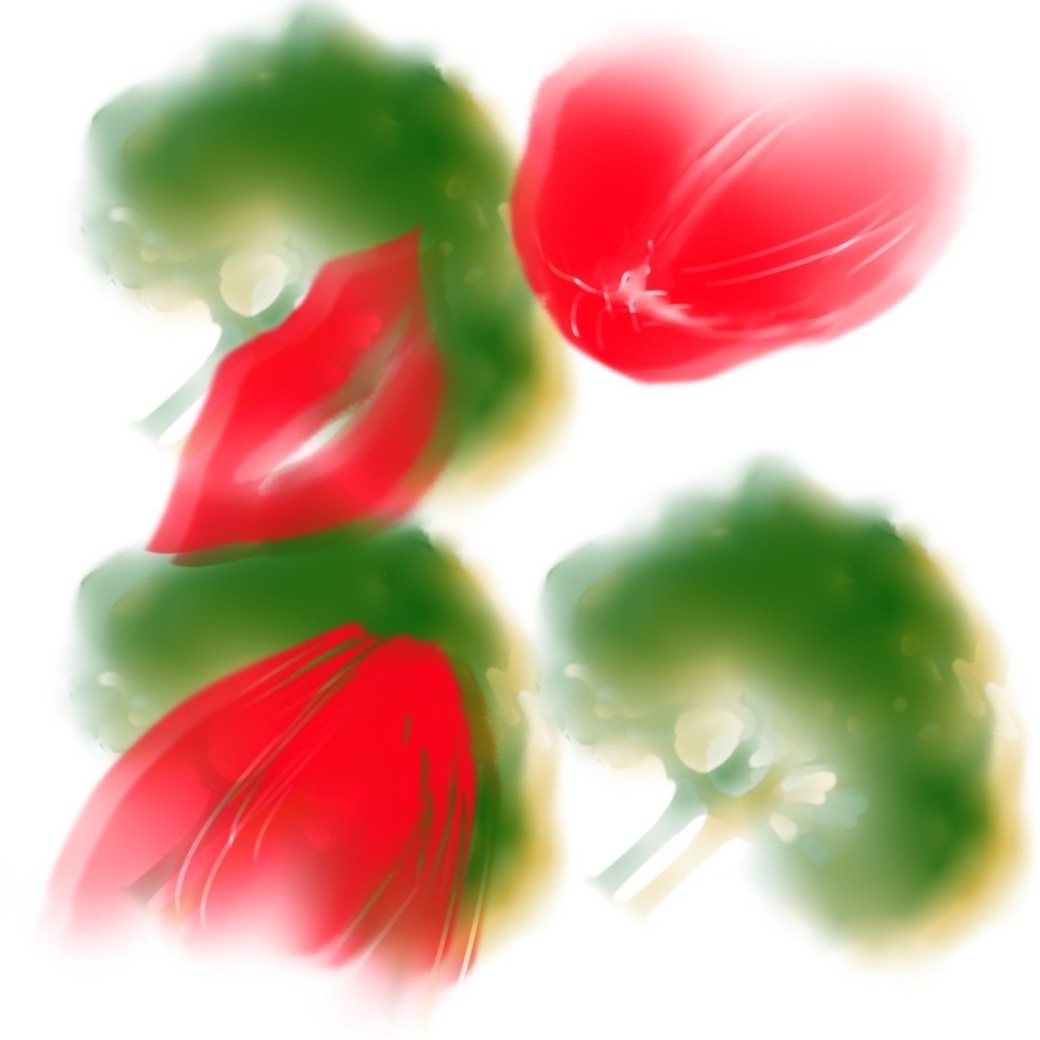第139回 佐藤千佳子(47)真夜中の逢い引き
手と手を合わせ、男性と見つめ合う。身長差があるので、千佳子が見上げる格好になる。
まるで『たとえこの雪が溶けてしまうとしても』の公演案内のイラストの構図だと千佳子は思い、のぼせているのに冷静な自分に気づく。夫も娘もいる身であり、いけない恋の入口に立っている自覚もあるが、背徳感はブレーキにはならない。むしろアクセルになっている。
自分の瞳が潤んでいるのを感じる。唇も潤んでいる。口の奥も、喉も、体のもっと深いところも細胞単位で潤んでいる。弾んでいる。
ネット検索でチューリップバッグのブランド「makimakimorizo」にたどり着いた流れで見つけた「モリゾウ」という名の演劇人は、パセリ先生だった。作と演出を手がけ、主演した舞台『たとえこの雪が溶けてしまうとしても』の公演案内のイラストの男性は、彼がモデルだろう。長身で長髪。公演当時の13年前から雰囲気は変わっていない。
主演の男女のポーズを現在のパセリ先生と千佳子が取っている。
「Even if」とパセリ先生が言う。
「Even if」と千佳子は繰り返す。
「たとえ〜しても」と頭の中で日本語に直し、パセリ先生は『たとえこの雪が溶けてしまうとしても』を英語で言おうとしているのだと気づく。
「Even if」ともう一度パセリ先生が言う。
「Even if」ともう一度千佳子は繰り返す。
なぜかパセリ先生はその先を続けない。言わなくても、ふたりにはわかっていることだから。それとも、言葉にしてしまうと、おののきが伝わってしまうから。
わたしたちにとって、この雪は、この恋のことだから。
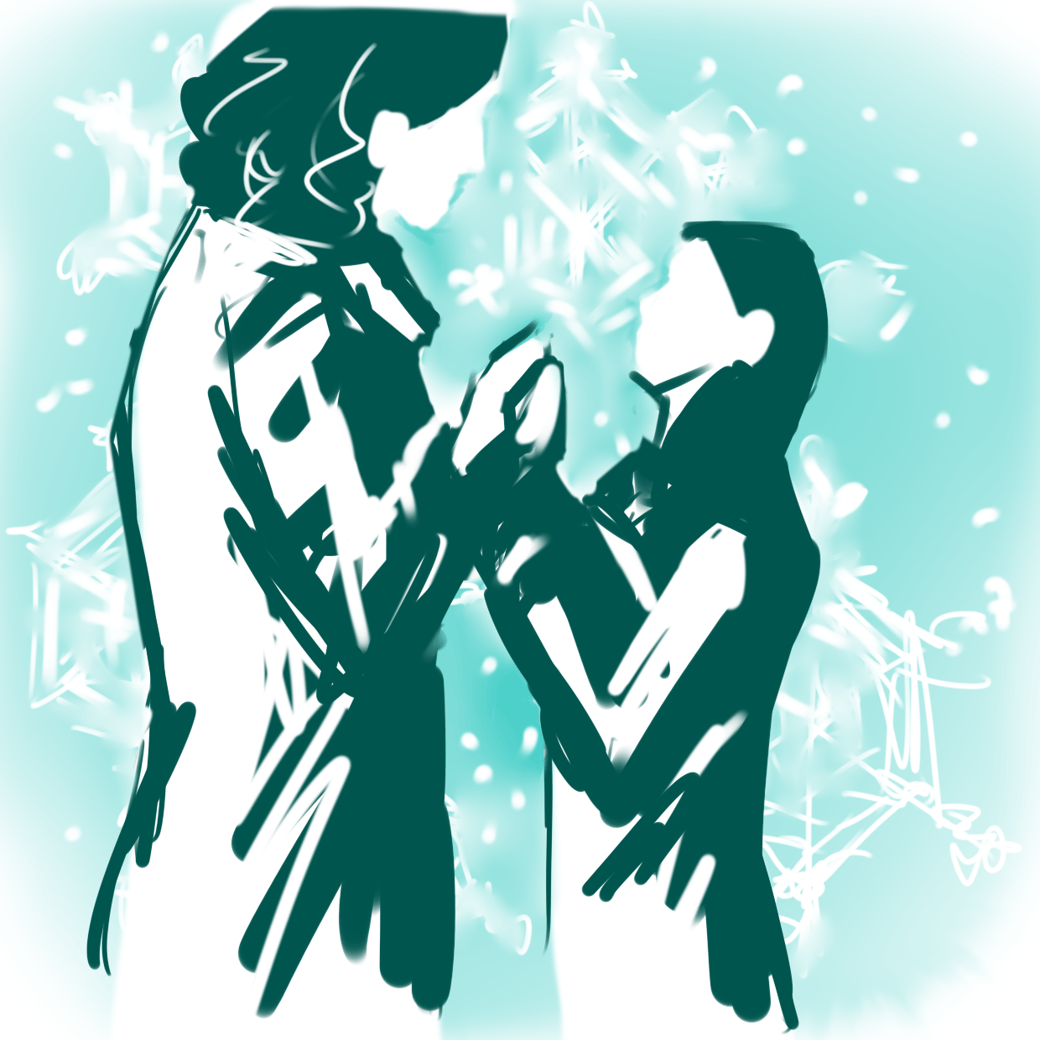
パセリ先生の顔が近づく。蕾が開くようにゆったりと、もったいぶるようなスピードで。
あと10センチ、9センチ、8センチ、7センチ……。
唇と唇が触れそうなところまで来たとき、「ねえ」と声がした。パセリ先生の唇からではなかった。安定感のある重低音な声とは対照的な、細く遠慮がちな声。
夫だ。
「ねえ」
もう一度呼ばれた。
「電話、じゃない?」
千佳子が目を覚ますと、そこは夫婦の寝室で、一人分ほどの間を空けた隣には夫がいた。掛け毛布越しに見える体の線は細く薄い。
ベッド脇の棚の上でスマホが鳴っていた。千佳子より先に夫を起こしたその音は、メッセンジャーのビデオ通話の呼び出し音だ。
「こんな時間に誰から?」
スマホを手に取ると、0時47分という時刻と発信者の野間さんの名前が目に飛び込んだ。「こんな時間に」と「誰から」の謎が同時に解けた。
「野間さんだ」とつぶやくと、「ああ」と気の抜けた夫の声が返ってきた。夫も「こんな時間に誰から?」と身構えていて、その緊張を解かれたらしい。真夜中の着信が日本からだと緊急事態を疑うが、アムステルダムからであれば、時差で昼と夜が逆転しているだけだと思える。
通話ボタンを押し、「野間さん?」と応じると、返事がなかった。何度か呼びかけてみたが、やはり返事はない。
「間違えて、かかっちゃったのかな」と千佳子が言うと、
「起こさなくても良かったね」と夫が申し訳なさそうに言う。
「ううん。先に起こしたのは野間さんだから」
冗談めかして明るく答えたつもりだったが、声に未練が混じっていた。
起こされたくはなかった。
眠っていたかったのではない。もう少し夢を見ていたかった。蕾が開くところを見届けたかった。

「静かだね」と夫が言う。
「え?」と思わず聞き返した千佳子の声が裏返る。
真夜中の逢い引きについて説明しない沈黙をとがめられたように聞こえたのだった。パセリ先生と会っていたのは夢の中の出来事なのに、夢の外から呼びかけた夫に現場を見られていて、事情を聞かれているように錯覚している。寝ぼけているのか、余韻からまだ覚めていないのか。
静かだと夫が言ったのはスマホの向こうの野間さんのことだと気づき、現実にピントが合ってくる。耳を澄ますと、ザザ、ザザと微かなざわめきが聞こえる。野間さんは外を歩いているのだろうか。けれど、車の音がまったく聞こえない。
盗み聞きしているような後ろめたさを覚え、通話を切ろうとした指が止まった。
今、夫とふたりきりになってしまうのは気まずい。
「野間さんが気づくかもしれないから」
そう言って、起こした頭を夫の隣に再び並べ、夫との間にスマホを置いた。
何も知らない野間さんに、間にいてもらおう。
コホンと小さな咳払いが聞こえた。音がくぐもって聞こえる。少し遅れて、もう一度。先ほどと距離感は変わらない。咳払いの主は野間さんのようだ。野間さんのスマホはバッグの中だろうか。
もしかしたらチューリップバッグ。
赤のイメージとともにパセリ先生との逢い引きが脳内で再生される。チューリップバッグみたいな真っ赤な口紅に彩られた唇を潤ませ、パセリ先生を待ち受けていた。
パセリ先生の体温と息づかいが生々しく蘇る。今、夫がこちらを見たら、頬が火照っていることに気づかれてしまう。スマホの光の照り返しだと思ってもらえるだろうか。さっきは夢の中だったが、夢から覚めた後に隣に夫がいるベッドで振り返る逢い引きは、より罪深い。
でも、これは浮気なのだろうか。

たしかに夫の顔よりもパセリ先生の顔を見ている。夫の声よりもパセリ先生の声を聞いている。けれど、それは千佳子からの一方通行で、相手はこちらの顔も声も知らない。存在すら知らない。
学習動画を何百時間視聴しようと、積み重ねられるのは思い出ではなく単語や文法だ。知識をつなげて学習の理解は深められても、互いのことはわからないままで距離は縮まらない。
だから、演劇人モリゾウという別な顔を見つけてうれしくなった。手がけた舞台のあらすじや演出家の言葉を読み、これまで知らなかったパセリ先生を知ることができたが、片想い以前の片側通行の道幅を広げたに過ぎない。
これまでに何百時間も講義を見てきたのに、パセリ先生が夢に現れたことはなかった。初登場でいきなり手を取り合い見つめ合うという急展開は『たとえこの雪が溶けてしまうとしても』の公演案内のイラストの名残だが、あんな夢を見た心当たりがもうひとつあった。
「ママー、賞味期限切れてるよー」
スーパーのパートから帰宅し、夕飯の支度をしていると、高校から帰ってきた娘の文香が「お腹空いたー」と玄関から冷蔵庫に直行してドアを開け、納豆とミニパックの豆腐を見つけた。豆腐に納豆をかけて食べる「納豆腐」が夕飯まで待てない文香のおやつだが、納豆の賞味期限が過ぎていることに気づき、千佳子にパッケージを見せたのだった。
「一日ぐらい過ぎたって大丈夫。賞味期限はおいしく食べられる期限ってことなんだから」
何気なく答えた自分の言葉にドキリとして、トマトを切る手が止まった。
40代半ば。わたしはまだ賞味期限内なのだろうか。
次回12月9日に佐藤千佳子(48)を公開予定です。
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!