
第140回 佐藤千佳子(48) わたしの賞味期限問題
「夢は欲望の充足」だと短大の1年目に取った心理学の講義で教わった。昼間の思い残しを夢という形で埋め合わせるのだと。読み残した小説の続きを読むように。塗り残した塗り絵に色をつけるように。
これまでパセリ先生が夢に現れなかったのは、講義を何百時間も観てきたのに、ではなく、何百時間も観てきたから、なのだろう。起きている間に十分、満たされていたということだ。画面越しの一方通行ではあるけれど。
夫と娘が家を出て一人になった朝の時間、家事を進めながら講義動画を見る。休んだり再開したりの繰り返しだが、ネット検索で演劇人モリゾウという別な顔を知って以来、何度目かのパセリ先生ブームが来て、朝のルーティンに返り咲いた。
家事の手を動かしながらなので、耳だけ傾けていることが多い。パセリ先生の声が好きなのだ。その声で届けられる英語の発音が耳に心地良くなじみ、いつまでも聴いていられる。
パセリ先生の声を生で聴いてみたいと思ったことはあるが、オンラインの先生の講義を対面で受けてみたいという一受講生としての気持ちで、息のかかる距離で手を取り合って見つめ合いたいという願望はなかった。
あんな夢を見たのは、「賞味期限」が引っかかっていたからだ。そこに『いつかこの雪が溶けてしまうとしても』の公演案内のイラストの残像が合わさった。
野間さんがスマホを鳴らさなければ、その音で目を覚ました夫に起こされなければ、あのまま続けていた。
どこまで?
逢い引きの続きを想像して、千佳子は体の芯が熱くなる。
夫に抱いたことのないときめきを覚えていた。夢の中で。そして、今も。
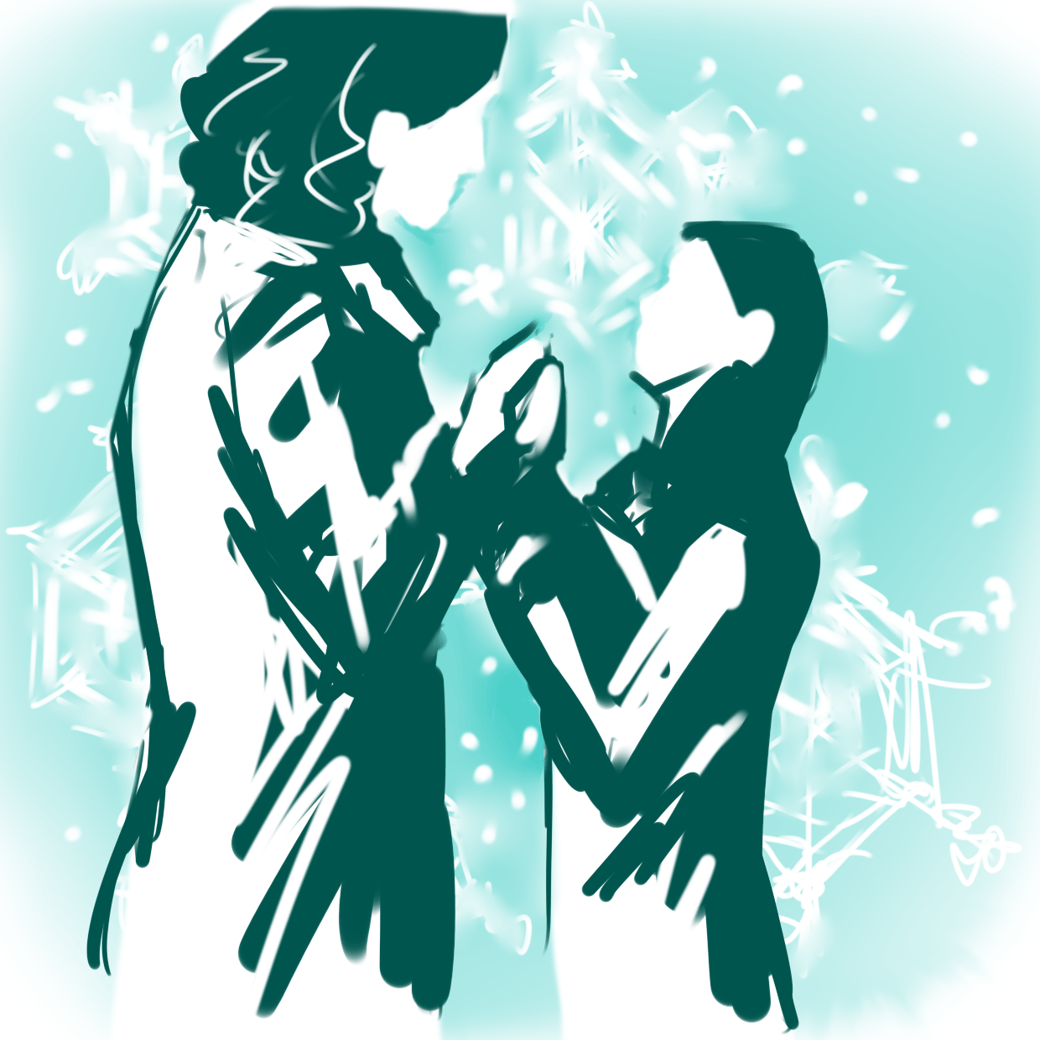
「鳥が鳴いてる」
頭の横に置いたスマホを挟んだ向こう側で夫がのどかなことを言う。夫に起こされてから10分ほど経っている。逢い引きの現場を目撃されたのは夢で、夫は何も見ていない。
「まだ起きてる?」
「アムステルダムの音を聞いてる」
その言い方が知的で詩的で、この人は自分よりはるかに教養のある人だったと千佳子は思い出す。野間さんと出会って少し詳しくなった植物の名前も、大学で食品工学の研究をしている夫のほうが詳しい。パセリが古代ローマ時代から使われていたハーブだと教えてくれたのも夫だ。
「この声、アヒルかな」
「犬も鳴いてない? 森の中みたい」
ベッドの中でこんな他愛のない会話を交わすのはいつぶりだろう。
体の交わりは、とっくに切れている。
愛されている喜びにうち震えたことも、心を奪われるような快楽を感じたこともなかった。モニター画面で見ると眠気を誘われるほど運動能力が低い夫の精子たちのどれかが卵子にたどり着き、結びつくことを願った。たったひとつでいい、そのひとつが生命となって宿ることを祈った。
夫の顔など見ていなかったし、甘いささやきも必要なかった。真面目な夫も、ひたむきに任務に励んでいた。
慎重に、息を詰めて。そこにあるのは責任感と団結心。
あるとき行為の最中に運動会のスプーン競走が思い浮かんだ。バトン代わりのピンポン玉をのせたスプーンを運ぶリレー。次の走者のスプーンにピンポン玉を受け渡すときが一番緊張した。落としてしまうとそこで失格になるので、渡すほうも受け取るほうも真剣だった。
わたしが今、夫としていることはスプーン競走だ。
頭の中で「天国と地獄」の急き立てるようなメロディが鳴り出した。その音と夫の規則正しい動きが妙に合っていた。こみ上げた笑いをこらえきれず吹き出すと、不具合を指摘されたかのように夫が動きを止めた。
「ごめんなさい。そうじゃなくて。運動会を思い出しちゃって……」
何も言わないほうがいいのに何か言わないと落ち着かず、口から出た言葉には笑いが混じっていて、気まずさを煮詰めた。夫は戸惑った表情を浮かべ、表情以上に正直な性器をしぼませた。
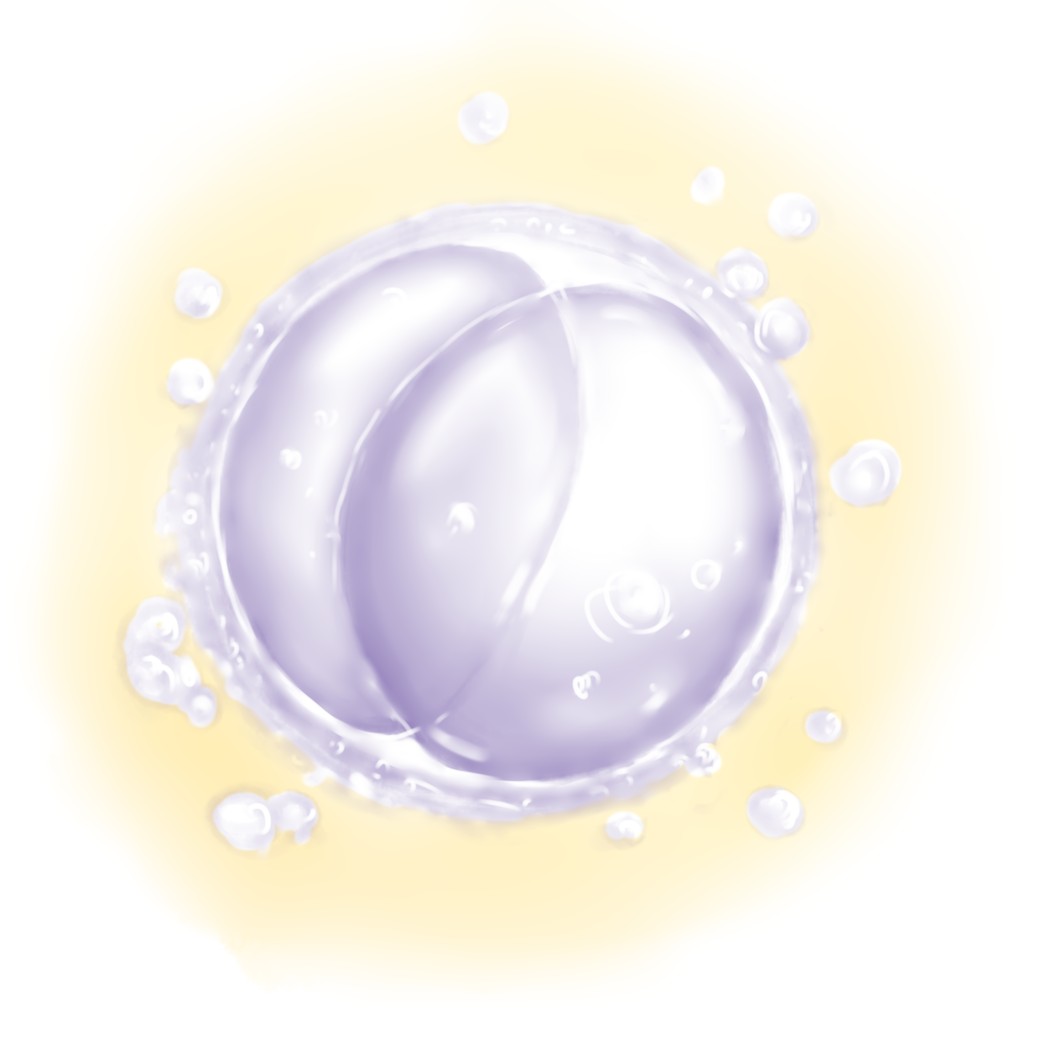
娘がお腹に入った日が、夫と交わりを持った最後だ。
娘の文香の誕生日が巡ってくるたび、夫婦の営みの不在を計算した。年齢プラス9か月。文香が3歳になったときは、オリンピック1回分空いたのかとしみじみした。幼稚園で同じクラスのママから2人目、3人目の報告を聞くと、あの人はまだ営みが続いているのかと動揺し、うちはとっくになくなっているのにと焦りを覚えた。
うらやましいというのとは違う。人にはあるものが自分にはないという引き算が、取りっぱぐれ感を抱かせるのだ。特に、自分より性的に魅力が薄いと思っている人が、自分より性的に満たされていることを知ると、なんであの人がと屈折したひがみを覚えてしまう。そんな自分に疲れた。
交わることが役割を終えたのだと自分に言い聞かせたが、時間を置くと顔を出すしつこい吹き出物のように未練の芯が残っていた。ようやくママ友の懐妊報告を聞くことがなくなり、よその夫婦の事情に胸をざわつかせることがなくなった頃、夫が思い出したように手をのばしてきた。
手が当たることはあっても意思を持って千佳子に触れてくることはなかったのだが、その夜、夫の手は、はっきりと目的に向かって千佳子の体を這ってきた。
4年前、文香が小学校の修学旅行に出かけた夜だった。あまりに久しぶりで、あまりに突然で、夫にそういう衝動がまだあったのかと驚いた。
咄嗟に頭をかすめたのはムダ毛のことだった。訪ねる人がいなくなり、散らかり放題になっていた部屋に、何の前触れもなく客がやって来た。ドアを開けるわけにはいかない。
「ごめんなさい。今日は……」
夫は何も言わず、熱を帯びた手を引き上げた。
次の夜は受け入れ体勢を整えていたが、夫は手をのばして来なかった。あれは夢だったのか、寝ぼけていただけなのか。その次も、それからも。待つことをやめ、再びムダ毛を伸ばすようになった。
足りなかったのはパセリ先生ではない。ときめきだった。自分はまだ賞味期限が切れていないことを確かめたかった。誰も訪ねて来ない部屋を荒れるに任せてしまうのは、やっぱりわびしい。夫が訪ねて来ないなら、誰か他に、会いに来てくれる人はいないだろうか。
いくつになっても求められたい気持ちはあるのだと千佳子は自覚する。ネットで出会った相手との恋愛を楽しむ同年代の主婦たちは遠い世界の人たちではなく、今の自分の延長線上にあるのだ。
そう言えば、夢の中ではムダ毛のことを気にしていなかった。賞味態勢を整えて、逢い引きの場所に向かったのだろう。
性的な関係を持つことを「食う」「食われる」などど言い表すのは、盛りのついた男子学生のようで品がないと若い頃は思っていたが、今の千佳子には自分を食べものに喩えるのがしっくり来る。

「Even if」と千佳子は呟き、そこで止まる。英語が続かない。夢の中でパセリ先生が「Even if」で止まった理由がわかった。千佳子の翻訳が追いつかなかったのだ。
「この雪」は「this snow」だろうか。「the snow」だろうか。それとも「our snow」。わたしたちの雪。雪のように儚く溶けた、真夜中の逢い引き。
いつの間にか鳥の声が聞こえなくなっていた。
スマホを確かめると「制限時間」の表示が出ている。夜更かしをしないよう、24時以降はアプリの使用制限をかけている。メッセンジャーからの通話は24時で自動的に切れたらしい。
アムステルダムの音と入れ替わりに、隣で夫が寝息を立てている。
夫の髪はますます薄くなり、白髪が混じっている。千佳子の6つ上の51歳だが、50代には見えない。唇も薄く、カサついている。かつて、この唇とキスをしたことがあった。布団の下の体と肌を合わせ、交わったことがあった。その歴史があって、文香を授かったのだと遺跡を見るような思いで夫の寝顔を見る。ときめきとは違う温もりが体を穏やかに満たしていく。
瞼が重くなってきた。スマホを元あった棚の上に戻し、千佳子は目を閉じる。
これから見る夢に、パセリ先生は、きっと出て来ない。
次回12月16日に伊澤直美(47)を公開予定です。
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!






















































































































































































































































































































































































































































