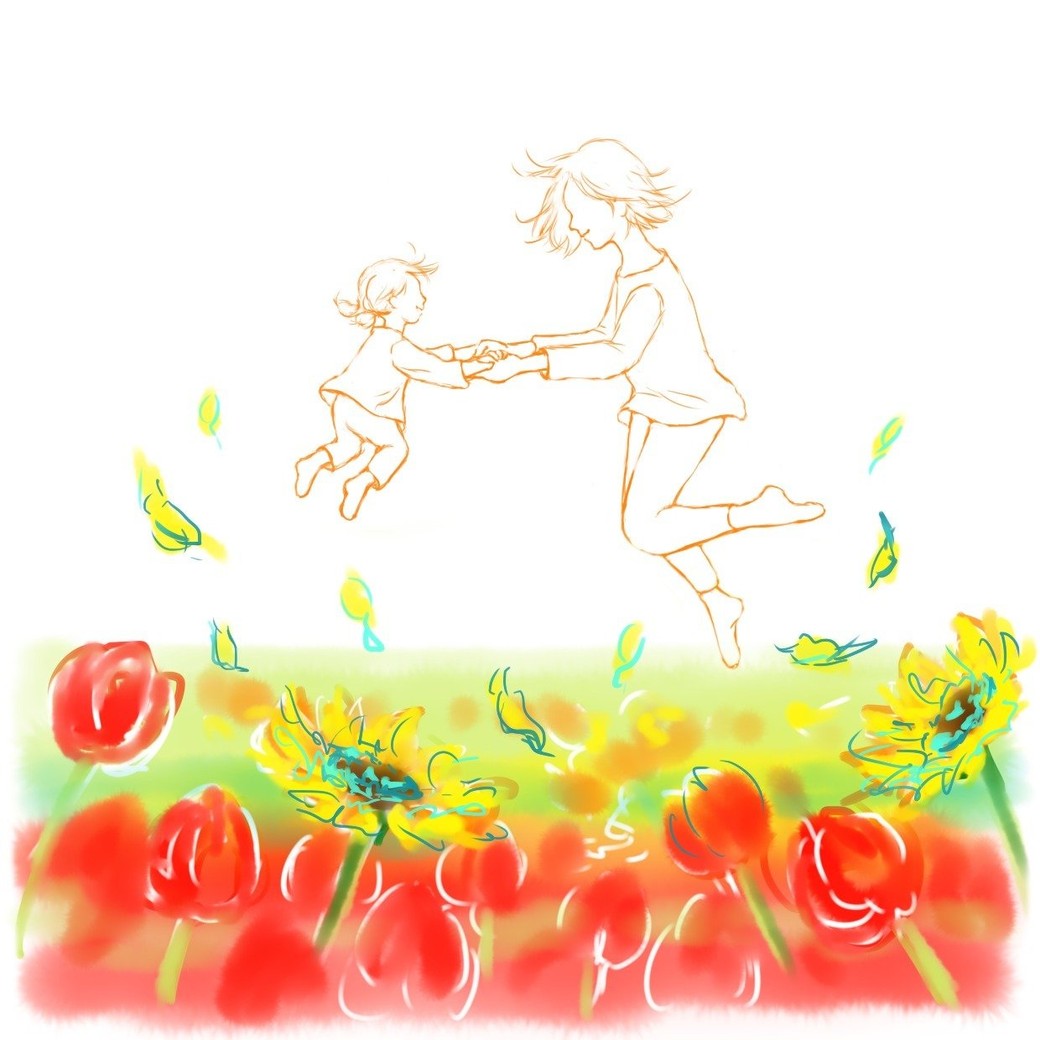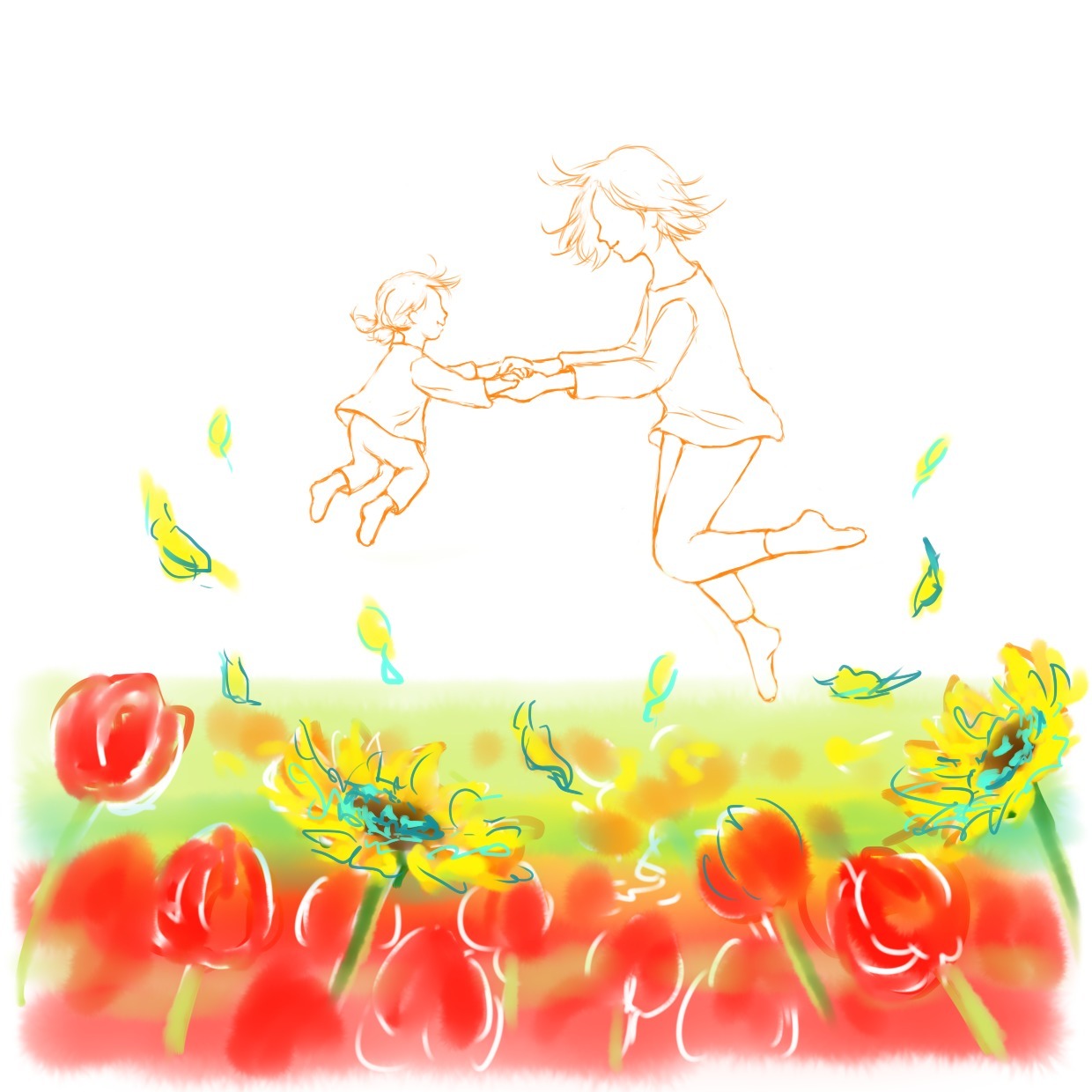第148回 伊澤直美(50)大人は子どもで子どもは大人で
寝息を立てる優亜の顔をじっと見る。直美側にある左の耳の上に小さな出っ張りがある。
気づいたのは、産んだあくる朝だった。シャワーを浴びに行っている間に、まだ名前もつけていない赤ちゃんが消えていた。大騒ぎして探し回ったら、大人のベッドの下の隙間に入り込んでいた。
かかとで床を蹴って後ろ向きに進んだのだ。生後1日の赤ちゃんが。
無事を確かめ、抱き上げたとき、耳の上のイボのような出っ張りに気づいた。いなくなったらいなくなったで心配して、あればあったで心配になり、親というのは心配し続ける生き物なのだと自覚した。
産婦人科の先生に「これ何ですか?」と聞くと、「フクジです」と答えが返ってきた。音に漢字がついて来ず、「フクジ?」と聞き返すと、「副音声の副に耳」と先生は字解きし、珍しいものでも悪いものでもないと教えてくれた。
「取ることもできますが、この子が大きくなって気になるって言ったら、そのときにどうするか考えてもいいと思いますよ」
白髪を染めずにグレイヘアにしている先生らしい大らかな答えとともに「こんな小さな出っ張りの心配ができるのは、他に大きな心配がないってこと」と言われたのが懐かしい。
優亜を挟んだ向こう側、川の字の一画目の位置で眠っていたイザオが目を覚まし、寝ぼけ眼と目が合った。
「起きた?」と直美が言うのと、「起きてた?」とイザオが言うのが同時だった。
「優亜、息してる?」
「え? なんで?」
「ハラミ、よく夜中に確かめたから。手をこうやって」
イザオが体をこちら側にひねり、優亜の顔の上に右手をかざした。
「ああ。やってた」
息をしている。生きている。そのことを何度も確かめた。息をしているのが当たり前になって、確かめなくなった。
大きな病気をすることもなく、流行りのウイルスにつかまることもなく、手がかからないことに慣れていた。甘えていた。だから、トマトのサンタをおもちゃにされてあんなに動揺したのだ。
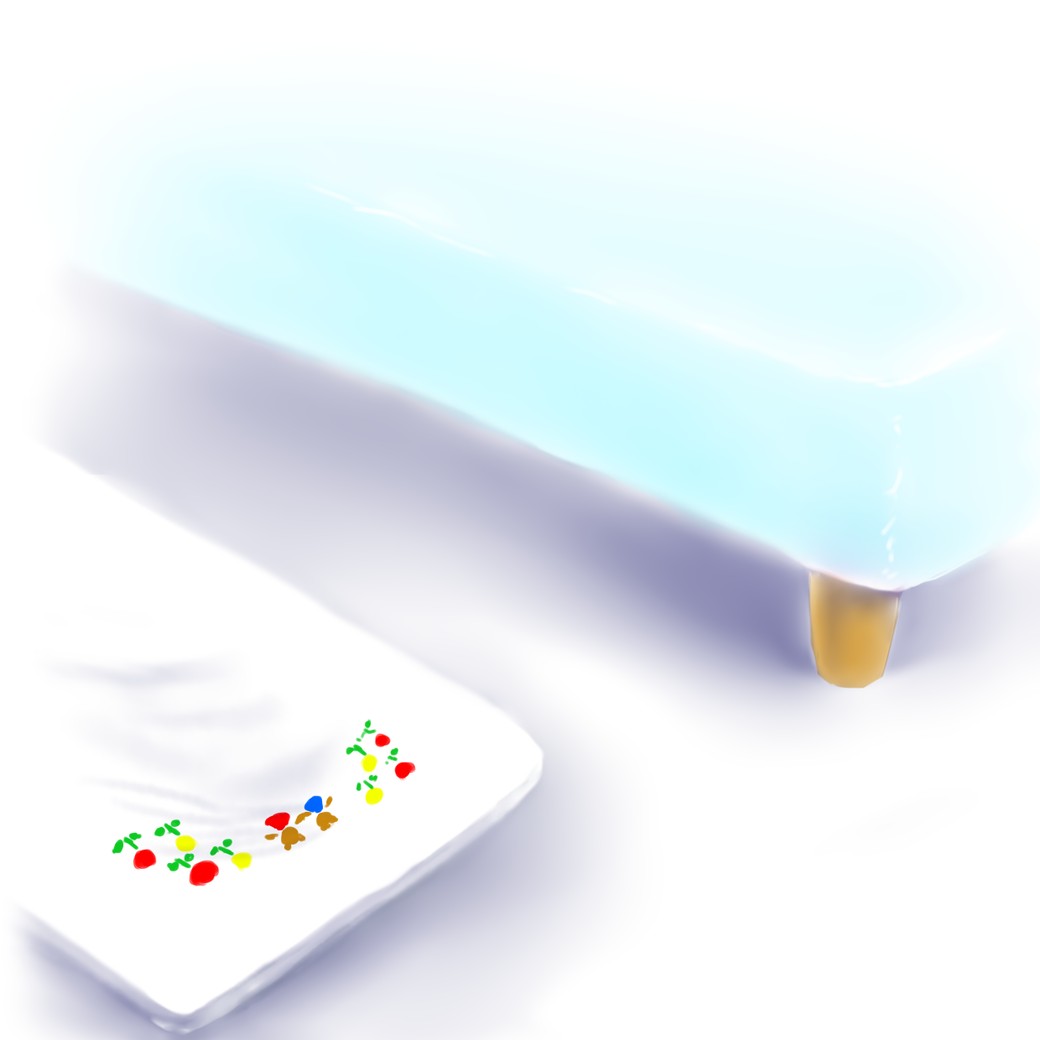
「みみっぽ、見てた」と直美が言うと、
「みみっぽ。久しぶりに聞いたな」と名づけ親のイザオは笑った。
副耳について調べたイザオは「耳ができるときの余りが残ってるのか」と理解し、「耳のしっぽだから、みみっぽだ」とあだ名をつけたのだった。「みみっぽ」と呼ぶと、出っ張りが可愛くなった。
耳っぽは大きくも小さくもならず、優亜にくっついている。髪を垂らしていると隠れるが、結ぶと露わになる。「それどうしたの?」と聞かれたら「耳っぽです」と答える用意をしているのだが、聞かれたことはない。
親にしか見えてなかったりして。
イザオとそう話したこともある。気づいているけれど気づかないふりをする配慮のヴェールのようなものがかけられているのを感じる。
トマトサンタ事件だって、そうだ。
あの日以来、夫婦でそのことを話題にしたことはない。イザオは触れないでおこうとしてくれたし、直美も蒸し返そうとはしなかった。イザオがいつの間にか跡形もなく片づけてくれたように、ミニトマトで作ったサンタクロースごと存在しないことになっている。
「……さっき、優亜の寝言で起きた」
「寝言なんか言うんだ? いっちょ前だな」
寝言の内容を知らないイザオは、無邪気だ。
「なんて言ってた?」
言おうかどうしようか、まばたき1回分ためらってから告げた。
「……『いらない』って」
まばたき2回の間を挟んで、イザオは「ふうん」と反応した。
「トマトのサンタのこと、思い出しちゃった」
別に気にしてないけど、というニュアンスで直美が明るく言うと、
「ああ。あったな」
イザオも明るく返した。たったいま思い出したような言い方だったけれど、余白がなさすぎて、とっくに思い出していたのがバレバレだ。床でバラバラになったトマトのサンタがイザオにも見えているのだろう。さっき「いらない」を聞いたときから。
「たかがトマトに、なんであんな大声出しちゃったんだろね」
あのときはどうかしてたねと友だちに言うような軽さで自分のことを笑った。笑い話にしてしまったほうがラクだから。イザオにも一緒に笑ってもらいたかったが、イザオはつられなかった。
「たかがトマトじゃないよ。トマトのサンタだよ」
それはあの日わたしが言ったことだよと直美は心の中で反論する。「たかがトマト」とイザオに言われて、悔しくて言い返したのだ。
今さらオトナを後出しするなんてずるいよ、イザオ。
「あれは俺が悪かった。ハラミが頑張ってたの、わかってなかった」
イザオが後出しのオトナを続ける。
「頑張ってた」と言われて、甥っ子の幸太の絵に描かれた「がんばってる」を思い出す。

優亜がお腹に入るずっと前、子どもを欲しいイザオとそのことでぎくしゃくしていた頃。幸太を預かった休日、書斎にこもってパソコンに向かっていた。急ぎの仕事ではなかったのに、一人になりたくて。幸太が何度か呼びに来たが、背を向けたまま「後でね」と気のない返事をした。
幸太が描き残した絵に、《なおみちゃんおしごとがんばってる》とひらがなが添えられていた。
《がんばってね》だったら泣かなかったが、《がんばってる》に泣かされた。
がんばってるから邪魔しちゃいけないと我慢しているようにも、それ以上がんばらなくていいよと労ってくれているようにも読めた。どちらにしても幸太のほうがオトナだった。
トマトサンタ事件の日も書斎で自己嫌悪を募らせたが、つくづく成長していない自分がイヤになる。
「『ママなんて、いらない』って夢を見てたのかも」
「なんで?」
「今日、イザオに迎えに行ってもらったじゃない? 実は朝、送って行ったとき、『ママ、今日は来る?』って言われてた」
気を持たせることを避けて、「どっちかな」と答えたが、結局間に合わなかった。
「じゃあ『いらない』って俺のことじゃない? またパパのお迎えかーって」
そういえばとイザオが続けた。「こないだの日曜日、優亜連れて出かけたじゃない? 夕方になって、帰ろっかって言ったら、優亜が言ったんだ。『ママ、待ってないよ』って」
そんなこと言ったんだ。言わせてしまってたんだ。
「わたしがうちで仕事してるのわかってて、邪魔しちゃいけないって思ってたんだ?」
2歳になったばかりの子どもでも「がんばってる」をわかっている。わかっているから我慢している。やっぱり淋しい思いをさせているんだと反省する。
「あー、淋しがってるっていうのとは、ちょっと違って。親が子どもに言い聞かせるみたいな口ぶりだったんだ」
「どういうこと?」
「子どもって、大人が思っているより大人なのかも」
子どもは大人より大人で、大人は子どもより子どもだったりする。
「いらない!」はわたしの寝言だったかもしれない。子どもみたいにわがままを言って、誰かを困らせたくて、夢の中で叶えたのだろうか。
気持ちが軽くなると瞼が重くなった。イザオの声が遠ざかり、体がふわふわしてくる。
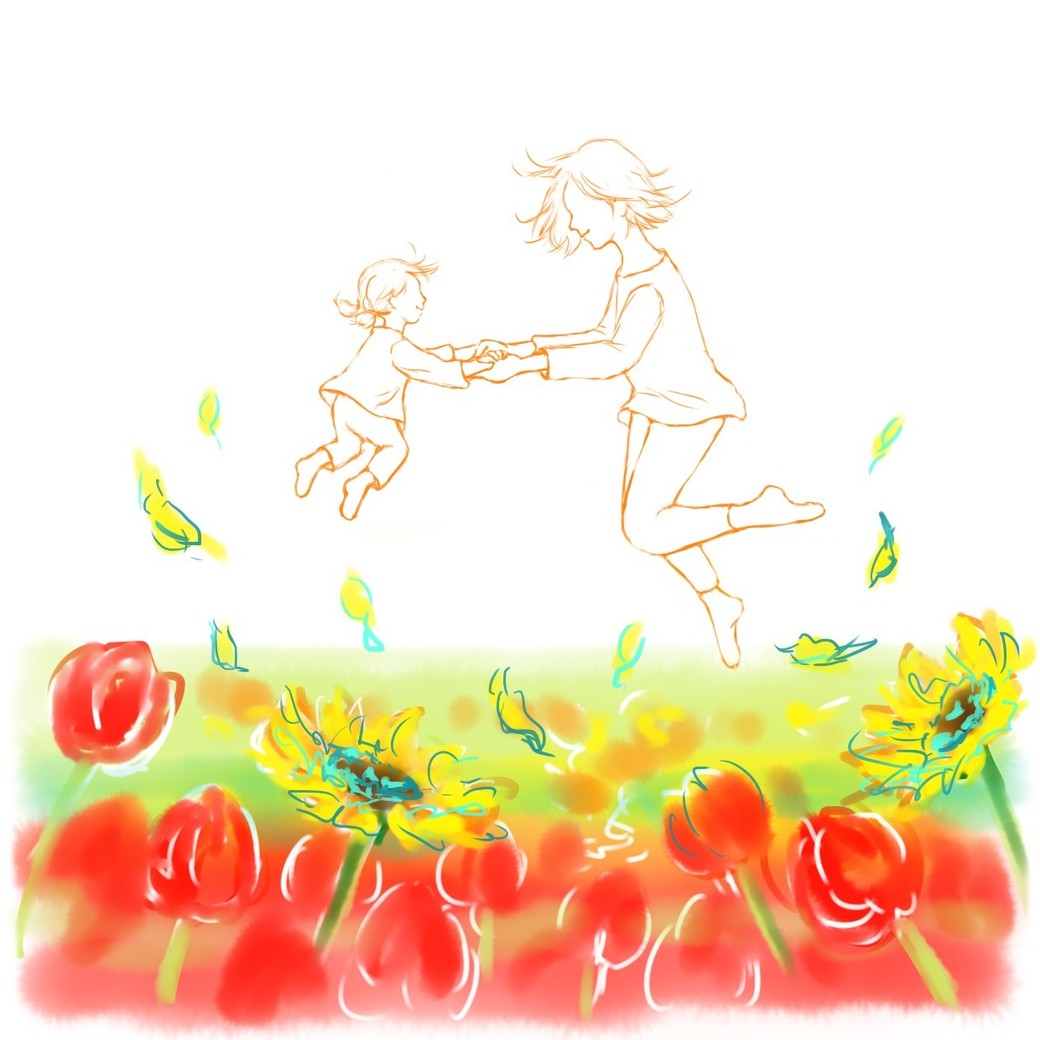
優亜の手を引いて向かった先は、保育園ではなく野原だった。
「はる!」
優亜が声を弾ませ、地平線まで絨毯のように続く花畑を指差した。
クリスマスを見つけると「ここ!」と知らせていたのが、ほんの数か月で「はる!」と季節の訪れを知らせるようになっている。
「春!」と直美も声を弾ませる。
「はる!」と優亜の声がもっと弾む。
手を取り合って飛び上がると、ふわりと体が舞い上がった。
「春!」
「はる!」
「春!」
「はる!」
「春!」と言ったら、「はる!」が返ってくるのがうれしくて、楽しくて、子どもみたいにいつまでも同じ言葉を言い合った。
優亜にママが足りなかったんじゃない。
わたしに優亜が足りなかったんだ。
はるか下でチューリップとひまわりが仲良く揺れていた。春の花と夏の花が一緒に咲いているここは夢の中だと思う冷静さは残っていて、子どもになりきれないくらいには大人だった。
次回3月9日に多賀麻希(49)を公開予定です。
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!