
第215回 多賀麻希(71)彼を一人にしてはいけない
一緒に行こうかとモリゾウは言ってくれたが、大丈夫と麻希は一人で家を出た。
病院の診察室の前のソファ。胆のうのMRI検査を受けた結果を聞きに来て、名前が呼ばれるのを待っている。
5年前、モリゾウと出かけた先でお腹に差し込むような痛みが走り、救急外来を受けつけている病院を探して駆け込み、腹部エコー検査を受けて結果を待った。その同じ病院の同じ診察室の前。
正面の壁に絵が飾られている。5年前にはなかった絵だが、先日の診察のときは待ち時間がなく、すぐに名前を呼ばれたので、よく見ていなかった。
茶色い円の真ん中に赤い点がある。左下に山並みのようなものが描かれ、青い旗のようなものが見える。
赤い点は何だろうか。胆のうの中の胆石のようにも見える。胆石が小さくて少ないと、胆のうの中で動き回れる余裕があり、痛みを引き起こす。あの日の痛みは、それが原因ではという診断だった。
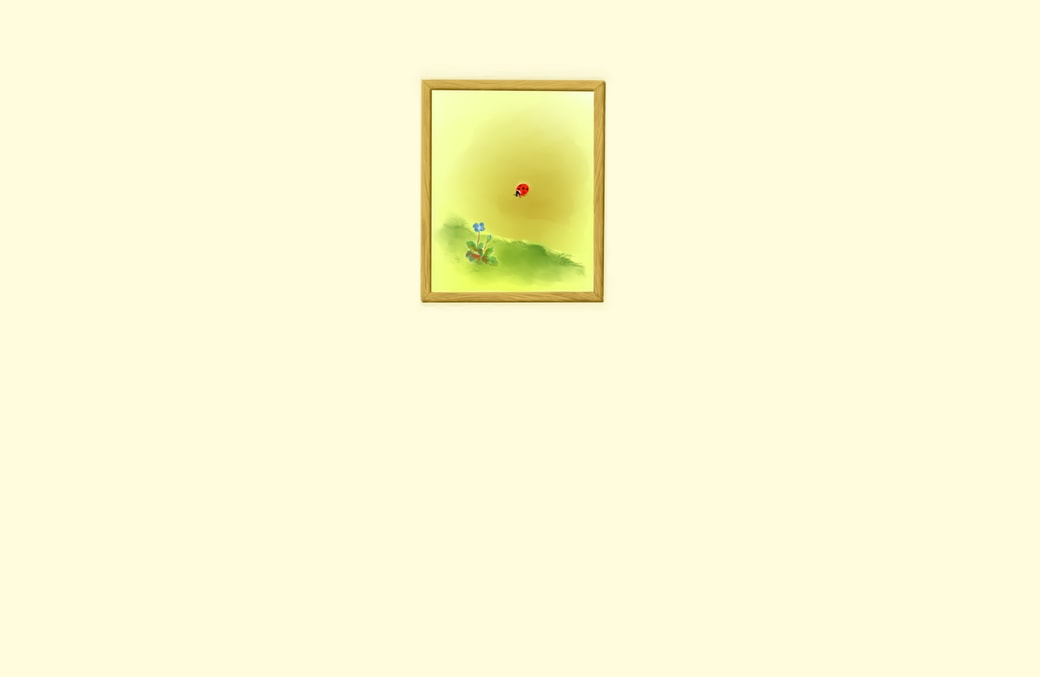
あの日、痛みがおさまったから大丈夫だと麻希は言ったが、今すぐ病院に行こうとモリゾウは言い張った。病気が隠れているかもしれないからと。
「人はあっけなく死にますよ」
突き放すようにモリゾウが言った声が忘れられない。いつもの重低音をいっそう重苦しくしたような暗く冷たい声だった。
モリゾウは身近な誰かを亡くしていて、その命は、もしかしたら病院に行けば助かったかもしれなくて、そのことを悔やんでいるのだろうと思った。
モリゾウとどういう関係の人で、何の病気で、いつ亡くなったのか、麻希は聞かなかったし、モリゾウも語ろうとしなかった。
点字ブロックを隔てて立つモリゾウが遠い人に思えた。モリゾウも同じことを感じていたのかもしれない。
モリゾウはまだ、ただの居候だったけれど。
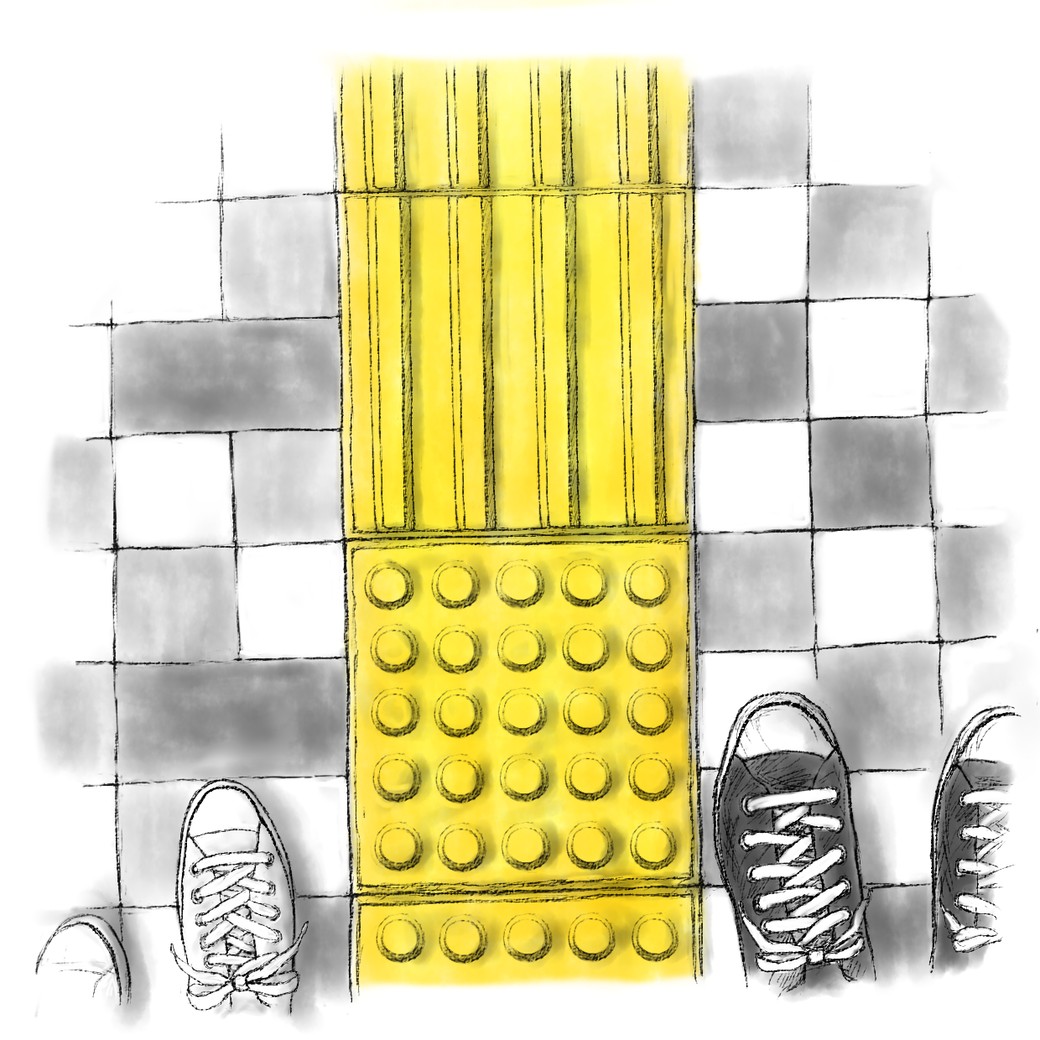
気がつけば、あれから5年経っていた。
いずれ胆石が悪さをするかもしれないと診察した医師に言われ、胆のうごと取ることを勧められた。取らないのであれば定期的に経過観察をと言われたが、その後、大きな痛みを感じることはなく、病院が苦手ということもあり、病院に行ってなかった。
そういえば、しばらく診てもらってないなと思い出したのは、背中から腰にかけて鈍い痛みが続いたからだった。ストレッチをしても改善は見られず、検索すると「内臓疾患の可能性」があると書かれていて、慌てて診察の予約を入れた。
医師は5年前と同じ女性で、5年分、歳を取っていた。5年前は同年代のように思ったが、もう少し上のようだ。50代くらいに見えるのは、前髪に白髪が目立つせいだろうか。以前は白髪がなかったのか、それとも染めていたのか。染めるヒマもないくらい忙しいのだろうか。
「武田麻希さん。5年前に一度いらしてますね」
「はい。そのときは名前が違って、多賀でした」
そんなことわざわざ報告しなくてもいいのかもしれない。あのとき隣にいた人が夫になりましたと心の中で続けた。
「そうですか」と先生は興味なさそうに言った。
5年前、胆のうを取っちゃいますかと言ったときも淡々としていた。臓器を取るというのに、庭のミニトマトをもいじゃいましょうと言うような、あっさりとした言い方だった。
胆のうを取っても、特に影響はないとも言われた。まるで使い捨てにされる派遣社員みたいだ。そんな言い方はないんじゃないかと噛みついた。

「臓器なのに、あってもなくても変わらないって、おかしくないですか? 何か意味があって、役割があって、存在しているんですよね? 役に立たないから、邪魔だから、もういらないって切り捨てるんですか? だったらせめて、今までありがとう、ほんとはいて欲しいって、名残を惜しんで欲しいです。40年近く働いてきて、実はいなくても良かったなんて言われたら、やり切れないです!」
診察室でぶちまけることではなかったが、くすぶっていた感情が爆発してしまった。
先生は何も言わなかった。モリゾウも止めようとしなかった。頭のいいふたりは、何か言っても燃料を投下するだけだと判断したのかもしれない。麻希が吐き出すだけ吐き出すのを静かに待っていた。
あの日のことを覚えているのか、忘れたふりをしているのか、5年ぶりに会った先生は、やはり淡々としていた。
毎日入れ替わり立ち替わり患者が来るし、5年も経っている。そんな患者がいたことは覚えていても、麻希とは結びつかないかもしれない。カルテには「胆のうに異様な執着あり」などとは書かれていないのだろう。
「検査をしましょう」
そう言われ、MRIを受けた。その結果を聞きに来ている。
病院のベンチに腰を下ろしていると、熊本の父が倒れ、モリゾウとふたりで駆けつけた日のことを思い出す。麻希がクローバーの刺繍を施した田沼深雪のウエディングドレス姿を遠目に見た帰りに突然のプロポーズを受けた後で、家族に報告する前だった。
たぶん今、モリゾウにとって家族と呼べるのは麻希だけで、麻希を失えば、モリゾウは一人になってしまう。
「どこにも行かないで」
初めて結ばれた日、モリゾウがそう言った声は、うわずって、かすかに震えていた。
それは、わたしが言いたかった言葉なのに。
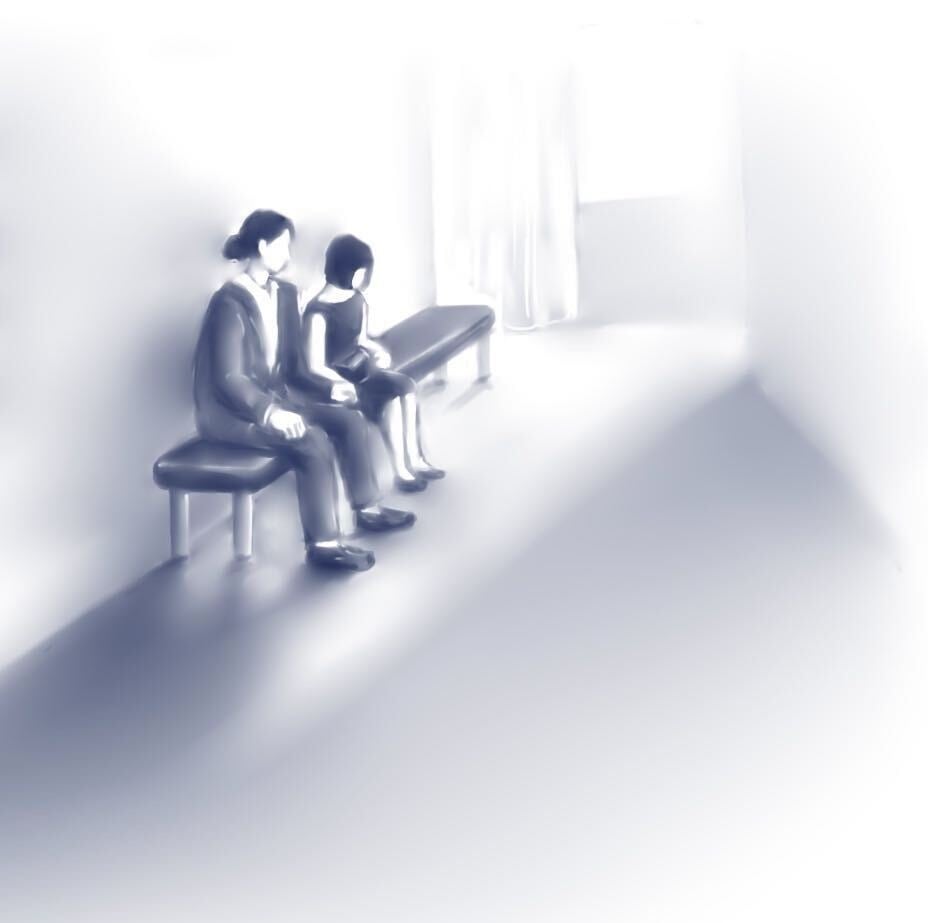
麻希より強く、切実に、モリゾウは身近な人を亡くすことをおそれている。
だから、MRIの筒の中で鳴り続ける金属音のような高い音を聴きながら麻希が思っていたのは、モリゾウを一人にしてはいけないということだった。
一人で生きていくしかないと諦めていた39歳のわたしの前に現れ、東京に残る理由を作ってくれ、夫になってくれた彼を一人にしてはいけない。
誰かのために生きるというより、誰かのために死ねない。そんな風に思える人が自分にできたことが不思議だった。
MRIの筒が棺のようにも思えて、「棺に入るだけ残しなさい」と告げた占い師のことも思い出した。
映画製作プロダクションで働いていた20代の頃、撮影現場で出会ったエキストラの中にネットワークビジネスをやっている女の子がいて、その子に勧められるまま、使いもしない美顔器や空気清浄機を買った。
夢を食べるのにはお金がかかるのだと教えてくれた彼女から夢を買っていた。いつか彼女が大きな舞台に立てたら、苦しい時代を一緒に支えたのだと誇りたかった。彼女が劇団を去り、東京を去っていたことを麻希が知ったのは、ずっと後だった。
棺に入るだけ残して、あとのものは手放しなさい。そうすれば、欲しいものが手に入るからと占い師は告げた。
アパートを引っ越し、美顔器や空気清浄機やいろんな人につけ込まれ、いいように使われていた大小のツケを手放した。
占いが当たったのか、偶然なのか、モリゾウと出会ったのは、その後だ。
胆のうを手放したら、また望むものが手に入るのだろうか。手放さないと、大切なものを失うのだろうか。胆のうは棺に入るけれど。
まだ名前は呼ばれない。
立ち上がり、正面の絵に近づいてよく見ると、赤い点はてんとう虫で、青い旗のようなものは花だった。

てんとう虫のまわりの茶色は地面で、歩いて花に近づいているらしい。山並みのように見えたのは、草むらのようだ。
同じ絵でも近くで見るのと遠くから見るのとでは違って見える。
同じ出来事でもそうだなと思う。
胆のうに感情移入し、衝動的に胆のうの思いを代弁した5年前の麻希は、まだ若かったのだ。熊本から東京に出てきて、東京にしがみついて、引き換えに得られたものといえば胆石くらいで、それをあってもなくても変わらないなどと言われ、これまでやってきたことは何だったのかとやりきれなくなった。
あの日、胆のうにしがみついたのは、他にしがみつくものがなかったからだ。
「武田麻希さん」
名前を呼ばれ、立ち上がる。
診察室に入ったら、たぶん、5年前と同じことを言われる。
胆のう、取っちゃいますか。
だけどわたしは、あの日とは違う。もっと手放したくないものができたから。

次回2月28日に多賀麻希(72)を公開予定です。
編集部note:https://note.com/saita_media
みなさまからの「フォロー」「スキ」お待ちしています!
























































































































































































































































































































































































































































