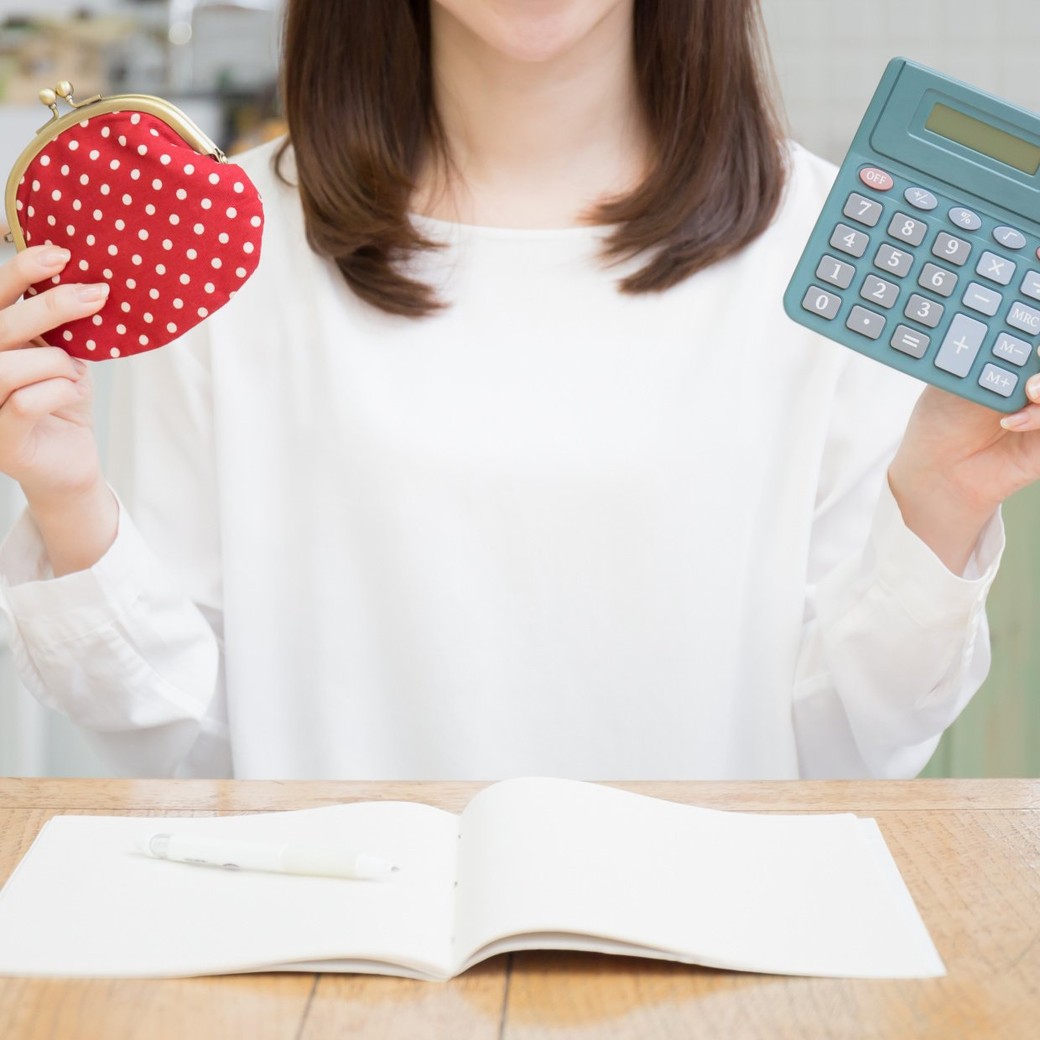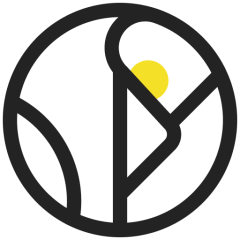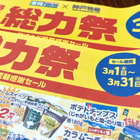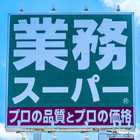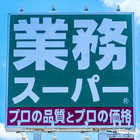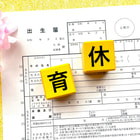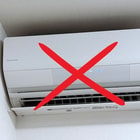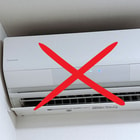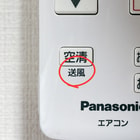教えてくれたのは、ウェルスナビ株式会社 小松原さん
働く世代が豊かさを実感できる社会をつくりたいという理念に共感し、ウェルスナビにセミナー講師として入社。これまでに、1,000回以上の資産運用セミナーに登壇し、参加者からの多くの質問にも答えている。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。
知っておきたい「控除」
食料品、日用品など、私たちの身近な商品の値段が日々上がっている昨今、生活にかかる負担を少しでも減らしたいと感じている方も多いのではないでしょうか。
今年の春、ウェルスナビが働く世代に実施した調査では「物価上昇により、家計に影響を感じた」と答えた人が全体の9割にのぼりました(※1)。
物価高に負けないためには、毎日の家計管理を工夫することはもちろん、NISAやiDeCoのような制度を活用した資産形成が大切です。さらに、生活に身近なお金の制度について知識をもつことも、将来のご自身の強い味方になります。
たとえば、そのひとつが「控除」です。わかりづらい言葉と認識している方も多いかと思いますが、「一定の金額を差し引く」ことです。税金の話題で出てきた際には、ひらたくいえば「払う税金が少なくなる」ことを意味します。控除をうまく活用することで、支払う税金を減らし、家計の負担を軽くすることができます。
今回はその中で身近な二つの制度について解説します。
「税金の先払い+返礼品」でお得なふるさと納税
まず一つ目は、ふるさと納税です。自分の故郷や応援したい自治体など、好きな自治体に寄付ができる制度です。本来であれば、自分の住んでいる自治体に納める税金の一部を、選んだ自治体に寄付することで、所得税・住民税の優遇が受けられます。「寄付金額-2,000円」の範囲で税金が差し引かれ、寄付のお返しとして自治体から返礼品が送られます。
支払う予定の税金を「先払い」して、結果として翌年の納税が減るという仕組みです。制度を使わなければ「納税」だけなのが、ふるさと納税を活用することで「納税+返礼品」になるという点ではお得です。
「寄付金控除」の申請忘れに注意
一つ注意していただきたいのが、翌年の税金を差し引くための「寄付金控除」という手続きをとっていない人が意外と多いという点です(※2)。
寄付金控除の申請には、ワンストップ特例制度もしくは確定申告が必要となります。ふるさと納税をした人は忘れないようにしたいですね。
ワンストップ特例制度は、寄付した自治体が5か所以下で、確定申告を行う必要がない人が対象です。寄付をした翌年の1月10日までに各自治体に申請書を提出します。オンラインでも申請可能です。
ワンストップ特例制度が利用できない場合もあります。例えば、住宅ローン控除や医療費控除などを利用するため、すでに確定申告をする予定がある人は利用できません。さらに、寄付した自治体が6か所以上の人も確定申告が必要です。確定申告は、寄付をした翌年の例年2月16日~3月15日頃に行います。
見落としがちな「医療費控除」
もう一つが、医療費控除です。1年間に支払った医療費が一定の金額を超えたら、支払う税金が安くなるという制度です。自分や家族の支払った医療費が10万円を超えたら、対象になります(※3)。税金の計算の際に、支払った医療費に応じて税金が戻ってきます。医療費分がそのまま戻ってくるわけではないのですが、家計のプラスにはなります。
病院での診療費、通院にかかった交通費、処方箋をもとに購入した医薬品の費用などが対象。見落としがちだけれども、重要なポイントが二つあります。
一つ目は、保険適用ではない治療も対象となる場合があるという点。例えば、レーシック手術、インプラント治療などが当てはまります。自分や家族が病院で受けた治療が対象となるか、確認してみてはいかがでしょうか。
二つ目に、過去5年以内であれば、さかのぼって申告できるという点です。過去の明細書や領収書が残っていれば、この機会に見直しもおすすめです。医療費控除の申請は、確定申告の時期(例年2月16日~3月15日頃)に行います。
今のうちに領収書の整理を
ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」は納付をしてからすぐにでき、期限は寄付をした翌年の1月10日頃です。確定申告までには時間があるので、今できることは、関連する領収書などを保管しておくこと。
時間があるときに保管場所を決めておくだけでも、申請時期になってから安心です。
まとめ
今回は、生活に身近なお金の制度を活用して、家計の負担を減らし、実質的な手取り収入を増やす方法について紹介しました。いずれも手続きが伴うものではありますが、家計の支えになりそうなものがあれば、取り入れてみてはいかがでしょうか。
参考:
※1 ウェルスナビのインターネット調査(2025年3月実施)より。「近年の物価上昇によりあなたの家計への影響をどの程度感じていますか。もっともあてはまるものをお選びください」(回答者数4,120人、単一回答)に対し、「非常に影響を感じている」「やや影響を感じている」と回答した人の合計から。
※2 トラストバンク「ふるさと納税の確定申告に関する実態・意識調査」より(https://www.trustbank.co.jp/newsroom/newsrelease/press870/)
※3 総所得金額が200万円未満の人は総所得金額×5%。最高で200万円分が控除される。(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm)